グローバル展開を考える企業にとって、東南アジアは魅力的な市場の一つです。ASEAN諸国は人口規模や経済成長率の面で高いポテンシャルを秘めており、生産拠点・販売拠点として注目を集めています。しかし、海外進出を検討するうえで見落とせないのが、現地での知的財産権の保護対策です。特にブランドイメージを担う商標は、模倣品や無断使用のリスクが高まる新興国市場において、しっかりと対策を講じていないと、後々大きなトラブルを招きかねません。
本記事では、東南アジアにおける商標・知財保護の実情を網羅的に解説します。なぜ今、東南アジアで商標を守ることが重要なのか、各国の知財制度はどうなっているのか、そして実際に商標を取得・管理するにはどのような手順を踏むべきか、といった点について、公的機関や専門家の情報を交えながらわかりやすくまとめました。初心者でも理解しやすい形で整理していますので、これからASEAN諸国へ進出を考えている企業の担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
なぜ東南アジアで商標保護が重要なのか

東南アジア市場における製品・サービス展開を成功させるには、コスト面や物流面だけでなく、ブランド戦略が欠かせません。現地の生活者や企業との信頼関係を築くうえで、商標をきちんと保護しておくことは大きなメリットをもたらします。逆に、模倣品が出回ってブランドイメージを損なうようなことがあると、市場シェアや企業評価に深刻なダメージを与えかねません。まずは、東南アジアで商標保護の重要性が高まっている背景を見てみましょう。
経済成長と模倣品リスクの高まり
ASEAN諸国は近年、高い経済成長率を維持してきました。ベトナムやインドネシア、フィリピンなどはGDPが年率5~7%程度で成長しており、若年層の人口も多いことから、今後の消費需要や製造業の発展が期待されています。一方で、このように市場が拡大している地域では、模倣品や商標権侵害のリスクも増大する傾向があります。製品やブランドの認知度が高まれば高まるほど、それを模倣する動きも活発化するからです。
実際、世界知的所有権機関(WIPO)の報告や、日本貿易振興機構(JETRO)が現地企業から得たヒアリングなどによれば、アジア地域では依然として偽造商品が大量に出回っている実態が指摘されています。たとえば、有名ブランドのアパレルや高級時計、電化製品、日用消費財など、あらゆる業界で模倣品が問題視されているのです。商標をきちんと取得・管理していないと、それらの被害を防ぎにくい現実があります。
公的機関(JETROなど)の最新データによる動向
JETROや在外公館など公的機関が発表している各種レポートでは、東南アジアでの知財侵害に関する事例が数多く報告されています。特に、模倣品を取り扱う業者はインターネット通販やSNSを通じて商取引を行うことも増えており、国境を越えた取り締まりが難しくなっているのが現状です。このようなグローバル規模の模倣ビジネスは巨大な闇市場を形成し、企業の本来得られるはずの収益機会を奪っています。
また、各国政府は知財保護の強化を図ろうとしてはいるものの、法整備が追いついていない分野が存在したり、運用面で課題を抱えていたりするケースもあります。外資企業にとっては、こうした法的リスクに対処するためのコストやリソースをあらかじめ見込む必要があるでしょう。商標保護をしっかり行うことで、自社のブランド価値を守るだけでなく、トラブルに巻き込まれた際のリスク管理が行いやすくなります。
東南アジアの知財制度の現状と各国の概略

東南アジアでは、ASEAN加盟国が中心となって「商標・特許など知的財産保護の枠組み」を整備しようという動きが進んでいます。一方で、各国によって法制度や実務手続きが微妙に異なるため、どの国に進出するかによって対策は変わってきます。ここでは、主要国の知財制度の概略をざっくりと見ていきましょう。
ベトナム・タイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポールなどの比較
たとえば、ベトナムは「工業所有権法」と呼ばれる法律を中心に知財を保護しており、商標登録に関しては国家知的財産庁(NOIP)が管轄しています。登録までに時間がかかることが多く、早めの申請が重要とされています。タイでは商標法が整備されてはいるものの、英語以外にタイ語での書類作成が必要となるケースもあり、ローカルへの対応が欠かせません。
インドネシアは「DGIP(Directorate General of Intellectual Property)」が知財行政を統括し、オンラインでの出願システムが整いつつありますが、審査期間や書類不備による遅延が課題とされます。マレーシアでは「マレーシア知的財産公社(MyIPO)」が商標登録手続きを受け付け、審査も比較的スムーズといわれていますが、特定の業種における外資規制の影響なども考慮が必要となるでしょう。
フィリピンは「IPOPHL(Intellectual Property Office of the Philippines)」が商標審査を行っており、ラテン文字以外の商標やロゴマークの保護にも対応しています。シンガポールはASEANのなかでも知財保護が最も進んでいる国の一つとされ、商標出願に関しては比較的明確なガイドラインが設けられています。英語が公用語であることや、国際仲裁センターとしての地位も高いため、グローバル企業がアジアHQとしてシンガポールを選ぶケースが多いのも特徴です。
ASEAN全体での知財関連の取り組み(ASEAN IP Portal など)
ASEAN各国は、国際協定などを通じて共通の知財保護水準を高めようという動きを見せています。具体的には、ASEAN IP Portalというウェブサイトで各国の商標データベースや審査状況を確認できる仕組みが提供されており、域内企業が知財関連情報を収集しやすい環境が整えられています。また、マドリッド協定議定書に加盟している国が増えている点も、東南アジア地域での商標管理を容易にする方向へと繋がっています。
とはいえ、域内で完全に統一された商標制度があるわけではなく、各国別の申請プロセスや言語要件は依然として存在します。公的機関が推進する協力体制も、まだ完全には成熟していない部分があるため、油断は禁物です。最終的には進出先の国ごとに個別に商標登録を取得する形が一般的となっています。
商標出願・登録の基本的な手順
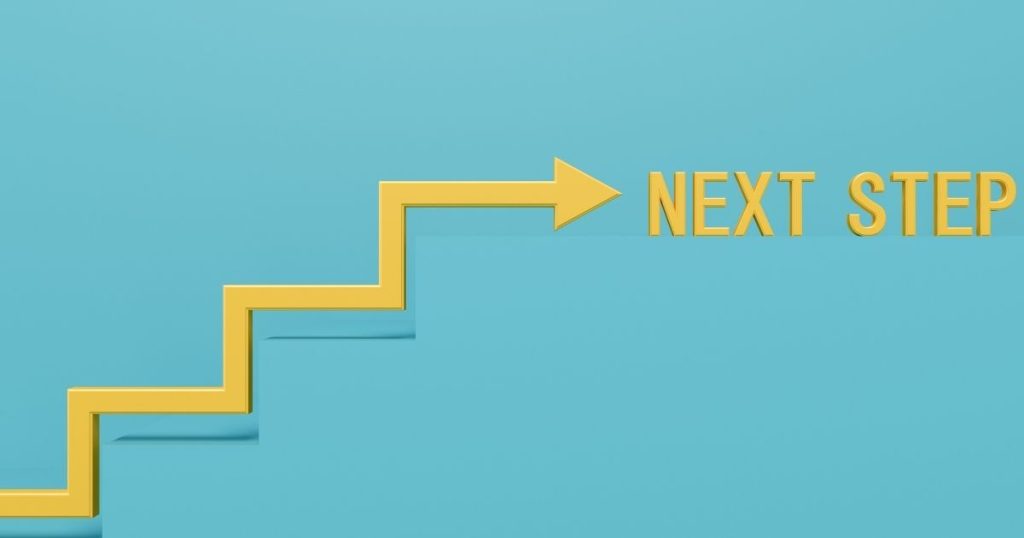
東南アジアでの商標をきちんと保護するためには、早めの出願と登録手続きを進めることが大前提です。商品やサービスの投入前に現地での商標調査を行い、侵害リスクや重複登録の有無を確認しておくとトラブル回避に効果的です。ここでは、代表的な出願方法や必要書類、審査の流れを簡単にまとめます。
現地単独出願とマドリッド協定議定書による国際出願
商標出願の方法としては、大きく分けて以下の2つのルートがあります:
- 現地単独出願:進出先の国の知財庁に対し、直接出願手続きを行う方法。ローカル代理人や弁護士を通じて申請するケースが多い。
- マドリッド協定議定書による国際出願:自国(日本)で基本出願または基本登録をした上で、対象国を指定して国際出願する方法。WIPOを通じて出願し、指定国ごとに審査を受ける。
マドリッド協定議定書に加盟している国(シンガポール、ベトナム、フィリピン、インドネシアなど)であれば、国際出願によって手続きを統一化できるメリットがありますが、最終的には各国の審査に合格する必要があるため、却下されるリスクは残ります。一方で、加盟していない国(タイ、マレーシアなど)に対しては現地出願が必須となるので注意が必要です。
書類準備・審査プロセス・手続きの所要期間
出願に際しては、一般的に以下の書類が求められます:
- 商標を示す図案や文字のサンプル
- 商標の指定商品・指定役務(クラス)のリスト
- 出願人の情報(会社名、住所、代表者名など)
- 委任状(代理人を立てる場合)
審査プロセスは各国で異なりますが、概ね以下のステップを経ます:
- 形式審査:提出書類が形式要件を満たしているか確認
- 実体審査:既存の商標との類似性や識別力の有無などを審査
- 公告:問題がなければ官報や知財庁サイトで公告し、異議申立を受け付ける期間を設定
- 登録:異議がなければ商標登録証が発行され、保護が正式に開始
手続きの所要期間は国によって大きく差があり、スムーズに進んでも1年程度、トラブルがあると2~3年かかる場合も珍しくありません。商品やサービスを現地投入するタイミングに合わせて出願しても、登録までに時間を要するため、できるだけ早い段階で準備するのが賢明です。
知的財産権侵害への対応策

商標を登録していても、模倣品や無断使用のリスクを完全にゼロにはできません。もし侵害を発見した場合、どのような行動をとるべきか、事前にシミュレーションしておくことが重要です。ここでは、侵害対応の基本的なフローや、専門家のサポートを活用する際のポイントを説明します。
模倣品や無断使用を発見したときの行動フロー
現地で自社のブランドを模倣した商品が出回っている、あるいは商標を無断使用されている疑いを持った場合、以下のステップで対応するとスムーズです:
- 証拠収集:模倣品の実物や販売場所、写真、取引先情報などを確保し、侵害の事実を裏付けるデータを集める。
- 権利関係の確認:自社の商標登録証や出願状況を再確認し、保護対象範囲が侵害に該当するかを判断。
- 専門家へ相談:現地の弁護士や知財コンサルタントに状況を報告し、法的措置の可能性や協議方針を検討。
- 警告書・差止請求:相手方に書面で警告を行い、模倣行為の停止と損害賠償を求める。場合によっては裁判所に差止命令を申請。
- 行政・税関への働きかけ:国によっては、行政当局が模倣品を摘発したり、税関で輸出入を差し止めたりできる仕組みがあるため、連携を図る。
この過程で、現地の企業が「知らなかった」「正規ルートで仕入れた」などと主張するケースも多く、必ずしも悪意があるとは限らない場合もあります。そのため、円満に解決するためには、まず事実関係を丁寧に確認し、相手との交渉で妥協点を探ることも重要です。
弁護士や調査会社の活用事例
海外での知財侵害をめぐる係争は、言語・文化・法制度の違いによる複雑さが伴います。こうした状況で、社内リソースだけで対応しようとすると時間とコストが膨大にかかり、適切な証拠収集や交渉がままならないこともあります。そのため、多くの企業が弁護士や調査会社を活用しています。
- 弁護士:法的手続きの専門家として、警告書の作成や裁判所への申し立て、行政機関とのやりとりを代理してくれる。現地法に通じた弁護士を選ぶことが重要。
- 調査会社:市場での模倣品の流通実態を調べたり、販売経路を特定したりする役割を担う。必要に応じて証拠を撮影・購入し、法的手続きに活用することも。
信頼できる専門家に依頼することで、無駄な労力を割かずに商標侵害問題の解決を図れるだけでなく、リスクを最小限に抑えた上で相手方と和解やライセンス交渉を行う道も開けます。
公的機関や専門家のサポート活用方法

商標に関する法律や運用は国や地域によって大きく異なるため、海外での対応には公的機関や専門家のサポートを受けるのが効果的です。JETROや各国の知財庁、在外公館などは、企業が知財保護を行ううえで役立つ情報や相談窓口を提供しています。ここでは、具体的にどのような支援が受けられるかをまとめます。
JETRO、在外公館、各国知財庁などから得られる情報
日本貿易振興機構(JETRO)は、海外進出を目指す企業に向けてさまざまなサポートを行っています。中でも、各国の知財関連法令や商標出願の手続きなどをまとめたガイドを公開しており、無料でアクセスできる情報だけでもかなり具体的な内容を把握できます。また、JETROの海外事務所では現地の企業事情や法改正情報などを随時アップデートしており、個別相談に乗ってもらえることもあります。
在外公館(日本大使館・領事館)も、現地企業とのトラブル相談や、専門家(弁護士など)の紹介を行っている場合があります。さらに、各国の知財庁(たとえばフィリピンのIPOPHL、マレーシアのMyIPOなど)の公式ウェブサイトには、商標出願手順や審査状況を確認できるポータルが用意されているケースが増えています。英語や現地語に対応しているので、ローカルの情報源としても有用です。
コンサルティングや弁護士事務所への相談ポイント
商標管理や侵害対策など、具体的な業務をアウトソーシングしたい場合は、現地に拠点を持つ日系コンサルティング企業や弁護士事務所を活用するとスムーズです。特に、以下のような点を事前に相談しておくとよいでしょう:
- 費用体系:着手金や成功報酬、月額顧問料などの料金形態が明確になっているか。
- 実務経験:商標出願や侵害対応の実績が豊富か。過去の事例や成功率などを確認すると安心。
- 言語対応:日本語だけでなく、現地語や英語を使った交渉・書類作成に対応できるか。
- コミュニケーション体制:連絡方法やレスポンス速度、定期レポートの有無など、やりとりが円滑に進む仕組みがあるか。
また、複数の専門家や事務所に見積もりを依頼し、料金やサービス内容を比較検討することも大切です。企業規模や製品カテゴリーによって必要なサポートの範囲は大きく異なるため、事業のフェーズや予算に合わせた選択を行いましょう。
まとめ

東南アジアでのビジネス展開を成功させるには、製品やサービスの優位性を高めるだけでなく、商標保護をはじめとした知的財産戦略が欠かせません。特に、成長著しい市場では模倣品や商標侵害のリスクが高まるため、早めの出願と適切な管理が企業の価値を守る要となります。以下に、本記事の重要なポイントを整理します:
- 東南アジア市場の成長によって模倣リスクが増加
経済が活発になるほど模倣ビジネスや侵害行為が拡大しやすく、未対策の企業は大きな損害を被る可能性がある。 - 各国の知財制度や手続きに違いがある
ASEAN各国の法制度や実務プロセスは一様ではなく、マドリッド協定議定書を活用できる国とそうでない国がある。国別の特性を把握し、進出計画に応じて出願計画を立てることが重要。 - 商標出願・登録には時間とコストがかかる
申請から登録まで1年以上かかることも珍しくなく、不備や異議申し立てがあるとさらに延びる。事業計画に合わせて早めに手続きを開始しよう。 - 侵害対策には専門家の活用が効果的
弁護士や調査会社をうまく使うことで、模倣品の流通経路把握や警告書の送付、行政への働きかけを効率的に行える。自社だけで対応しきれない部分はプロに任せるのがおすすめ。 - 公的機関の情報収集でリスクを減らす
JETROや在外公館、各国知財庁のポータルサイトなどを活用して最新情報を入手する。法改正や運用の変化を把握していないと、思わぬ落とし穴にはまりやすい。
商標をはじめとする知的財産権は、企業にとって大切な「無形の資産」です。特にブランド力や製品の独自性に頼るビジネスモデルでは、知財の保護が不十分だと市場での競争優位を失うリスクが高まります。海外での知財保護は日本国内よりも複雑に感じるかもしれませんが、適切な手順を踏み、専門家と連携しながら進めることで、リスクを抑えつつグローバル展開を加速させることができます。
もし商標取得や模倣品対策について具体的に検討中であれば、一度JETROなどの公的機関に相談し、進出先の法制度や事例を確認してみるとよいでしょう。また、弁護士事務所やコンサルタントへの相談も視野に入れ、コストや効果を天秤にかけながら最適な方法を選択することが大切です。東南アジアの活気ある市場で、知財トラブルを未然に防ぎ、安心してビジネスを拡大していきましょう。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
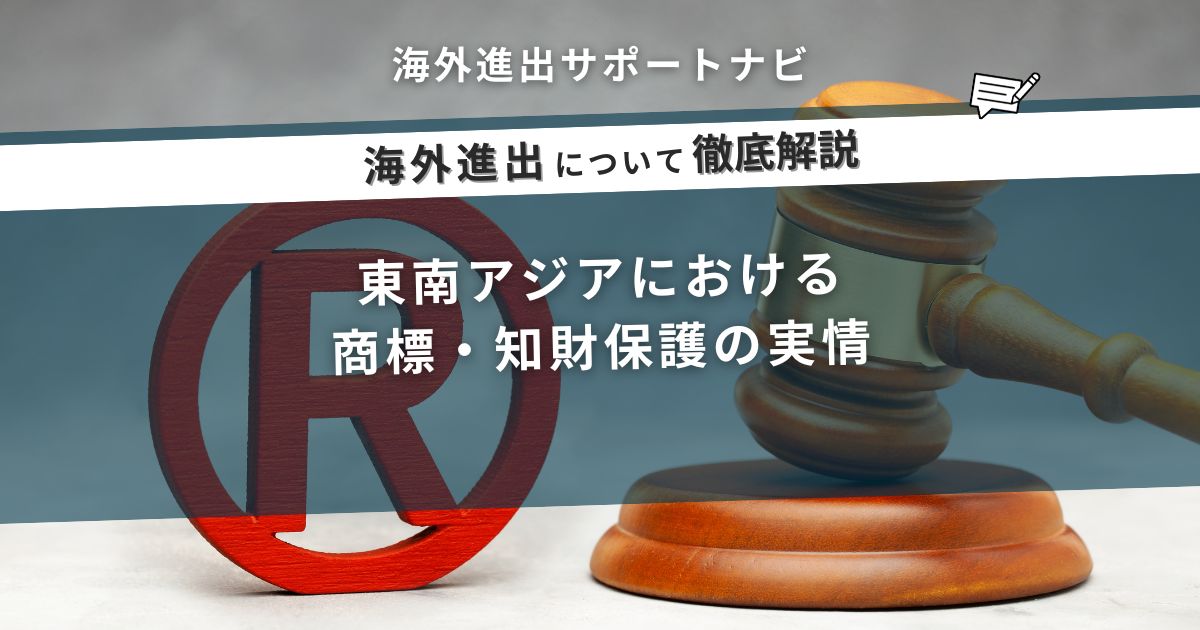
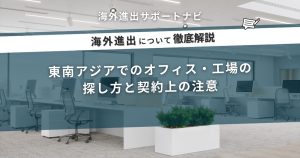
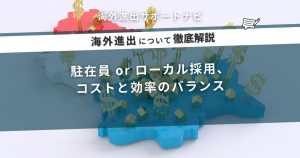
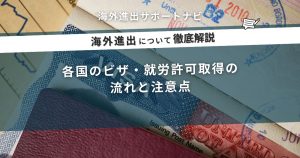
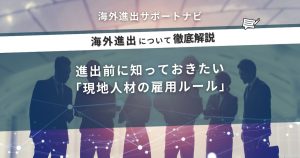
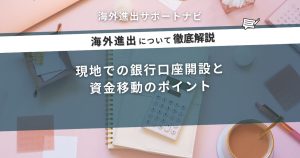
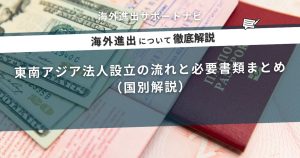
コメント