東南アジアを中心とした海外市場への進出を検討する際、事業スキームや販売計画だけでなく、現地での法人税や消費税の仕組みを正しく理解しておくことはとても大切です。国によって税率や課税対象、申告手続きが大きく異なるため、あらかじめ調べずに事業を始めてしまうと、想定外の税コストやコンプライアンスリスクに直面する恐れがあります。特にタイやベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールなどの国々では、高い経済成長率や投資誘致の動きがある一方で、税制が複雑だったり改正が頻繁に行われたりするケースも珍しくありません。
そこで本記事では、「法人税・消費税」の視点から、東南アジア主要6か国(タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール)それぞれの税制度を比較しながら、どのような点に注意すべきかを解説します。公的機関(JETROや世界銀行など)が提供する最新データも引用しつつ、初心者にもわかりやすい形でまとめました。将来的に現地法人を設立する、あるいは越境ECやパートナー企業を通じて販売を行うときに役立つ情報を網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
なぜ東南アジアの法人税・消費税を理解する必要があるのか

海外進出を成功に導くためには、現地での事業戦略やマーケティング施策だけでなく、「税制面での最適化」も欠かせません。特に東南アジアの国々は、若い人口や成長市場を背景に投資魅力が高まっている一方、税制が国ごとに独特であり、規定の改定も頻繁に行われるのが実情です。
経済成長率が高い地域での税制対応が企業戦略を左右
タイやインドネシア、ベトナムなどは世界銀行やIMFのレポートで、5〜7%近いGDP成長率を記録することが少なくありません。こうしたダイナミックな市場に参入する企業は、需要拡大の恩恵を享受しやすい一方で、適切な税務戦略を取らないと利益を大きく削られるリスクがあります。法人税率が20%なのか30%なのか、消費税(付加価値税)が10%なのか15%なのかといった差は、事業収益に直結します。
また、各国政府が投資誘致を目的とした税制優遇策(例えばタイのBOIやシンガポールのタックスホリデーなど)を打ち出しているケースもあり、それを活用できるかどうかでコスト構造や競争力に大きな差が出ます。進出前に現地の税制を調べ、シミュレーションを行うことで最適な拠点や法人形態を選択できるでしょう。
公的機関(JETROなど)のデータから見る東南アジアの税務環境
日本貿易振興機構(JETRO)が発行する各種資料や、在外公館のレポート、世界銀行の「Doing Business」ランキングなどを見ると、東南アジア各国は「税率の水準」「申告・納税の手間」「投資優遇制度の整備状況」にかなりのばらつきがあることがわかります。例えばベトナムでは法人税率が統一的に設定されている一方、インドネシアでは租税特区(Special Economic Zone)内に投資する企業に対して減免措置が適用されるなど、多様な制度があります。
また、消費税の課税方式(VATやGST、SSTなど)や税率も国ごとに異なり、課税対象や計算方法に注意が必要です。こうした情報は公的機関のウェブサイトやセミナー、あるいはコンサルタント経由で収集するのが効率的です。早めに情報をキャッチしておけば、法人設立やライセンス取得に向けた行動をスムーズに進められます。
タイの法人税と消費税(VAT)の概要

まずはタイの税制を見ていきましょう。タイは東南アジアの中でも日本企業の進出実績が多い国であり、比較的整備されたインフラと投資誘致策が魅力的な市場です。自動車や電機など製造業の拠点として知られていますが、最近ではサービス産業やスタートアップ領域でも注目を集めています。
タイの法人税率と優遇策(BOIなど)
タイの法人税率は基本的に20%とされています。ただし、企業の規模や所得額が一定基準以下の場合、段階的な低税率が適用されることがあります。加えて、タイ投資委員会(BOI)が認可する投資プロジェクト(ハイテク産業や地方開発産業など)に対しては、一定期間の法人税免除や輸入関税の免除などの優遇策があります。
BOI認可を受けるには、投資額や雇用人数、技術移転の要件を満たす必要があるため、事前に計画を策定し、BOIへ申請する形になります。成功すれば10年程度の法人税免除が得られるケースもあるため、特に製造業や研究開発型の企業にとっては大きなメリットとなるでしょう。
VAT制度と対象外取引に関する注意点
タイでは消費税に相当する税金としてValue Added Tax(VAT)が導入されています。基本税率は7%で、多くの商品やサービスに対して課税されます。ただし、医薬品や出版物など一部の品目は免税対象となっているほか、輸出取引は基本的にゼロ税率です。
VATの申告・納付は通常月次で行われ、売上VATから仕入VATを差し引いて納付する仕組みです。事業者が登録義務を負うのは年間売上が1,800,000バーツを超える場合などと定められています。海外企業がタイで活動する場合も、支店や子会社が設立された際にはこのVAT登録が必要となる場合があり、取引形態によっては税務上のリスクを招かないよう注意が必要です。
ベトナムの法人税・VATの制度と注意すべき実務ポイント

次にベトナムを取り上げます。ベトナムはASEAN地域の中でも特に高い経済成長率を示しており、外資企業の進出が急増している国の一つです。製造業だけでなくITやサービス分野でも存在感を高めていますが、税制や手続き面で独自の慣習があるため注意が必要です。
ベトナムの法人税率と優遇エリア
ベトナムの法人税率は、原則として20%となっています。ただし、特定の投資奨励エリア(経済特区など)やハイテク産業に指定されるプロジェクトに対しては、一時的な法人税の免除や減税が認められる場合があります。例えば、主要都市から離れた地方での工場設立や雇用創出を行う企業に対しては、優遇措置を受けられる可能性があります。
また、企業所得税のほかに個人所得税や社会保険料なども考慮する必要があるため、ベトナムに進出する際は労務面と合わせて総合的にシミュレーションすることが望ましいでしょう。公的機関(ベトナム計画投資省やJETROハノイ・ホーチミン事務所など)が提供する投資ガイドを参照しつつ、必要に応じてコンサルティング企業のサポートを受ける形がおすすめです。
VAT申告やRed Invoice(赤インボイス)にまつわる実務
ベトナムのVAT税率は基本10%で、売上に対して課税される仕組みです。輸出にはゼロ税率が適用されます。一方、食品や医療品など一部の品目には5%の軽減税率が設けられているケースがあります。申告・納税は月次または四半期ごとに行われ、仕入VATと売上VATの差額を納付する形が一般的です。
ベトナムの税務上の特徴として「Red Invoice(赤インボイス)」の存在が挙げられます。公式のインボイス用紙を使って発行される伝票が赤字で印刷されるため、こう呼ばれていますが、企業間の取引で仕入VAT控除などを適用するためには正規のRed Invoiceの発行が必須となります。管理が煩雑な部分もあるため、会計ソフトや専門家を活用してしっかりと運用することが大切です。
インドネシア・マレーシアの法人税・消費税比較

ここではインドネシアとマレーシアを取り上げ、両国の法人税や消費税の概要を比較してみます。同じASEAN加盟国でも、名称や制度、税率が大きく異なるため、進出国の状況に合わせた対応が不可欠です。
インドネシアの法人税率と付加価値税(PPN)
インドネシアの法人税率は、2020年の法改正によって30%から22%へ段階的に引き下げられ、2022年以降は20〜22%程度で推移しています(法改正の動向によって変更される可能性あり)。さらに、中小企業向けに低率が適用される制度もあります。一方、付加価値税(PPN)と呼ばれる消費税に関しては、一般的に10%が標準税率となりますが、輸出時はゼロ税率の適用が可能です。
インドネシアでは、所得税法やVAT法が改正されるタイミングが比較的多く、その運用に現地慣行が色濃く影響することもあるため、専門家の助力が欠かせません。特に製造業や飲食関連など、ライセンスや検査が必要な業種では、税務当局や貿易省とのやり取りが増えがちです。
マレーシアの法人税とSST(Sales and Service Tax)復活の経緯
マレーシアの法人税率は一般的に24%で、ASEAN内でも中程度の水準とされます。また、マルチメディア・スーパーコリドー(MSC)をはじめとした特定エリアやハイテク産業には特別優遇税制が設けられている場合があります。
かつてマレーシアでは物品サービス税(GST)が導入されていましたが、政権交代の影響などで2018年に廃止され、現在はSST(Sales and Service Tax)という方式に戻っています。SSTは売上税(5〜10%)とサービス税(6%)から成り、その適用範囲や税率が業種ごとに細かく区分されています。GST時代とは計算方法や申告手続きが異なるため、最新のガイドラインを確認する必要があります。
フィリピン・シンガポール:独自の税制と優遇策

最後に、フィリピンとシンガポールについて見ていきます。フィリピンは英語が通じる人口が多く、BPO産業やサービス分野の伸びが期待される国です。シンガポールはアジアの金融センターとして知られ、外資企業誘致にも積極的な姿勢を示しており、法人税やGST制度が整備されています。
フィリピンの法人税改正(CREATE法)とVAT免除
フィリピンの法人税率は、2021年に施行されたCREATE法(Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act)によって段階的に引き下げられています。大企業向けには従来30%の法人税率が25%に下げられ、中小企業(所得が500万ペソ以下)には20%まで引き下げが適用されるなど、投資環境改善を目指す動きが進んでいます。
消費税に相当するバリュー・アドデッド・タックス(VAT)は基本12%で、輸出取引や特定業種に対してはゼロ税率あるいは免除が設定されています。ただし、VATの還付手続きには時間がかかることもあり、特に輸出型ビジネスを行う企業はキャッシュフロー計画を慎重に立てる必要があります。公的機関(フィリピン投資委員会やPEZA)による投資優遇制度との組み合わせによって、法人税率やVAT負担が一部軽減される場合もあるため、適用要件をしっかり確認しましょう。
シンガポールの法人税率・GST・タックスホリデーなどの投資誘致策
シンガポールの法人税率は一律17%で、アジアの主要国の中でも低めの水準となっています。また、各種の投資奨励策や優遇税制(例えばパイオニア・インセンティブや金融セクターにおける特別措置など)が充実しており、外資企業の地域統括拠点として人気の高い国です。政治・経済的な安定や英語の公用語化も相まって、多国籍企業がアジア戦略の拠点とするケースが少なくありません。
消費税にあたるGST(Goods and Services Tax)は長らく7%でしたが、2023年に8%へ引き上げられ、今後2024年以降はさらに9%へ引き上げが予定されています。輸出取引や国際サービスにはゼロ税率が適用される場合が多く、サービス業を中心とする企業にとっても比較的分かりやすい仕組みです。また、タックスホリデーと呼ばれる特定期間の法人税免除措置や、スタートアップ向けの税制優遇など、多角的な投資誘致策も整備されています。
まとめ

東南アジアの主要6か国(タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール)に焦点を当て、「法人税・消費税」の視点で比較してきました。各国とも経済成長が著しく、投資誘致の動きが活発ですが、税率や制度、優遇措置の有無は大きく異なります。加えて、消費税(VATやSST、GSTなど)の課税範囲や還付手続きも国によって違いがあり、事前の情報収集が不可欠です。
- タイ:法人税20%が基本。投資委員会(BOI)の優遇策で法人税免除などが得られる場合あり。VATは7%が基本。
- ベトナム:法人税20%。特定の投資エリアで優遇。VATは10%が標準で、輸出はゼロ税率。Red Invoice管理が重要。
- インドネシア:法人税は近年改正され22%前後(さらに20%への引き下げ可能性あり)。付加価値税(PPN)は10%。
- マレーシア:法人税24%。SST方式を採用(売上税5〜10%、サービス税6%)。過去にGSTからSSTへ戻るなど制度変更あり。
- フィリピン:法人税はCREATE法で大企業25%、中小企業20%。VAT12%が基本だが免除・ゼロ税率措置も。投資優遇エリアあり。
- シンガポール:法人税17%と低水準。GSTは2023年に8%へ、将来的に9%への引き上げ予定。タックスホリデーや投資優遇多数。
いずれの国でも、税制は政治・経済情勢の変化に伴って改正される可能性があるため、最新情報のキャッチアップが重要です。企業としては、現地法人を設立するのか、パートナー企業を通じて販売するのか、ライセンス契約や越境ECにするのかなど、ビジネス形態に応じて税務戦略を設計しなければなりません。公的機関(JETROなど)のカントリーレポートや専門家の助言を受けながらシミュレーションを行うことで、不要なリスクを避けつつ最適な進出スキームを構築できるでしょう。
本記事で紹介した税率や制度は執筆時点の情報であり、法改正や政権交代などで変わる場合があります。海外での法人税や消費税を正確に把握するためには、現地の税務当局や最新の法令をチェックしたり、税理士や会計士、コンサルタントのサポートを受けるのが安心です。長期的な視点で「どの国にどの形で進出するか」を考え、税務面でも戦略的なアプローチを取ることが、東南アジアビジネスで成功する鍵になるはずです。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
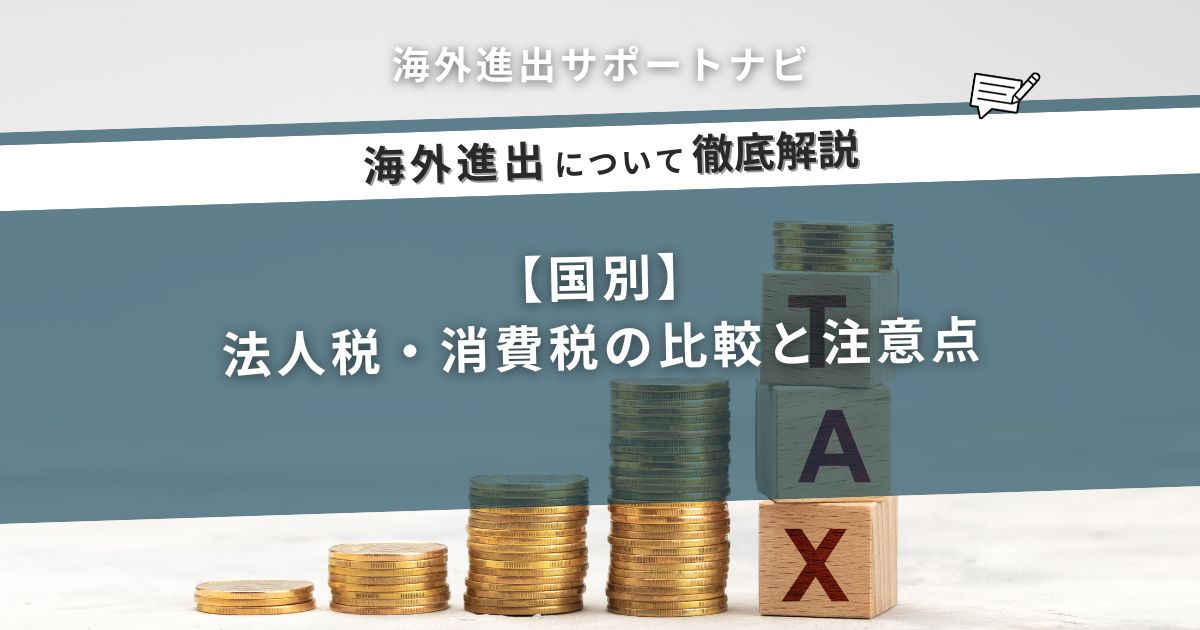
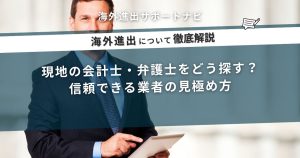
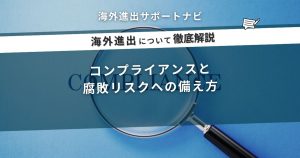
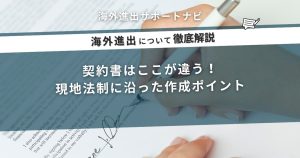
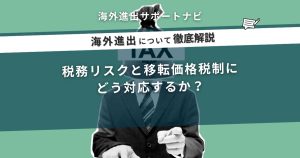

コメント