東南アジアの市場は、近年めざましい成長を遂げており、日本企業の海外展開においても注目度が高まっています。タイやベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールなど、人口規模や経済成長率、投資誘致策などを背景に、多くの企業が「海外契約」に関する情報を求めているのが実情です。しかし、いざ現地で契約書を作成しようとした際、言語や文化的な違いだけでなく、法律制度やビジネス慣習が大きく異なるため、戸惑うケースが少なくありません。
たとえば、英語が通じると思っていた国でも、公式文書はローカル言語で作成・提出が求められることがある一方、日本語や英語を使った契約書がそのまま法的に有効なのかどうか、不安を感じることもあるでしょう。さらに、契約書に盛り込むべき条項や仲裁方法、裁判管轄の選定など、東南アジア各国では日本とは大きく異なるポイントが存在します。こうした点を正しく理解していないと、後々トラブルに発展し、想定外のリスクやコストを負う可能性があります。
本記事では、東南アジアにおける「契約書はここが違う!」という視点から、現地法制に沿った作成ポイントを丁寧に解説します。海外 契約を結ぶうえで注意すべき共通事項や国別の特徴を整理しながら、初心者でも読みやすい形でまとめました。JETROなど公的機関の情報や実務での経験に基づく事例も交えつつ、企業が無用なリスクを回避しながらスムーズにビジネスを進めるためのヒントを提供します。
なぜ海外契約の作成で現地法制が重要なのか

海外の相手先とビジネスを行う際、契約書が単なる形式的な書類にとどまらず、法的拘束力を持つ「ルールブック」として機能します。ましてや東南アジアの国々では、日本とは違う法体系や文化背景が存在するため、契約書における一文が大きな意味を持つことも少なくありません。まずは、この現地法制を理解する意義と、その背景にあるトラブル事例や公的機関のデータに目を向けてみましょう。
東南アジアにおける法的リスクとビジネスチャンス
タイやベトナム、インドネシアなどの国々では、経済成長に伴い新たなビジネスが次々に生まれています。若年人口が多く、消費需要が拡大する中で、日本企業も積極的に合弁会社を作ったり、代理店契約を締結して販路を広げたりといった動きが盛んです。一方で、法的リスクも高まりつつあることを忘れてはなりません。
例えば、ローカル法制に反した契約条文や、不当に一方の当事者が有利になるような規定が含まれている場合、契約そのものが無効とみなされる可能性があります。さらに、紛争が生じた際に裁判所がどのように条文を解釈するのか、仲裁機関を利用する場合の手続きをどう定めるかなど、国ごとのルールを踏まえた設計が欠かせません。こうした法的リスクを軽減しつつ、大きなビジネスチャンスを逃さないためには、契約書の段階から慎重な検討を行う必要があります。
公的機関(JETROなど)のデータから見る契約トラブル事例
日本貿易振興機構(JETRO)や各国の商工会議所が公表するレポートには、海外での契約トラブル事例が数多く掲載されています。その中には、以下のようなケースが含まれます:
- 契約書を英語だけで作成したが、現地法ではローカル言語が優先され、裁判で認められなかった
- 仲裁条項を含んでいたものの、実際に紛争が起きた際に仲裁機関が国外にあり、相手が応じなかった
- 準拠法を日本法としていたが、現地での強行法規に抵触する部分があり、その部分が無効と判断された
こうした事例は決して珍しいものではなく、対処を間違えると大きな損失や信用失墜につながります。逆に言えば、契約書をきちんとローカライズし、現地法制に合致する形で締結していれば、多くの紛争やコストを事前に回避できる可能性が高まるわけです。
東南アジア各国で異なる契約法制の基本ポイント

では、具体的に東南アジア主要国(タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール)における契約法制はどうなっているのでしょうか。それぞれの国が持つ特徴や、注意すべき点を概観していきます。
タイ:契約言語・文化要素、仲裁条項の扱い
タイでは、法律上、契約書を必ずしもタイ語で作成しなければならないわけではありませんが、実務としては「タイ語版」を用意するか、英語版とタイ語版を並行して作成する企業が多いです。特に、タイ語の書面が裁判所や公的機関で重視されやすいケースがあり、英語だけの契約で合意していても、現地訴訟時に不利になるリスクが考えられます。
また、契約トラブルが起きた場合に備えて、仲裁条項を入れる企業が増えていますが、タイ国内の仲裁機関を利用するか、シンガポールなど第三国の仲裁機関を利用するかで、手続きの難易度や費用が変わってきます。さらに、タイは微笑みの国といわれるように、商習慣や文化で「表立った対立」を避ける傾向が強いという特性があります。そのため、契約上のコミュニケーション手段を明確に定めることで、後々の誤解や感情的対立を避けることが望ましいでしょう。
ベトナム:ローカル言語契約と英語版の使い分け
ベトナムでは、基本的に契約書がベトナム語で作成されることが多く、英語版を併用する場合もありますが、現地法での裁判においてはベトナム語文書が優先される傾向があります。また、ベトナム国内での取引では「公証役場で認証を得るべき契約種類」が存在する場合もあり、ローカル法の定めに従う必要があります。
さらに、ベトナムでは赤インボイス(Red Invoice)制度などがあるように、書類の厳格な管理が求められます。契約書だけでなく、関連する納品書や請求書などが適正な形式を満たしていないと、紛争時に証拠として認められにくいケースもあります。英語契約を使う際も、ベトナム語訳と相互参照できる形で整えるなど、トラブルを未然に防ぐ工夫が必要でしょう。
インドネシア:印紙税や外国語使用の注意点
インドネシアでは、「バハサ・インドネシア語(インドネシア語)」での契約作成が推奨されており、法律上もインドネシア語の契約書を用意することが望ましいとされています。英語との二言語契約形式にする場合は、どちらの言語版を優先するか、明記しておくのが通例です。また、印紙税(Meterai)を貼付しないと契約書としての効力が認められにくい場合があるなど、実務面で特有のルールが存在します。
さらに、インドネシアは宗教や習慣の多様性が高い国でもあり、商取引において「ハラル認証」や「地域慣習法(アダット法)」などが意外な形で影響を与えることがあります。契約締結時には、ローカルパートナーや法律事務所を通じて、現地の文化・慣行に合った形の文言や条項を検討することが望ましいでしょう。
マレーシア:英語が主体だがローカル法の要確認
マレーシアは、英語がビジネス上で広く通用する国の一つです。英語で作成した契約書は法的にも認められる場合が多く、特に外国企業間の取引では英語のみの契約書を利用することも珍しくありません。しかし、マレー語(バハサ・マレーシア)が国語であるため、一部の行政手続きや公証においてはマレー語訳を求められる可能性もあります。
マレーシアでは、州によってイスラム法(シャリーア)が適用される範囲が異なるなど、地域差がある点も見落としがちです。契約対象がハラル製品や金融サービスなどの場合、シャリーア・コンプライアンスが追加要件となるケースがあるため、事前に調査が必要です。また、販売代理店契約やフランチャイズ契約などに関しては、ローカル法で特別な規制がある場合もあるので、条文の作り込みに細心の注意を払いましょう。
フィリピン:英語対応が可能でもローカル慣習に注意
フィリピンでは英語が公用語の一つとして使われるため、契約書を英語で作成する企業が多く見受けられます。しかし、その一方で、裁判所や行政機関での手続きがすべて英語でスムーズに進むわけではない場合もあります。特に地方自治体との契約や許認可取得に絡む場合、タガログ語での補足説明を用意する必要があるかもしれません。
また、フィリピンは労働慣行やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)に関する法律などで独自の規定を持ち、そうした分野の契約では細かい条文調整が必要です。企業がコールセンター事業を委託する際など、サービスレベルアグリーメント(SLA)をどのように設定するかで紛争が発生するケースもあるため、法律事務所を通じて契約書をチェックするのがおすすめです。
シンガポール:コモンロー系、英語契約が中心
シンガポールはコモンロー(イギリス系)をベースとした法体系を持ち、ビジネス上の契約書は英語で作成・締結するのが一般的です。国際商事仲裁の拠点としても知られ、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)は多くの外国企業が紛争解決の場として利用しています。契約書に仲裁条項を入れる場合、SIACを指定する例も多いです。
ただし、英語が公用語だからといって油断は禁物です。シンガポール独自の法規(例えば個人情報保護法など)に抵触しないか、法人税や消費税(GST)に関する条文をどう扱うかなど、ローカルのルールへの配慮が求められます。M&Aや投資契約などでは、現地の弁護士を活用して慎重に契約内容を検証することが一般的です。
契約書作成で押さえるべき主要条項

ここでは、東南アジア各国で契約書を作成する際に共通して意識しておきたい条項を挙げ、それぞれのポイントを解説します。もちろん、各国の法制や取引内容によって微調整が必要ですが、一般的なビジネス契約で盛り込むべき要素を把握しておくとスムーズに進められるでしょう。
当事者・目的・期間・対価・支払条件
契約書の冒頭で明確にすべきなのは、当事者の正式名称と所在地、契約の目的(例えば「商品の販売」「製造委託」「技術ライセンス」など)、および契約期間や更新方法です。東南アジアでは、現地法人と契約を交わす場合に会社名の英語表記・ローカル表記を両方記載するケースも少なくありません。
さらに、契約の中心となる対価(価格や手数料、ロイヤルティなど)と支払条件(通貨、支払期日、支払方法、遅延利息など)を明確にすることで、後々の金銭トラブルを防げます。ローカル通貨を用いる場合は為替リスクへの配慮、ドル建てや円建てであれば為替差損益の負担をどうするかなども考慮すると良いでしょう。
準拠法・裁判管轄・仲裁条項の設定
海外契約においては「どの国の法律を準拠法とするか」を決めることが非常に重要です。相手国の法律を採用すると自社に不利な規定が多くなる場合もあれば、日本法を主張しても現地の強行法規に抵触するリスクもあります。また、裁判管轄を日本の裁判所にするのか、現地裁判所にするのか、あるいは国際仲裁機関を指定するのかも大きな争点です。
例えば、シンガポールを国際仲裁の場に指定する企業は多いですが、相手国が仲裁判断を実際に執行してくれるかは別問題となります。仲裁条項を設定する際は、その仲裁機関の管轄や執行力、手続き費用も見積もりに入れながら慎重に検討しましょう。
不可抗力・機密保持・競業避止などの特約
契約条項の中には、状況に応じて特約や付随条項を盛り込むケースが多いです。不可抗力条項(Force Majeure)では、天災や戦争、法律改正などのやむを得ない事由により契約不履行が生じた場合の責任免除を定めます。東南アジアは自然災害や政治的変動が起きやすい地域でもあるため、この条項をどの程度まで認めるかが重要です。
また、機密保持条項(NDA)や競業避止義務の規定についても注意が必要です。一部の国では、過度に広範な競業避止を設定すると違法となる場合もありますし、機密情報の定義を明確にしておかないと十分に保護が及ばない可能性があります。さらに、個人情報保護法制が急速に整備されつつある国もあるため、個人情報や顧客データの取り扱いについても契約で言及することが望ましいでしょう。
ローカル言語・英語契約の使い分けと翻訳リスク
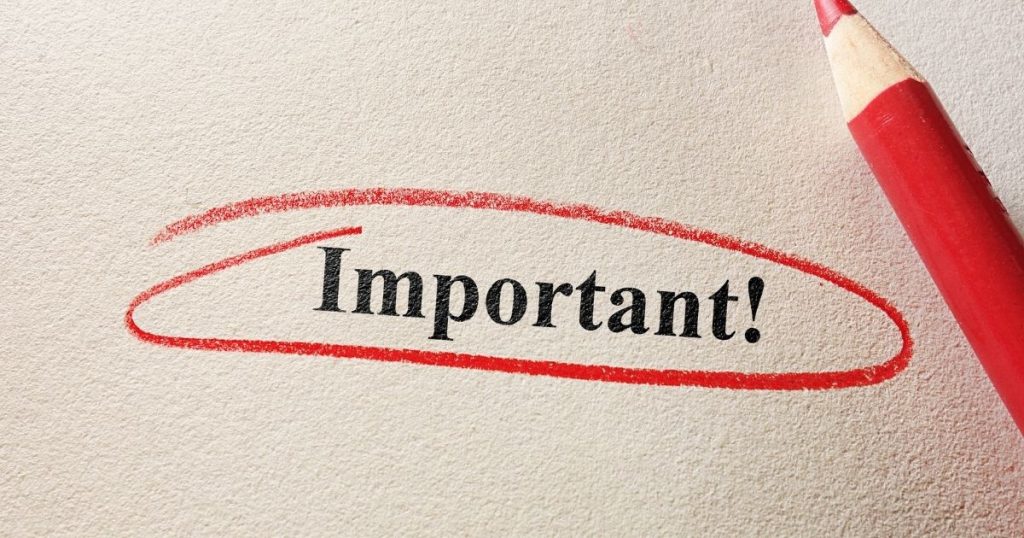
東南アジアの多くの国でビジネスをする際、契約言語として英語を用いるのが一般的ですが、必ずしもそれだけで済むわけではありません。ローカル言語での契約が法的に優先される場合や、公的機関への提出で現地語を求められるケースもあります。ここでは言語面での注意点と、翻訳リスクの対処法を確認します。
二言語契約の注意点(どちらが正本か)
英語とローカル言語(タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マレー語など)の両方を併記した「二言語契約」は、当事者が言語の壁を超えて合意内容を共有できるメリットがあります。しかし、万一条文のニュアンスが食い違う場合、どちらを優先するのかを契約書で明確にしておかないと、紛争発生時に深刻な対立を招くリスクがあります。
例えば、「本契約は英語版を正本とし、ローカル言語版は参考訳とする」といった条項を入れる方法や、逆に「ローカル言語版を正本とし、英語版は参考とする」と定めることも可能です。どちらを正本にするかは交渉次第ですが、現地裁判所や仲裁機関がどちらを尊重しやすいかも考慮する必要があります。
翻訳のずれによるトラブル事例
翻訳作業でありがちなトラブルとして、専門用語や法的表現が英語とローカル言語で微妙に食い違い、結果的に契約上の権利義務が変わってしまうケースが挙げられます。特に、技術ライセンス契約や知的財産契約、長期的な製造委託契約などでは、細かい定義や範囲が翻訳のずれによって大きな差を生むことがあり、注意が必要です。
翻訳コストを節約しようと自動翻訳ツールを使ったり、現地語の分かるスタッフに片手間でお願いしたりすると、後になって取り返しのつかない問題が発覚する可能性があります。できれば法律専門の翻訳業者や弁護士などを介して、慎重に表現を検討するのが理想的です。
公証・認証制度の有無
国や取引内容によっては、公証役場などで契約書を認証する手続きが必要になる場合があります。例えば、インドネシアで土地・不動産に関する契約を結ぶ際には公証人の立ち会いが義務付けられるケースがあるほか、ベトナムで特定の契約を正式化するために公証が求められる事例も存在します。
また、海外で結んだ契約書を日本国内で効力を発揮させたい場合には、外務省や在外公館を通じて認証手続きを行うことも考えられます。どの段階で、どの機関の認証が必要かは取引対象や国によって違うため、現地の法律事務所に事前に確認すると良いでしょう。
契約交渉・レビュー時に留意する実務ポイント

「契約書はここが違う!」と実感する場面が最も多いのは、実際の交渉やレビューの場面かもしれません。ローカルパートナーと合意内容をすり合わせるプロセスで、どのように言葉を選び、どのようなリスクを想定しておくべきか、具体的な実務の注意点を紹介します。
ローカルパートナーとの交渉プロセスと対話
東南アジアのパートナー企業や代理店と契約を結ぶ際、いきなり詳細な契約書ドラフトを示して「サインしてください」と迫っても、相手が抵抗を感じるかもしれません。特に、メンツや信頼関係を重視する文化圏では、丁寧な意思疎通と段階的な合意形成が大切です。メールやチャットツールだけでなく、ビデオ会議や直接訪問を通じて相互理解を深めるとスムーズに話が進むでしょう。
交渉時には、争点となりやすい条項(価格、支払条件、独占権、契約期間、紛争解決など)をリストアップし、優先度を明確にすることが大事です。相手の主張や文化的背景を尊重しつつ、自社が譲れない部分もはっきり伝えることで、後々のトラブルを避けやすくなります。
弁護士・コンサルタントの活用でリスク軽減
現地の法制度に詳しい弁護士やコンサルタントを活用するのは、海外契約におけるリスクを大きく下げる有効な手段です。契約書を一から自社で作成・交渉する場合でも、最終的には専門家によるリーガルチェックを受けることで、条文の抜けや違法要素を事前に修正できるでしょう。
また、国際契約に精通したコンサルティング企業に依頼すれば、相手国の商習慣や業界動向を踏まえた実務的なアドバイスを得られる可能性もあります。コストはかかるものの、契約トラブルや裁判に発展した際に生じる損失と比べれば、むしろ安い投資となるケースが多いです。
法改正情報や公的機関情報の取り入れ方
東南アジアは法改正が比較的頻繁に行われる地域であり、ビジネス法制が短期間で変わることも珍しくありません。日本貿易振興機構(JETRO)や在外公館、各国投資庁などが定期的に発行するニュースレターやガイドブックをチェックし、契約に影響を与えるような法改正情報が出たら素早く契約条項を見直す体制を整えたいところです。
さらに、企業が複数国でビジネスを展開している場合、特定の国での法改正がグループ全体の契約ポリシーに波及することもあります。例えば、ある国で禁止された条項が近隣国にも波及する形で規制強化されるケースなどがあり、常にアンテナを張っておくことが重要です。
まとめ

東南アジアでビジネスを展開する際、「契約書はここが違う!」と痛感する場面は多々あります。日本の常識や欧米型の契約観とは異なる文化・法制度が存在するため、海外 契約のポイントをしっかり押さえておかなければ、後から大きな代償を払う恐れがあるのです。最終的なリスク回避と円滑なビジネス推進のためにも、以下の点を改めて確認しておきましょう。
- 東南アジア各国が持つ法文化を理解する:タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールは、それぞれ異なる法律体系や商習慣を持つ。契約書は各国法制に沿った形でローカライズする必要がある。
- 英語だけではなく、ローカル言語の契約が優先される場合もある:二言語契約を結ぶ際は、どちらが正本なのかを明記し、翻訳のずれによる誤解を回避する工夫が大切。
- 仲裁条項や裁判管轄、準拠法の設定がトラブル回避に重要:紛争が起きた際にどこでどう解決するかを明確にしておくことで、不当な費用や時間の浪費を避けられる。
- 不可抗力・競業避止・機密保持などの特約をしっかりと盛り込む:国によって通用する範囲が違うため、ローカル法を踏まえた条文を細かく検討する。
- 公的機関や専門家を活用して法改正情報を常にアップデート:JETROや投資庁の情報、現地の弁護士・コンサルタントの助力によって、定期的に契約書を見直す仕組みを作ると安心。
こうしたステップを踏むことで、海外 契約にまつわるリスクを最小限に抑えながら、現地のビジネスパートナーや顧客との良好な関係を築ける確率が高まります。契約書はビジネス上のトラブルを未然に防ぎ、相互信頼を固めるための重要なツールです。ぜひ本記事で得た知識を活かして、現地法制に合致した契約書を作成し、安心して東南アジアのビジネスを推進していってください。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
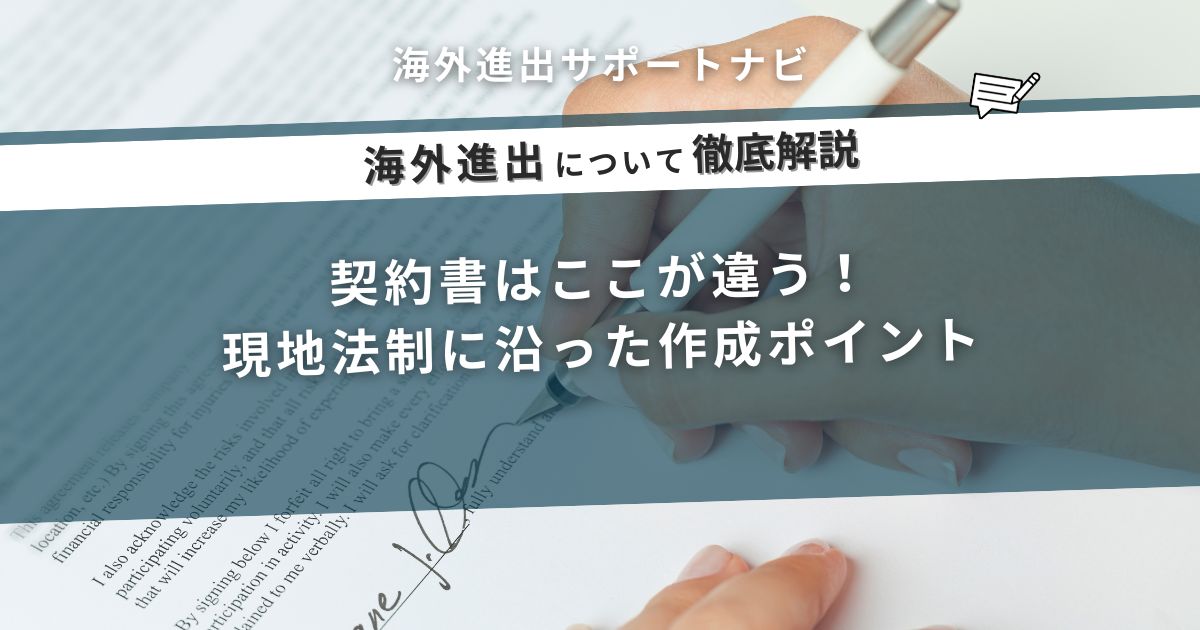
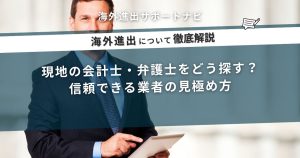
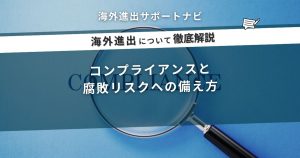
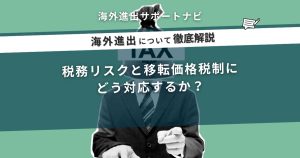

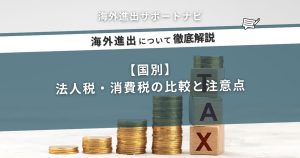
コメント