オンライン技術やデジタルコミュニケーションが急速に発展する一方で、実際に人と人が対面する「オフライン展示会・商談会」の存在感は依然として大きいものがあります。特に海外進出を検討する企業や、新規顧客の獲得を狙う事業者にとっては、展示会や商談会が直接的なビジネスチャンスを創出する場となり得ます。しかし、実際に出展してみると、思ったほど成果につながらないという声も少なくありません。どうすれば限られた時間とコストのなかで成果を最大化できるのでしょうか。
本記事では、オフラインでの「展示会成果」を上げるためのポイントを網羅的に解説します。まずはなぜリアルなイベントが重視されるのか、その背景を確認し、続いて事前準備・ブース設計・商談の進め方・アフターフォローなど具体的なステップを紹介。公的機関(JETROなど)が発表する統計データや経験豊富な企業の事例を踏まえながら、初心者にもやさしくまとめていますので、「これから展示会に出てみたいけれど、どうやって成果を上げるか分からない」という方はぜひ参考にしてください。
オフライン展示会・商談会で成果を出す理由と最新動向

オンラインでの情報収集や営業活動が一般化する昨今でも、実際の「場」で人と会い、商品やサービスを直接見てもらうことの価値は軽視できません。ここでは、なぜオフラインの展示会・商談会が依然として注目されているのか、その背景を探っていきます。あわせて、公的機関のデータを通じて最新の動向を確認しましょう。
デジタル時代でもリアルな接点が重要な背景
コロナ禍を経て、オンライン商談やウェビナーが急速に普及しましたが、一方で「リアルに会うことで得られる信頼感や熱量」はオンラインにはない強みがあります。特に新興国を含む海外市場への進出を狙う企業にとっては、現地のバイヤーやパートナー候補が一堂に集まる展示会・商談会は、効率的に「顔の見える」ビジネス関係を構築できる貴重な機会です。
実際に商品を手に取って確認したり、デモンストレーションを間近で体験できたりすることは、オンラインカタログや動画だけでは伝わりにくい情報を補完します。さらに、その場で疑問点や要望を直接やりとりすることで、「この企業は信頼できそうだ」「思った以上に要望を聞いてくれそうだ」といった具体的な印象を与えやすいのです。
公的機関(JETROなど)のデータから見る展示会の価値
日本貿易振興機構(JETRO)が発表する海外ビジネス支援関連のレポートでも、展示会や商談会への出展効果が度々言及されています。JETROの調査によると、海外展示会でブースを構えた企業のうち、多くが「即時の成約には至らなくても、アフターフォローを行うことで半年〜1年後に大口契約が成立した」といった事例を挙げています。つまり、展示会そのものはあくまで「きっかけ作り」の場であり、その後のフォローアップ次第で大きく成果が変わるというわけです。
また、経済産業省がまとめた資料によると、製造業やIT企業だけでなく、食品や農産物など幅広い業種で海外の展示会を活用する動きが強まっているとのことです。海外バイヤーや投資家が一堂に会する機会は限られているため、わざわざ現地に足を運んでも得られるリターンが大きいという認識が広がっているのではないでしょうか。
準備段階で大切になる3つのポイント

オフライン展示会や商談会で「展示会 成果」を求めるなら、まずは事前準備が肝心です。限られた会期やブーススペースで最大限のパフォーマンスを発揮するために、以下の3つのポイントに注目しましょう。
目的設定とターゲットの明確化
何をゴールとするのかを明確にしないまま出展してしまうと、成果を計測しにくく、出展コストに見合ったリターンが得られない可能性があります。例えば「海外代理店の発掘」なのか、「自社ブランドの認知度アップ」なのか、「短期的なリード獲得」なのか。目的が異なれば、ブースの作り方やスタッフのアクションも変わってきます。
また、どのような層をターゲットにするのかも重要です。業界バイヤーなのか、一般消費者なのか、あるいは現地政府機関やメディアなのか。ターゲット層によって配布する資料の内容やデモンストレーションの仕方が変わってくるでしょう。対象が明確であればあるほど、展示会当日に焦点を絞ったアピールができます。
ブース位置選定や出展社マニュアル確認
展示会会場のブース位置選定は、集客力に大きく影響します。メイン通路に面しているかどうか、近くに競合や大型企業のブースがあるかどうかなど、申し込みのタイミングや出展社マニュアルに記載の条件によって配置が決まるケースも多いので、主催者との交渉を早めに始めるとよいでしょう。
また、電源やインターネット回線の確保、搬入・搬出時のルール、会場の装飾規定などは「出展社マニュアル」に細かく記載されています。これを熟読していないと、展示会直前や会場設営時にトラブルが発生することも。特に海外での展示会では言語の壁や文化の違いもあり、想定外の制約がある場合があるので注意が必要です。
現地語の資料・パンフレット準備の重要性
海外市場で展示会に出るなら、現地語(英語を含む)に対応した資料やパンフレットを準備しておくことが望ましいです。ブースに訪れた人が母国語で製品情報を読めると、それだけで親近感を抱きやすく、会話のきっかけをつかみやすくなります。英語が通じる国であっても、専門用語や固有名詞をローカル言語で示すと理解が深まる場合があります。
また、資料のデザイン面でも、ローカルユーザーに好まれる色使いやレイアウトを取り入れると効果的です。各国の文化や宗教的背景に合わない表現を避けることも忘れないようにしましょう。細部に気を配ることで、他の海外企業とは違う「丁寧な対応をする企業」という印象を与えられます。
魅力的なブースデザインとアピール手法

十分な準備を行ったら、次はいよいよ展示会当日のブース作りです。ブースが通りがかった人の目を引き、立ち寄りたくなる雰囲気を作り出すことが「展示会 成果」を上げるための第一歩となります。以下では、ブースデザインやスタッフの動き方などを具体的に探ります。
視覚的に目を引くレイアウトや看板
来場者は多数のブースを見て回るため、如何にして一瞬で興味を持ってもらうかが勝負です。大きく分かりやすい看板や、目を引く配色、シンプルなキャッチコピーなどを活用し、遠目からでも「何を扱っている企業か」がひと目で伝わるようにすることが大切です。
加えて、大きなモニターやディスプレイを設置して動画を流す方法も有効です。製品紹介や使用例を映像で見せると、説明の手間を軽減できるだけでなく、注目度を高めることができます。ポイントは、動画や画像が途切れずに繰り返し流れるよう設定し、音量や画質にも配慮することです。
適切なスタッフ配置と接客マニュアル
ブース内でどのスタッフがどの位置に立ち、来場者へどうアプローチするかも重要な戦略です。入り口付近にスタッフを配置し、「こんにちは、何をお探しですか?」などと明るく声をかけられる体制を整えることで、通り過ぎようとする人を引き留めやすくなります。英語や現地語が堪能なスタッフを配置すれば、訪問者が話しやすい雰囲気を作れます。
また、事前にスタッフ間でロールプレイや接客マニュアルを共有しておくと、全員が同じレベルで製品知識や商談の進め方を理解している状態を作れます。質問が来たときに答えに詰まってしまうと、せっかくの来場者の興味が失われる可能性があるため、スタッフ教育には力を入れるべきです。
ノベルティ・サンプリング・デモンストレーションの活用
ノベルティや試供品(サンプリング)を配布する方法は、展示会での定番といえます。来場者が手に取って持ち帰るものがあると、後日思い出してもらいやすくなります。ただし、配るだけで終わらないように、「詳細を知りたい方は名刺をいただけますか?」など、リード獲得に繋げる一言を添えると有効です。
さらに、実際に商品を動かして見せるデモンストレーションは、特に技術系や食品系の企業にとって強力なアピール手段です。目の前で操作や調理、味見などを体験してもらうと、テキストや写真だけでは伝わらない魅力をダイレクトに感じてもらえます。見せ方を工夫することで、周囲のお客さんも引き寄せる効果が期待できます。
商談の進め方とリード獲得のコツ

ブースに人を集められたとしても、実際の商談へ発展できなければ「展示会 成果」としては物足りません。短い時間で効率的に自社製品やサービスをアピールし、具体的な商談相手やパートナー候補を獲得するための進め方を見てみましょう。
短時間での効果的なプレゼンや製品説明
展示会場では多くのバイヤーや来場者が限られた時間内に多数のブースを回るため、一度に取れる時間は長くありません。したがって、商談を切り出す際には最初の1〜2分で要点を伝え、相手の興味を引く必要があります。例えば、結論から述べて相手に質問を投げかける、あるいは実績や導入事例を先に提示し、「当社の○○が御社の課題解決に役立つと思います」といった短いキャッチフレーズを用意しておくとスムーズです。
資料を見せる場合も、文字だらけではなく、写真や図解などビジュアル要素を多用したものが好まれます。もし英語が共通言語として通じるのであれば、簡潔な英語版のプレゼンシートを作成しておき、詳細を補足で説明できるように準備しておくとよいでしょう。
競合との差別化を伝えるポイント
展示会場には競合企業も出展している場合が多く、ブースを回るバイヤーからすると「どこも似たような製品に見える」と感じるケースもあります。そんな中で差別化を図るには、自社が持つ独自の技術やサービス、あるいは価格面での優位性やサポート体制などを端的にアピールすることが大切です。
例えば、他社にはない特許技術や製造プロセスがある、納期短縮につながる独自の物流ネットワークがある、日本品質による信頼性を打ち出せるなど、相手が「それなら興味があるかもしれない」と思えるフックを提示します。ただし、一方的な自慢に終わるのではなく、相手の課題やニーズを聞き取り、それに対するソリューションとして提案する形が望ましいです。
リード情報の管理と名刺交換のフォロー体制
商談の最後に重要なのが、リード情報の取得とその後のフォローアップです。名刺交換や連絡先の入力フォームを活用し、興味を示してくれた相手の情報を確実に管理しましょう。展示会中は忙しく、複数の名刺が乱雑になりがちですが、最低限「どんな話をしたか」や「どの程度の興味度合いを示したか」をメモしておくと、後日の連絡がスムーズになります。
もしブースでの商談時間が十分取れなかった場合、「後日改めてオンライン商談をしましょう」と提案し、日程調整を行うのも効果的です。展示会の熱気が冷める前にフォロー連絡を入れることで、相手も企業の熱意や対応の早さを評価しやすく、商談継続率が高まります。
フォローアップと関係構築で実績を伸ばす

展示会や商談会は1〜3日程度で終わるケースが多いため、そこで「展示会 成果」を得るのは難しいと思われがちです。しかし、本当の勝負はイベント終了後のフォローアップにあります。ここでは、メールやDMなどを活用したアプローチや、成果を可視化する手法を紹介します。
イベント後のメール配信やDM戦略
展示会で接触した見込み客に対して、イベント終了直後に「お礼メール」を送るのが基本です。ここで、簡単な挨拶とあわせて、自社製品のカタログやウェブサイトURL、担当者の連絡先を添付すると、相手が検討を進めやすくなります。特に海外取引を目指す場合は、英語や相手の母国語でメールを作成し、専門用語を分かりやすく解説する心配りが大切です。
また、印刷したカタログを郵送する際は、宛先やビジネス形態に合った送り先を選定し、到着時期を把握してからフォローコールを行うと効果的です。DMには簡単なパーソナライズ(「展示会でお話しした○○です」など)を加えることで、相手に思い出してもらいやすくなります。
評価会・反省会の重要性と次回への改善
イベント後には社内で評価会や反省会を行い、「どのような来場者が多かったか」「どのターゲット層との商談が手応えがあったか」「ブースのデザインやスタッフ体制に改善余地があったか」などを洗い出しましょう。これにより次回の展示会や商談会での戦略をブラッシュアップできます。特に海外での展示会の場合は、文化や商習慣の違いから予想外の課題が浮上することもあるため、率直な意見交換が重要です。
もし可能であれば、現地パートナー企業やアテンドをお願いしたスタッフにもフィードバックを求めると、より客観的な視点が得られます。成功事例だけでなく失敗事例も共有し、次の挑戦に活かすことで、チーム全体の経験値が高まります。
効果測定(KPI設定)で「展示会 成果」を可視化
「展示会 成果」を判断するためには、定量的なKPIを設定し、イベント前後での数値を比較するのが望ましいです。例えば、以下のような指標が考えられます:
- リード獲得数:名刺交換数や問い合わせフォーム記入数など
- 商談数:実際に詳しい打ち合わせに進んだ件数(展示会中、展示会後)
- 成約率:最終的に受注・契約に至った割合
- ROI(投資対効果):展示会出展費や人件費などのコストをかけ、どれだけ売上・利益が得られたか
もちろん、展示会後すぐに成約につながる場合は稀で、数ヶ月〜1年後に結実するケースも多いでしょう。それでも、定期的にフォローを行い、どの案件がどのタイミングで成約したかを追跡していくことで、展示会出展の費用対効果をおおよそ把握できます。こうしたデータを積み重ねれば、社内での予算承認や次回出展の意思決定にも役立つはずです。
まとめ

オフライン展示会や商談会は、デジタル化が進む時代だからこそ、対面での信頼構築や実物を見せた上での商談が大きなアドバンテージをもたらします。日本国内だけでなく海外進出を狙う企業にとって、展示会・商談会は一度に多くの潜在顧客やパートナーと接点を持つための絶好の機会です。しかし、成果を上げるためには単に出展するだけでなく、下記のポイントを意識して準備・運営・フォローアップを徹底する必要があります。
- オフラインイベントが重要視される理由を理解する:デジタル化が進んでもリアルな接点が持つ説得力と熱量を活かし、「展示会成果」を狙う。
- 事前準備で差がつく:目的設定とターゲットの明確化、ブース位置の選定、現地語資料の用意など、周到なプランニングが成功の鍵。
- ブースデザインとスタッフ対応で印象を左右する:目立つレイアウトや動画デモ、スタッフの接客力が来場者の興味を引き留め、商談へ繋げる。
- 商談の段取りと差別化ポイント:短時間で競合との差別化を伝え、相手のニーズに合ったソリューションを提示。名刺交換後のフォロー体制も欠かせない。
- フォローアップとKPI測定で継続的に成果を追う:展示会後のメールやDM配信、評価会を通じて次回の出展に活かす。ROIなどの指標を把握して経営判断の材料とする。
これらのプロセスを丁寧に実行することで、短期的な受注だけでなく、長期的なビジネスパートナーの発掘やブランド認知の向上にもつなげられます。海外市場での展示会や商談会に初めて臨む方にとっては不安も多いかもしれませんが、JETROなどの公的機関や在外公館、海外ビジネス経験の豊富なコンサルタントを活用すれば、スムーズに準備を進められるはずです。
ぜひ今回の記事をきっかけに、「オフライン展示会・商談会で成果を出すための流れ」を一通り把握し、実際の出展や商談計画に活かしてみてください。対面でのコミュニケーションが生む信頼と熱意は、オンラインだけでは得られない大きな武器となるでしょう。時間と労力をかけるだけの価値が、きっとそこにあります。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
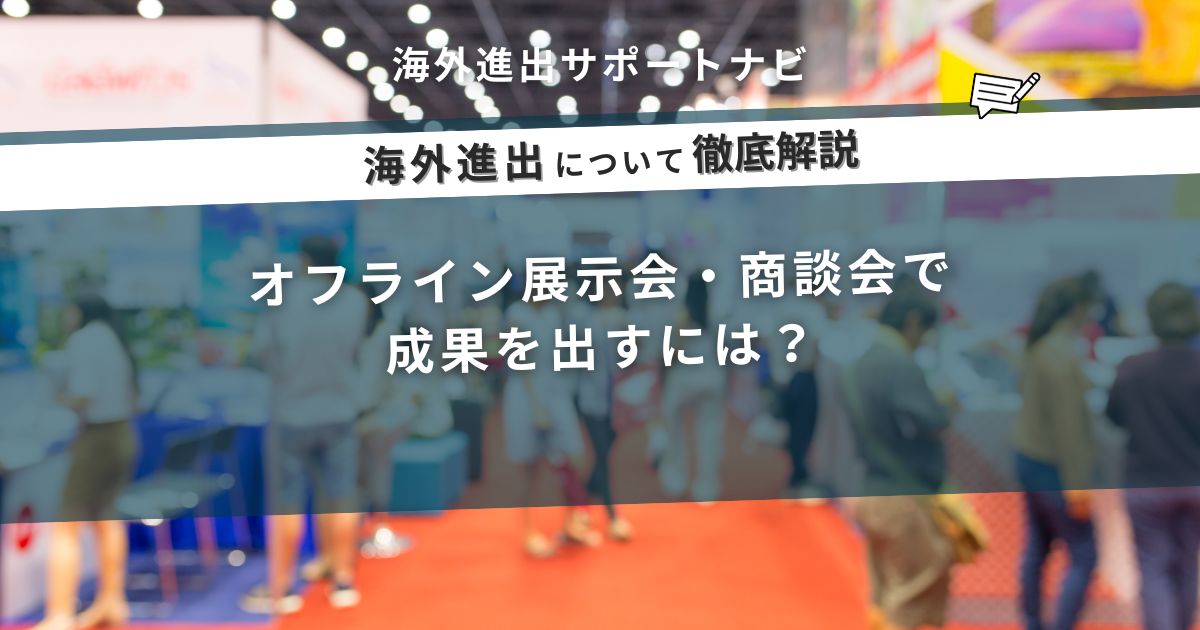
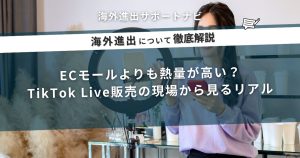
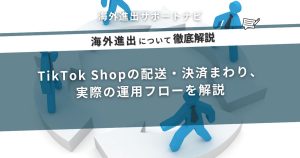


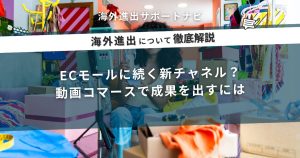

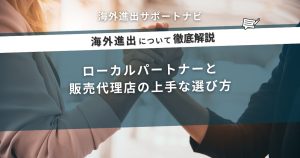
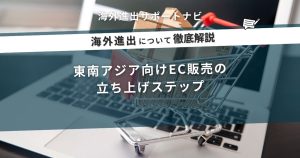
コメント