東南アジアにおけるEC市場の中でも特に注目を集めているのがインドネシアです。人口の多さやスマートフォンの普及率の高さを背景に、オンラインショッピングを利用する消費者が急増し、国内外の企業が続々と参入しています。一方で、市場規模が拡大しているからといって、誰しもが簡単に成功できるわけではありません。
インドネシアのEC市場で成果を上げるには、「ローカライズ」「物流」「価格・プロモーション戦略」といった要素をバランスよく押さえる必要があります。しかし、こうした要素を軽視したり理解を誤ったりすることで、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうケースが後を絶ちません。
本記事では、インドネシアECに参入した際に多くの企業が陥りがちな3つの失敗パターンを解説します。あらかじめ失敗しやすいポイントを知っておくことで、リスクを回避し、安定的に売上を拡大していくためのヒントを得ていただければ幸いです。
インドネシアEC市場の魅力と参入企業の増加

インドネシアは約2億7千万人を超える人口を抱え、世界第4位の人口大国として知られています。若年層の割合が高く、SNSやモバイルアプリを通じたコミュニケーションが日常的に行われているのが特徴です。こうした背景から、オンラインショッピングに抵抗が少なく、スマートフォンさえあればどこからでも簡単に商品を購入できる環境が広がっています。
また、国内ECモール(Shopee、Tokopedia、Bukalapakなど)が積極的なキャンペーンや物流インフラの整備を進めていることもあり、初めてオンライン購入を試みるユーザーが増加している状況です。こうした市場の魅力を背景に、日本を含む多くの海外企業がインドネシアに参入し始めています。ここでは、インドネシアEC市場の魅力と、なぜ多くの企業が注目するのかを掘り下げてみましょう。
人口規模とモバイル中心の購買行動
インドネシアには2億7千万人以上の人口が存在しているため、単純に消費者の母数が非常に大きいという点は魅力です。さらに、国土が広範囲にわたっているため、実店舗へ出向くよりもオンラインで購入した方が便利という地域も少なくありません。
インドネシアのEC事情を語る上で重要なのが、スマートフォンの普及率の高さです。多くのユーザーがパソコンを使わず、スマホのアプリやモバイルブラウザを使って商品を探し、購入するという行動パターンが当たり前になっています。さらに、SNSで情報を収集し、そのままショッピングアプリへアクセスして商品を買うといった流れが一般的です。こうした消費者行動の特徴を理解し、スマホに最適化されたUI/UXやSNSマーケティングを意識しないと、競合に埋もれてしまうでしょう。
なぜ多くの企業がインドネシアに注目するのか
インドネシアは経済成長が続き、今後もEC市場の拡大が期待できると予測されています。ASEAN諸国の中でも特に人口規模が大きいため、中長期的なビジネスポテンシャルはきわめて高いと言えます。さらに、政府や民間企業によるデジタル化推進、インフラ投資の増加が進んでいるため、オンラインショッピングへのハードルが着実に下がっているのが現状です。
また、ShopeeやTokopediaなど、大手プラットフォームがユーザー獲得のために大々的なセールやクーポン配布、ライブ配信機能の拡充などを行っており、オンラインショッピングが「当たり前」の文化になりつつあります。参入障壁が比較的低い反面、新規参入企業が増加していることから、今後はサービスの質やマーケティング戦略によって優勝劣敗が明確化していくと考えられるでしょう。
失敗パターン①:ローカライズ不足によるコンバージョン低下
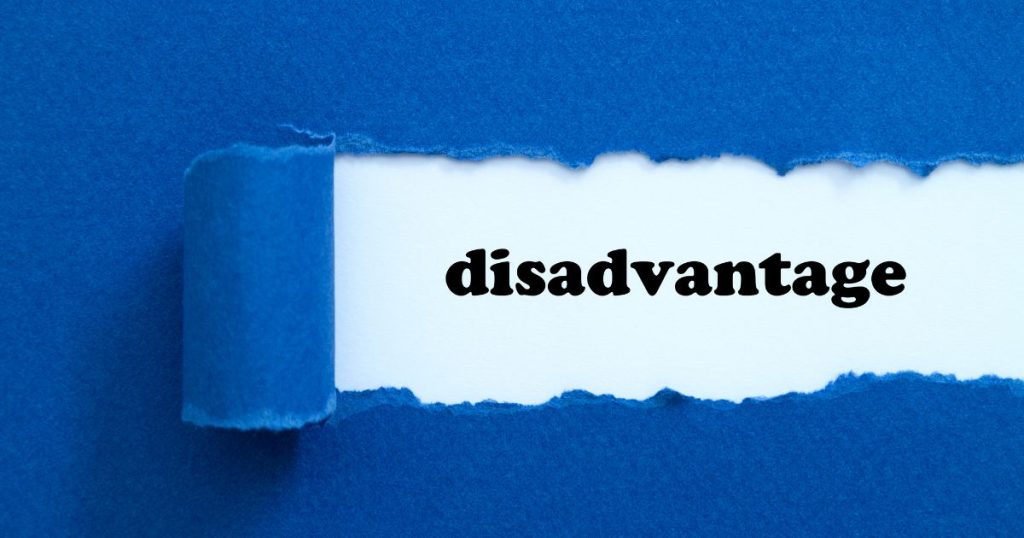
インドネシアのEC市場で失敗してしまう代表的な理由の一つが、「ローカライズ不足」です。どんなに優れた商品であっても、日本国内で成功した販売手法をそのまま当てはめるだけでは、インドネシアの消費者の心をつかむことは難しいかもしれません。なぜなら、言語・文化・習慣が異なるうえに、オンライン上での購買行動も日本とは大きく違う部分があるからです。
ここでは、特に重要となる言語・文化への理解不足、そして商品説明文や対応チャネルの選択ミスがどのようにコンバージョンに影響を与えるかを紹介します。
言語・文化の理解不足がUI/UXに与える影響
インドネシアでは公用語としてインドネシア語(Bahasa Indonesia)が使われます。英語もある程度通じる場合がありますが、国民全体が流暢に使いこなせるわけではありません。そのため、商品ページやカスタマーサポートを英語だけで対応しようとすると、多くのユーザーにとって情報が十分に伝わらず、結果的に離脱率が高まる要因になりがちです。
また、インドネシア固有の文化的背景や慣習を踏まえた表現を理解していないと、ユーザーが商品に興味を示してくれても、サイトやアプリの操作画面で戸惑ってしまう場合もあります。たとえば、宗教的な観点からアルコールや豚肉由来の原材料が敬遠されることがある、ラマダンの時期には消費行動が一時的に大きく変化する、といった特徴をUI/UX面で考慮していないと、思わぬところで信頼を損ねてしまうことがあるのです。
商品説明文や対応チャネルのミスマッチ
日本からの出品者が意外と見落としがちなのが「商品説明文」のローカライズです。たとえばコスメや健康食品など、実際の成分や使用方法に細かい注意点がある商品ほど、その説明をローカル言語で明確に伝えることが重要です。翻訳が不十分だと、ユーザーは「この商品は本当に安全なのだろうか?」と不安を感じて離脱してしまう可能性があります。
また、対応チャネルの選び方も大きなポイントです。インドネシアのユーザーはSNSを活発に利用しており、特にInstagramやTikTok、Facebook Messengerなどを通じた問い合わせや購入誘導が多い傾向があります。日本と同じく「メールのみで問い合わせを受け付ける」「問い合わせフォームに誘導する」だけではユーザーが面倒に感じ、購入を断念してしまうリスクが高まります。
言語と文化の両面でユーザーが安心して購買行動を取れるように配慮することが、ローカライズの第一歩となるでしょう。
失敗パターン②:物流・配送トラブルの軽視

インドネシアは広大な国土を持ち、離島が多数存在します。そのため、物流インフラが十分に整っていない地域も多く、配送に時間がかかったりトラブルが頻発したりすることがあります。こうした課題を軽視してしまうと、商品が期日どおりに届かない、追跡ができない、返品がスムーズに行えないといった問題が多発し、ユーザーからの信頼を大きく損ねる結果につながるのです。
企業にとっては、商品を売ること以上に、「商品を確実に届ける」体制を整えることが大きなチャレンジとなります。ここでは、具体的にどのような物流トラブルが起きやすいのか、その影響と原因を探ってみましょう。
倉庫戦略なしで配送遅延が常態化
多くの企業がインドネシアで陥りがちなのは、現地に適切な倉庫拠点を設けず、単一の拠点から全国に配送しようとしてしまうケースです。インドネシアは地理的に非常に広いため、ジャカルタ近郊の倉庫だけで全国配送をカバーするのは、想像以上に時間とコストがかかります。また、交通インフラが未整備な地域では、想定外の配送遅延も発生しやすくなります。
倉庫戦略をしっかり立てないまま参入すると、ユーザーは「商品が届かない」「届くのが遅い」という不満を抱えやすく、後々のリピート購入や評判にも悪影響が出ます。ECモールによっては、倉庫やフルフィルメントセンターを提供している場合がありますが、それも都市部中心であることが多いため、地方の消費者に商品を届けるには別途手を打つ必要があるでしょう。
返品対応や追跡不可による信頼喪失
インドネシアのEC市場においては、購入後の返品対応や商品追跡に対するユーザーの不安が大きいという特徴があります。特に海外企業から購入する場合、「もし壊れた商品が届いたらどうしよう」「商品がずっと追跡できないままになったらどうしよう」といった懸念が高まりやすいのです。
物流業者の中には、追跡情報が遅れて更新されたり、荷物がどこにあるのかが分かりにくいシステムのところもあります。こうした環境下で購入者がスムーズに返品・交換を行える仕組みを用意していないと、「この店は対応が遅い」「問い合わせの返事が来ない」といった評価がSNSやレビューサイトで瞬く間に広まってしまいます。信頼回復には多大な時間とコストがかかるため、事前に物流・配送の仕組みを整えることが不可欠です。
失敗パターン③:価格設定とプロモーション設計の甘さ
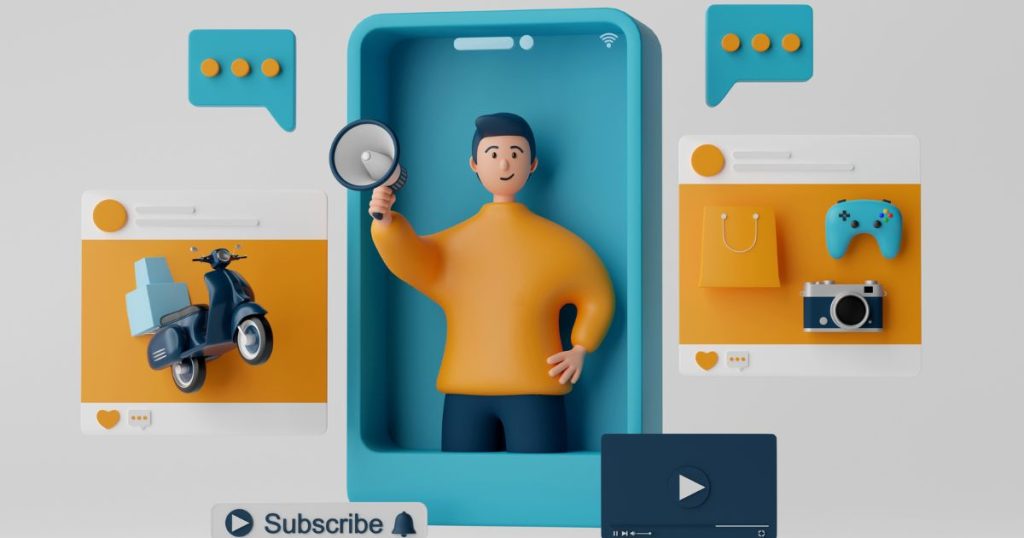
インドネシアのEC市場では、大規模セールやバウチャーの配布など、価格面での競争が活発に行われています。日本企業が提供する商品の品質や信頼性は、現地のユーザーにも評価されることがありますが、それでも高すぎる価格設定やタイミングの悪いセール企画は、購買意欲を一気に削ぎかねません。
さらに、現地特有のセール時期や祝祭日に合わせたプロモーションを外すと、十分な流入を得られないことも珍しくありません。ここでは、現地の価格感覚を無視した高値設定と、バウチャーやセールの活用不足が引き起こす問題について解説します。
現地価格感覚を無視した高値設定
日本から商品を輸出する場合、どうしても輸送コストや関税などが上乗せされるため、ある程度は価格が高くなる傾向にあります。しかし、インドネシアの一般的な消費者の所得水準や物価水準を考慮して価格設定をしないと、「同じような商品が国内や他の海外出品者からもっと安く買える」という比較によって、すぐに離脱されてしまう可能性が大きいです。
とくに、現地では日常的にディスカウントや値下げ交渉が行われる文化が根強く、ユーザーは常にお得感を求めています。日本では普通の価格だと思っていても、インドネシアのユーザーにとっては「割高」「高級すぎて手が届かない」と感じられることがあり、購買意欲を削ぐ原因になりかねません。まずは競合調査をしっかり行い、現地ユーザーが受け入れられる価格帯を探ることが成功の鍵です。
バウチャーやセールタイミングの活用不足
インドネシアでは、ShopeeやTokopediaをはじめとしたモールが定期的に大規模セールを実施しています。また、ラマダン(断食月)や独立記念日、年末年始などのイベントに合わせて、大量のバウチャー配布やディスカウントキャンペーンが展開されるのが一般的です。
このタイミングに合わせて自店舗もセールを行い、目立つ位置に広告を出すなどの対策を行わないと、「ユーザーが一番購入したい時期」に存在感を発揮できません。逆に言えば、この時期に合わせてうまくキャンペーンを仕掛けることで、一気に知名度と売上を伸ばすチャンスが生まれます。日本企業が見落としがちなのは、これら現地独自のセールイベントを把握していないことです。
さらに、バウチャー配布のタイミングや割引率も、ユーザーの購入行動に大きく影響します。ライブ配信中に限定バウチャーを出したり、SNS広告と連動して特定のハッシュタグを使ったユーザーにクーポンを提供するなど、工夫次第で多面的な集客施策が可能になります。
これから参入する企業が気をつけるべきポイント

ここまで3つの失敗パターン(ローカライズ不足、物流トラブルの軽視、価格設定・プロモーション設計の甘さ)を取り上げましたが、これらの失敗を回避するためにはどうすればよいのでしょうか。実は、成功している企業の多くは、現地ユーザーの購買行動や信頼基準に深く根ざした戦略を構築し、さらにShopeeやTokopediaといったプラットフォームに最適化した運営を行っています。
一方で、すべてを自力で賄うのはかなりの労力がかかるため、場合によっては現地パートナーや支援会社と連携しながらオペレーションを進める選択肢も検討すべきです。ここでは特に気をつけるべきポイントを整理してみます。
現地ユーザーの購買行動と信頼基準の把握
インドネシアのユーザーがどのように商品を探し、どうやって購入に至るかを詳細に理解することは非常に重要です。たとえば、InstagramやTikTokで商品の評判を調べてからShopeeで検索し、さらにレビュー数や星の数を見たうえで購入を決めるといった流れがよくあります。
このとき、レビュー数が少ない商品や、評価が低い店舗を利用することに抵抗を感じるユーザーが多いのも特徴です。また、インドネシアの消費者は問い合わせに対する即時性を重視します。チャット機能を使ってすぐに質問できる店舗や、SNS経由でサポートが受けられる店舗に信頼感を抱きやすいといえます。
こうした購買行動と信頼基準を踏まえて、言語対応(インドネシア語対応)やSNS連携を強化し、顧客対応をスピーディに行う体制を整えることが大切です。
Shopee・Tokopediaそれぞれのアルゴリズムと戦略
インドネシアのEC市場を語る上で必ず触れられるプラットフォームが、ShopeeとTokopediaです。この2つは特徴や強みが異なり、ユーザー層も微妙にずれています。Shopeeはクーポンやゲーム要素、ライブ配信などを使ったエンタメ性の高い施策を積極的に展開し、若年層を中心に大きな人気を獲得しています。一方、Tokopediaは本格的なECモールとしての信頼度が高く、中堅層やビジネスユーザーも多く利用している傾向があります。
出店者としては、これらのプラットフォームが用意する広告枠や検索アルゴリズムを理解し、最適化することが重要です。たとえば、Shopeeでは「フラッシュセール」への参加や「Shopee Live」活用が大きなトラフィックを獲得する鍵になりやすい一方、Tokopediaでは検索連動型広告やキーワードの最適化を地道に行うことで、商品を上位に表示させる手法が有効となることもあります。どちらのプラットフォームに注力するか、あるいは両方を併用するかは、扱う商品のジャンルやターゲット顧客によって異なります。
現地パートナーや支援会社との連携も視野に
ローカライズ対応や物流管理、マーケティング施策をすべて自社内で完結させるのは、現地事情に詳しくない企業にとってハードルが高いのが実情です。そのため、最初の段階ではインドネシアに拠点を持つパートナー企業や支援会社と連携し、ノウハウを吸収しながらビジネスを拡大していく方法が現実的です。
たとえば、物流面ではJ&TやSiCepatなどの主要物流企業と提携しているパートナーを探し、在庫管理や配送の最適化を委託することができます。また、ローカルSNSの運用やライブコマースの企画、言語サポートなど、専門領域のサービスを提供している会社も多数存在します。こうした支援を受けることで、失敗リスクを大幅に低減し、短期間で市場に適応できる可能性が高まるでしょう。
まとめ|インドネシアECで失敗しないために必要な準備とは

インドネシアのEC市場は多くの企業にとって魅力的なフロンティアですが、同時に独自の課題や競争の激しさを併せ持っています。今回紹介した3つの失敗パターン(ローカライズ不足、物流の軽視、価格・プロモーション設計の甘さ)は、どれか一つでも陥るとビジネス成果に大きなダメージを与えかねません。
それを回避するためには、まず「現地の文化やユーザーの行動様式を理解する」ことから始め、次に「安定した物流体制と迅速な顧客対応」を整え、最後に「価格帯やセール施策を現地の感覚に合わせて最適化する」ことが求められます。
ローカルニーズとシステム面の両方を押さえる
インドネシアのユーザーは、単に安さだけを求めているわけではありません。商品が安全であること、返品・交換がスムーズであること、問い合わせに素早く応じてくれることなどを含めた総合的なユーザー体験が重視されます。
一方で、システム面の整備が不十分なまま参入すると、配送追跡の不備や在庫管理ミスなどが頻発し、ユーザーからの苦情や低評価レビューにつながりかねません。まずは小規模からテスト的に販売を行い、受注・配送・サポートまでの流れを確立してから本格的に規模を拡大する方が、安全かつ着実に成功へ近づくでしょう。
事前リサーチと継続的なPDCAが成功のカギ
インドネシアECで成功を収めている企業は、例外なく「現地リサーチを徹底する」「データをもとにPDCAを回す」ことを怠りません。プラットフォームのトレンドやユーザーの嗜好は変化が早いため、一度立てた戦略に固執せず、常に改善を追求する姿勢が不可欠です。
たとえば、新商品の追加やセール時期の設定、物流パートナーの見直しなど、あらゆる意思決定で都度テストを実施し、その結果を分析して軌道修正を行います。特に競合が多いジャンルほど、差別化を図るためのクリエイティブな施策が必要になりますが、綿密なリサーチとデータ分析があればこそ、成功確率が高まるのです。
以上を踏まえ、インドネシアでのEC事業に挑む際は、ローカライズと物流戦略、価格・プロモーションの最適化を核とした包括的な準備を行ってください。そうすることで、単なる参入ではなく、安定した売上を生み出せるビジネスとして定着させることが可能となるでしょう。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
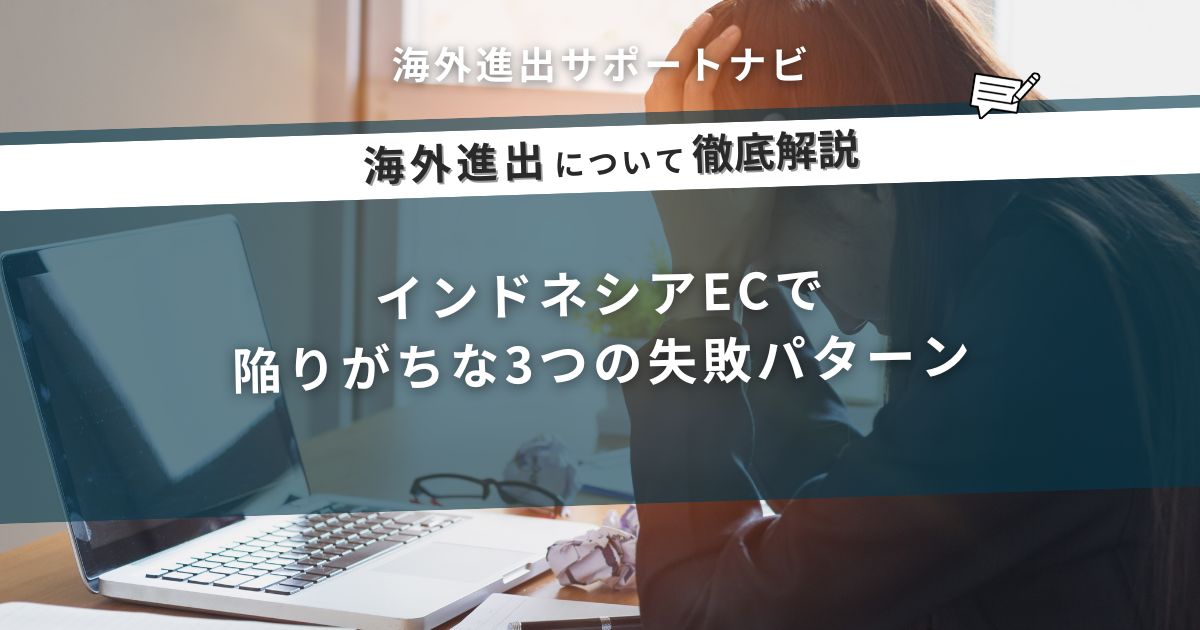
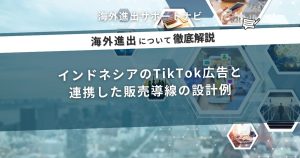



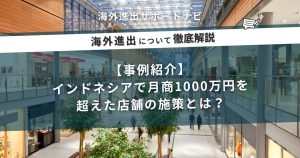



コメント