近年、インターネットやスマートフォンが急速に普及し、オンラインショッピングが世界的なトレンドとなっています。その流れの中で、特に注目を集めているのが東南アジア地域です。タイやベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピンなど、人口規模が大きく経済成長が著しい国々が集まり、「海外EC」の新たな市場として存在感を増しています。これらの国では、若い世代を中心にデジタル化が加速しており、EC(電子商取引)の需要が年々拡大しているのです。
本記事では、東南アジア向けEC販売を始める際に役立つ基本的なステップを網羅的に整理しました。公的機関(JETROや世界銀行など)が発表するデータや各国のECプラットフォーム情報を交えつつ、初心者にもわかりやすい形で解説していきます。海外市場へ進出を検討する企業担当者の皆様にとって、実際にどのようにリスクを管理し、どのように「海外EC」を運営していくのか、そのヒントを得られる内容となっているはずです。ぜひ最後までご覧いただき、東南アジアというダイナミックな市場へ飛び込むきっかけにしていただければ幸いです。
なぜ東南アジアへの海外ECが注目されるのか

まず、東南アジアがなぜ海外ECの新興市場として注目されているのかを整理してみましょう。ここでは、経済成長と人口規模、そして公的機関が示すデータを中心に、その背景を探っていきます。
東南アジアの経済成長と人口規模
東南アジア諸国連合(ASEAN)に属する国々は、合わせて約6億5,000万人を超える人口を抱えています。これはEU(欧州連合)と匹敵する規模であり、世界的にも大きな市場といえるでしょう。中でもインドネシアは単独で約2億7,000万人もの人口があり、若年層が厚い人口ピラミッドを形成しています。タイやベトナム、フィリピンも、それぞれ6,000万〜1億人程度の大規模な人口を擁し、国内需要だけでも非常に大きなマーケットが存在します。
こうした国々では近年、高い経済成長率を維持しているケースが目立ちます。世界銀行やIMFのレポートによれば、ベトナムやフィリピン、インドネシアなどで年5〜7%程度のGDP成長率を記録する年が少なくありません。これに伴い生活水準が向上し、消費意欲が高まってきた中間所得層が急増していることが、ECの需要を押し上げる大きな要因となっています。
公的機関データから見るEC市場の伸びしろ
日本貿易振興機構(JETRO)が公表する海外市場データや、各国政府が発行する統計情報を見ても、東南アジアのEC市場は今後も高い成長が見込まれています。例えば、インドネシアのEC取引額は年率20〜30%程度で拡大しているとの推計もあり、スマートフォンの普及とともに地方部へのオンラインショッピングが広がってきている実態がうかがえます。タイやマレーシア、フィリピン、ベトナムなどでもインターネットインフラの整備が進み、EC人口が増加傾向にあることが確認できます。
さらに、東南アジアのユーザーはSNSやモバイルアプリを通じて商品情報を得る傾向が強く、ECサイトへのアクセスもスマートフォンからが中心になりつつあります。こうした「モバイルファースト社会」が形成されることで、EC事業者は日本国内とは異なるマーケティング戦略やユーザーエクスペリエンス(UX)設計を求められる一方、うまく対応できれば日本国内以上のビジネスチャンスを獲得できる可能性があるでしょう。
東南アジアECの主要プラットフォームと特徴

東南アジアにおけるEC販売の成否を大きく左右するのが、どのプラットフォームを利用するかという点です。国ごとに人気のECサイトやアプリが異なるため、進出先やターゲット層に合わせて選択する必要があります。ここでは、いくつか代表的なプラットフォームを取り上げ、その特徴を比較してみましょう。
Shopee・Lazada・Tokopediaなど主要サイトの比較
Shopee:シンガポール発のECプラットフォームで、東南アジア全域(タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、インドネシアなど)で展開しています。モバイルアプリの使いやすさに定評があり、ゲーム感覚のプロモーション(クーポン配布やポイント集めなど)でユーザーのリピート購入を促進しています。セール時には大規模なキャンペーンを打ち出すため、売上が一時的に急増する傾向があります。
Lazada:アリババグループの傘下に入り、東南アジア6カ国(タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン、インドネシア)で事業を展開するプラットフォームです。特にマレーシアやフィリピンでの認知度が高く、ブランド公式ストアの立ち上げがしやすいメリットがあります。また、物流面でアリババグループのノウハウを活かしたサービスが充実しているのも強みです。
Tokopedia:インドネシア国内で圧倒的なシェアを持つECサイトで、C2C(個人対個人)やB2C(企業対個人)の取引が盛んです。地元の中小店舗が多数出店し、多彩な商品が揃っていることが特徴です。インドネシア市場への特化度が高いため、同国向けにビジネスを展開したい場合には有力な選択肢となります。
これらのプラットフォームには共通して「セールイベントや限定クーポンなど、大規模キャンペーンで一気にユーザーを集める」という文化が根付いています。特に11月11日(ダブルイレブン)や12月12日(ダブルトゥエルブ)などの日付を合わせたセールイベント、あるいは国の祝日に合わせた大型セールが行われるため、ここに照準を合わせることで売上を大きく伸ばせるチャンスがあります。
国別(タイ・ベトナム・インドネシア等)での人気サービス
同じShopeeやLazadaでも、国や地域によってユーザー数や競合状況が異なるため、進出前に調査が必要です。例えば、ベトナムのEC市場ではShopeeがシェアを伸ばしており、タイではLazadaとShopeeがしのぎを削っています。インドネシアではTokopediaとShopeeがトップシェアを競い合う展開であり、新規に参入する場合はどちらのプラットフォームに注力するかによってマーケティングコストや効果が大きく変わります。
また、シンガポールを含めた小規模市場では、英語対応が進んでいる反面、消費者の所得水準が比較的高めであるため、高級ブランドや輸入品が売れやすい場合があります。一方で、フィリピンやマレーシアでは複数言語が入り混じり、物流コストや配送インフラの状況によって商品の到着期間が変動しやすいという難しさも存在します。どの市場を狙うか、どんな商品を取り扱うかによって最適なプラットフォーム選定は変わってくるのです。
越境ECを始める前に押さえるポイント

日本国内のECとは異なり、海外向けECを運営するには様々な追加の手続きやローカライズが必要です。ここでは、最低限知っておきたい「海外 EC」ならではのポイントを整理します。
ローカライズ(言語・通貨・配送方法)の重要性
海外ECを行う場合、消費者が使う言語や通貨、配送事情などを考慮したローカライズが欠かせません。サイトや商品ページの言語は英語だけでは不十分なことが多く、タイ語やベトナム語、インドネシア語など現地語への対応が求められる場合があります。商品説明やカスタマーサポートを現地語で行うことで、ユーザーの安心感を高めるとともに、競合との差別化を図ることが可能です。
また、通貨に関しても、現地通貨での表示や決済オプションを用意することで、ユーザーが価格を把握しやすくなり、購入ハードルを下げられます。クレジットカード決済だけでなく、銀行振り込みや電子ウォレット、代金引換など、その国で一般的に利用されている支払い方法を導入するのもローカライズの一環です。
外貨決済や税関手続きなどの基本的な準備事項
日本から商品を発送する「越境EC」の形をとる場合、輸出入に関する税関手続きや関税、各国の輸入規制に注意する必要があります。例えば、食品や化粧品など特定カテゴリの商品には輸入許可証が求められる場合があり、必要書類や検査手続きに時間とコストがかかるケースもあるため、事前リサーチが重要です。
また、商品を現地倉庫に置くのか、あるいは注文が入ってから日本から直送するのかによって物流スキームが異なります。直送の場合は配送日数が長くなり、返品や交換対応が複雑になりがちですが、在庫リスクを抑えられるメリットがあります。現地倉庫を利用すれば配送が速くなる反面、倉庫費用や在庫管理の手間が増えます。自社のビジネス規模やキャッシュフローを考慮しつつ、最適な物流体制を検討しましょう。
東南アジア向けECサイト立ち上げステップ
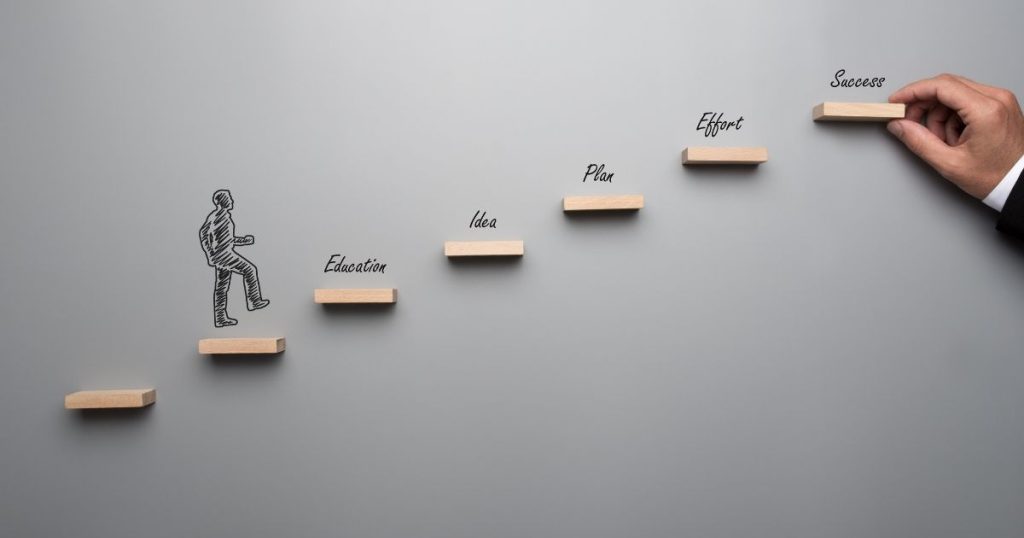
では、実際に東南アジア向けのEC販売を始めるには、どのような手順で進めればよいのでしょうか。ここでは大まかなプロセスを6つのステップに分けて解説します。もちろん企業の規模や取扱商品によって細部は異なりますが、全体像を把握することで計画の立案や要件定義がスムーズになるはずです。
市場調査・ターゲット分析
まずは進出先の国や地域を絞り込み、消費者の嗜好や競合状況をリサーチすることから始めましょう。具体的には以下のような情報を収集すると効果的です:
- 人口構成と所得水準(中間層の拡大度合い)
- 主要ECプラットフォームの利用状況や競合製品の有無
- SNS利用率や広告コストの相場
- 宗教・文化的要素(ハラルや祝祭日など)
公的機関(JETROなど)が提供する国別投資ガイドや商工会議所のレポート、あるいは市販の市場調査レポートを参考にすると、効率的に情報を集められます。この段階で「どの国のどの層をターゲットとするか」を明確にし、戦略上の優先順位を設定しておくことが大切です。
ECサイト構築・支払い方法設定
次に、自社独自のECサイトを構築するか、ショッピングモール型プラットフォーム(例:Shopee、Lazada)に出店するかを決めます。独自サイトの場合はブランドイメージの統一やリピーター施策を行いやすい反面、集客コストやサイト翻訳などが負担となります。一方、プラットフォーム出店では集客基盤が整っているメリットがあるものの、手数料や他店舗との価格競争などの課題もあります。
いずれの場合も、決済方法を現地のユーザーが使いやすい形に整備することが重要です。クレジットカード決済、銀行振り込み、電子ウォレット、代金引換など、国によって主流な支払い方法が異なるため、ターゲット国のニーズに合わせて複数の決済オプションを用意すると離脱率を下げられます。
プラットフォーム上でのブランド登録とプロモーション施策
もしショッピングモール型プラットフォームに出店する場合は、ブランド公式ストアの開設や商品ページのカスタマイズに力を入れましょう。各プラットフォームではセールイベントやクーポン配布などの販促機能を提供しており、これらを効果的に活用することで短期間での認知度アップを図れます。
また、プラットフォーム内検索におけるSEO(検索最適化)も重要です。商品名や商品説明に現地語のキーワードを入れる、商品のカテゴリ設定を正しく行うなど、基本的な施策を怠らないようにしましょう。
SNS・インフルエンサー活用で現地ユーザーを取り込む

ECサイトやプラットフォームでの販売基盤が整ったら、次は「いかにして現地の消費者の目に留まるか」がポイントとなります。東南アジアではSNSが日常生活に深く根付いており、インフルエンサーの影響力も大きいのが特徴です。ここでは、SNSプロモーションやインフルエンサーマーケティングを組み合わせる具体策を見ていきましょう。
SNS上でのプロモーション事例
FacebookやInstagram、TikTokは東南アジア各国で高い利用率を誇り、企業が公式アカウントを運営するだけでなく広告(Facebook Ads、Instagram Ads、TikTok Adsなど)を出すことで、短期間に多くのユーザーへリーチできます。特にタイやベトナム、フィリピンではFacebookユーザー数が非常に多く、製品写真やセール情報などを投稿しながら、ECサイトへのリンクを設置するのが一般的です。
また、タイやインドネシアではInstagramやTikTokのショート動画が人気で、商品デモンストレーションや利用シーンを動画化して投稿すると視聴者の興味を引きやすい傾向があります。SNSのストーリーズ機能を活用して期間限定クーポンを配布する、ライブコマース(ライブ配信中に商品を紹介し、その場で購入可能にする)を行うといった手法も有効です。
インフルエンサーとの連携によるブランディング強化
SNS ブランディングの一環として、各国のインフルエンサーやKOL(Key Opinion Leader)とコラボレーションするのは非常に有力な手段です。たとえば、ファッション系のインフルエンサーに自社の商品を実際に使ってもらい、その感想を配信してもらうことでターゲット層へ直接アプローチできます。インフルエンサーのフォロワーは、彼ら・彼女らのセンスやライフスタイルに憧れを抱いていることが多いため、企業側が広告を打つよりも自然な形でブランドイメージを訴求できるメリットがあります。
ただし、インフルエンサー選びでは単にフォロワー数の多さだけでなく、エンゲージメント率やフォロワーの属性を重視しましょう。また、コラボ内容や報酬形態、投稿内容における透明性(ステマと疑われない)などを事前に調整し、ブランドイメージを損なわない範囲で企画を進めることが重要です。
まとめ

東南アジア向けEC販売は、人口規模や経済成長によって膨大なポテンシャルを秘めています。一方で、多様な文化や言語、インフラ状況の違いがあるため、日本国内の感覚で参入してしまうと戸惑う場面が多いのも事実です。しかし、適切な準備と戦略をもって取り組めば、確実に大きな市場チャンスを掴む可能性があります。以下に、本記事で紹介したポイントを再整理します。
- 経済成長と人口規模を背景に、東南アジアEC市場は今後も拡大
インドネシアやベトナム、タイなどで若年層の消費意欲が高まり、EC取引額が急伸している。 - 主要プラットフォーム(Shopee、Lazada、Tokopediaなど)の特徴を把握
国ごとに人気サイトやユーザーの特徴が異なるため、販売戦略や出店方法を慎重に選ぶ必要がある。 - ローカライズや税関手続きなど「海外 EC」ならではの課題への対策
言語対応、通貨対応、物流・配送スキームの設計、輸入規制への対応などを事前に調査・準備する。 - SNS・インフルエンサーマーケティングの活用で現地ユーザーにアプローチ
モバイルファースト社会である東南アジアでは、SNSやインフルエンサー施策が認知拡大や信頼獲得に直結しやすい。 - 成果測定とPDCAサイクルを回しながら改善を続ける
リーチやエンゲージメント、CVRなどのKPIを監視し、常に施策の効果を分析して最適化する。
最終的にどの国にどんな形で進出するかは、企業のビジネスモデルや取り扱う商品の特性によって大きく変わります。もし迷いがある場合は、JETROや在外公館の情報を参考にしつつ、現地の専門コンサルタントやローカルパートナーと組む方法も有効です。また、一度に複数国に進出するのではなく、まずは比較的ハードルが低い国やプラットフォームでテスト販売を行い、ノウハウを積み上げるアプローチも考えられます。
いずれにせよ、「海外EC」を成功させるには、現地の消費者心理を理解したローカライズと適切なマーケティングが欠かせません。東南アジアの消費者はSNSを介して情報を得るケースが多く、インフルエンサーの発言力も強いため、現地の文化や習慣に沿った形でブランディングを行うと大きな成果が期待できるでしょう。この記事を参考に、まずは一歩踏み出してみてください。多様性に満ちた東南アジア市場でのEC事業は、きっと大きな可能性をもたらすはずです。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
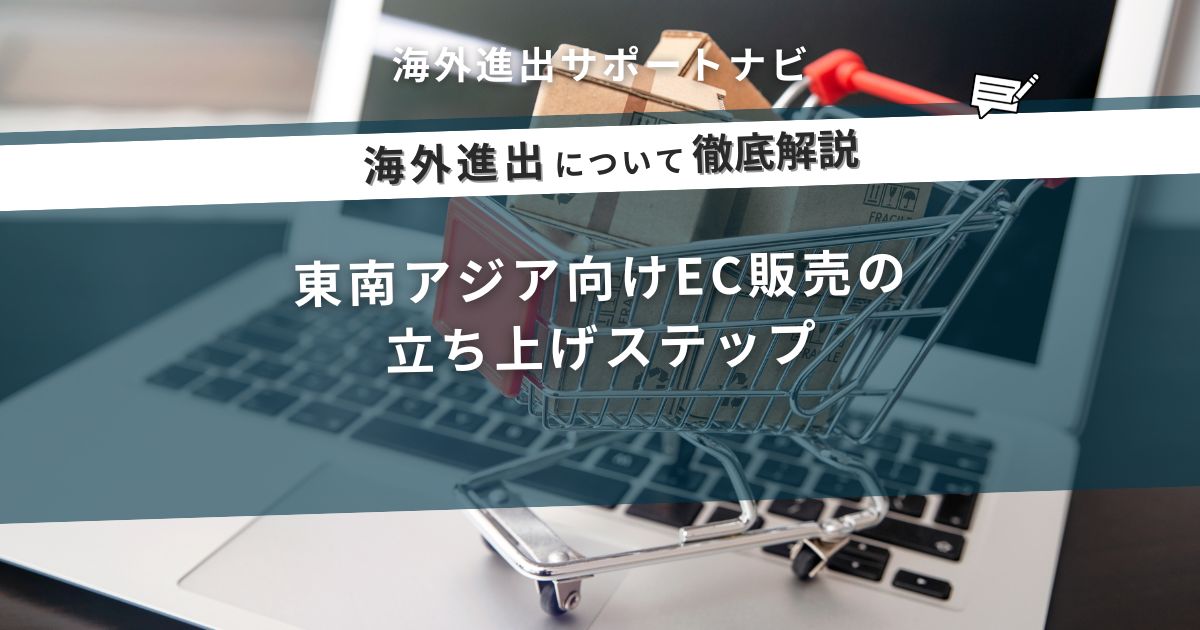
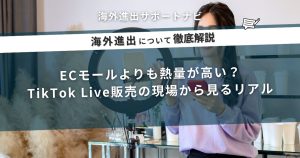
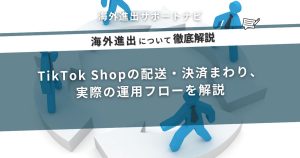


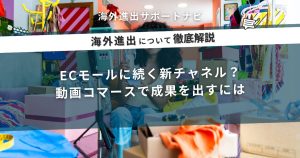

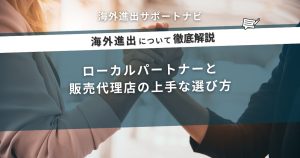
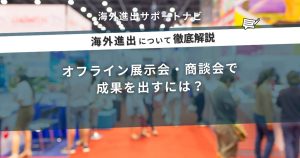
コメント