海外に進出する企業にとって、「税務リスク」は見過ごせない大きな課題です。なかでも、グローバルに展開する多国籍企業や、海外に関連会社を持つ日系企業にとって、移転価格税制の遵守は避けて通れない問題といえます。移転価格税制は、国際取引における利益配分を公正に行うために各国税務当局が監視を強化している分野であり、もし適切な対応を怠ると、追徴課税やペナルティを受けるリスクが高まります。
近年は、OECD(経済協力開発機構)が主導するBEPS(Base Erosion and Profit Shifting)プロジェクトの影響や、各国の財政事情の変化を背景に、東南アジアの国々でも移転価格に関する監査や報告義務が強化される動きが続いています。タイやベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールなど、いずれの市場でも国外からの投資が増え、国際取引が拡大するほど、移転価格調査が行われる可能性が高くなるのです。
本記事では、「移転価格・税務」という視点から、東南アジアでの税務リスクや移転価格制度の基礎知識を整理し、実際に企業がどのように対応すればよいのかを解説します。公的機関(OECDなど)が示すグローバルなルールや各国税務当局の状況を交えつつ、文書化要件やローカルファイルの作成など、実務のヒントを具体的に紹介していますので、これから海外拠点を展開する方や、すでに現地子会社を運営している企業の担当者の皆さまは、ぜひ参考にしてみてください。
なぜ移転価格税制が企業の税務リスクとなるのか
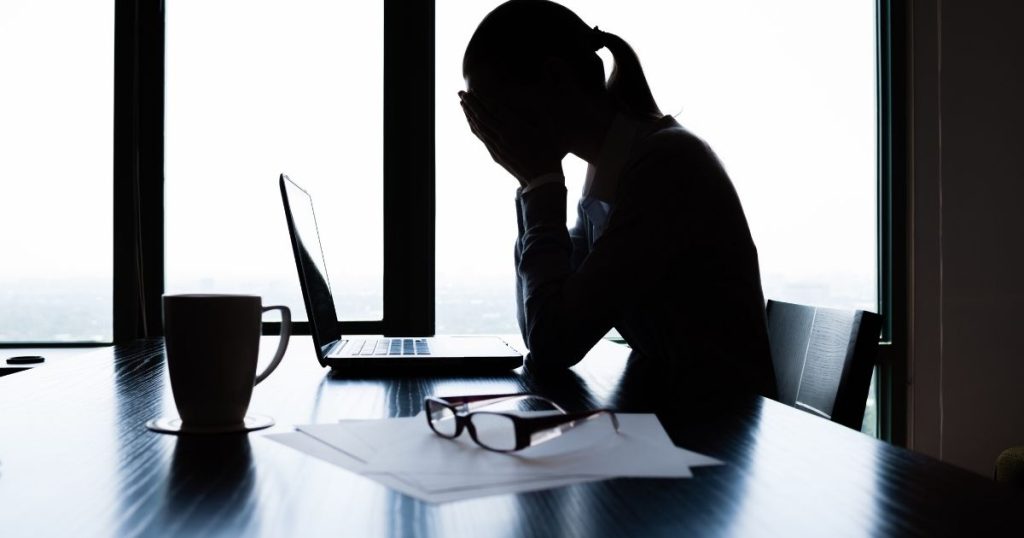
海外子会社との取引が増えるほどに注目されるのが「移転価格税制」です。親会社と子会社、あるいは関連企業同士での取引価格が不自然に低い(もしくは高い)と、税務当局が「利益の移転」を疑い、追加課税を行う可能性が高まります。まずは、この制度が企業にとってどのようなリスクをもたらすのか、背景を見ていきましょう。
国際取引にまつわる利益配分の難しさ
国際取引を行う多国籍企業は、原材料や製品の売買、技術使用料やブランドロイヤルティの支払い、コンサルティングサービスの提供など、さまざまな形でグループ内取引を行います。本来であれば、第三者同士の取引と同様の価格(アームズレングス・プライス)を設定し、各国で公平に課税される形を保つのが原則です。しかし、実際には法人税率の低い国や優遇措置のある国に利益を集中させる方法を模索する企業も存在し、税務当局としては「適正価格で取引されているか」を厳しくチェックする必要があります。
こうした背景から、移転価格税制は単なる「国ごとの法人税率差」だけでなく、企業のグローバル戦略や財務計画にも大きく影響します。たとえば、研究開発費や知的財産権のロイヤルティをどこの拠点に計上するか、仕入価格をどう設定するかなど、取引価格ひとつで各国の利益配分が大きく変わるのです。結果として、関連企業間取引の透明性と公正性が求められるようになり、移転価格税制が国際税務の主要テーマとなりました。
公的機関(OECD、各国税当局)による監視強化の背景
OECDは、多国籍企業による利益移転を防ぐためのガイドラインを作成し、加盟国を中心に「BEPSプロジェクト」として各種施策を推進しています。BEPSプロジェクトのアクションプランでは、移転価格ドキュメンテーションに関する義務(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書など)を定め、情報の透明性を高めることで過度な節税(タックスプランニング)を抑止する狙いがあります。
東南アジア各国も、このOECDガイドラインを参考に独自の移転価格規定を整備してきました。タイやインドネシア、ベトナム、マレーシアなどが相次いで移転価格関連の法規制を強化し、関連企業間取引の報告義務や文書化要件を導入しています。また、域内の税務当局間で情報交換が活発化しており、一国での不正な取引価格設定が他国にも波及するような時代になったのです。これに伴い、企業が記録を整備せずにいると、税務調査の際に多額の追徴金を課されるリスクが増大しています。
移転価格税制の基本概念と関連ルール

具体的な国別の状況を見ていく前に、まず移転価格税制の基本用語や国際的な枠組みを確認しましょう。ここで紹介するのは、「アームズレングス・プライス」と呼ばれる独立企業間価格の原則や、文書化義務の代表例などです。
アームズレングス・プライス(独立企業間価格)とは
移転価格税制において最も重要なのが、「独立企業間原則(アームズレングス・プライス)」です。これは、関連企業同士の取引価格が、もし独立した第三者同士で取引を行った場合に設定されるであろう水準と一致しているかを基準に課税するという考え方を指します。
たとえば、日本の親会社と東南アジアの子会社が部品を売買する場合、子会社が支払う金額が極端に低かったり、高かったりすると、日本と現地国いずれかが過剰または過少に利益を計上することになり税収が歪む恐れがあります。そのため、税務当局は「市場価格に照らしてこの取引は妥当か」を判断するのです。
ローカルファイル、マスターファイルなど文書化義務
移転価格税制の運用強化によって、多くの国が一定条件を満たす多国籍企業に対して「文書化義務」を課すようになっています。これは、取引価格が独立企業間価格に合致していることを示すための根拠資料を作成・提出しなければならないというルールです。代表的な文書としては、以下の三つが挙げられます:
- マスターファイル:グループ全体の事業内容や組織構造、移転価格方針などを総括した文書
- ローカルファイル:各国・各拠点レベルでの具体的な取引内容、利益配分根拠、比較データなどをまとめた文書
- 国別報告書(CbCレポート):各国ごとの売上高や利益、従業員数、納税額などを一覧にした報告書
国別報告書は、グループ全体の透明性を向上するために作成が義務付けられることが多く、税務当局同士で情報交換が行われる仕組みがあります。これらの文書が欠けていると、税務調査で不備を指摘され、追加税額の評価が行われる可能性が高まるのです。
BEPS(Base Erosion and Profit Shifting)プロジェクトの影響
OECDが推進するBEPSプロジェクトは、法人税率の低い国や租税回避地に不当に利益を移転することを防ぎ、国際的な課税ルールを公正に保つことを目的としています。東南アジアの国々もこの動きに呼応する形で、自国の移転価格規定を整備・改正し、違反企業への追徴課税やペナルティを強化しているのが現状です。
結果として、これまで曖昧に設定していた取引価格やロイヤルティ支払いなどに対して、「どのような算定根拠があるのか」「第三者取引の水準と比べてどうか」と厳格に問われることになります。企業が証拠書類を用意できなければ、不当に低い価格で部品を海外子会社に売却していたとみなされ、追加の法人税を課されるリスクが否めません。
東南アジア主要国(タイ・ベトナム・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール)の特徴

具体的に、東南アジア各国の移転価格税制はどのように運用されているのでしょうか。それぞれの国が導入しているルールや、税務当局の監査動向、留意点をざっくり見ていきましょう。
タイ:最近の移転価格ルール強化と書類要求
タイでは2019年に移転価格関連の法律が施行され、関連企業の定義や報告義務が明確化されました。一定基準(売上高など)を超える企業は、移転価格文書や関連企業間取引情報の提出が義務付けられ、税務当局の監査対象となる可能性が高まっています。VATやBOIの優遇策を活用する企業も多いため、取引価格が実質的に優遇されていないかをチェックされることがあります。
さらに、国際取引におけるロイヤルティやサービスフィーの内容を詳しく調べられるケースも増えており、具体的な契約書や費用対効果の資料が求められることがあるので注意が必要です。タイの歳入局や税務当局は今後も監査を強化すると予測されているため、日系企業も早めに文書化対応を進めるのが望ましいでしょう。
ベトナム:関連企業取引の申告書と実務リスク
ベトナムでは、2017年に移転価格規制を大幅に改正する政令が施行され、関連企業間取引を行う企業に対して詳細な申告と文書化を求める流れが強まっています。一定規模以上の企業は、税務申告書とともに関連取引の情報を提出し、価格の算定方法や比較対象データを説明する必要があります。
ベトナム税務当局は、以前より外国企業に対して積極的に税務調査を実施しており、赤インボイス(Red Invoice)制度などの理由で会計・経理が厳格化されている点もあって、不備が見つかると厳しい追徴課税が行われることがあります。親会社と子会社の間で設定している販売価格や技術支援料が適正かどうかを証明できる資料を準備することが重要です。
インドネシア:OECDガイドラインをベースにした文書化義務
インドネシアは「PMK-213号令」などで移転価格文書化義務を定めており、OECDガイドラインにかなり近い形でローカルファイル・マスターファイルの作成を求めています。一定条件(売上や関連取引額)を超える企業はこれらを整備し、税務当局から要求があった場合すぐに提出できる状態にしておく必要があります。提出が遅れたり内容が不十分だったりすると、推定課税のリスクが高まるので注意が必要です。
インドネシアでは法人税率が段階的に引き下げられており、近年は20〜22%程度となっています。こうした税率変動に伴って、関連企業間取引の最適化を図る動きが見られますが、移転価格調査も同時に厳格化しているため、適切な価格設定と文書化が不可欠です。
マレーシア:SSTや法人税との絡みと移転価格
マレーシアでは、2019年の租税改正で移転価格ガイドラインが強化され、グループ内取引の文書化要件が拡充されました。法人税は24%が基本ですが、中小企業や特定産業向けの優遇措置もあり、さらにSST(Sales and Service Tax)が再導入されたことで、さまざまな経理処理が複雑化しています。
移転価格に関しては、特にサービス料やロイヤルティの取引が厳しく監視される傾向にあり、根拠資料が不十分だと「経済的実態がない」とみなされて追徴課税を受ける可能性があるのです。マレーシア国内の関連企業との間で取引を行う場合でも、グループ全体で利益配分が不自然にならないよう注意する必要があります。
フィリピン:コングロマリット監視の実態
フィリピンは英語が通じやすい国であり、多数の多国籍企業がBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)やサービス事業を展開しています。法人税はCREATE法によって2021年以降に大幅に引き下げられ、投資を呼び込みやすい環境が整いつつあります。
その一方で、大規模なコングロマリット(企業グループ)が国内経済を支配している事実もあり、フィリピン国税庁(BIR)はグループ内取引に対して移転価格の検証を強化しています。特にサービス取引やブランドロイヤルティなど、形のない無形資産をめぐる取引価格を精査する事例が増えているため、資料の整備や価格算定根拠が欠かせません。
シンガポール:低税率だが移転価格監査厳格化の動き
シンガポールは法人税率17%(一部企業に優遇措置あり)と低水準であり、アジアの金融拠点として多国籍企業が地域統括拠点を置くケースが多い国です。ただし、税率が低いからといって移転価格調査が甘いわけではなく、近年IRAS(Inland Revenue Authority of Singapore)はOECDガイドラインに基づく監査を強化しています。
シンガポール国内で関連企業取引を行う場合は、アームズレングス原則に基づくドキュメンテーションを保持し、税務当局から要求があれば提示できるようにしておく必要があります。国際的な企業がシンガポールに本社機能を集中させる事例が増えるほど、移転価格監査が行われやすい土壌が整っているとも言えるでしょう。
税務リスクを最小化するための実務対応

ここまで、各国の移転価格税制の概略を見てきました。では、実際に企業がどのようにリスクを低減しながら移転価格に対応すればよいのでしょうか。ここでは、基本的な実務対策や手順をまとめます。
トランスファープライシング・ポリシーの策定
移転価格税制の対象となる取引を洗い出し、それに関する「トランスファープライシング・ポリシー(TPポリシー)」を社内で文書化しておくことが第一歩です。どのような根拠に基づいて海外子会社との取引価格を設定しているのか、類似取引の市場価格やコスト構造、リスク分担の内容を定義することで、税務当局から質問があった際にも筋道を立てて回答できます。
このポリシーは、親会社だけでなく、現地法人や関連会社の担当者にも周知する必要があります。取引内容の変更や新規プロジェクトの立ち上げ時には、TPポリシーに従って価格決定プロセスを検証し、必要に応じて修正を行うことで透明性が保たれます。
日常の会計処理や取引証拠の整備
移転価格税制の監査では、取引実態が本当にあるのか、請求書や契約書、取引記録が正しく保存されているかが厳しくチェックされます。したがって、日常の会計処理の段階から、請求書や納品書、ロイヤルティの計算根拠などをきちんと整理しておくことが大事です。
特に中間会社を介した取引や無形資産の使用料などは、外部から見えにくい部分が多いため、社内で「取引目的」「価格算定の根拠」「役務の内容やボリューム」を説明できる資料を作成・保管しておきましょう。電子化された書類であっても税務当局が提出を求める場合があるので、可能な範囲でバックアップや認証を取ると安心です。
対外文書提出や税務調査への備え
多くの国では、移転価格文書(ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書など)の準備と提出義務を定めています。企業がこの義務を怠ると、税務調査の際に取引が不適正とみなされ、推定課税を受けるリスクが高まります。提出期限や要件は国ごとに違うため、どの国でどの文書が必要かをリスト化し、作成スケジュールを明確に管理しましょう。
また、税務調査に入られた場合、指定された期限内に文書を提出できなければ推定課税のリスクが一層高まります。海外子会社の現地スタッフや会計事務所、監査法人と密に連携し、万全の備えをしておくことが重要です。
ローカルファイル・マスターファイル作成のステップ
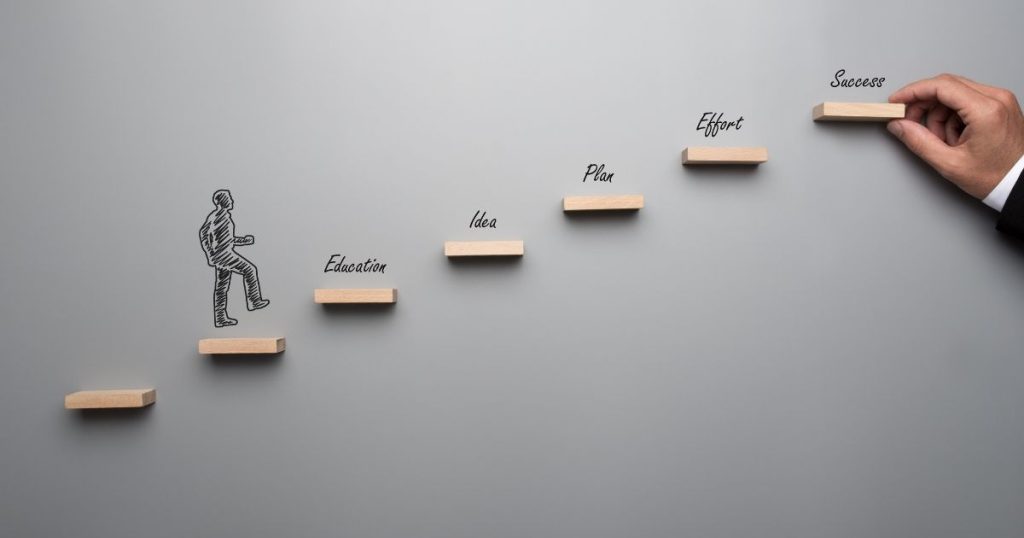
文書化義務の中核となるのが、ローカルファイルとマスターファイルの作成です。これらは企業グループ全体の取引状況を整理しつつ、各国税務当局に対して独立企業間価格の正当性を示すための具体的資料となります。ここでは、その作成ステップや要点を説明します。
文書化要件を満たすための情報収集とスケジュール管理
まず、どの国でどの程度の売上や取引があるかによって、文書化義務の対象範囲や提出期限が変わります。大まかな流れとしては、以下のようになります:
- グループ全体の売上・利益や、各海外子会社の取引規模を把握する
- BEPSアクション13に基づく文書化要件(マスターファイル、ローカルファイル、CbCレポートなど)を確認する
- 各国税務当局の規定(提出期限や様式、ボリューム)を調べる
- 親会社や海外子会社から必要データを収集し、情報を整理・分析する
- 外部コンサルタントや監査法人を活用し、ドラフトの文書を作成
- 社内レビューの後、最終的な文書を各国で提出できるようスケジュールを組む
このプロセスを円滑に進めるには、関連部門(経理・財務・事業部門など)や海外子会社との連携が欠かせません。年度末や決算時期に集中して書類を作ろうとすると情報が揃わなかったり、締切に間に合わなかったりするリスクがあるため、普段からデータを共有する仕組みを作るのが望ましいでしょう。
国別報告書(CbCレポート)との関係
大規模な多国籍企業(連結売上高が一定額を超える場合など)には、国別報告書(CbCレポート)の作成と提出が求められることがあります。このレポートでは、各国での売上高・利益・納税額・従業員数などを一覧にまとめるため、どの国にどの程度の利益を計上しているかが明確に見えてしまいます。結果的に「特定の国だけやけに利益率が高い(または低い)」といった不自然さが浮かび上がると、移転価格調査の対象となる恐れがあります。
ローカルファイルやマスターファイルだけでなく、CbCレポートの情報とも矛盾しないように整合性をチェックすることが大切です。大手監査法人や国際税務専門のコンサルタントなど、外部リソースを積極的に活用することで漏れやミスを防ぎやすくなります。
専門家やクラウドシステム活用のメリット
移転価格税制への対応は、グループ全体の取引実態を把握し、膨大なデータを整理・分析する作業を伴います。自社だけで完結させる場合、税務専門家や英語・現地語が堪能なスタッフを多く抱える必要があり、コストや工数が増大するかもしれません。そのため、専門のコンサルタントや監査法人に文書化支援を依頼する企業が多いのが実情です。
さらに、クラウド型の移転価格管理ツールやERPシステムと連動したソリューションを導入することで、日々の取引データが自動的に集計・分析され、文書化作業の効率が高まるケースもあります。特に複数の国や地域で同時に事業を展開する企業は、中央集権的にデータを一元管理し、ローカルファイル・マスターファイルを迅速に作成できる体制を整えるのが理想でしょう。
まとめ

多国籍企業や海外関連会社を持つ日系企業にとって、移転価格税制への対応は無視できない税務リスクの一つです。「移転価格・税務」というキーワードを通じて見てきたように、OECDのBEPSプロジェクトを契機として、東南アジア各国(タイ・ベトナム・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール)でも移転価格調査や文書化義務が次々と導入・強化されています。リスクを最小化し、グローバルな事業展開を安定させるためにも、次のポイントを改めて整理しておきましょう。
- 各国の移転価格制度を事前に把握する:タイ、ベトナム、インドネシアなど国によって文書化義務や税務調査のスタンスが異なるため、進出先のルールを早めに調べる。
- アームズレングス・プライス(独立企業間価格)の原則を守る:関連企業間取引を「市場価格と同等のレベル」に設定し、比較可能な第三者取引データを用意しておく。
- BEPSプロジェクトに基づく文書化要件に注意:ローカルファイルやマスターファイル、国別報告書などの作成義務があり、提出期限や形式が国ごとに違う。
- 日常の会計処理や契約の整合性を確保する:インボイスや契約書、ロイヤルティ算定根拠などを正しく保管し、税務調査に備える。
- 専門家やシステムの活用で効率化を図る:移転価格コンサルタントやクラウドツールを導入し、社内外での情報共有と書類作成を迅速に行う。
これらのステップを踏むことで、移転価格税制を巡る税務リスクを大幅に減らせるはずです。各国の法令や運用方針は変化が速く、定期的な情報収集とアップデートが欠かせません。JETROや在外公館、各国投資庁が発行するニュースレターやセミナー情報をチェックしながら、企業内部での記帳体制やコミュニケーションを強化していくことが大切です。
海外ビジネスは、製品・サービスの開発や現地営業、マーケティングに目が行きがちですが、税務や会計面でのリスク管理こそが、長期的に見た安定した事業運営のカギを握っています。移転価格に関する正しい知識と適切な対策を備えれば、余計な追徴課税や紛争を回避しながら、海外の成長市場でより自由度の高い戦略展開が実現できるでしょう。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
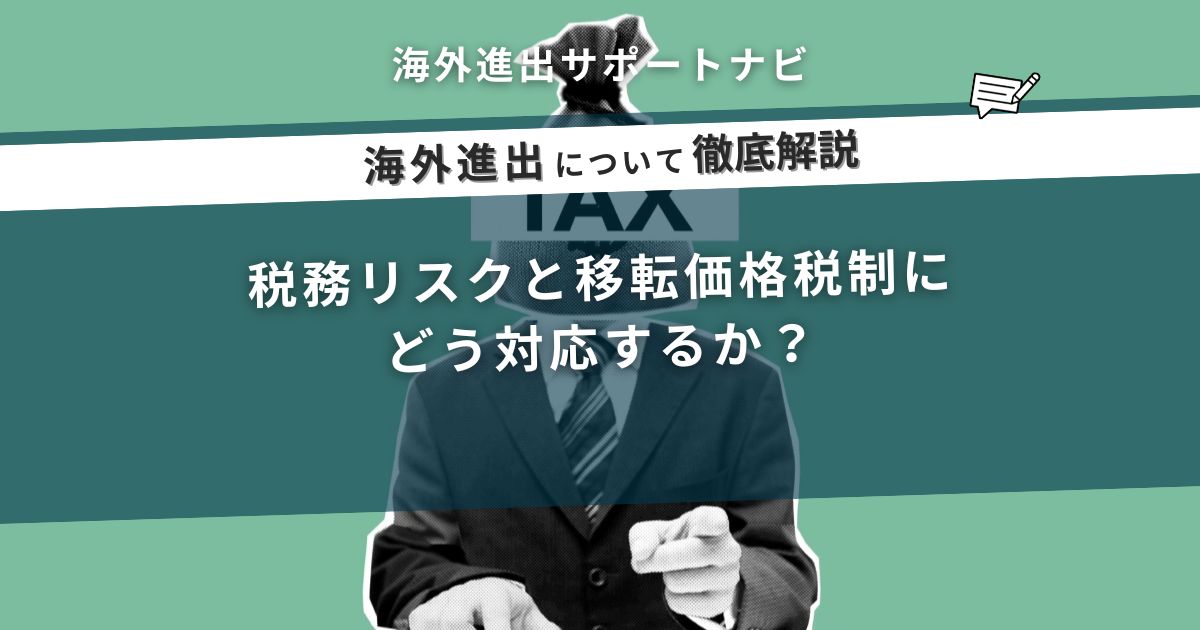
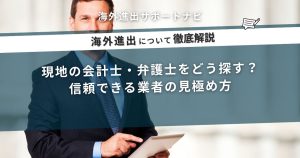
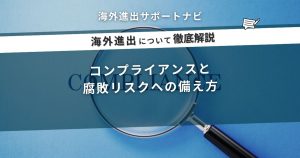
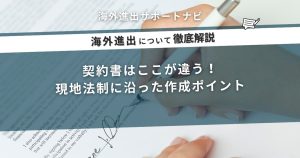

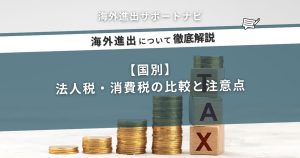
コメント