東南アジアをはじめとした海外市場への進出が活発化するなか、企業にとって海外に拠点を設ける際には、日本人スタッフや専門人材を現地に派遣する機会が増えています。また、個人レベルでも外国で働くことを目指す人が多く、グローバル化の波に乗る形で「海外就労」のニーズが拡大しています。しかし、海外で仕事をするためには、単にその国へ行くだけでは足りません。渡航目的に合ったビザを取得し、さらに就労許可(ワークパーミット)などの法的手続きが必要となります。
本記事では、海外就労を希望する方や海外進出を検討する企業担当者向けに、「各国のビザ・就労許可取得の流れと注意点」を詳しく解説します。具体的には、そもそも就労ビザ取得がなぜ重要なのか、ビザと就労許可の違い、そしてタイ・ベトナム・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポールなど主要国の手続き概要をまとめました。さらに、申請時によくあるトラブルや最新動向、公的機関のサポートも紹介し、初心者にもわかりやすい形で整理しています。JETROや各国政府が発表している情報を交えているので、安心して参考にしていただければ幸いです。
なぜ海外での就労ビザ取得が重要なのか

海外で働くには、観光目的のビザでは不十分です。就労ビザを取得していなければ、現地当局の監視対象となり、最悪の場合、罰則や国外退去が命じられる可能性もあります。なぜ就労ビザがそれほど重視されるのか、まずは基本的な意義を理解しましょう。
就労ビザと観光ビザの違いを理解する
多くの国では短期旅行向けに観光ビザ(あるいはビザ免除措置)が用意されていますが、これらはあくまで旅行や出張など短期間の活動を想定したものです。通常、観光ビザで働くことは禁じられており、報酬を伴う業務は不法就労とみなされます。
一方、就労ビザは、渡航者が現地で合法的に報酬を得て働く権利を得るためのビザです。取得のためには雇用契約書や企業の招へい状、経歴証明書など、書類の準備が必要となります。国によっては、審査に数週間~数か月かかるケースも珍しくありません。そのため、海外に駐在員を派遣する企業や、現地就職を目指す個人にとっては、早めの計画的な準備が欠かせないのです。
現地当局からの信頼とリスク回避
就労ビザを正規に取得することは、現地当局から見た「適法な外国人労働者」であることの証明にもなります。万が一、職場や住居に当局の調査が入った場合でも、正規のビザと就労許可を所持していれば、問題なく業務を継続できるでしょう。逆に不法就労の疑いをかけられると、高額な罰金や国外退去処分を受ける恐れもあり、企業の場合は現地の信用を失うリスクがあります。
また、就労ビザがなければ現地の社会保障や公的サービスへのアクセスが制限される場合が多く、医療保険の適用範囲が限られるケースも考えられます。正規のビザを持っていることで、想定外のリスクから自分自身や企業を守ることができるのです。
就労ビザと就労許可の基本をおさえる

「海外に出るならビザが必要」とはよく言われますが、実は「ビザ」と「就労許可(ワークパーミットなど)」は別物である場合が少なくありません。国によっては両方を取得しなければ働けないところもあります。その違いと、一般的に用意しておくべき書類について整理してみましょう。
ビザとワークパーミット(労働許可)の違い
ビザとは、簡単にいえば「特定の目的で一定期間、その国に滞在することを認める許可」です。観光ビザ、留学ビザ、就労ビザなど種類はさまざまで、それぞれ適用される活動範囲や期間が異なります。就労ビザの場合、その国で働くことが目的のビザとして扱われます。
一方、就労許可(ワークパーミット)は「外国人が労働活動を行ってよい」という別の許可であり、ビザとは別の役所(労働省や移民局など)が管轄しているケースも多いです。たとえば、ビザは外務省系の機関が扱う一方、就労許可は労働省が担当するといった具合です。したがって、企業や個人は、まず就労ビザを取得したあと、労働許可の手続きを進める必要がある場合があるのです。
各国の法的要件と共通の書類手続き
国によって詳細は異なるものの、就労ビザ・就労許可取得の際には、以下のような書類を求められることが一般的です:
- 有効なパスポート(残存有効期間が一定以上必要)
- 雇用契約書や企業からの招聘状
- 最終学歴や職務経歴を証明する書類
- 健康診断書や無犯罪証明書(国によって必要になる)
- 顔写真(ビザ申請フォームに貼付)
また、企業側は「この外国人を雇用する理由」や「現地人材ではカバーできない専門性がある」などを説明する資料を用意することが求められる場合もあります。JETROのウェブサイトなどでは国別の必要書類リストが掲載されていることがあるため、事前に確認しておきましょう。
国別の就労ビザ取得手続きと特徴(タイ・ベトナム・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール)

ここからは、東南アジアを代表する6つの国を例に、就労ビザ・労働許可の取得フローや特徴を簡単にご紹介します。各国ごとに手続き上のポイントや注意点が異なるため、進出先の国の最新情報を必ずチェックしてください。
タイの就労ビザ:BOI認可と労働許可証の手続き
タイでは、海外企業が投資委員会(BOI)の認可を取得している場合、就労ビザやワークパーミットの手続きが通常よりも簡略化されるメリットがあります。一般的な手続きとしては、まずNon-Immigrant Visa(通称:Non-Bビザ)をタイ大使館・領事館で申請し、その後、労働局でワークパーミットを取得するという流れです。
BOI認可企業の場合はOne Stop Service Centerという窓口を利用でき、申請から許可取得までがスムーズに進む傾向にあります。ただし、最低資本金や現地雇用の条件を満たしていないと認可を得られないこともあるので注意が必要です。また、滞在許可期限が切れる前に必ず更新申請を行う必要があります。
ベトナムの就労許可証:労働省が管轄する申請プロセス
ベトナムでは、外国人が4週間を超えて働く場合、就労許可証(Work Permit)の取得が原則義務となります。管轄は労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)で、企業が必要書類を揃えて申請します。並行して、外国人はビザ(DL・DN・LDなど)を取得する必要があり、目的ごとに在ベトナム大使館または領事館で申請する形です。
就労許可証の発行後、在留資格を労働ビザ(LDビザ)に切り替えるか、もしくはTRC(Temporary Residence Card)を取得して長期滞在するのが一般的な流れとなります。近年は労働法が改正され、外国人労働者への要件(学位証明、実務経験など)が一層厳格化されているので、最新情報を追いかけることが不可欠です。
インドネシア:KITAS取得と関連する書類
インドネシアで働くには、就労ビザ(通称:VITAS)と、KITAS(滞在許可証)をセットで取得する流れが一般的です。まず雇用企業が労働省から外国人雇用計画(RPTKA)の承認を得て、その後、就労ビザ(VITAS)を取得するために移民局へ申請を行います。VITASの発給が許可されると、入国後にKITASや労働許可(IMTA)を整える手続きを進めることになります。
書類提出先や担当する官公庁が複数にわたるため、企業が専門のコンサルタントや代理サービスを利用するケースが多いです。特に、首都ジャカルタと地方の事務所では対応や必要書類が微妙に異なる場合もあるため、混乱を避けるには早めの準備が大切です。
マレーシア:MDECによるIT人材優遇などのポイント
マレーシアでは、雇用パス(Employment Pass)、レジデントパス、プロフェッショナル・ビジットパスなど複数のビザカテゴリが用意されており、雇用パスはさらにカテゴリーI~IIIに分かれています。雇用パスカテゴリーI(高所得・高技能)は最長5年まで、カテゴリーII(中所得)は最長2年までの滞在が可能など、資格要件と在留期間が連動している点が特徴です。
また、IT関連の高度人材に対しては、MDEC(マレーシア・デジタル・エコノミー公社)が優遇措置を行っている場合があります。たとえば「MSCステータス」を取得している企業であれば、一部の申請手続きが簡略化されることもあるのです。申請時に学位証明や職務経歴書の翻訳を求められることが多いので、事前に用意しておくとスムーズに進みます。
フィリピン:各種ビザの分類と投資庁との連携
フィリピンでは、外国人が働く際に一般的に使用されるのが9(g)ビザ(Pre-Arranged Employment Visa)や47(a)(2)ビザなどです。特に、47(a)(2)ビザはPEZA(フィリピン経済区庁)やBOI(投資委員会)登録企業の外国人スタッフ向けに活用されるケースが多く、比較的スピーディに取得できるメリットがあります。
一方、外国人就労者に対してAEP(Alien Employment Permit)という労働省発行の許可証が必要となるなど、ビザと労働許可が別々に管理されている点に注意が必要です。無許可で働いていると、違法就労として多額の罰金が科される恐れがあるため、必ず渡航前に手続きを確認しましょう。
シンガポール:Employment PassとS Passの違い
シンガポールはアジアの金融センターとして、外国人材の受け入れが比較的盛んな国です。ただし、近年は労働力の質を高める目的でビザ要件が厳格化されており、最低月収要件が引き上げられています。代表的な就労ビザとしては、専門人材向けのEmployment Pass(EP)と、中級スキル人材向けのS Passがあります。
Employment Passは、大学卒以上の学歴と管理職・専門職クラスの年収要件を満たすことが求められます。S Passはそれよりもハードルが低いものの、月収要件とクォータ(外国人比率の上限)が設けられているため、企業ごとに割り当て数の制限がある点に注意が必要です。
就労ビザ申請における注意点と書類不備のリスク

多くの国でビザや就労許可の申請には書類が大量に必要となり、提出先も複数にわたります。書類不備があった場合、申請却下や再申請など時間とコストのロスが発生するため、しっかり準備を進めることが大切です。
書類不備による申請却下と再申請の手間
国によって求められる書類はさまざまですが、共通しているのは「不備や不誠実な記載があると申請却下されやすい」という点です。たとえば、企業からの招へい状に記載されている職務内容と実際の職務が大きく異なったり、申請フォームでの数字や日付が一致しなかったりすると、担当官が審査に慎重になってしまいます。
一度申請が却下されると、再申請には新たな手数料と時間がかかるだけでなく、場合によっては追加書類を求められることも少なくありません。ビザの期限が迫っていたり、出張や赴任のスケジュールが決まっていたりすると大きなダメージとなるため、最初から書類の整合性をしっかり確認することが肝要です。
無許可就労がもたらすトラブル事例
ビザの申請遅延や書類不備などを理由に、「とりあえず観光ビザで入国して働き始めてしまう」ケースは絶対に避けましょう。無許可就労が発覚した場合、罰金や企業への制裁、個人のブラックリスト入りなど深刻な問題に発展する可能性があります。特に東南アジア各国では外国人労働者の取り締まりを強化しており、一度違反を犯すと今後のビザ申請に大きなマイナス影響を及ぼすこともあります。
また、無許可就労の状態では労働紛争が起きても法的に保護されにくく、医療保険や社会保障が受けられないといったリスクもあります。企業にとっては、従業員の安全管理上の問題に加え、現地政府やパートナー企業からの信用失墜につながりかねません。
公的機関のチェックポイントを踏まえた事前準備
ビザ申請の前に、各国の移民局や労働省が提示している「チェックリスト」や「ガイドライン」を熟読することをおすすめします。たとえば、シンガポール人材開発省(MOM)やマレーシアのImmigration Departmentなどは公式サイトで詳細な情報を公開しており、書類テンプレートやFAQも掲載されています。JETROなどの日本の公的機関も国別情報をまとめているため、こちらも有効活用するとよいでしょう。
書類作成時には、雇用契約書や経歴証明書の翻訳、企業側の登記証明、税務申告状況など、多岐にわたる要素を確認する必要があります。場合によっては海外在住の行政書士やコンサルタントへ依頼し、抜け漏れなく手続きを進めるのが無難です。
最新の動向と公的機関のサポートを活用するコツ

コロナ禍を経て、多くの国が出入国規制や就労ビザの発給条件を見直しました。現在(2020年代中盤以降)は徐々に緩和が進みつつあるものの、国によってはまだ制限が残っているところもあります。最新のビザ発給情報を把握し、公的機関のサポートを上手に使うことで、スムーズに手続きを進められるでしょう。
コロナ禍以降の入国制限とビザ発給状況
一部の国では、コロナ前と比べてビザ申請数が減り、審査が早く進むケースも報告されていますが、逆に慎重な審査を行う国もあります。たとえば、健康診断書の提出要件が厳しくなったり、ワクチン接種証明が必須となったりする例もあり、時期や国によって変動が大きいのが現状です。
また、オンライン申請に移行した国・地域も増えています。これにより利便性が増す一方で、システムの不具合や提出フォーマットの変更に対応できず、トラブルが発生するケースもあるようです。常に最新の政府公式サイトを確認し、必要があればコールセンターや在日大使館に問い合わせるなど、早め早めの行動を心がけましょう。
JETROや大使館・領事館、現地の投資庁との連携
日本から海外へ進出する場合、JETRO(日本貿易振興機構)は非常に頼りになる存在です。国別の投資ガイドやビザ情報をまとめているほか、セミナーや個別相談会を実施していることも多いので、情報収集の一環としてぜひ活用してください。公的機関だけでなく、各国大使館や領事館、現地の投資庁(BOI、PEZAなど)と連絡を取ることで、具体的な申請手順や優遇措置など有益な情報を得られる可能性があります。
また、進出先での事業内容が現地政府の優先分野(たとえばITやハイテク産業など)に該当する場合、ビザ取得が優遇されるケースがあるため、事業計画書や現地採用計画をしっかり練っておくことも大切です。
まとめ

海外で働くうえで欠かせない「各国のビザ・就労許可取得の流れと注意点」について、基礎から国別の特徴、申請時の注意点、最新動向までを整理してきました。改めて本記事のポイントを振り返ると、以下のステップを意識することでスムーズな手続きが可能になります:
- 就労ビザの意義を正しく理解する
– 観光ビザと違って合法的に働くためのビザであることを認識し、違反リスクを避ける。 - ビザと就労許可の違いを把握して両方を取得する
– 多くの国で就労ビザと労働許可は別々に審査されるため、セットで準備を進める。 - 国ごとの手続きフローを早めに確認する
– タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールなど、それぞれの要件や流れを理解してから行動。 - 書類不備や無許可就労に注意する
– 申請却下やトラブルを避けるため、必要書類リストを事前に確認し、期限と内容に気を配る。 - 最新動向を把握し、公的機関のサポートを活用する
– コロナ禍以降の規制変化や優遇措置をキャッチし、JETROや大使館、投資庁に相談する。
特に、海外事業の円滑な立ち上げを目指す企業にとって、駐在員の派遣は欠かせないステップです。就労ビザが遅れてしまうと、現地での人材配置計画が大幅に狂う恐れがあります。個人で海外就職を目指す場合でも、不法就労や書類不備でトラブルに巻き込まれないためにも、十分な情報収集と計画性が重要です。
もし申請フローが複雑で不安がある場合は、現地に精通したコンサルティング会社や行政書士事務所に依頼するのも一つの手です。最終的には自分自身または自社が責任を持って申請を進める必要がありますが、専門家のサポートを受けることで、書類作成や交渉、言語面での不安を大幅に軽減できます。
海外就労ビザや就労許可を正しく取得し、安全かつ合法的に働く環境を整えられれば、現地でのビジネス拡大やキャリアアップのチャンスは大いに広がります。ぜひ本記事を参考に、早めの準備と適切な手続きを心がけて、東南アジアを中心とする海外での活躍を実現してください。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
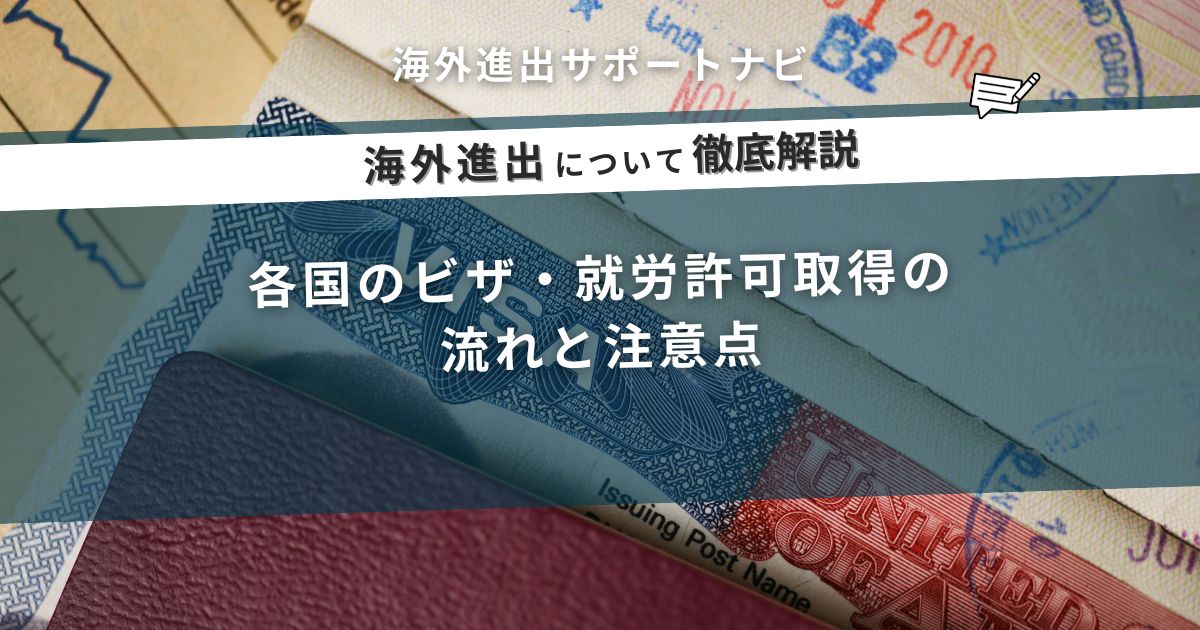
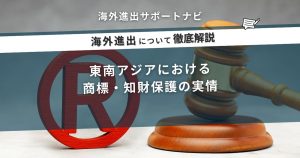
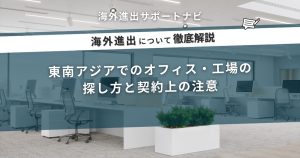
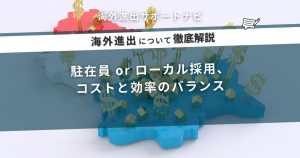
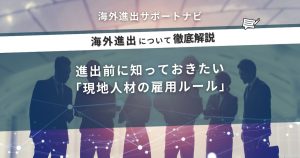
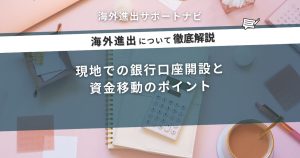
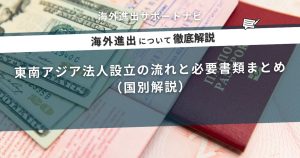
コメント