議事録作成、まだ手作業で行っていませんか?
会議や商談、打ち合わせの内容をしっかり記録しながらも、メモに集中して内容を聞き逃してしまった経験は多くの方にあるはずです。
そんな課題を解決するのが、AIによる「自動文字起こし」や「要約機能」を備えた最新の音声解析ツールです。
本記事では、会議の録音からAIによる要約までの流れを丁寧に解説し、2025年時点で本当に使えるおすすめのAI議事録ツールをご紹介します。
特に注目を集めている「PLAUD AI(プラウド・エーアイ)」についても詳しく解説。
デバイス選びに悩んでいる方や、議事録の効率化を目指すビジネスパーソン必見です。
なぜ今「会議録音×AI要約」が注目されているのか?
近年、業務のデジタル化や働き方の多様化が進む中で、「会議の録音を活用し、AIで自動的に要約・議事録作成を行う」というソリューションが急速に注目を集めています。
これまでのように会議中に必死でメモを取り、後から文章に起こして要約する作業は、もはや非効率の象徴となりつつあります。
こうした中で、音声解析ツールやAI文字起こし技術の進化により、「録音データをそのまま議事録として活用できる時代」が到来したのです。
リモート・ハイブリッド会議の増加
2020年以降、コロナ禍の影響で急速に広まったのが、ZoomやGoogle Meetなどを使ったリモート会議です。
現在では、完全オンラインに限らず、社内の会議室と自宅や外出先をつなぐ「ハイブリッド型」のミーティングも定着しつつあります。
こうした会議体の変化により、参加者の発言を正確に記録・共有するニーズがこれまで以上に高まっているのです。
たとえば、会議中にWi-Fi接続が一時的に不安定になった場合や、他のタスクと並行して会議に参加していたメンバーにとっては、「会議内容の聞き逃し」が避けられません。
このような状況でも、録音を残しておけば後から内容を確認できますし、AIが要点だけを抜き出して要約してくれることで、情報の共有スピードと精度が大幅に向上します。
また、多拠点で働くチームやグローバルな業務環境においても、リアルタイムで議事録を作成することが難しいケースが多くあります。
こうした背景から、「録音×AI要約」は、分散した業務環境における情報伝達手段として非常に重要な役割を果たすようになってきました。
議事録作成の負担と人手不足
議事録の作成は、単に会議内容を記録するだけの作業ではありません。
発言者ごとの内容を正確に把握し、意図を汲み取り、重要な要点をまとめて、読み手に伝わりやすい文章に整える必要があります。
この作業には高度なリスニング力とライティング能力が求められるため、実は非常に負担の大きい業務のひとつです。
特に中小企業やスタートアップでは、専任の議事録担当者を配置することが難しく、多くの場合、会議に参加した人自身が記録を兼ねているケースがほとんど。
こうなると、「発言する側」と「記録する側」を同時に担うことになり、会議の質も記録の精度もどちらも犠牲になるリスクが高まります。
さらに近年では、労働力不足や業務効率化への要求が加速しており、「省人化」と「情報資産の可視化」はあらゆる業界において共通の課題となっています。
こうした背景の中で、AIによる自動文字起こし・要約は、議事録作成という日常業務を抜本的に変革する技術として、非常に注目されています。
生成AIの進化で要約精度が飛躍的に向上
AIによる議事録作成は、以前から一部の業務現場で導入されてきましたが、当初は「文字起こしの精度が低い」「要約の質にばらつきがある」といった課題も多く見られました。
しかし、2023年以降、ChatGPT、Claude、Geminiといった大規模言語モデル(LLM)の進化によって、要約AIの精度は飛躍的に向上しています。
これらのAIは、単に文章を短くするだけではなく、文脈を理解し、「誰が・何を・なぜ」発言したのかという意図まで汲み取って要約を生成できるレベルに到達しています。
特に、日本語の口語表現や会話の曖昧なニュアンスに対応できるモデルも登場し、これまで「使い物にならない」とされていた日本語会議の要約も実用段階に入りました。
このように、AIの進化と活用環境の変化が同時に進んだことで、2025年現在、録音から文字起こし・要約までの自動化は、あらゆる企業で実装可能な実務ツールとなっているのです。
AI要約の仕組みとは?録音から要約までの流れ
AIによる議事録作成は、一見すると魔法のような仕組みに感じられるかもしれません。
しかし実際には、「音声の記録」「音声からテキストへの変換」「テキストの要約」という3つのステップで成り立っています。
ここでは、それぞれの工程について詳しく見ていきましょう。
ステップ① 音声録音
最初のステップは、会議や商談などの音声を正確に録音することです。
この段階で重要なのは、「高品質な音声を収録する」という点です。
雑音が多かったり、話者の声が不明瞭だったりすると、後のAI解析の精度にも大きな影響が出てしまいます。
録音にはスマートフォンのボイスメモ機能でも対応可能ですが、近年ではAI議事録作成に特化した録音デバイスも登場しています。
例えば、「PLAUD Clip」のような小型デバイスは、AI要約を前提としたノイズキャンセリングや自動クラウド連携機能を搭載しており、初心者でも簡単に高品質な録音が可能です。
また、録音は単なる「記録」ではなく、「再利用される情報資産の入力工程」と捉えることが重要です。
AIが活用する前提であれば、声の大きさやマイクとの距離にも配慮し、会話の録音精度を最大限に高める工夫が求められます。
ステップ② 音声認識(自動文字起こし)
次に、録音した音声をAIがテキストに変換する「自動文字起こし」の工程に入ります。
このフェーズでは、AIの音声認識モデルが発言をリアルタイム、または録音ファイルを後処理してテキストに変換します。
現在主流となっているAIモデルは、従来の音声認識よりも格段に高精度で、日常会話や専門用語、イントネーションの違いにも対応できるようになっています。
例えば、PLAUD AIの音声解析では、複数話者の音声を聞き分けて自動的に「誰が何を話したか」を判別する機能も備わっており、人手をかけずに正確な発言記録を作成することが可能です。
さらに、文字起こしされたテキストはクラウドに自動保存され、後から見直すことも、共有することも容易です。
紙や手書きのメモに頼っていた従来の記録手法と比較すると、圧倒的な効率化を実現できます。
ステップ③ 要点抽出・自動要約
文字起こしされた膨大なテキスト情報から、AIが重要な発言や結論を抽出し、簡潔な要約文を生成するのが最終ステップです。
この工程こそ、近年の生成AIの進化が最も発揮される場面でもあります。
従来の要約は「ただ短くする」だけのものでしたが、現在のAI要約は文脈を理解し、「この会議の目的」「何が議論され、どのような結論に至ったのか」を人間のように把握して文章にまとめることができます。
たとえばPLAUD AIでは、音声解析された内容から会議の流れ・結論・アクション項目まで一括で整理され、数秒で議事録形式に出力されるため、業務効率が劇的に向上します。
また、PLAUD AIにはAIによるマインドマップ生成や要点を質問形式で引き出す「Ask AI」といった機能も備わっており、要約の先までを視野に入れた活用が可能です。
単なる「文字起こし」ではなく、情報を“活かす”ための整理・編集までを含めたトータルソリューションへと進化しているのです。
おすすめのAI議事録ツール5選【2025年最新】
会議の録音と要約をAIで効率化できるツールは年々進化しており、2025年現在では数多くの選択肢があります。
ここでは、特にビジネス現場での実用性が高く、実績やユーザー満足度の高いツールを厳選してご紹介します。
特徴や価格帯、使い勝手の違いを把握し、自社に最適なツールを選ぶ参考にしてください。
PLAUD AI|録音から要約・マインドマップ生成まで1台完結
PLAUD AI(プラウド・エーアイ)は、専用デバイス「PLAUD Clip」を使ったAI議事録ソリューションです。
このツールの最大の特徴は、録音・文字起こし・要約・マインドマップ生成までをワンタップ・オールインワンで実現できる点です。
録音はワイヤレスクリップ型のデバイスで手軽に行え、クラウド上のAIが音声を解析して自動的にテキスト化・要点抽出を行います。
さらに、議論内容をマインドマップ形式で整理したり、AIアシスタント(Ask AI)を使って要点を再確認したりと、一歩進んだ情報活用が可能です。
ビジネスだけでなく、セミナー、インタビュー、取材など幅広いシーンで活用でき、操作もシンプルなので、AI初心者にも導入しやすいのも魅力です。
料金はデバイス代と月額のサブスクリプション形式で、詳細は以下の公式サイトでチェックできます。
Otter.ai|英語圏で人気の自動文字起こしツール
Otter.ai(オッター・エーアイ)は、アメリカを中心に人気の高い文字起こしサービスで、特に英語の音声認識精度に定評があります。
ZoomやGoogle Meetといったビデオ会議ツールと連携し、リアルタイムで音声をテキストに変換しながら議事録を生成できるのが特徴です。
日本語対応は限定的ではありますが、英語でのグローバル会議やオンライン講義などで活用するには非常に優秀な選択肢です。
無料プランもあるため、まず試してみたいという方にも適しています。
Notta|多言語対応・ビジネス活用に強い
Notta(ノッタ)は日本国内でも利用者が増えている多言語対応型の音声解析ツールです。
録音データのアップロードによる文字起こしはもちろん、Zoom連携によるリアルタイム書き起こしにも対応しています。
議事録形式で要点を抽出する「要約」機能も搭載されており、プロジェクト管理やチーム共有にも向いた構成が強みです。
操作性も高く、音声解析に関するUXがしっかり設計されている点も評価ポイントです。
Google Recorder|Android端末向けの手軽な選択肢
Google Recorder(グーグル・レコーダー)は、Google Pixelなど一部のAndroidスマートフォンに搭載されている純正録音アプリです。
無料で利用できるにも関わらず、音声から文字起こしまでを自動で行ってくれるため、手軽な議事録代替ツールとして注目されています。
ただし、要約機能や多言語対応、クラウド同期などの面ではやや限定的です。
「まず試したい」「個人利用から始めたい」という方にとっては、十分な機能を備えたエントリーレベルの選択肢と言えるでしょう。
CLOVA Note|LINEの音声AI技術を活用
CLOVA Note(クローバ・ノート)は、LINEヤフーが提供する音声文字起こしサービスで、日本語の自然な会話に強い点が魅力です。
会話ごとの話者分離や、重要発言のハイライト機能など、日本語会議に特化した設計が特徴となっています。
無料プランでも一定の利用が可能で、LINEアカウントと連携することで手軽に始められる点も嬉しいポイントです。
ただし、要約機能や高度な解析については限定されているため、「聞き返し防止」や「メモ代替」としての活用に向いています。
PLAUD AIを使った録音・要約の具体的な使い方
ここからは、PLAUD AIを実際にどのように使って「録音 → 文字起こし → 要約」までを完結させるのか、その具体的な流れを3ステップでご紹介します。
「音声解析ツールは難しそう」「機械が苦手」という方でも安心して使える設計になっているため、初めてAI議事録ツールを導入する企業や個人にもおすすめです。
専用デバイス「PLAUD Clip」での録音
PLAUD AIの魅力のひとつは、録音専用デバイスである「PLAUD Clip」の存在です。
この小型クリップ型デバイスは、シャツや胸元に装着するだけで会議や商談の音声を高音質で録音してくれます。
ノイズリダクションや複数マイクによる音声補正機能も搭載されており、雑音の多い場所でもクリアな音声を収録できるのが特徴です。
録音操作も非常にシンプルで、ボタンをワンタップするだけ。
録音が終了すると、デバイスがスマートフォンアプリと自動的に同期され、音声データは即座にクラウド上にアップロードされます。
これにより、その場で文字起こし・要約の処理がスタートします。
アプリ連携で自動文字起こし・要約生成
録音したデータは、PLAUD AIのモバイルアプリ(iOS/Android)と連携して自動的に文字起こしが行われます。
この際、話者の区別(スピーカーダイアリゼーション)や時間ごとの発言タイムスタンプも自動で付与されるため、後から確認・編集する際も非常に便利です。
文字起こしが完了すると、AIがテキスト内容を解析し、会議の要点を数行でまとめた要約文を自動生成します。
この要約は、読みやすいナチュラルな日本語で表現されており、社内資料や報告書にもそのまま転用できる品質です。
編集機能も備わっているため、必要に応じて補足や修正も可能です。
特に便利なのは、複数の会議や打ち合わせを日付・テーマごとに自動分類できる点です。
「どの案件の議事録だったか?」と後で探す手間が省け、過去のデータをすぐに参照できるナレッジ管理にも役立ちます。
マインドマップ・Ask AIで情報整理もスムーズ
PLAUD AIのもうひとつの革新的な機能が、自動マインドマップ生成機能です。
会議の議題や議論の流れ、結論に至るまでの要素をビジュアル的に整理してくれるため、「何が重要だったか?」を視覚的に捉えることができます。
また、文字起こしされた内容に対して「この会議の結論は?」「誰がどの発言をした?」などの質問をすると、AIが要点を回答してくれる「Ask AI」機能も搭載。
情報をただ保管するだけでなく、“使える知識”として再活用できる仕組みが整っています。
これらの機能を活用することで、単なる議事録作成にとどまらず、業務の可視化・ナレッジ共有・意思決定の高速化にもつながります。
まさにPLAUD AIは、「録音×AI」のその先を見据えたツールなのです。
AI議事録ツールを選ぶときの3つの注意点
AI議事録ツールは非常に便利ですが、選定を誤ると「思ったほど使えなかった」「精度が低くて結局手動で直すことに…」といった残念な結果につながることもあります。
ここでは、導入前に確認すべき3つのポイントをご紹介します。
特に業務での本格利用を検討している方は、必ずチェックしておきましょう。
セキュリティ・クラウド保存の有無
議事録には、企業の機密情報や個人情報、顧客情報などが含まれるケースも少なくありません。
そのため、AIツールを選ぶ際にはデータの暗号化、保存先クラウドの安全性、アクセス制限などのセキュリティ対策が重要です。
特に、海外製のフリーツールや無料サービスは、データ保管先が不明瞭だったり、商用利用に関する制限があるケースもあるため要注意です。
PLAUD AIでは、クラウド上に保存された音声・テキストデータはすべて暗号化通信によって保護され、日本語環境に最適化されたプラットフォームで運用されています。
「議事録の内容を外部に漏らしたくない」「情報統制が求められる業種に従事している」という方は、必ずセキュリティ仕様も確認したうえで導入しましょう。
精度と話者分離性能
AI議事録ツールの実用性は、文字起こしと要約の精度によって大きく左右されます。
特に日本語では、話し言葉が省略されたり曖昧な表現が多かったりするため、言語処理性能の高さが重要です。
また、1対1の会話であれば問題なくても、3人以上の会議になると「誰が何を話したか」を識別する話者分離機能が求められます。
この機能が不十分なツールでは、議事録に誤情報が混在する恐れもあるため、実際の利用シーンに即して比較することが大切です。
PLAUD AIは、日本語音声に特化した音声認識モデルを搭載しており、複数話者の区別や発言順の整合性にも優れているのが大きな特長です。
商談・会議・セミナーなど、複数人が発言するシーンでも精度の高い記録が可能です。
費用対効果(デバイス・月額・無料枠)
AI議事録ツールは無料で使えるものから、専用デバイスと連携した有料サービスまで、料金体系が大きく異なります。
ツール選びの際には、初期費用(端末代など)と月額利用料のバランスをしっかり確認することが重要です。
「無料で試せるけど機能が制限されている」「課金しないと要約機能が使えない」などの制約がある場合もあります。
その点、PLAUD AIは録音・文字起こし・要約・マインドマップ生成までをワンパッケージ</strongで提供しており、追加費用なしで一通りの機能をフル活用できる構成になっています。
業務効率化によって得られる「時間的コストの削減」を含めて考えると、月数千円の投資で大きな生産性向上が見込めるツールは、非常に費用対効果に優れていると言えるでしょう。
まとめ|AIで議事録作成をもっとラクに。PLAUD AIは初心者にも最適
会議や打ち合わせの議事録作成は、多くのビジネスパーソンにとって「地味だけど避けられない」業務のひとつです。
しかし、AI技術の進化により、音声を録音するだけで文字起こしから要約、さらにはマインドマップ生成まで自動化できる時代が到来しました。
中でもPLAUD AIは、録音専用の高性能デバイス「PLAUD Clip」と、使いやすいスマートフォンアプリを連携させることで、“議事録作成”という業務を丸ごと効率化できる革新的なツールです。
特別なスキルや操作は一切不要で、録音→自動テキスト化→要約→活用という流れを誰でも簡単に実現できます。
導入すれば、議事録作成にかかっていた時間やストレスから解放され、会議の本質である「内容の充実」と「決定事項の活用」に集中できるようになります。
「議事録に時間をかけたくない」「会議をもっと意味あるものにしたい」「記録と要点整理を自動化したい」——。
そんな思いをお持ちの方にこそ、PLAUD AIは自信を持っておすすめできる一台です。
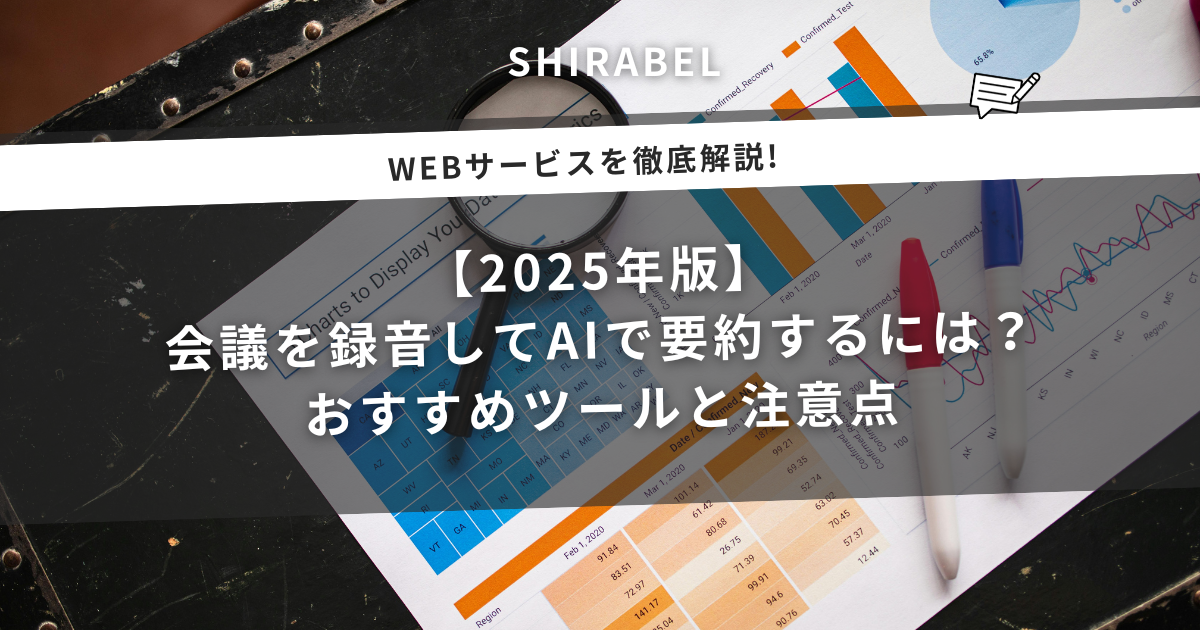
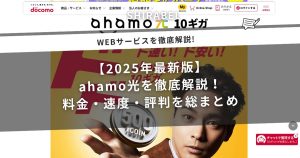
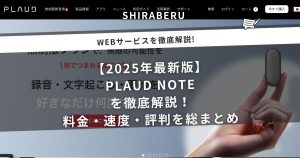


コメント