会議や打ち合わせの議事録を作成する作業に、毎回時間と労力をかけていませんか?
近年、音声をAIで自動的に文字に起こし、議事録まで整えてくれる「文字起こしAI」ツールの導入が、業務効率化の切り札として注目されています。
本記事では、2025年現在で本当に使える文字起こしAIツールを10種類厳選してご紹介します。
議事録の自動化を目指す方、録音データをすぐにテキスト化してチーム共有したい方に向けて、それぞれの特徴・違い・活用方法を徹底比較。
特に日本語対応の精度と要約機能で高評価を得ている「PLAUD AI」にも注目しながら、最適なツール選びをサポートします。
なぜ今「文字起こしAI」がビジネスで注目されているのか?
リモート会議・録音文化の定着
2020年以降、テレワークの普及によりZoomやGoogle Meetなどを活用したオンライン会議が一般化しました。
現在ではハイブリッド型のミーティングや、音声・動画のアーカイブ文化が根付いており、「録音してあとで見返す」というスタイルがスタンダードになりつつあります。
こうした変化により、録音データを業務に活かすニーズが爆発的に高まりました。
特に「会議中にメモを取らなくても済む」「重要な発言だけを後から確認できる」など、録音→文字起こし→議事録の自動化という流れが、新たな業務効率化の定番として定着し始めています。
議事録作成の省人化ニーズの急増
議事録を正確に作成するには、録音を聞き直し、発言内容を要約し、文体を整える必要があります。
このプロセスは時間もスキルも求められ、特にリソースの限られた中小企業やスタートアップでは大きな負担となっていました。
そこで今注目されているのが、AIによる自動文字起こしと要約生成を活用する方法です。
1時間の会議を録音すれば、そのまま数分以内にテキスト化され、議事録としてチームに共有できる。
これにより、1人あたり月に数時間〜十数時間の削減が可能となり、バックオフィス業務のコストダウンにも直結します。
さらに、従業員の定着や人手不足への対策としても、省人化の手段としてAI議事録の導入が進んでいます。
会議に集中しながら記録は自動化できる環境は、現代のスマートな働き方にぴったりと言えるでしょう。
生成AIの進化と日本語対応の質向上
かつての文字起こしツールは、単なる音声認識ソフトにとどまり、変換精度や文章構造の不自然さが課題でした。
しかし2023年以降、ChatGPTやClaudeなどの生成AI(大規模言語モデル)の登場により、音声から自然な文章への変換能力が格段に進化しました。
とりわけ日本語においては、従来の「カタコト翻訳的」な精度から、会話の流れや意図、話者ごとの文脈を読み取る高度な自然言語処理が可能に。
「誰が、何を、なぜ発言したか」までをAIが理解し、文脈のある文章として出力できるようになったことで、文字起こしAIは議事録作成の代替ではなく“アップグレード”という位置付けに変わりつつあります。
この流れに乗り、PLAUD AIのように日本語特化の音声処理と生成AIを融合させた新しい世代のツールが誕生しています。
今後、議事録に限らず、取材・インタビュー・講義・カスタマーサポートなど、あらゆる分野で文字起こしAIの活用は拡大していくでしょう。
文字起こしAIの選び方|チェックすべき5つのポイント
文字起こしAIツールは年々増加しており、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
単純に「音声がテキスト化されればOK」ではなく、用途・業種・精度・機能・価格によって、選ぶべきサービスは変わってきます。
ここでは、失敗しないための選定基準を5つに絞って解説します。
日本語精度と要約機能の有無
日本語対応の精度は、文字起こしAIを選ぶ上で最も重要なポイントです。
英語圏の開発ツールは多く存在しますが、日本語独特の曖昧な表現や敬語・イントネーションに対応しきれないケースも多く見られます。
また、文字起こしだけでなく要約が可能かどうかも重要です。
会議や講演のすべてを文字に起こすと膨大な情報量になりますが、要点だけを抜き出してくれるツールであれば、議事録作成や報告資料の作成が一気に楽になります。
たとえば、PLAUD AIは日本語対応に特化しており、音声認識精度と自然な要約生成の両立を実現しています。
「話し言葉を“書き言葉”に変換する能力」が高いため、業務レポートへの転用にも適しています。
リアルタイム対応 vs 録音アップロード型
文字起こしには大きく分けて「リアルタイムで書き起こすタイプ」と「録音したデータを後でアップロードするタイプ」の2種類があります。
リアルタイム型はZoomやGoogle Meetと連携して会議中にテキスト化できるのが利点ですが、処理がやや不安定になるケースや、内容を落とすリスクもあります。
一方、録音型は後処理のため時間はかかりますが、正確な書き起こしと要約生成に適しているのが特徴です。
PLAUD AIは録音特化型で、専用デバイスを使って高音質に録音した音声をクラウド上で処理するため、精度と安定性の面で非常に優れています。
セキュリティ・保存場所(クラウド/ローカル)
業務上の会話や顧客との打ち合わせ内容など、機密性の高い情報を扱う場面では、保存形式やセキュリティ対策にも注目する必要があります。
クラウド保存の場合、通信やデータ管理が安全に行われているか、暗号化やログ管理の仕組みがあるかを必ず確認しましょう。
ローカル保存が可能なツールであれば、自社内のセキュリティポリシーにも柔軟に対応できます。
PLAUD AIは録音データを暗号化通信でクラウドに保存し、ユーザーごとにアクセス制限を設定可能。
法人ユースでも安心して導入できるセキュリティ設計が整っています。
コストと導入しやすさ(無料枠・月額)
文字起こしAIツールは、無料プラン・定額サブスクリプション・買い切り型など様々な料金体系があります。
「無料だから」と飛びつくと、機能制限が多すぎて業務利用に耐えないケースもあるため注意が必要です。
有料プランでは、月額1,000〜3,000円程度が一般的ですが、要約や翻訳など追加機能があると価格が上がる傾向にあります。
そのため、「自分に必要な機能が含まれているか」と「月額に見合う効果が得られるか」を見極めることが重要です。
PLAUD AIは専用デバイスの購入が必要ですが、録音から要約までを一括で完結できるため、長期的に見れば最も高コスパな選択肢とも言えるでしょう。
議事録フォーマット・共有機能の有無
文字起こしができても、結局その後の「議事録として整える作業」が手間になってしまう場合もあります。
そのため、要点を自動で整理して、議事録形式で出力できる機能が備わっているかどうかは見逃せません。
また、社内共有やGoogle Docs連携、Slack通知など、チーム単位で情報共有しやすい環境が整っているかも選定のポイントです。
PLAUD AIは、マインドマップ生成や「Ask AI」による要点検索など、議事録の“その先”を見据えた機能が充実しています。
録音内容をチームのナレッジとして活用する観点からも、高い評価を得ています。
【比較表付き】音声→テキスト化ツール10選まとめ
ここでは、2025年現在で評価の高い文字起こしAIツールを厳選して10種類ご紹介します。
それぞれに特長や得意分野があるため、「何に使いたいか?」「どんな機能が必要か?」に応じて最適なツールを選びましょう。
まずは比較表で主要スペックを一覧化し、その後に各ツールの詳細を紹介します。
| ツール名 | 日本語対応 | 要約機能 | 録音方式 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| PLAUD AI | ◎ | ◎ | 専用デバイス | 高精度日本語・要点抽出・マインドマップ |
| Otter.ai | △(精度低) | ○ | リアルタイム&録音 | 英語圏で高評価/Zoom連携◎ |
| Notta | ○ | ○ | 録音アップロード | 多言語対応/使いやすいUI |
| CLOVA Note | ◎ | △ | 録音アップロード | 日本語話者分離/LINE連携 |
| Google Recorder | ○ | × | リアルタイム | Pixel限定/無料で使える |
| Whisper | ◎(環境依存) | × | 録音アップロード | OpenAIのOSS/開発者向け |
| AI GIJIROKU | ◎ | ○ | リアルタイム&録音 | 法人導入多数/議事録特化 |
| AmiVoice ScribeAssist | ◎ | ○ | 録音アップロード | 老舗の安定感/医療・会議に強い |
| Voistand | ○ | × | 録音アップロード | 教育機関向け/コスパ◎ |
| Speechy | ○ | × | リアルタイム | iOS専用/手軽に使える |
PLAUD AI|高精度な日本語文字起こし+要約+マインドマップ
PLAUD AIは、日本語対応に特化した文字起こし&要約AIツールです。専用の録音デバイス「PLAUD Clip」を使用することで、高精度の音声データをクラウド上で自動処理。
文字起こしから要約生成、マインドマップ作成まで、ワンタップで完結できるのが大きな特長です。
特に、日本語の口語表現や曖昧な言い回しに対応する精度の高さは業界トップクラス。
生成された議事録は文脈が自然で、報告書や資料としてそのまま転用可能です。
また、AIアシスタント「Ask AI」を使えば、「誰が何を話したか」「重要な結論はどこか」といった情報を対話形式で抽出可能。
営業、会議、取材、講演、教育など幅広い業務にフィットするオールインワン型の業務効率化ツールです。
Otter.ai|英語圏で高評価のリアルタイム議事録化ツール
Otter.aiは、アメリカを中心に人気の高い文字起こしAIツールです。
英語のリアルタイム文字起こしに特化しており、Zoom・Google Meet・Microsoft Teamsなどとの連携で会議中にそのまま文字起こしと要点の抽出が可能です。
日本語への対応は限定的なため、日本国内の会議用途には不向きですが、英語での国際会議や講義録音には最適。
無料プランでも毎月一定時間まで利用でき、操作も直感的で使いやすいため、英語ユーザーには根強い人気があります。
Notta|多言語対応&高い操作性が魅力の万能型
Nottaは、日本語・英語・中国語など100以上の言語に対応した多言語型の文字起こしAIです。
録音した音声ファイルをアップロードすれば数分で文字起こしが完了し、要約・翻訳・共有もスムーズに行えます。
ビジネス向けの議事録テンプレートやタイムスタンプ機能も充実しており、音声データの管理・活用に優れたUI/UXが高く評価されています。
Zoom連携によるリアルタイム文字起こしも可能で、柔軟性の高いツールです。
CLOVA Note|LINEヤフーの日本語話者分離に強いツール
CLOVA Noteは、LINEヤフーが提供する日本語の話者分離に強い音声解析サービスです。
複数人の会話を録音した際に、「誰が・何を・いつ」話したかを自動判別して文字起こししてくれるため、インタビューや会議の整理に最適です。
音声ファイルのアップロード型であり、LINEアカウントがあれば簡単に始められるのも利点。
ただし、要約機能や連携性の面ではやや限定的なため、補助的な用途や個人利用に向いています。
Google Recorder|Pixelユーザー限定の無料文字起こしアプリ
Google Recorderは、Pixelスマートフォン専用に提供されている純正の文字起こしアプリです。
録音と同時にリアルタイムで文字に変換され、検索・コピー・共有などの基本機能も揃っています。
Google製という安心感がありながら完全無料で使えるのが最大の魅力ですが、日本語認識の精度や要約機能は未対応です。
個人でメモ用途に使うには十分な機能を備えていますが、業務用途にはやや物足りなさがあるかもしれません。
Whisper(OpenAI)|開発者向けの高精度なオープンソースモデル
Whisperは、ChatGPTなどを開発したOpenAIが公開しているオープンソースの音声認識モデルです。
ローカル環境に構築して利用でき、複数言語に高精度で対応可能。
日本語音声の認識率も非常に高く、エンジニアやAI開発者に人気があります。
ただし、自力で環境構築やプログラミング知識が必要であり、一般ユーザー向けではありません。
API連携やカスタム処理など、独自システムに文字起こしを組み込みたい場合には強力な選択肢です。
AI GIJIROKU|議事録自動化に特化した法人向けツール
AI GIJIROKUは、その名の通り議事録作成に特化した国内製AIツールです。
複数話者の音声をリアルタイムで文字起こしし、発言者ごとの要点を自動整理する機能を備えています。
ZoomなどのWeb会議ツールとも連携可能で、導入実績も豊富。
料金は法人向けのためやや高額ですが、社内の情報資産化・ナレッジ共有を重視する企業には非常にマッチします。
AmiVoice ScribeAssist|医療・議会でも活用される老舗ソリューション
AmiVoice ScribeAssistは、音声認識技術で20年以上の実績を持つアドバンスト・メディア社の法人向けAI議事録サービスです。
医療・議会・裁判など、精度が強く求められる現場で多数採用されています。
発言者ごとの話し方のクセに対応した学習型の文字起こしや、クローズド環境での利用も可能な高セキュリティ設計が特長です。
一方で、個人や小規模チームには導入ハードルが高いため、エンタープライズ向けの本格ツールとして位置づけられます。
Voistand|教育機関で注目されるコスパ重視型
Voistandは、音声ファイルをアップロードして文字起こしを行うシンプルなクラウドツールです。
リーズナブルな価格設定と簡易な操作性から、学校やゼミ、インターン現場など教育分野で多く利用されています。
リアルタイム文字起こしや高精度な話者分離には非対応ですが、「授業内容をテキストで残したい」「議論の記録を取りたい」といった用途には十分な性能を発揮します。
Speechy(スピーチー)|iOS専用のシンプル録音+文字起こしアプリ
Speechyは、iPhone/iPadで使える音声録音&文字起こしアプリです。
会話をその場で録音し、アプリ内で文字に変換できる手軽さが魅力で、学生や個人事業主に人気です。
文字起こしの精度は日常会話レベルであれば十分ですが、要約機能やビジネス向けテンプレートなどは備わっていません。
「とりあえず文字にしたい」「アプリで完結したい」という人向けのライトユース型ツールと言えるでしょう。
PLAUD AIが選ばれる理由と活用シーン
多くの文字起こしAIツールがある中で、なぜPLAUD AIが支持されているのでしょうか?
ここではその3つの大きな理由と、実際に活用されているシーンをご紹介します。
日本語会議・商談に最適な理由
PLAUD AIは、海外製ツールでは対応が難しい日本語特有の口語表現・会話の文脈理解に強みがあります。
単なる「文字変換」にとどまらず、話者の意図や結論をくみ取った自然な文章に仕上げるため、会議記録や営業報告としてそのまま活用できるのが特徴です。
特に、複数人が自由に話す「会議形式」の音声でも、話者を識別しながら文字起こしが行えるため、読みやすく、使いやすい日本語議事録が自動で完成します。
要点抽出・要約・マインドマップが1クリック
PLAUD AIのもうひとつの大きな強みが、要点抽出機能とマインドマップ生成機能です。
通常の文字起こしでは、膨大なテキストから必要な情報を探すのが大変ですが、PLAUD AIなら議事の要点を数行で自動要約してくれます。
さらに、会話の流れや論点をマインドマップ形式で自動整理することで、情報の関連性がひと目で把握可能に。
「この会議、結局何が決まったんだっけ?」という疑問を解消し、議事の“可視化”を強力にサポートします。
また、生成された内容に対して「この議題の結論は?」「発言者Aの主張は?」といった質問を投げかけると、AIが瞬時に回答してくれる「Ask AI」機能も搭載。
文字起こしの先にある“活用”までを視野に入れた、非常に実用性の高いツールです。
現場導入事例(営業・医療・メディアなど)
PLAUD AIは、業種を問わず多くの現場で導入されています。代表的な活用例としては、以下のようなシーンがあります:
- 営業現場:商談の録音をPLAUD Clipで収録 → 要点抽出 → 日報やCRMへの転記が不要に
- 医療現場:問診内容やカンファレンスの記録を正確に残し、スタッフ間の情報共有をスムーズに
- 報道・メディア:インタビュー音声からのスピーディな文字起こし&要点まとめで記事制作を時短化
- 人事・労務:1on1面談や社内会議の記録を自動化し、レポート提出の手間を削減
- 講義・教育:講演や授業を記録し、学生向けに内容をマインドマップで整理・共有
このように、“記録する”だけでなく、“伝える・使う・残す”という視点で業務の質を底上げできるのがPLAUD AIの真価です。
よくある質問と導入前の注意点
ここでは、初めて文字起こしAIやPLAUD AIの導入を検討している方からよく寄せられる質問と、その回答をQ&A形式でまとめました。
不安や疑問を解消し、自信をもって導入に踏み出すための参考にしてください。
Q1. 無料でどこまで使えますか?お試しは可能ですか?
PLAUD AIにはアプリ単体での無料お試し期間が用意されており、一部の機能(文字起こしや短い音声ファイルの処理)を体験できます。
ただし、本格的な録音・要約機能を最大限に活用するには、専用デバイス「PLAUD Clip」の導入が推奨されます。
比較的手頃な価格帯でありながら、議事録作成からマインドマップ整理まで一括で自動化できるため、費用対効果は非常に高いです。
Q2. 音質が悪いと文字起こしの精度は落ちますか?
はい、AIの文字起こし精度は録音時の音質に大きく左右されます。
雑音が多かったり、話者の声が小さい場合には、誤認識や抜け落ちが発生することがあります。
PLAUD AIは、専用デバイスが高性能なノイズリダクション・マイク補正機能を備えているため、一般的なスマホ録音よりも圧倒的に認識率が高く、文字起こし精度の安定性に優れている点が強みです。
Q3. 社外秘や個人情報を録音しても安全ですか?
PLAUD AIでは、音声やテキストデータをクラウド上に暗号化して安全に保存しており、ユーザーごとに閲覧権限を管理できます。
また、データは日本語環境に最適化された国内のセキュアサーバーに保管される設計のため、機密性の高い業務でも安心して利用可能です。
企業として情報保護体制を重視している場合も、利用ガイドラインに沿って活用すれば、セキュリティポリシーにも十分対応できます。
Q4. 導入にあたって面倒な設定やIT知識は必要ですか?
一切不要です。PLAUD Clipはワンタップ操作で録音・送信でき、スマホアプリと連携するだけで文字起こし・要約処理が自動で開始されます。
専用アプリは直感的に使えるデザインとなっており、ITが苦手な方でもすぐに業務で活用できるのが魅力です。
初期設定も数分で完了し、導入ハードルは極めて低いと言えるでしょう。
まとめ|議事録作成を自動化するなら日本語に強いPLAUD AIから
議事録作成の手間や、会議内容の記録ミス、情報共有の遅れ…。
そんな日常的な業務課題を、いまやAIが丸ごと解決してくれる時代が到来しています。
本記事でご紹介した通り、文字起こしAIツールにはさまざまな種類があり、それぞれに得意分野があります。
その中でも「日本語での会議や商談の議事録を、自動で・正確に・すぐ使える形でまとめたい」というニーズに対しては、PLAUD AIが最も信頼できる選択肢と言えるでしょう。
録音から文字起こし、要約、マインドマップ生成までをワンタップで完了でき、ITスキルがなくても扱える操作性。
さらに、セキュリティや共有性にも配慮されており、個人から法人まで、幅広いビジネスシーンに対応しています。
議事録にかけていた時間が10分の1になれば、その分だけ「考える」「判断する」ことに集中できます。
AIを“記録係”として活用し、チームの生産性を底上げする一歩を、今すぐ踏み出してみませんか?
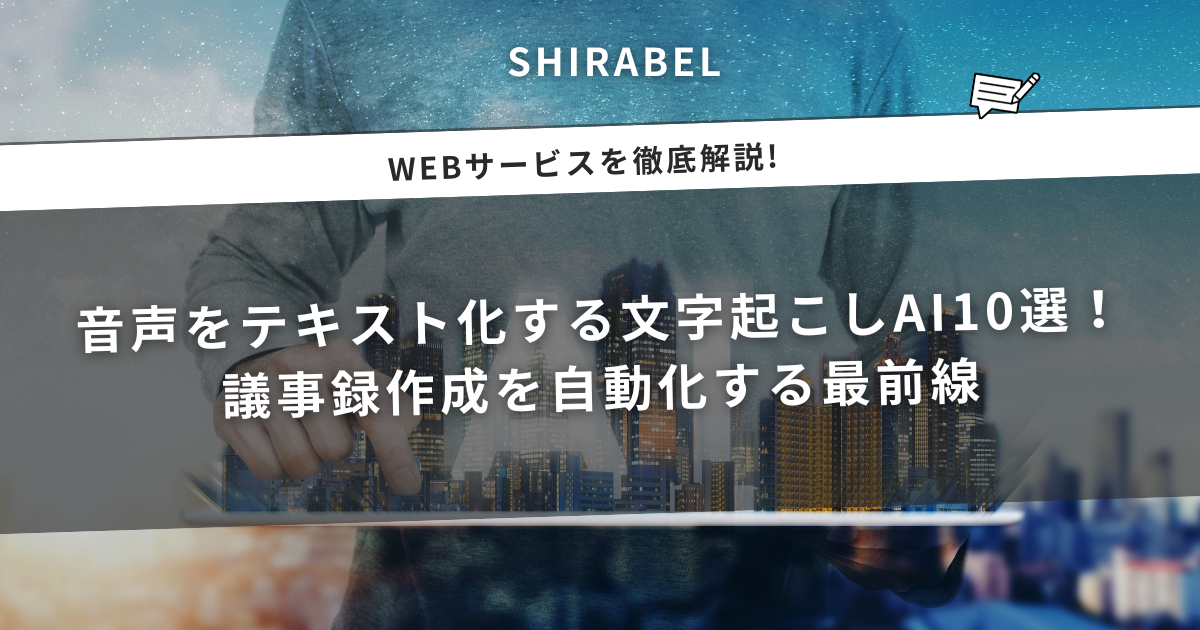
コメント