東南アジアは、世界銀行や国際通貨基金(IMF)が公表する経済指標においても、近年高い成長率を維持しており、日本企業の海外進出先として人気の高い地域となっています。タイやベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールなどの国々では、若年層が多く内需が拡大しているほか、外国企業誘致に積極的な政策を打ち出していることも追い風です。
しかし、こうした国々へビジネスを展開するにあたって見落とせないのが、現地での会計・記帳実務です。各国ごとに異なる会計基準や税制に対応しなければならないうえ、言語や文化の違いも加わるため、日本企業にとっては難易度が高いと感じられる場面が少なくありません。特に、現地法人や支店を構える場合は、月次・年次の決算業務や税務申告など「会計処理」にまつわる手続きを正しく行わないと、余計なペナルティやトラブルを招く可能性があるでしょう。
そこで本記事では、東南アジア6か国の会計処理や記帳ルールについて、初心者にもわかりやすくポイントを整理します。それぞれの国が採用している会計基準や、法人税・消費税(VAT、SST、GSTなど)との関連性、さらに現地スタッフや会計事務所との連携方法など、幅広く解説していきます。公的機関(JETROなど)のデータや実務事例も交えながら、長期的に安定した事業運営を実現するためのヒントを提供しますので、ぜひ参考にしてください。
なぜ東南アジアの会計処理を理解する必要があるのか

海外に進出する際、最も優先されるのは市場のポテンシャルや商談のチャンス、あるいは生産コストの低減などですが、現地の会計や税務制度を無視すると後々大きなリスクに直面することになります。ここでは、東南アジアの会計処理の特徴を把握すべき背景と、関連データのポイントを見ていきましょう。
国ごとに異なる会計基準や税制の複雑さ
タイやベトナム、インドネシアなど、東南アジアの主要国はそれぞれ独自の会計基準や税制を採用しています。日本の会計基準やIFRS(国際財務報告基準)とは似ている部分もあれば、まったく違うルールがある場合もあり、そのまま日本国内の経理感覚で運用しようとすると混乱が生じるかもしれません。
例えば、ベトナムには「赤インボイス(Red Invoice)」という独特の帳票管理があり、これを適切に処理しないと仕入VATの控除を受けられないリスクがある一方、タイでは企業規模に応じて月次決算やVAT申告の頻度が決まっているケースがあるなど、細かいルールが多数存在します。こうした違いを把握せずに記帳を行うと、最終的な決算や税務申告に不備が出やすくなり、罰則や追加徴税のリスクが高まるのです。
公的機関データから見る海外進出企業の課題
日本貿易振興機構(JETRO)や各国の投資庁、世界銀行が発表する資料を読むと、海外進出に成功している企業は早い段階で現地の会計・税務制度を把握し、それに合わせた内部体制を整備している事例が多いことがわかります。逆に、現地ビジネスの規模が拡大するにつれて経理業務が煩雑化し、手が回らなくなるケースや、申告期限を失念してペナルティを受けるケースなども報告されています。
また、COVID-19以降はデジタル化やリモートワークが進む一方で、現地の税務当局がオンライン申告システムを採用し始めるなど、ルールが頻繁に変わる可能性もあります。最新情報を常に追いかけながら、記帳・会計処理をアップデートしていく姿勢が求められているのです。
記帳・会計処理における各国の基本ルール(タイ・ベトナム・インドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール)
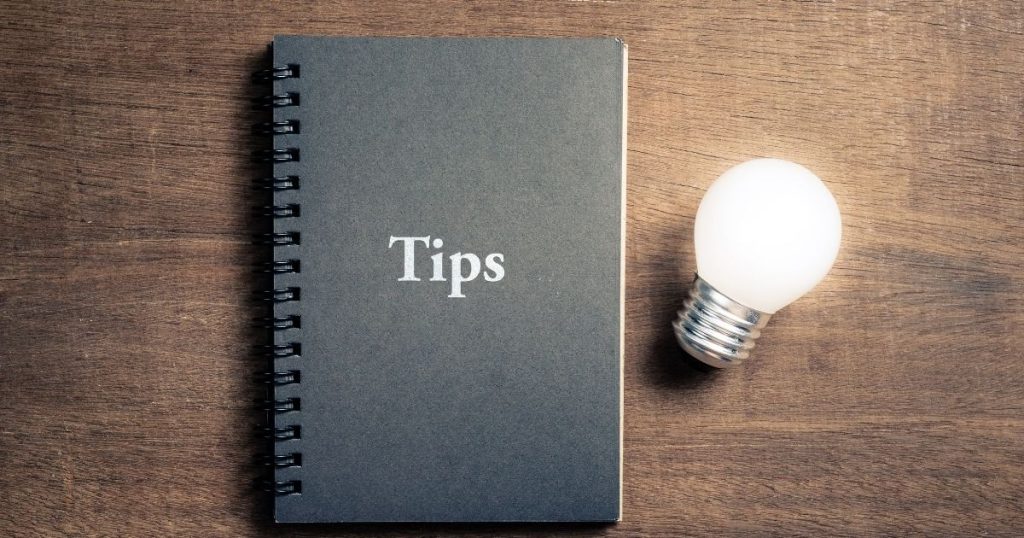
ここからは、東南アジア6か国それぞれの会計処理・記帳面で押さえておきたいポイントを概観していきます。国ごとの特徴を把握するだけでも、事前準備やトラブル回避に大いに役立つでしょう。
タイ:月次決算とVAT申告のポイント
タイでは企業規模に関係なく、基本的に毎月決算を行うことが求められ、付加価値税(VAT)の申告・納付も月次ベースで行われます。VAT税率は通常7%で、サービス・商品によっては免税扱いや軽減税率が適用される場合があります。タイ投資委員会(BOI)の認可を受けた企業は法人税率の減免や一部のVAT免除措置を受けられるため、投資プロジェクトの性質によっては会計処理に影響を及ぼすケースもあります。
また、タイ国歳入局の規定では原本の帳簿を英語で作成することは可能ですが、タイ語での対応を求められる場面もあるため、ローカルスタッフや会計事務所との連携が不可欠です。給与計算や社会保険処理も毎月同時期に行われるため、タイ独自の休日やカレンダーを踏まえたスケジュール管理が大事になります。
ベトナム:赤インボイス(Red Invoice)と帳簿整備
ベトナムの会計制度は、基本的にベトナム会計基準(VAS)をベースにしていますが、近年はIFRS導入へのロードマップが検討されています。消費税にあたるVATは通常10%で、食品など一部品目は5%の軽減税率が適用され、輸出取引にはゼロ税率となっています。企業は定期的にVAT申告を行い、仕入VATと売上VATを差し引いて納付する仕組みです。
独特なのが「Red Invoice(赤インボイス)」という公式インボイスです。正規のRed Invoiceを発行・受領しないと仕入VAT控除が認められないなど、インボイス管理が厳格な点が挙げられます。これを電子化する動きも加速しており、2020年代に入ってからはE-Invoiceの導入が進んでいるため、システム対応や帳簿電子化の準備が必要となるでしょう。
インドネシア:現地GAAPと付加価値税(PPN)の管理
インドネシアは、2012年頃から自国の会計基準をIFRSに近づける動きを見せており、実質的にインドネシアGAAP(PSAK)がIFRSを踏襲している部分があります。ただし、一部の測定や開示要件で独自の規定が残っているため、IFRSとの完全な整合性はまだ達成されていません。
付加価値税(PPN)の標準税率は10%で、輸出はゼロ税率です。さらにラグジュアリー税(PPnBM)が特定の高級商品に対して上乗せ課税されるケースもあります。月次のVAT申告が必要で、申告期限を過ぎると罰金が科される恐れがあるため、現地の税務カレンダーに沿った確実な処理が求められます。
マレーシア:SST下での売上税・サービス税の記帳
マレーシアでは2015年にGoods and Services Tax(GST)が導入されましたが、2018年に政権交代があった影響で再度廃止され、Sales and Service Tax(SST)方式へ回帰しています。SSTは売上税(5〜10%)とサービス税(6%)に分かれ、業種・品目ごとに課税対象や税率が変わる点が特徴です。申告・納税は2か月ごとのバイマンスリー形式が一般的です。
法人税は原則24%のフラットレートで、中小企業向けに低減税率が適用される場合もあります。会計基準はマレーシア独自の「Malaysian Financial Reporting Standards(MFRS)」がベースとなり、多くの場合IFRSとほぼ同様ですが、特定の差異に留意が必要です。
フィリピン:英語での会計処理とローカル要件
フィリピンは英語が公用語の一つであり、会計処理や帳簿作成を英語で行いやすい国ですが、その一方でローカル税務署の規定により、ローカル言語(タガログ語)での書類提出や表記を求められるケースがある点に注意が必要です。法人税は、2021年に施行されたCREATE法により大企業25%、中小企業20%に引き下げられ、投資誘致策が強化されました。
消費税に相当するVATは基本12%で、輸出取引や特定サービスに対してはゼロ税率が適用されることがあります。VAT還付手続きが煩雑なため、一定の売上規模を超える企業では、月次記帳と厳格なインボイス管理が不可欠です。国税庁(BIR)が定める規定に従って書類を保管し、定期的な監査や抜き打ち検査に備える必要があるでしょう。
シンガポール:低法人税率とGST制度の特徴
シンガポールはアジアの金融・商業ハブとして有名で、法人税率は17%と比較的低めの設定です。さらに、スタートアップ企業や特定の投資プロジェクトに対して追加の税務優遇が適用されるなど、ビジネスにフレンドリーな投資誘致策が多数用意されています。会計基準は「Singapore Financial Reporting Standards(SFRS)」で、IFRSとの整合性が高く、外国企業にも馴染みやすい環境です。
消費税にあたるGSTは2023年に7%から8%へ引き上げられ、さらに2024年以降は9%への引き上げが予定されています。ただし、輸出取引はゼロ税率となるため、国際取引が中心の企業にとっては実質的な負担が少ない面もあります。また、一定の売上規模を超える企業がGST登録を行う義務があり、申告は3か月ごとの四半期サイクルが基本です。
ローカル会計基準とIFRSの違い、注意点

東南アジア各国は、グローバルスタンダードであるIFRS(国際財務報告基準)の導入や適用に前向きな姿勢を示している国が多い一方、完全にIFRSを採用しているわけではない場合もあります。ローカルな修正や追加要件があると、連結決算を行う際に整合性を取るのが難しくなるケースもあるため、親会社との調整が重要です。
IFRSとの整合性を意識した各国の独自基準
例えば、シンガポールの会計基準(SFRS)はほぼIFRSと同等とされていますが、一部のセクターや特定取引において独自ルールが加わっています。タイも近年IFRSとの整合性を高めており、実質的にIFRSベースの「Thai Financial Reporting Standards(TFRS)」を運用中です。ベトナムやインドネシアではIFRSの段階的導入が計画されているものの、まだ完全移行には至っていない状況と言えます。
もし日本の親会社がIFRSを採用している場合、現地法人の決算をローカル基準で行ったうえで、連結用にIFRSへ組み替える必要が生じるかもしれません。この際、資産評価や減価償却、金融商品会計などで差異が発生する可能性があるため、監査法人や専門家と連携して対応を検討しましょう。
会計ソフトやコンサルタント活用のメリット
ローカル基準とIFRSの違いを手作業で調整するのは手間がかかるため、多くの企業がクラウド会計ソフトやERPシステムの機能を活用して、複数基準への対応を自動化しています。例えば、国別設定や勘定科目のマッピングを行うことで、ローカル基準とIFRSの両方を簡易的に管理できる仕組みを作ることが可能です。
また、現地会計事務所やコンサルタントに支援を依頼すると、単なる帳簿付けだけでなく「どのように税務リスクを最小化するか」「投資優遇策をどう適用するか」といった戦略面のアドバイスをもらえる場合もあります。コストはかかりますが、長期的に見れば、安定した会計・税務運営につながるメリットが大きいでしょう。
税務申告・監査要件との関連(法人税・消費税を含む)

会計処理は最終的に法人税や消費税(付加価値税、SST、GSTなど)の計算基盤となるため、これらの税務申告や監査要件を無視できません。国によっては監査義務が一定規模以上の企業に課され、監査報告書を提出しないと法人税申告が完了しないケースもあるため、しっかり確認しておきましょう。
会計処理が法人税計算やVAT/SST算出に及ぼす影響
法人税の計算では、収益や費用を正しく会計処理しておくことが前提となります。もし記帳がずさんだと、過大な費用計上や収益の計上漏れが発生し、追徴課税や罰金を受けるリスクが高まります。消費税(VAT、SST、GSTなど)に関しても、仕入税額控除の計算や免税・軽減税率の適用などが正確に行われなければ、余分な税負担や還付申請の失敗が起こりかねません。
また、多くの国では会計帳簿と税務申告書の間に大きな差異があると調査対象になりやすいのが実情です。会計基準上はOKでも、税務当局の解釈ではNGという事例もあるため、ローカルの税法や通達を踏まえた慎重な対応が求められます。
監査義務の有無と提出書類のタイミング
東南アジアでは企業規模(資本金や売上高)や業種によって、外部監査を受ける義務が課される場合があります。シンガポールでは年次決算において一定の条件(年間売上や総資産など)を超える企業は監査が必須となり、インドネシアやマレーシアなどでも類似の規定が存在します。
監査を受ける際、監査法人はローカル基準で作成された財務諸表が適正かどうかをチェックします。仮にIFRSとの整合を意識している場合でも、ローカルの監査法人や公認会計士(CPA)が最終的に判断を行うため、国内基準とIFRSの差異を説明できる体制を整えておくとスムーズです。また、監査報告書の提出時期も国によって異なるので、決算日からどのくらいの余裕をもって申告すべきかを事前に調べておく必要があります。
現地スタッフ・会計事務所との連携方法

実際に東南アジアで記帳・会計処理を運用するには、自社の中に経理担当を置くか、現地スタッフを採用するか、または外部の会計事務所にアウトソースするかといった選択肢が考えられます。ここでは、それぞれの形態のメリット・デメリットや、コミュニケーションを円滑に行うコツを紹介します。
社内人材を育成すべきか、外注すべきかの判断基準
自社で経理体制を構築する場合、現地法人に日本人または現地人材を雇用し、ローカル会計基準や税務に詳しいスタッフを配置する必要があります。これにより企業内でノウハウが蓄積され、細かいトラブルや意思決定が早くなるメリットがありますが、人件費や教育コストがかかる点がデメリットです。特に初期段階で事業規模が小さい場合には、コスト負担が重く感じられるかもしれません。
一方、会計事務所やコンサルタントにアウトソースする場合は、最新の法改正や税務当局の動向をプロが把握してくれるため、トラブルが起こりにくい安心感があります。複数国を一括でサポートしてくれる大手の国際会計事務所も存在するため、進出国が増えた場合でも柔軟に対応できるでしょう。しかし、毎月の顧問料や決算時の監査費用などが嵩む可能性があり、また緊急時の対応スピードが社内スタッフほど早くない場合もあります。
日常業務でのコミュニケーション手段とトラブル回避策
海外の会計処理では言語の違いも大きな障壁となります。英語が通じやすい国(シンガポール、マレーシア、フィリピンなど)ではまだしも、タイやベトナム、インドネシアではローカル言語での書類作成や申告が義務付けられることが多く、スタッフ間のやり取りにも通訳や翻訳が不可欠かもしれません。したがって、オンラインツールを活用しながら、日々の経費精算や請求書処理を円滑に行う仕組みづくりがポイントです。
トラブルを回避するためには、業務の役割分担と承認フローを明確に定義しておくことが効果的です。例えば、経費精算は現地スタッフが行い、日本本社は月次レポートを確認するだけに留めるのか、それとも一定金額以上の支出に対しては本社の承認が必須なのかなど、ルールを事前に設定しておくとスムーズです。クラウド会計ソフトを導入してリアルタイムでデータ共有する企業も増えています。
まとめ

東南アジアで事業を行ううえで、会計処理や記帳の問題は見逃せない要素です。それぞれの国が独自の会計基準や税制を持ち、申告期限や監査義務、インボイス制度などが多岐にわたるため、「会計処理」を正しく理解しないと予期せぬコスト増や法令違反を招くリスクがあります。以下に、本記事で触れた主要ポイントを再度整理してみましょう。
- 東南アジアの会計・税制度は国ごとに大きく異なる:タイやベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールでは会計基準や消費税の名称・税率が違う。最新動向を常に確認することが大事。
- IFRSとの整合性を意識しつつ、ローカルルールも把握する:多くの国がIFRSをベースにしているが、独自の修正や追加規定があるため、連結決算との整合を図るには専門家の助力が有効。
- 税務申告・監査要件を見据えた記帳が必要:法人税や消費税(VAT、SST、GSTなど)の計算根拠となる会計帳簿を正確に作成し、監査報告書の提出時期や方法を事前に確認する。
- 現地スタッフや会計事務所との連携で運用効率化:社内人材を育成して内製化するか、外部専門家にアウトソースするかを慎重に判断し、コミュニケーション体制を整える。
- 言語・文化の壁を乗り越える工夫が不可欠:英語が通じる国でもローカル言語を使った書類や申告が必要な場合が多い。オンラインツールや翻訳リソースの活用、定期的な打ち合わせが重要。
今後、東南アジア各国でさらなる経済発展や法改正が進めば、会計・税務の制度も変化していく可能性があります。こうした変化に対応できるよう、常に最新情報を追いかける姿勢と柔軟なマネジメントが求められるでしょう。JETROや各国の投資誘致機関、在外公館の情報にアクセスし、専門家やコンサルタントのアドバイスを受けることも選択肢の一つです。
「会計処理」という視点で見ても、東南アジアはまだまだ未開拓の可能性にあふれた市場です。現地での正確な記帳・決算・申告がビジネスの基盤を支えることを忘れずに、長期的な目線で収益拡大とリスク管理の両立を目指していきましょう。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
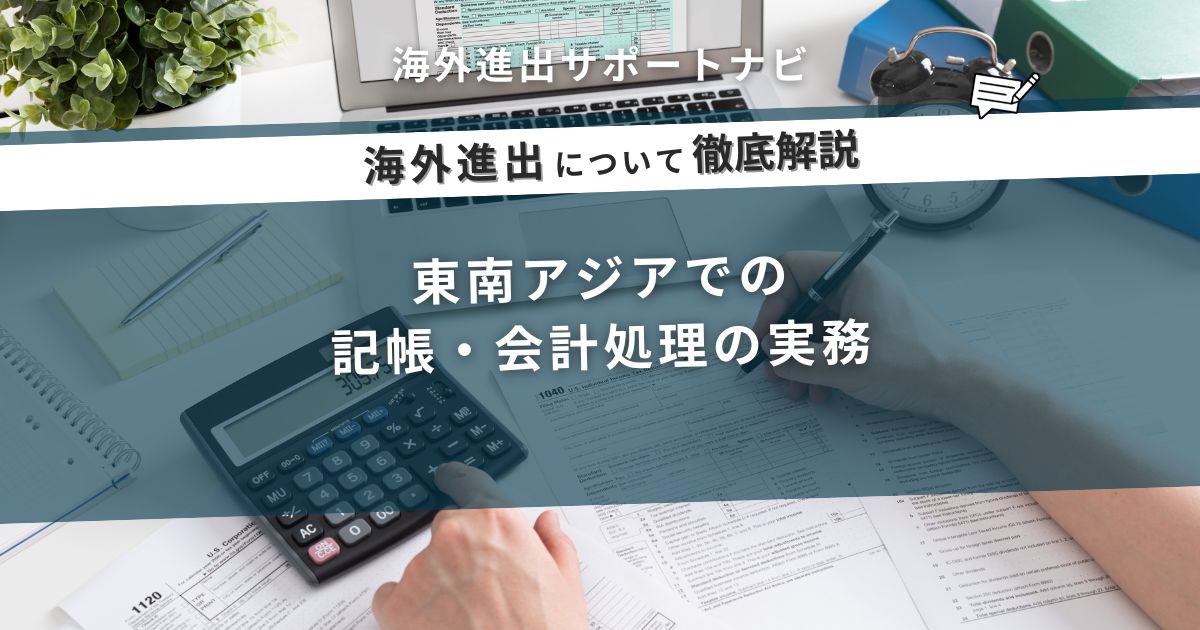
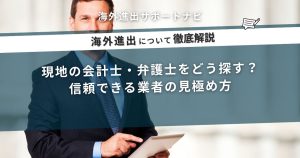
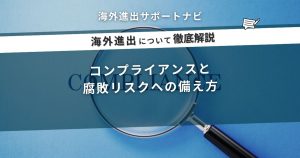
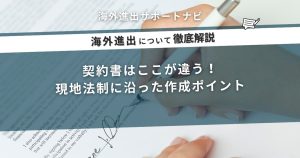
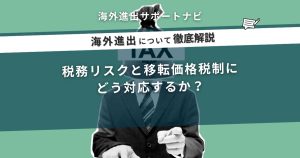
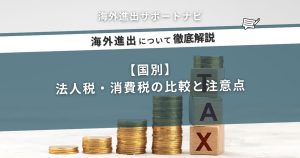
コメント