グローバル化が加速するなかで、アジア新興国を中心とする海外市場への注目度が年々高まっています。特に、タイやベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールなど東南アジア諸国は、人口増加や経済成長に支えられ、大きなビジネスチャンスを秘めた地域として日本企業の進出が相次いでいるのです。しかし、実際に現地拠点を設立したり、海外の見本市や商談会へ出展したりするには、渡航費や初期投資、マーケティング費用など、さまざまなコストをカバーしなければなりません。
そうしたときに活用したいのが、国や自治体が提供する助成金・補助金の仕組みです。公的な資金を活用することで、海外 展開のハードルを一気に下げることができます。本記事では、日本国内の代表的な助成・補助制度から、地方自治体や商工会議所が行う独自支援、さらに東南アジア各国で利用できる投資優遇制度まで網羅的に解説します。助成金申請に必要な書類や注意点も紹介するので、これから海外ビジネスを拡大したい企業にとって役立つ情報が詰まっています。ぜひ参考にしてください。
なぜ海外展開に助成金・補助金が必要なのか

海外進出、特に東南アジアへの事業展開には、マーケットの成長余地が大きい反面、初期費用やリスクも少なくありません。製造拠点の設立や営業拠点の開設を考える場合、オフィスや工場の賃貸・建設コスト、人材の雇用費用、通関や輸送に関する諸経費など、多岐にわたる出費が発生します。また、ローカル企業との競合も激しく、迅速に販路開拓を行う必要があるでしょう。そうしたコスト負担を少しでも軽減し、事業計画を円滑に進めるために、公的機関が提供する助成金や補助金を活用する意義は非常に大きいのです。
東南アジア進出における初期コストとリスク
初めて東南アジアの市場に参入する企業にとっては、現地調査やパートナー探し、法人設立・ライセンス取得などのステップが待ち受けています。国によってビザ手続きや登記に必要な期間や費用が異なるだけでなく、オフィスや工場を探す際も不動産契約にかかるデポジットや保証金など予想外の出費が発生することも多いです。さらに、もし現地での展開が思うようにいかず撤退を検討する事態となれば、損失が大きく膨らむリスクも考えられます。
こうした不確実性を少しでも下げるために、助成金・補助金を活用してイニシャルコストを抑える方法が注目されています。たとえば海外見本市への出展費用や調査費用を補助してくれる制度を使えば、実際に市場での可能性を確認してから大きく投資するか判断できるでしょう。
公的機関データから見る補助金活用の実態
日本貿易振興機構(JETRO)の調査や中小企業庁が発行するレポートによると、海外進出時に企業が直面する主な課題として「情報収集の不足」「資金負担の高さ」「現地パートナーとの関係構築の難しさ」などが挙げられています。そのうち資金面に関する課題を助成金・補助金でサポートできれば、海外 展開を行うハードルが大幅に下がることがわかります。
実際に助成制度を活用した企業の声を見ても、「見本市出展費の大部分が補助されたおかげで販路開拓の成功率が上がった」「初期投資が抑えられた結果、撤退リスクを恐れずトライできた」といった好意的な反応が多いです。ただし、助成金を受け取るには、申請書類や報告義務などの手続きをしっかり行う必要がある点には注意が必要です。
日本国内の主要な助成金・補助金の概要

海外展開を視野に入れた日本企業がまずチェックすべきなのが、国内で申請できる助成金・補助金制度です。中小企業庁やJETRO、地方自治体など、さまざまな主体が海外ビジネス支援策を打ち出しているので、自社の事業計画や業種に合う制度を探してみましょう。ここでは代表的なものをいくつか取り上げます。
中小企業向け海外ビジネス展開支援事業
中小企業庁が主導する「中小企業海外展開支援事業」は、海外展開を検討・実施する中小企業に対し、市場調査や販路開拓などの経費を一部補助する取り組みです。公的機関が実施する海外見本市や商談会への出展費の補助も含まれるケースがあり、対象になる国や地域、事業内容によって補助率や補助上限額が変わります。
この制度を利用するには、事業計画書や費用見積もりなどが求められますが、採択されれば数十万円から数百万円単位の資金支援を得られる可能性があります。実際に展示会ブースの費用や渡航費の一部がカバーされ、資金面での負担が軽減できるメリットは大きいでしょう。
ものづくり補助金・事業再構築補助金との関連
国内で比較的有名な補助金として「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」が挙げられます。これらは海外展開専用の制度ではありませんが、製造業やサービス業で新たな設備投資や事業モデル転換を行う際に補助を受けられる可能性があり、それが海外市場への進出や拡大に繋がるケースもあります。
例えば、海外向けの商品開発や海外ECサイト構築のためのシステム導入費を対象経費として計上できる場合があるため、海外戦略と結びつけられる形で申請できるかどうかを検討しましょう。ただし、要件が頻繁に変わることもあるため、最新の公募要領や公的機関の案内をよくチェックすることが大切です。
JETROなどが紹介する施策の特徴
JETRO自体が直接助成金を出すわけではありませんが、ウェブサイトやセミナー、個別相談などで海外ビジネス支援策を幅広く紹介しています。たとえば「自治体が独自に行う補助金」「業界団体の助成金プログラム」など、あまり知名度が高くないものまで網羅的に案内している場合があるため、情報収集の入り口として利用してみると便利でしょう。
さらに、JETROのマッチングイベントや海外見本市サポートを受ける際に、同時に助成金・補助金を利用すれば、イベント出展費用を抑えられるといった相乗効果が期待できます。結果的により多くの企業が海外ビジネスを実践するチャンスを得られるのです。
地方自治体・商工会議所が提供する独自支援

日本政府や中央機関だけでなく、地方自治体(都道府県や市町村)や商工会議所も独自の海外ビジネス支援を行っています。特に地域密着型の取り組みや補助制度が用意されている場合があるので、自社が本社を置く自治体や所属している商工会議所の情報も見逃せません。
県や市の国際ビジネス助成制度
例えば東京都や大阪府などの大都市圏をはじめ、最近では地方自治体でも「海外販路開拓支援」「海外見本市出展補助」「海外向けWeb広告支援」など、幅広い制度を用意しているケースがあります。申請要件は自治体ごとに違うため、自社が所在地を置く自治体の公式サイトや産業振興課の窓口をチェックし、使える補助がないか確認しましょう。
自治体によっては、中小企業向けに海外事業の専門家を招いたセミナーを無料で開催していたり、企業訪問を通じて個別アドバイスを行うなど、手厚いサービスを提供している例もあります。こうした機会に参加することで、同じ地域の他社と連携しながら海外市場進出をめざすことも可能です。
商工会議所との協業事例
各地の商工会議所は、地元企業同士を結びつけるネットワークとして機能しているだけでなく、独自の海外視察ツアーやビジネスマッチングイベントを行うこともあります。こうしたイベント参加費の補助や、渡航費補助といった施策を商工会議所が主体となって運用しているケースもあり、利用できる企業には大きなメリットがあります。
また、商工会議所は海外の在外公館や現地の商工会議所とのパイプを持っているため、情報交換や相互訪問を通じて、新たなビジネスチャンスを得られる機会が生まれやすいのです。特に現地の商工会議所と協力関係を築けば、各種優遇制度や助成策へのアクセスがさらに広がります。
小規模事業者向けセミナーやマッチング支援
大企業ばかりが海外展開の支援を受けている印象を持つ方もいるかもしれませんが、最近では小規模事業者やベンチャー企業を対象とした海外ビジネスセミナーや補助金制度が増えています。商工会や商工会議所が主催するセミナーで得られる情報は、中小企業が直面しがちな課題(資金繰り、少人数体制でのオペレーション、現地語への対応など)に焦点を当てている場合が多く、実践的です。
こうしたセミナーや説明会に足を運ぶことで、申請可能な助成金を知ると同時に、仲間となる企業家やコンサルタントとのネットワークが広がるでしょう。実際、小規模の食品メーカーや工芸品業者が海外見本市へ出展し、思わぬ受注を獲得した成功例も多数報告されています。
東南アジア各国の投資誘致策と優遇制度

日本の助成金・補助金に加えて、進出先である東南アジア各国が独自に用意している投資誘致策や優遇税制を活用することで、さらにコストを抑えたり、法人税減免などの恩恵を受けたりすることが可能です。国ごとに条件や対象分野は異なるため、どの国に拠点を置くかを検討するときに比較してみるとよいでしょう。
タイBOI、マレーシアMIDA、ベトナム投資優遇など
タイのBOI(投資委員会)は、ハイテク産業や研究開発など特定分野に進出する企業に対し、法人税免除や輸入関税の減免などを提供しています。マレーシアMIDA(マレーシア投資開発庁)も、ICTや製造業などにフォーカスした優遇策を打ち出しており、一定期間の課税免除や土地の格安リースなどを受けられる場合があります。
ベトナムでは経済特区や工業団地での投資に対し、土地使用料の減免や法人税の優遇が行われることが多いです。ただし、これらの制度は常に変化しているため、各国の投資庁や公的機関の最新情報を収集しておく必要があります。もし外国企業向けの優遇策を検討している国が複数あるなら、それぞれのメリット・デメリットを比較して意思決定を行うとリスクを最小限に抑えられるでしょう。
法人税減免や賃貸料補助の具体例
たとえば、インドネシアでは「Tax Holiday」と呼ばれる制度を活用し、一定期間法人税をゼロまたは大幅に減税できる場合があります。フィリピンでもPEZA(フィリピン経済区庁)に登録した企業が大幅な税率優遇を受けるケースがあり、電子部品製造など特定セクターでは非常に有利になる可能性があります。また、一部の工業団地や産業パークでは、入居企業に対し賃貸料や公共料金の補助を行っている例も見られます。
こうした東南アジア各国の優遇策は、「海外 助成金」と併用することで初期投資を大幅に軽減できる可能性があるため、具体的にどの国に、どんな形で拠点を置くかを考える際に必ず確認しておきましょう。公的機関(JETROなど)の個別相談で情報をもらったり、現地の投資庁に問い合わせたりすれば、最新の優遇プログラムを把握しやすくなります。
申請手続き・書類準備のポイント

助成金や補助金を実際に受け取るには、申請書類の作成や事業計画の提出など、一定の手続きを踏む必要があります。審査を通過しなければ支給されない場合がほとんどであり、「いい制度があるのに申請要件を満たさなかった」「書類不備で期限に間に合わなかった」という失敗を避けるためにも、下記のポイントをしっかり押さえましょう。
事業計画書の書き方とコスト見積もり
多くの助成金・補助金では、申請企業が事業計画書や収支計画、海外進出の具体的なビジョンを明確に示すことが求められます。単に「海外で売上を伸ばしたい」と言うだけでは説得力に欠けるため、ターゲット市場のニーズや競合状況、販路開拓の方法論などを盛り込むと良いでしょう。また、必要経費(設備投資、渡航費、人件費など)を詳細に見積もり、補助金を使う目的や使い道を明確に示すことが大切です。
なお、事業計画書のフォーマットは制度ごとに異なり、公募要領や申請マニュアルに沿った形で作成しないと審査が通りにくくなる可能性があります。特に経費区分(対象経費と対象外経費の線引き)を間違えると修正を求められたり、最悪の場合不採択となることもあるため、注意が必要です。
スケジュール管理と専門家活用のメリット
助成金や補助金には、申請受付期間や審査期間、交付決定後の実施期間など、厳密なスケジュールが設定されています。締切直前になると窓口が混み合ったり、オンライン申請システムが繋がりにくくなることもあるため、余裕をもって準備を進めるのが得策です。
また、申請書類を自社だけで作成しきれない場合は、行政書士や中小企業診断士などの専門家に部分的または全面的にサポートを依頼する方法もあります。一定の報酬は発生しますが、採択率が上がるというメリットや、事業計画のブラッシュアップにつながる効果が期待できます。
成果報告・実績検証の重要性
助成金や補助金は、交付決定を受けた後も事業完了時や年度末などに成果報告を提出する義務がある場合が大半です。海外見本市に出展したのであれば、得られた商談数や受注成果、海外調査であれば収集したデータと事業成長への影響など、定量的・定性的な結果を整理して報告書をまとめる必要があります。
報告書の内容が不十分だと、最終的に補助金の一部が支払われなかったり、次回の助成金申請に影響が出る恐れがあるため注意が必要です。逆に、しっかりと実績を示すことで、今後の追加支援や他の制度への応募でも有利になる場合があります。
まとめ

東南アジアをはじめとする海外市場への進出は、企業にとって大きな成長機会であると同時に、多額の投資や不確定要素を伴うリスクでもあります。そんなとき、国や自治体、JETRO、商工会議所などが提供する「海外助成金」や補助金制度をうまく活用すれば、資金負担を軽減しながら段階的に海外ビジネスを拡大できる可能性が高まります。
- 助成金や補助金は初期投資の負担を軽くする:海外 展開に際して、調査費や出展費用、設備投資などを一部補助してもらうことでリスクを抑えられる。
- 日本国内の公的機関・自治体だけでなく、東南アジア各国の優遇策にも注目:BOI(タイ)やMIDA(マレーシア)など、現地投資庁が独自の優遇制度を設けている場合がある。
- 申請には事業計画書や経費詳細の準備が必要:募集要領をしっかり読み、締切や必要書類を早めに整えておく。専門家の力を借りる選択肢も検討。
- 成果報告や実績検証を怠ると次回以降の支援が受けにくい:補助金を得た後も、決められた形で効果を報告し、透明性を確保する。
- 情報源はJETROや商工会議所だけでなく、在外公館や同業者ネットワークも:多角的な情報収集で申請のチャンスを逃さない。
以上のポイントを踏まえれば、自社に合った助成金・補助金を見極め、現地進出のスピードアップやリスク低減を図ることができるはずです。実際に海外市場で成功を収めている企業の多くは、公的資金や優遇策を効果的に活用しながら段階的に成長を遂げています。「海外展開」を一層有利に進めたいと考えている企業は、この記事をきっかけにぜひ助成金情報や公的支援施策を探してみてください。
申請手続きや報告義務に不安がある場合は、行政書士や中小企業診断士、海外進出支援に特化したコンサルタントなど専門家のサポートを受けるのも良い選択肢です。彼らは過去の採択実績や現地の法規制に精通しており、書類作成や計画策定を効率化してくれます。もちろん、自社でノウハウを蓄積していくことも大切ですが、必要に応じて外部リソースを活用することで、貴重な時間と人員を事業のコア活動に集中できるでしょう。
「助成金を使ってリスクを抑えた海外展開が可能かもしれない」と感じたら、まずはJETROや自治体のホームページを覗いてみたり、商工会議所の窓口に足を運んだりするところから始めてみてはいかがでしょうか。公的機関や専門家との連携をスムーズに行いながら、海外ビジネスの成功を目指す第一歩を踏み出してください。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
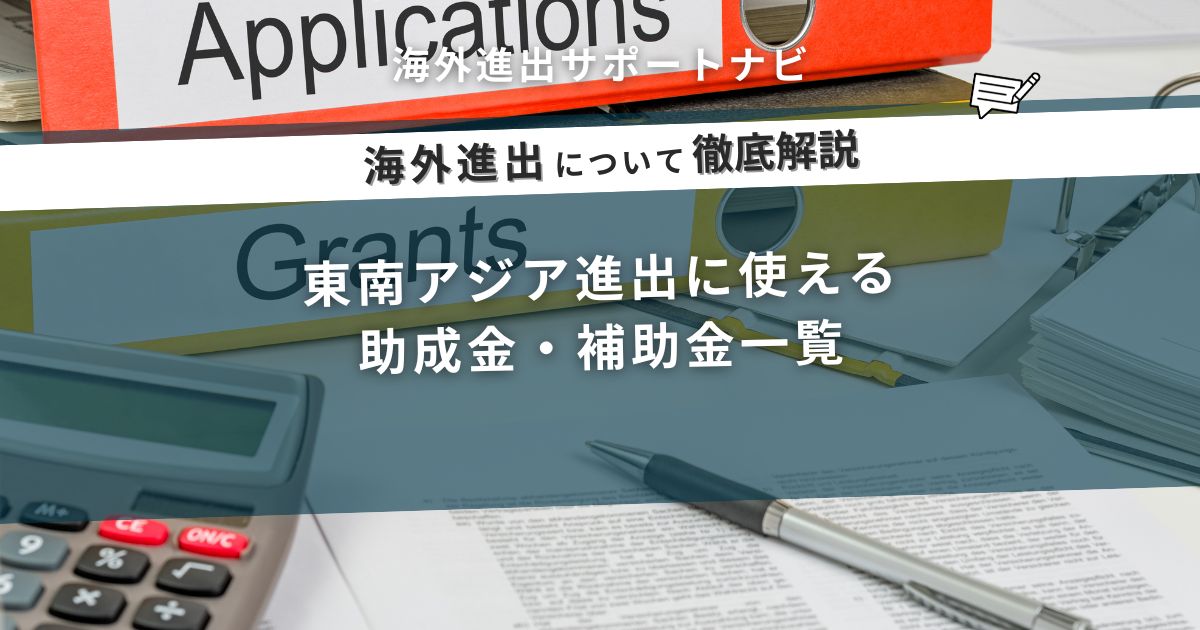
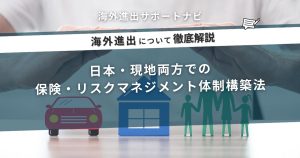
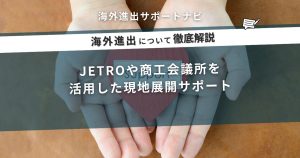
コメント