海外市場に進出する際、「日本製品は品質が良い」「おしゃれなイメージ」などの強みを全面に押し出すだけでは、現地のユーザーに深くアピールできないことが増えています。特に東南アジア市場では、SNSや口コミを通じて身近な存在として感じてもらえるかどうかが重要です。
この「身近さ」や「親しみやすさ」を演出するうえで欠かせないのが「ローカル感」です。本記事では、ローカル感を取り入れたプロモーション施策の作り方と、国ごとの傾向や注意点について解説します。現地の文化や消費者心理を理解し、愛されるブランドへとステップアップするためのヒントをお伝えします。
なぜローカル感がプロモーション成果を左右するのか?

海外販促では「日本ブランドであること」そのものが武器になる面も多々ありますが、それだけでは消費者の購買意欲を高めきれないケースが増えています。なぜなら、国ごとに異なる文化や生活習慣、言語表現を踏まえたコミュニケーションこそが、ユーザーの共感や親しみを引き出すからです。
共感・親しみ・信頼が購入を後押しする理由
現地の言葉や文化を尊重している企業は、ユーザーから「自分たちを理解してくれている」というポジティブな印象を持たれやすいです。特に東南アジアのユーザーは、SNSを通じた口コミやレビューを重視し、「このブランドは私たちと同じ視点を持っている」と感じれば一気に親近感が高まります。
ローカル感を取り入れたプロモーションは、単なる価格訴求やキャンペーンだけでなく、感情的なつながりを生み出す力があるのです。
「日本ブランド=おしゃれ」だけでは売れない背景
東南アジアでは確かに「日本製品への信頼感」や「日本のトレンドに憧れを持つ層」が存在します。しかし、それはあくまで一部ユーザーの意識であり、競合ブランドも多数存在する中で、単に「日本のものだから高品質」というだけでは差別化できない状況が増えています。
ユーザーが本当に知りたいのは、「自分たちの日常や文化にどうフィットするのか」であり、日本製だけを強調するよりも、ローカルに寄り添う姿勢を見せるほうが成果に結びつきやすいのです。
押さえておきたい“ローカル感”の5つの要素

ローカル感を出すには、単に言語を翻訳するだけでは不十分です。以下の5つの要素を意識しながら、現地ユーザーが「親しみやすい」「私たちの生活に合っている」と感じるプロモーションを作り上げましょう。
① 言語と口調:翻訳でなく“自然な表現”を使う
直訳によるぎこちない文章や不自然なワード選択は、むしろ現地ユーザーにとって違和感の原因になります。ネイティブに近い人材の校正を受けることで、現地で使われるスラングやカジュアルな表現を取り入れた“自然な”言い回しを目指しましょう。
また、同じ国でも地域や世代によって言語スタイルが異なる場合があります。ターゲット層が若年層なのか、ファミリー層なのかで口調や言葉遣いを変えるのも効果的です。
② ビジュアル:服装・背景・モデルの選び方
広告やSNS投稿に使う写真や動画は、服装や背景のスタイルをローカルに合わせると一気に親近感がアップします。アジアンテイストの服装やインテリア、小物をさりげなく配置し、モデルも現地のルックスに近い人材を起用すると効果が高いです。
逆に、日本国内向けのビジュアルをそのまま使うと、「異国感」が強調されすぎて、ユーザーが自分ごととしてイメージしにくくなるリスクがある点に注意しましょう。
③ 文化・祝日:国民的イベントや宗教的配慮
ローカルイベントや祝祭日、宗教行事に合わせたキャンペーンを行うと、ユーザーの共感を得やすいです。たとえば、ラマダン(イスラム教)、中秋節(華人文化)、ディパバリ(ヒンズー教)など、東南アジア諸国では多様な文化的背景があります。
現地で重要視されている日に合わせてセールや特別コンテンツを提供すると、「自分たちの行事をリスペクトしている」と認識され、好印象につながります。
④ キャラ設定:親しみやすいストーリーと登場人物
動画広告やSNSでの発信においては、主人公やキャラクターを設定し、その人物の日常や体験を通じて商品を紹介する手法が効果的です。
ここでのポイントは、登場人物が現地の生活様式や価値観を反映しているかどうか。家族構成や食事シーン、ユーモアのツボなどをローカルに合わせることで、視聴者の共感を得やすくなります。
⑤ ハッシュタグ・ミーム:現地SNSトレンドを活用
東南アジア各国では、FacebookやInstagram、TikTokを活用するユーザーが多く、頻繁に流行りのハッシュタグやミーム(ネット上のネタ)が生まれます。
ローカルで話題のハッシュタグをプロモーション投稿に取り入れたり、最新のミームを軽くアレンジして商品を紹介することで、「今のトレンドに乗っている」というポジティブなイメージを与えられます。ただし、使い方を誤ると「媚びている」「ズレている」と見なされる恐れがあるため、タイミングや内容には注意が必要です。
東南アジア主要国ごとの「ウケる表現」の傾向

東南アジアと一括りに言っても、国ごとに文化・宗教・経済状況が大きく異なるため、ローカル感を演出する際のポイントも違ってきます。ここではインドネシア、フィリピン、タイを例に、その傾向を簡単に紹介します。
インドネシア:カジュアル・日常・家族感が強い
世界最大のイスラム教国であるインドネシアでは、宗教的な配慮(ハラル対応など)が重要になる場合があります。また、家族やコミュニティを大切にする文化が強いので、「日常生活の中で家族や友人と楽しめるシーン」を描くと好感を得やすいです。
SNSではカジュアルな言い回しやスタンプ、絵文字などを多用し、親しみやすい雰囲気を作るとエンゲージメントが高まります。
フィリピン:明るくポジティブ、ちょっと笑える要素も
フィリピン人は陽気でフレンドリーな国民性が強く、SNS上でもジョークやおもしろ動画がよく共有されます。広告や投稿に少しユーモアを交えると、拡散力を高めやすいでしょう。
また、英語が通じる一方で、タガログ語を織り交ぜたローカル感を出すとさらに親近感が高まります。サプライズやスペシャルオファーを前面に打ち出すのも効果的です。
タイ:SNS映え+ちょっとユニークでかわいい演出
「微笑みの国」と呼ばれるタイでは、ビジュアルのかわいらしさやユニークさが支持されやすいです。SNS映えするきれいな色合いや、ゆるいイラストなどが好まれる傾向があります。
また、タイ独特のインターネットスラングや文字表現(タイ語略称など)を上手く活用すると、現地ユーザーに響きやすいです。ただし、発音やニュアンスに注意しないと誤解されるリスクもあるため、ローカルスタッフの協力があると安心です。
ローカル感を表現できるプロモーション施策例
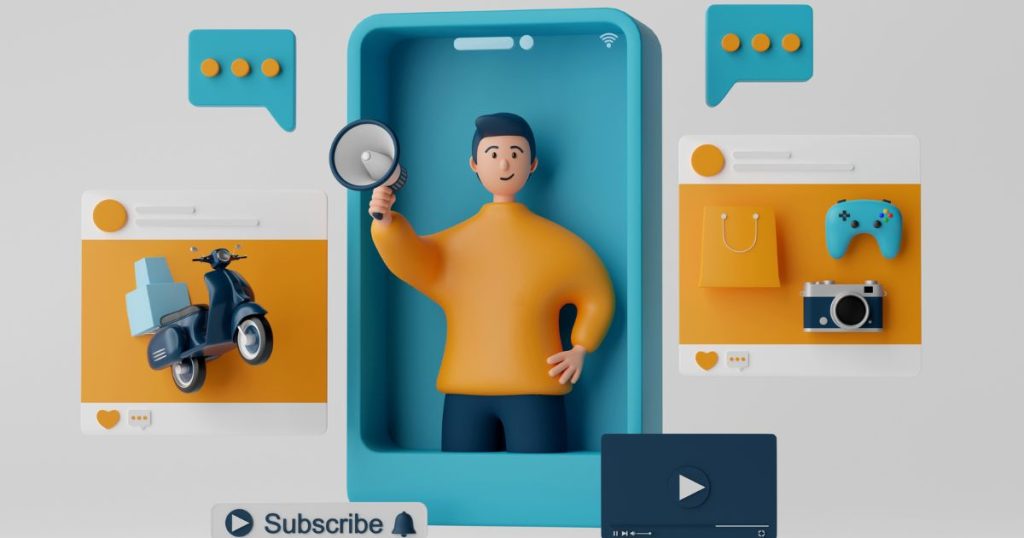
実際にローカル感を取り入れたプロモーションを行うには、具体的にどのような形が考えられるでしょうか。ここでは3つの事例を挙げます。
ローカルインフルエンサーとのコラボ投稿
インフルエンサーやKOL(Key Opinion Leader)と呼ばれる人物に商品を使用してもらい、その様子をSNSで発信してもらう手法です。
ローカル感のある背景や日常シーンを交え、普段使いの様子をリアルに見せてもらうことで、ユーザーは「自分の生活にも合いそう」とイメージしやすくなります。ハッシュタグや地域の流行語を入れて、拡散力を高めることがポイントです。
国民的イベント(例:ラマダン、クリスマス)連動企画
前述の通り、東南アジアではさまざまな宗教行事や祝日、フェスティバルが存在します。たとえばラマダン期間の断食明け(レバラン)、フィリピンの盛大なクリスマスシーズン、タイのソンクラーン(旧正月・水掛け祭り)など。
これらのイベントに合わせて限定コラボ商品や特別セールを打ち出すと、ユーザーの注目度が一気に高まります。パッケージやビジュアルに当該イベントのモチーフを取り入れるのも効果的です。
ユーザー参加型レビュー・写真投稿キャンペーン
SNS上でユーザーから写真を募集し、抽選でプレゼントを渡すなど、ユーザー参加型のキャンペーンは現地のコミュニティ感を醸成するうえで重要です。
特に東南アジアでは写真付きレビューや動画での使用レポートが購買決定に大きく影響します。商品の使い方や活用シーンをユーザー自身が発信してくれるよう誘導すれば、口コミパワーを爆発的に高められます。
逆効果にならないための注意点

ローカル感を意識しすぎて、逆に違和感を与えてしまうケースも存在します。文化的タブーやステレオタイプな演出などに注意しなければ、せっかくのプロモーションが炎上や不評につながるリスクがあります。
現地文化への無理解が炎上・誤解を招くことも
宗教や歴史、政治的背景など、現地ではデリケートなトピックに軽率に触れると、批判やボイコット運動につながる恐れがあります。たとえば、イスラム教徒向けに配慮をしたつもりが、ハラル認証に関する誤解が生じてクレームを受けるなど。
ローカル感を出すにあたっては、事前に現地スタッフやコンサルタントに確認し、リスクのある表現を避けることが重要です。
中途半端なローカル感は“ズレ”を生む
「一部だけ現地語にする」「モデルはローカル風だが背景が日本のまま」など、統一感がない演出はむしろ違和感を与えてしまいます。ユーザーは「無理やりローカルっぽさを装っている」と感じ、興ざめする可能性が高いです。
徹底的にローカル化を目指すか、逆に日本的要素を一部残して差別化を図るか、コンセプトを明確にすることが大切です。
多言語・多民族国家では“ローカルの多様性”に配慮
マレーシアやインドネシアなどでは、マレー語、英語、中国語など、地域や民族によって使われる言語が異なります。ローカル感といっても一種類ではなく、複数の文化が混在している点を踏まえ、どのターゲット層に向けて発信するのかを明確にしなければなりません。
すべての層に迎合しようとするとメッセージが分散し、本来の狙いが伝わりにくくなるので注意しましょう。
まとめ|“現地で愛される存在”になるための第一歩を

海外展開において、日本ブランドが持つ品質や信頼感は大きなアドバンテージです。しかし、そこにローカル感という“人間味”や“親しみ”を加えることで、消費者の心をさらに強く掴むことができます。とはいえ、中途半端なローカル化は誤解を招きかねないので、現地の文化的背景やSNSのトレンドをしっかりリサーチしたうえでプロモーションを設計しましょう。
ローカル感=“親しみ”と“配慮”のマーケティング
ローカル感を出すとは、単に言語を翻訳したり、見た目だけを現地仕様にすることではありません。現地の生活、文化、価値観を理解し、その上で消費者が「自分たちのための商品だ」と感じる仕組みを作るということです。
これは“配慮”や“共感”というマーケティング手法でもあり、信頼を得てリピーターやファンを増やすうえで欠かせない要素となるでしょう。
freedoorではローカル目線でのSNS設計や企画提案も支援可能
ローカル感を盛り込んだプロモーションを行うには、現地の文化や言語に精通した人材や、SNS運用に熟知したチームが必要です。弊社freedoorでは、東南アジア各国の事情を知る専門スタッフが在籍し、SNSキャンペーン企画やインフルエンサー連携、ビジュアル制作などをトータルでサポートしております。
自社商品を現地に根付かせ、「愛されるブランド」を目指すなら、ぜひお声掛けください。ローカル感を最大限に活かしたマーケティング戦略で、海外展開の成功を後押しします。
東南アジアビジネスを加速させるなら、freedoorにご相談ください

海外市場への進出や東南アジア向けのプロモーション戦略をお考えなら、私たちfreedoorにお任せください。AI事業をはじめ、WEB・システム開発、WEBマーケティング、コンサルティング、SNS運用、広告運用、そして東南アジアマーケティング支援まで、幅広い領域で豊富な実績を誇ります。
総合的なアプローチでビジネス全体を強化
freedoor株式会社では、以下のような多彩なサービスを組み合わせることで、東南アジアビジネスの成功をトータルにサポートします。
- 東南アジアマーケティング支援:海外市場向けの戦略立案から現地向けコンテンツ作成、広告配信、KOL(Key Opinion Leader)連携まで、グローバル展開を総合的にサポート。
- AI導入支援:無料ツールの試行結果を踏まえた本格導入やカスタムモデル開発、システム統合で、業務フローを革新。
- WEB/システム開発:AIツールを既存サイトや社内システムに組み込み、業務全体を最適化。オリジナルアプリや分析基盤の構築も可能。
- WEBマーケティング支援:AIで生成したコンテンツを最大限に活用し、SEO対策や広告運用、コンテンツ戦略などで東南アジアの顧客接点を拡大。
- SNS運用代行:TikTok、Instagram、Twitter、Facebookなど、多様なプラットフォームでAI生成コンテンツを活かし、ブランド価値を高める運用・分析・改善を一貫サポート。
- TikTok広告運用:注目度の高いTikTokを活用し、ブランド認知拡大や新規顧客獲得を促進。プラットフォームの特性を踏まえたクリエイティブ制作や効果検証までを実施。
これらのサービスを組み合わせることで、単なる部分的な支援にとどまらず、戦略的かつ持続的なビジネス成長へと導くことが可能です。特に東南アジアでのマーケティングを強化したい企業様にとっては、現地の消費動向や文化、媒体特性を理解した上での総合的なアプローチが不可欠。freedoorなら、こうした包括的な支援を通じて、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。
東南アジア市場への進出やマーケティングに関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
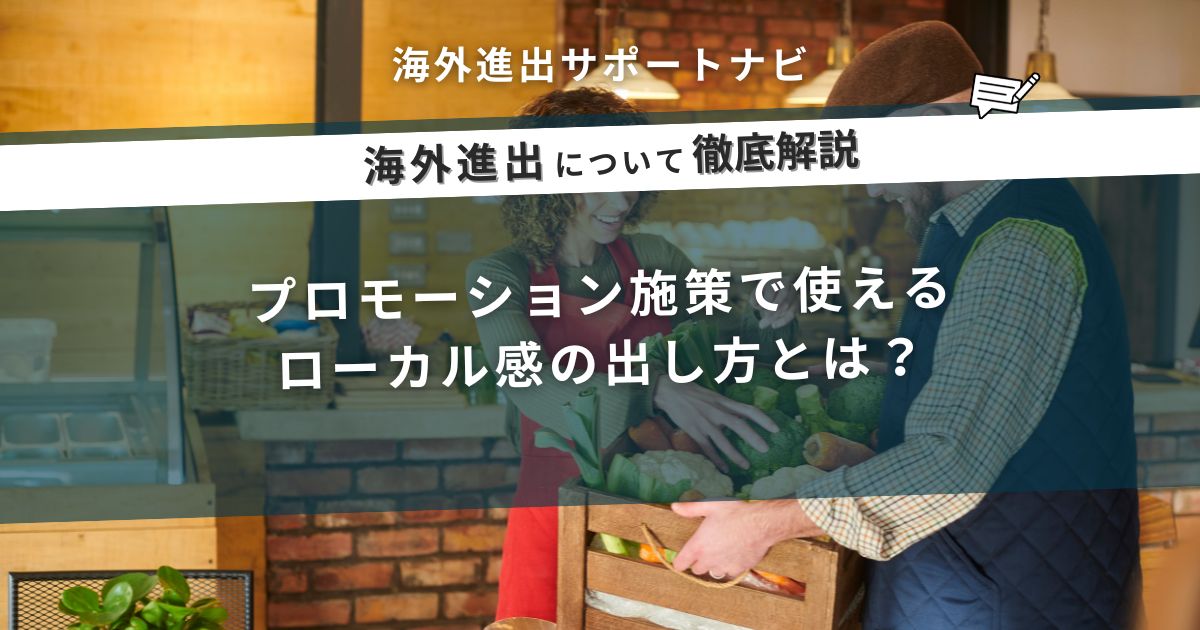
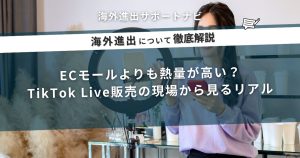
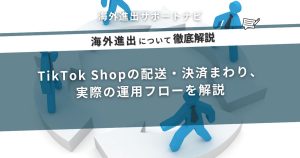


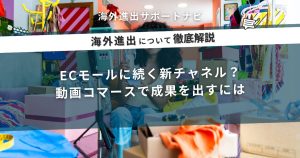



コメント