生成AIのおすすめ活用法とは?ビジネスで使えるツール12選【2025年版】
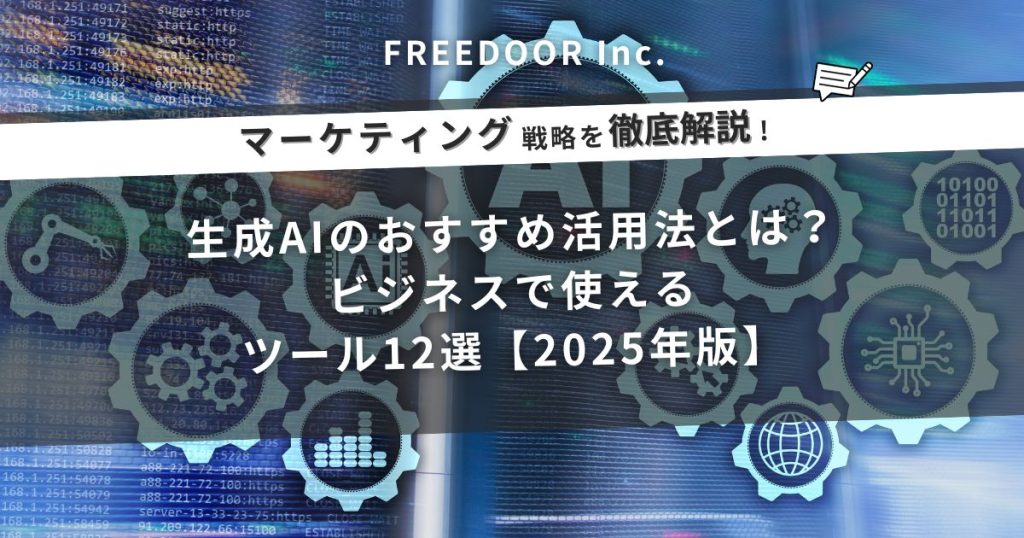
近年、生成AIと呼ばれるテクノロジーが注目を集めています。画像生成やテキスト生成、音声合成など幅広い分野で活用されるようになり、多くの企業や個人事業主が業務効率化やクリエイティビティの向上を目的に導入を検討しています。本記事では、生成AIとは何なのか、そのビジネス活用が注目される理由から、代表的な活用シーン、さらに2025年版の最新おすすめツール12選を目的別に紹介していきます。導入時に注意すべきリスクや運用ルール、そして専門的なサポートを提供するfreedoorのサービスについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
生成AIとは?ビジネス活用が注目される理由

生成AIの基本|画像・テキスト・音声などの生成機能
生成AIとは、大量のデータを学習させたモデルを用いて、新たなコンテンツや情報を“作り出す(生成する)”人工知能技術の総称です。具体的には以下のような分野が含まれます。
- 画像生成:イラストレーション、写真風画像、3DオブジェクトなどをAIが自動で作成
- テキスト生成:文章やコピー、メール文面、チャットの自動応答などを生成
- 音声生成:合成音声やボイスチェンジ、BGMや効果音の作成など
- 動画生成:短い映像クリップの生成や既存映像の高度な編集
これまで従来型のツールやソフトウェアでは、時間や専門知識を必要とする作業が多かった領域において、生成AIは大幅に手間を削減し、クリエイティブな可能性を拡張すると期待されています。たとえば、デザイナーが一から画像を描くのではなく、AIによる自動生成をベースに仕上げることで、業務スピードが格段に上がります。また、マーケティング担当者がキャッチコピーを考える際にも、AIによる候補案を下敷きにして、より洗練されたコピーを短時間で作り出すといった使い方が広がっています。
業務効率化・クリエイティブ支援としての可能性
生成AIが注目される最大の理由は、単なる効率化だけでなく、専門家の発想を支援する強力な「アシスタント」になり得る点です。従来のAI活用は、主に予測や分析、異常検知など、既存データを活用した判断支援にフォーカスしていました。しかし、生成AIは新しいアイデアやパターンを自動的に提案してくれるため、クリエイターやマーケターの発想の幅を大きく広げる可能性を秘めています。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- 広告のコンセプトデザインで行き詰まったとき、AIが大量のバリエーションを提示し、新しい着想を得る。
- 社内の会議資料作成や企画書作成でテンプレートや文章構造をAIが素案として提案し、担当者の作業時間を大幅に削減する。
- ECサイト運営で、商品画像やキャッチコピー、商品説明テキストをAIが自動生成し、担当者が校正・補正だけを行うことで運用効率を高める。
このように、生成AIを活用することで「クリエイティビティの拡張」や「業務効率の向上」が同時に実現する可能性が高まり、多くのビジネスパーソンから関心を集めています。
中小企業や個人事業主にも広がる活用例
大企業だけが生成AIを活用しているわけではありません。最近ではクラウドベースのサービスやオンラインツールの充実により、中小企業や個人事業主も容易に導入しやすい環境が整っています。特に次のようなシーンで注目されています。
- 小規模飲食店や雑貨店がSNS向けに魅力的な写真・文章を用意するために画像生成AIや文章生成AIを利用
- フリーランスのライターがクライアント向けのコピーや記事構成を考えるためのサポートとしてテキスト生成AIを活用
- オンライン講師が教材用の画像や簡易的な動画素材を制作するために生成AIを利用
これらの事例のように、資本力や人材リソースの限られた事業者でも、生成AIを導入することで大手企業並みのクリエイティブを生み出すことが可能となりつつあります。さらに、ソフトウェアのインストールが不要でブラウザだけで完結するサービスも増えており、ITの専門知識がなくても始められる点が大きなメリットです。
ビジネスで使える生成AIの代表的な活用シーン

営業・マーケティング:資料作成やキャッチコピー生成
営業やマーケティング部門では、日々多くのプレゼン資料や販売促進資料、あるいはセールストークやキャッチコピーを作成する必要があります。このようなクリエイティブな作業は、経験やセンスが求められる部分も大きい反面、単純なパターン作業が多い点も否めません。生成AIを導入することで、資料作成やキャッチコピー生成を高速化し、多数のバリエーションを一度に提案させることが可能になります。
たとえば、ある商品を販売するにあたって20種類のキャッチコピーを考えるようにAIに指示すれば、短時間で案をまとめることができます。その中から、実際に効果が高そうなものをマーケティング担当者が選び、微調整を施すことで、クリエイティブな作業にかかる時間と負担を大幅に削減できます。また、提案力が向上することで、顧客との商談やプレゼンテーションの質も高まります。
カスタマーサポート:自動応答・FAQ生成
生成AIは、チャットボットや自動応答システムにも活用されています。特に問い合わせ対応が多い企業では、人手不足やコスト削減の観点から、AIによる自動回答への期待が高まっています。AIが過去の問い合わせ履歴や製品マニュアルを学習し、新規の問い合わせに対して的確な回答を生成することで、サポート担当者の負荷を軽減しつつユーザーの満足度を維持・向上できるのがメリットです。
さらに、FAQを自動生成できるツールを導入すれば、定期的に更新や追加が必要なFAQページも効率的にメンテナンスできます。生成AIが文書の内容を自動で要約・整理し、わかりやすい質問と回答のセットを提案してくれるため、担当者は最終的なチェックや加筆修正に専念できるようになります。
クリエイティブ業務:画像制作・動画編集の支援
クリエイティブ領域においても生成AIの存在感は増しています。デザイナーや映像クリエイターは、アイデアのスケッチ段階でAIが瞬時に数多くの案を生み出してくれるため、その中から最適なものを取捨選択して完成度を高めることができます。たとえば、AIベースの画像生成ツールにキーワードやコンセプトを入力すると、アート作品風の画像やリアルなフォト風のイメージを一瞬で生成し、デザインのインスピレーションを得ることが可能です。
また、動画編集の現場でも、AIによる自動エフェクト追加や、動画内の不要シーンのカット、トランジションの提案などが行えるツールが増えています。従来は専門ソフトウェアと高いスキルが必要だった作業が、GUI(Graphical User Interface)の操作だけで完結する例もあり、映像制作に不慣れな人でも短時間でクオリティの高いコンテンツを作れるようになってきています。
目的別|生成AIおすすめツール12選【2025年最新版】

ここからは、実際にビジネスで活用できる生成AIツールを目的別に厳選して12種類紹介します。文章生成・画像生成・動画生成・音声生成・プレゼン支援など、さまざまなケースに対応できるものを取り上げていますので、ぜひ自社の業務やスキルレベルに合ったツール選びの参考にしてください。
文章生成:ChatGPT、Notion AI、Bing Chat、Writesonic
1. ChatGPT
ChatGPTは、自然言語処理の先端を行く大型言語モデル(LLM)をベースにしたチャットボット兼テキスト生成ツールです。ユーザーの質問や要望に応じて即座に文章を生成したり、アイデア出しや構成のサポートを行ったりできます。ビジネス文書のドラフト作成からキャッチコピー、ブログ記事の下書きまで幅広く活用可能で、操作もシンプルです。無料プランから有料プランまであり、用途に合わせて選べる柔軟性が魅力です。
2. Notion AI
Notionの中で利用できるAI機能で、メモやドキュメント作成の際に文章生成や要約ができます。Notionはプロジェクト管理やナレッジベースとしても人気ですが、AI機能が加わることで情報整理と文章作成が一気通貫で行えるようになりました。日常的にNotionを使っているチームや個人にとっては、非常に効率的なワークフローを構築できる点が強みです。
3. Bing Chat
検索エンジン大手が提供するチャット型AI。インターネット上の情報をリアルタイムで検索し、ユーザーの質問や要望に合わせて回答を生成します。コンテンツ作成や資料の下調べにおいて重宝し、他のテキスト生成AIと比較して最新情報に強いのが特徴です。文章校正から情報収集まで同時に行えるため、スピード感のある業務に適しています。
4. Writesonic
キャッチコピーやブログの見出し、SNS投稿など短い文章から長文コンテンツまで幅広く作成できる生成AIツールです。テンプレートが豊富で、マーケティング向けのコンテンツ作りに特化しており、広告文やLP(ランディングページ)向けのコピー生成にも定評があります。海外ツールですが日本語にも対応してきており、今後さらに便利になる期待が持てます。
画像生成:Canva AI、Midjourney、Adobe Firefly
5. Canva AI
デザイン初心者にも扱いやすいクラウド型デザインツールのCanvaに搭載されたAI機能です。テンプレート選択や写真編集に加え、テキストからイメージを生成できる機能が追加されました。SNS用のバナーやプレゼン資料、チラシなど、デザインの幅は多岐にわたり、初心者から上級者まで直感的に操作できます。無料版と有料版があり、有料版ではより高度な素材や機能を利用できます。
6. Midjourney
コミュニティを中心に急速に利用者が増えた高品質な画像生成ツール。テキストプロンプトを入力するだけで、イラストや写真風など多彩なスタイルの画像を自動生成します。操作は基本的にチャット形式で行い、指定するキーワードを工夫することでイメージに近い画像を作り出せます。独特のアート風表現に強みがあり、ハイセンスなビジュアルが必要な場合に重宝されます。
7. Adobe Firefly
クリエイティブソフトウェアの巨頭であるAdobeが提供する次世代の生成AIです。PhotoshopやIllustratorといった既存ツールとのシームレスな連携が想定されており、デザイナーが日常的に行う作業プロセスを大幅に効率化します。背景の差し替えやオブジェクトの追加、テキストのスタイル変換など、多岐にわたる画像処理をAIがサポート。品質の高さとプロ向けの機能が期待されています。
動画生成:Pictory、Runway ML、Synthesia
8. Pictory
テキストやスクリプトから自動的に動画を生成してくれるオンラインサービスです。キーワードベースで関連する映像素材や音声を組み合わせて、短い動画クリップを作成します。YouTubeのハウツー動画やSNS向けのプロモーション動画など、あらゆるジャンルで活用でき、動画編集の初心者にも使いやすい点が人気を集めています。
9. Runway ML
映像編集や特殊効果をAIが補助してくれるプラットフォームです。動画素材の自動切り抜きや背景合成、リアルタイムスタイル変換など、高度な技術をユーザーフレンドリーなインターフェイスで提供しているのが特徴。実験的なプロジェクトでも柔軟に使え、クリエイターだけでなくマーケッターや映像に馴染みのないビジネスパーソンも直感的に操作できる設計になっています。
10. Synthesia
アバターを使った動画生成を専門とするプラットフォームで、テキストを入力するだけでバーチャルな人物が音声とリップシンクを伴って話す動画を自動生成します。多言語に対応しているため、海外向けのプレゼン動画や学習コンテンツを低コストで制作できる点が魅力です。ナレーションや人件費をかけずに、複数の言語で映像コンテンツを配信できるので、グローバル展開する企業にも適しています。
音声・プレゼン:Voicemaker、Gamma
11. Voicemaker
テキストを入力すると、AI音声合成で人間に近い自然なナレーションを生成してくれるサービスです。日本語を含む多数の言語に対応し、声質やトーンの調整も自由度が高いのが特徴。YouTube動画のナレーションやeラーニングの教材音声など、さまざまな用途に合わせて使えます。音声合成の精度は年々向上しており、プロのナレーターによる録音が難しい場合でも、クオリティの高い音声コンテンツを作成可能です。
12. Gamma
オンラインでプレゼンテーション資料を作成・共有できるツールですが、AIによる自動スライド生成機能が注目されています。テキストや箇条書きを入力するだけで、見栄えのするデザインやアニメーションを自動的に割り当て、完成度の高いスライドデッキを瞬時に作成。プレゼン資料を作る時間が限られているときや、デザインに苦手意識がある方にとって、大きな助けとなるでしょう。
生成AIを導入する際の注意点とリスク管理

著作権・ライセンスの問題点
生成AIを利用して作成した作品については、著作権やライセンス面での問題が生じる可能性があります。利用するツールやプラットフォームによっては、AIが学習に用いた元データとの兼ね合いで権利関係が複雑になるケースもあるため、事前に利用規約や使用可能な範囲を確認しておく必要があります。また、AIが生成した画像や音声を商用利用する際には、その作品が第三者の権利を侵害していないかを慎重にチェックしなければなりません。
特に、中小企業や個人事業主が広告や商品パッケージなど大々的に使用する場合、法的リスクが発生すると経営に大きな影響を及ぼすことがあります。権利関係が不透明なサービスを利用するのではなく、信頼性の高いプラットフォームや明確なライセンスを提示しているツールの選択が望ましいでしょう。
情報の正確性とフェイク生成リスク
生成AIは膨大なデータを学習し、それをもとに新たなコンテンツを生み出します。しかし、その情報源が不正確だった場合や学習データが偏っていた場合、生成されるコンテンツにも誤情報が含まれるリスクがあります。文章生成AIであればフェイクニュースの拡散、画像生成AIであれば捏造画像の作成など、社会的に大きな問題へ発展しうる懸念点があります。
ビジネスで利用する際には、生成AIが出力した情報を鵜呑みにせず、常に人の目で確認・校正するプロセスが必要です。特に金融や医療など、正確性が強く求められる業界では、AIツールの導入時に入念な検証とガイドラインの策定が欠かせません。
社内運用ルールとデータ管理
生成AIを使いこなすためには、ツールを導入するだけでなく、社内の運用ルールやガイドラインを整備することが重要です。具体的には、以下の点に注意が必要です。
- どの部署・担当者がAIツールの導入・管理を行うのか明確化する
- 生成コンテンツの校正や承認フローをどうするのかルール化する
- AIに学習させるデータやアップロードする情報に機密性が含まれる場合の管理方針
- 外部サービスを利用する場合のセキュリティリスク、データの取扱いについての確認
これらの点を明確にしておくことで、組織全体として生成AIを有効に活用しながら、リスクを最小限に抑えることができるでしょう。導入前にポリシーを策定し、社員や関係者に周知徹底することが重要です。
生成AI導入を支援するサービスとは?

生成AI活用のコンサルティング
生成AIを自社に導入したいものの、何から始めればいいか分からない場合や、具体的なプロジェクトの企画段階でつまずいている場合には、専門家のコンサルティングを利用する方法があります。特に、freedoorのようなサービスは、生成AIの技術的背景からビジネス適用のノウハウまで幅広い知見をもっており、導入プロセスをスムーズに進めるためのアドバイスを受けられます。
具体的には以下のような内容をカバーします。
- 事業課題や目標に応じた最適なAI活用シナリオの設計
- 効果的な導入スケジュールと必要リソースの把握
- 既存業務へのAIツールの統合方法やサンプル事例の紹介
- 社内スタッフを対象としたAI活用研修の計画
業務フローへの導入支援・社内研修
単に「AIツールを使おう」と言っても、現場レベルでは既存の業務フローにどう落とし込むのか、どのように担当者間で連携するのかが大きな課題となります。freedoorでは、顧客の業務内容をヒアリングし、そこに最適なAIツールの選定や設定を行うだけでなく、具体的なオペレーションの組み立てまで支援を行います。
さらに、導入後も社内研修やフォローアップを行い、担当者がツールを使いこなし続けられるようサポートします。技術やソフトのアップデートが激しいAIの世界では、継続的な学習と情報交換が欠かせません。freedoorのような専門家のバックアップがあることで、最新の活用トレンドを逃さずに取り入れることが可能になります。
補助金申請サポートとAIツール選定支援
生成AIの導入にはソフトウェアのライセンス費用やコンサルティング費用がかかることがあります。中小企業や個人事業主にとっては、そのコストが大きな負担になる場合も少なくありません。しかし、国や自治体が実施している補助金制度を活用すれば、導入費用の一部を補填することが可能です。
freedoorは、そのような補助金を活用したい企業や個人事業主に対して、情報提供や申請手続きのサポートも行っています。慣れない補助金申請の書類作成や要件確認を代行してもらえるため、非常にスムーズに進められるでしょう。また、数多くのAIツールの中から自社の目的や予算に合ったものを選ぶ際にも、専門的な知見をもとに最適な選定を支援してくれます。
まとめ|生成AIを上手に活用し、ビジネスを加速させよう

選び方のポイントと始め方の一歩
生成AIは文章、画像、音声、動画など、さまざまな形式のコンテンツを瞬時に生み出し、ビジネスシーンに多大な恩恵をもたらします。しかし、その選択肢は非常に多岐にわたるため、まずは「どの業務を効率化したいのか」「どのようなクリエイティブ作業が必要なのか」を明確化し、それに合ったツールを選ぶことが重要です。特に以下のポイントを押さえると、スムーズに導入できます。
- 目的を明確にする(例:プレゼン資料を短時間で作りたい、SNS向けの画像を量産したいなど)
- ツールの特徴や得意分野、料金体系を比較検討する
- 導入後の運用体制やリスク管理(著作権、プライバシー)を考慮する
- 試用版やデモ版を活用して、実際の操作感や成果物を確認する
これらを踏まえて、自社や自身のビジネスにフィットするツールを導入すれば、作業効率やクリエイティブの質が格段に向上する可能性が高いでしょう。
freedoorが中小企業・個人事業主に提供できる価値
生成AIを導入する上で気になる点や不安な部分が多い場合、専門的な視点からサポートしてくれるパートナーを見つけることは大変心強いものです。freedoorは、生成AIのコンサルティング、導入支援、社内研修、さらには補助金申請サポートに至るまでトータルでサービスを提供しています。以下のようなメリットが期待できます。
- 豊富な事例・ノウハウをもとに適切なAIツールを提案してもらえる
- 導入後も最新情報や技術動向を共有し、継続的な活用をサポート
- コスト面での負担を軽減するための補助金情報を得られ、申請も代行してもらえる
- 専門用語や技術的な壁を感じることなく、スピーディにプロジェクトを進められる
生成AIの登場は、クリエイティブや情報発信の在り方を大きく変えています。個人や小規模事業者が、大手企業と同等あるいはそれ以上のスピード感とクオリティでコンテンツを作り出せるチャンスが増えているのです。競争が激しくなるビジネス環境の中で、AIを適切に使いこなせるかどうかが今後の差別化要因にもなり得るでしょう。
まずは自分が興味を持ったツールから試し、一定の成果が確認できたら、社内全体やビジネスの別領域に広げていく方法がおすすめです。生成AIを活用することで得られる価値は計り知れません。ぜひ本記事を参考に、あなたのビジネスを次のステージへと加速させてみてください。
AI×DX支援サービスのご案内

「AIを使って業務のデジタル化や自動化を進めたいけれど、どのツールを使えばいいのかわからない」「運用できる人材が社内にいない」というお悩みはありませんか?
freedoor株式会社では、単なるAIツール導入のご提案にとどまらず、企業全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための総合支援を行っています。システム開発、Webマーケティング、コンサルティングなど、幅広い分野で培ったノウハウを活かし、最先端のAI技術とビジネス課題のベストマッチを実現。自社内のみで完結しづらい部分を外部パートナーとしてサポートし、企業の持続的な成長を強力にバックアップします。
特に、昨今需要が高まっているAIによる動画生成や画像生成、チャットボットをはじめとしたさまざまなAIソリューションにも対応。これまでに培った総合力をもって、貴社が抱える経営課題・現場課題に合わせたオーダーメイドのDX化支援プランをご提案いたします。
AI導入支援
「どのAIツールを選定するべきか」「自社のシステムに合うカスタムモデルを開発できるか」「導入後の運用フローをどう構築するか」など、AI導入時に生じる悩みをトータルでサポートします。試行段階のPoC(概念実証)から本格導入、既存業務とのシステム統合に至るまで、幅広く対応。DX推進の鍵となるAI活用を、スピード感を持って実現します。
WEB/システム開発
自社サイトや既存の業務システムへAI機能を組み込む場合、ユーザー体験設計やセキュリティ面、運用管理など、多岐にわたる専門的知見が必要です。freedoorはシステム開発やアプリケーション構築の実績が豊富なため、「AIを活かせる開発環境」をスムーズに整備。分析基盤の構築やAPI連携、クラウドインフラの最適化など、DX推進に欠かせない技術面を幅広くサポートします。
WEBマーケティング・SNS運用代行
AIで生成したコンテンツを効果的に運用するには、ユーザー属性や市場動向を捉えたマーケティング戦略が欠かせません。freedoorでは、SEO対策やSNS運用代行、広告運用まで一気通貫でサポート。AIで生み出した魅力的なコンテンツを最大限活用し、顧客との接点拡大やブランド価値向上、海外展開サポートなど、ビジネス成長に直結する戦略を提案いたします。
オンラインアシスタントサービス
AI活用をはじめ、日々の運用タスクや業務サポートを任せたいというお客様には、オンラインアシスタントサービスを提供しています。業務の効率化やチーム全体の生産性向上を目指し、ルーチン業務の代行やスケジュール管理、リサーチなど、幅広い業務を支援いたします。
これらのサービスを柔軟に組み合わせることで、AI導入の試行段階から企業のDX化へと、一貫性のある戦略的なステップを踏むことが可能です。freedoor株式会社は、お客様にとって最適なAI・システム・マーケティング体制を構築し、ビジネスの持続的成長と競争力強化を実現します。
