無料で使える生成AIツール15選|文章作成が一瞬で終わるおすすめ比較【2025年最新】

生成AIを使って無料で文章を書きたい。
そう考える人が急増しています。
しかし、実際に検索してみると「どのツールを選べばいいかわからない」「登録が必要で面倒」と感じるケースも多いです。
本記事では、登録不要・無料・日本語対応・商用利用OKなど、さまざまなニーズに応じた文章生成AIを厳選。
比較表・目的別・機能別・注意点・活用法まで網羅して解説します。
初心者でも安心して使えるツールだけをピックアップしています。
ぜひ最後まで読んで、自分に最適なAIを見つけてください。
【比較表付き】無料で使える文章生成AIツール15選(登録不要含む)

ここでは、生成AIで文章作成を始めたい方に向けて、無料で利用できるツールを一挙に紹介します。
利用形式、対応言語、登録要否、商用利用の可否などをわかりやすく整理した比較表を掲載していますので、目的に応じて最適なツールを見つけてください。
| ツール名 | 対応言語 | 利用形式 | 登録要否 | 商用利用 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 多言語(日本語対応) | Web/アプリ | 要登録 | 可(要規約確認) |
| Claude | 多言語 | Web | 要登録 | 可 |
| Gemini(旧Bard) | 多言語(Google日本語対応) | Web | 要Googleアカウント | 可 |
| LeapMe | 日本語 | Web | 不要 | 可(要注意) |
| Catchy | 日本語 | Web | 要登録 | 可 |
高性能な汎用生成AI
AI初心者から上級者まで幅広く支持されているのが、汎用性の高い文章生成AIです。
ここでは、質問応答や会話、長文作成にも対応する代表的なツールを紹介します。
ChatGPT(GPT-3.5 / GPT-4)
OpenAIが提供するChatGPTは、現在最も広く活用されている生成AIの一つです。
無料プランではGPT-3.5を利用可能で、自然な日本語対応も充実しています。
ブログ、アイデア出し、要約、メール文作成など多用途で使える点が特長です。
ユーザー登録は必要ですが、ブラウザ・スマホアプリともに使いやすく、学習用途にも最適です。
Claude
Anthropicが開発したClaudeは、ChatGPTと並ぶ高性能な対話型AIです。
長文理解力に優れ、コンテキストを保持した文章生成に強みがあります。
海外では企業向けにも導入が進んでおり、ビジネス用途で高評価を得ています。
現在、英語を中心としながらも日本語対応が進んでおり、今後注目のツールです。
Gemini(旧Bard)
Googleが開発したGemini(旧Bard)は、Google検索との連携に強みを持つ生成AIです。
リアルタイム情報の取得能力が高く、最新情報に基づいた文章生成が可能です。
Googleアカウントがあればすぐに使える手軽さも魅力で、文章作成や下調べに向いています。
日本語対応・SEOにも強い国産AI
国内開発の生成AIツールは、日本語に最適化されている点が大きな強みです。
ここでは、SEOやWebライティングに特化した日本製ツールを紹介します。
Catchy
Catchyは広告やコピーライティングに強い日本製AIツールです。
「キャッチコピー」「商品紹介文」「SNS投稿」など、短く伝える文章を得意としています。
テンプレートも豊富で、プロンプトを入力するだけで数秒で文章が完成します。
Transcope
SEOに特化した文章を生成できるTranscopeは、記事構成から見出し提案まで自動化可能です。
特にキーワードを入れるだけでSEO最適な文章を出力してくれるため、Webマーケティング担当者にとって強力な味方になります。
ELYZA Pencil
ELYZA Pencilは、ビジネス文書や報告書など、フォーマルな文章の作成に最適です。
自然な敬語変換や業務メールの文例を提案してくれるため、ビジネスの現場でも重宝されています。
日本語ネイティブによる監修が行われているため、読みやすく説得力のある文章が生成されます。
登録不要で手軽に使えるAI
「まずは試してみたい」「登録が面倒」という方におすすめなのが、アカウント作成なしですぐに使える生成AIです。
以下のツールは、アクセス後すぐに文章生成を体験できます。
LeapMe
LeapMeは、登録不要でWeb上からすぐに文章生成を体験できる日本語対応ツールです。
入力画面にプロンプトを打ち込むだけで、簡潔な文章や定型文を瞬時に出力します。
SNS投稿や日常のメッセージ文作成など、ライトな用途に最適です。
AIのべりすと
AIのべりすとは、物語や小説の自動生成に特化した無料AIツールです。
キャラクター設定やジャンルを選ぶだけでストーリーが展開され、創作活動のサポートとして非常に便利です。
物語の続きを書かせたい人にとって、アイデア補助としても有効です。
小説・ストーリー・創作に強いAI
創作活動において、プロット作成や物語の続きを考えるのに行き詰まった経験はありませんか?
この章では、小説やストーリー制作に特化したAIツールを紹介します。
アイデア発想のきっかけや、作家支援として活用できる機能に注目してみましょう。
Muse
Museは、創作支援を目的に開発されたAIで、物語の構成・登場人物の設定・会話文生成などに強みがあります。
ユーザーの入力に応じてストーリーがどんどん展開していくので、アイデアを具現化する作業がスムーズになります。
特にジャンル指定(SF、恋愛、ホラーなど)が可能で、物語のトーンに合った自然な流れをつくることができます。
AI Writer
AI Writerは、長文コンテンツや創作ストーリー向けに設計された文章生成AIです。
アウトライン作成から章ごとの肉付けまで対応しており、ブログ小説や連載記事の作成にも使えます。
ストーリーの一貫性を保ちつつ、ユーザーの意図に沿った展開を生み出せるのが特徴です。
プロットに悩む作家やライターにもおすすめです。
ビジネス向けの実用AI
ビジネス文書は、正確性と丁寧な表現が求められる分野です。
この章では、社内報告書やメール文、提案書などに活用できるAIツールをご紹介します。
Microsoft Copilot
Microsoft Copilotは、WordやOutlookといったOffice製品と統合されているAI機能です。
過去の文書内容やトーンを読み取り、適切な文章を提案することで、業務時間を大幅に短縮できます。
レポート作成や会議資料の要約にも対応しており、ビジネスの現場で即戦力となる存在です。
Magic Write(Canva連携)
Magic Writeは、デザインツールCanvaと連携した文章作成AIです。
提案書やプレゼン資料を作る際に、キャッチコピーや説明文を自動生成してくれます。
プレゼン資料の「文章をどう書くか悩む」シーンで特に効果を発揮し、構成の骨組みづくりをサポートします。
文章+αのマルチ機能AI
単に文章を生成するだけでなく、画像検索・要約・情報収集など複数の機能を備えたツールも登場しています。
複合的なタスクに対応したい方に最適なAIをご紹介します。
Bing
Bing(Microsoftの検索エンジン)は、Copilotと統合されたことで文章生成とWeb検索を同時にこなせるようになりました。
リアルタイム情報を反映した自然な文章を作ることができ、ニュースや調査記事に適しています。
文章の根拠となる出典リンクが表示されるため、信頼性も高く、コンテンツ制作における情報収集効率を大きく高めてくれます。
Perplexity
PerplexityはAI検索エンジンとして知られ、ユーザーの質問に対して簡潔かつ文脈のある文章を返します。
検索と生成を掛け合わせたこのツールは、リサーチから文章作成までを1つのフローで完結できるのが魅力です。
しかも、回答には出典リンクが含まれており、ファクトチェックの手間も軽減されます。
目的別に見る|生成AIの活用シーンと選び方

生成AIで文章作成を行う際は、目的に応じたツールを選ぶことが重要です。
この章では「ブログ・小説・ビジネス・SNS・教育」といったシーンごとに、適した使い方やポイントを解説します。
ブログや記事作成向けAI
SEO記事やコンテンツマーケティングを目的としたブログ運営では、構成力と検索キーワード対応が求められます。
ここでは、Webライターやメディア担当者におすすめのAI活用方法をご紹介します。
長文生成・SEO対応のポイント
記事作成において、SEOに対応した構成やキーワード配置を考慮できるAIは非常に有用です。
たとえばTranscopeのようなSEO特化ツールでは、狙いたいキーワードを入力するだけで、タイトル・見出し・本文の下書きが完成します。
また、ChatGPTなどの汎用AIでも、プロンプト設計を工夫することで、自然な長文を効率よく生成できます。
以下のような観点で選ぶと良いでしょう:
- SEOテンプレート機能の有無
- 見出し構成と文章一括生成ができるか
- 複数パターンの文体・トーンが選べるか
創作・小説を書くクリエイター向けAI
物語の構成や登場人物の会話を考えるのが苦手という人にとって、生成AIは優れた創作パートナーになります。
ここでは、フィクション作品づくりに特化した使い方を紹介します。
ストーリー構成と続きを自動で生成
MuseやAIのべりすとのような小説特化型AIは、プロットからシーン展開まで自動で構築できます。
ユーザーが入力した「登場人物」「舞台」「ジャンル」に応じて、自然な物語の流れを提案してくれる点が魅力です。
続きを書くといったプロンプトを使えば、途中で止まった物語の続きをスムーズに生成できます。
創作初心者だけでなく、アイデアが煮詰まった中級者以上にも有用です。
メールやビジネス文書作成に使いたい場合
ビジネスの現場では、伝わりやすく丁寧な文章が求められます。
ここでは、仕事の効率化につながるAIの活用方法を解説します。
敬語変換や校正支援で業務効率化
ELYZA PencilやMicrosoft CopilotのようなAIは、メール文の作成からビジネス文書の校正まで幅広く対応しています。
例えば、箇条書きを入力するだけで、丁寧な文体へ変換する機能があり、社外メールや企画書の文章を瞬時に整えることが可能です。
また、Shodo AIなどは文章の論理性や誤字脱字をチェックしてくれるため、最終確認の手間も削減されます。
短文・SNS・教育向けの軽量活用
日常的なコミュニケーションや教育現場でも、生成AIは手軽に活用できます。
ここでは、SNS投稿や学生向けの作文作成に役立つ使い方を紹介します。
テンプレ対応で手早く文章を整える
Catchyのようなツールは、SNSの投稿文や短い広告文など、インパクトのある短文を自動で提案してくれます。
テンプレートが豊富に用意されており、プロンプトを数語入力するだけで文章が完成します。
Twitter・Instagram・LINEなど、用途別に最適化された文体をすぐに得られるため、SNS運用の効率が格段にアップします。
作文・読書感想文にも使えるAIとは?
教育分野では、生成AIを作文支援や発想補助に活用する動きが広がっています。
たとえば、LeapMeなどの簡易AIツールは、入力したテーマに沿って段落構成を提案してくれます。
「読書感想文」や「学校の課題作文」においては、書き出しやまとめ方を教えてくれるため、文章を書くのが苦手な学生のサポーターとして活用されています。
ただし、丸写しを避けて、自分の言葉でリライトすることが大切です。
無料プラン vs 有料プランの違いとは?
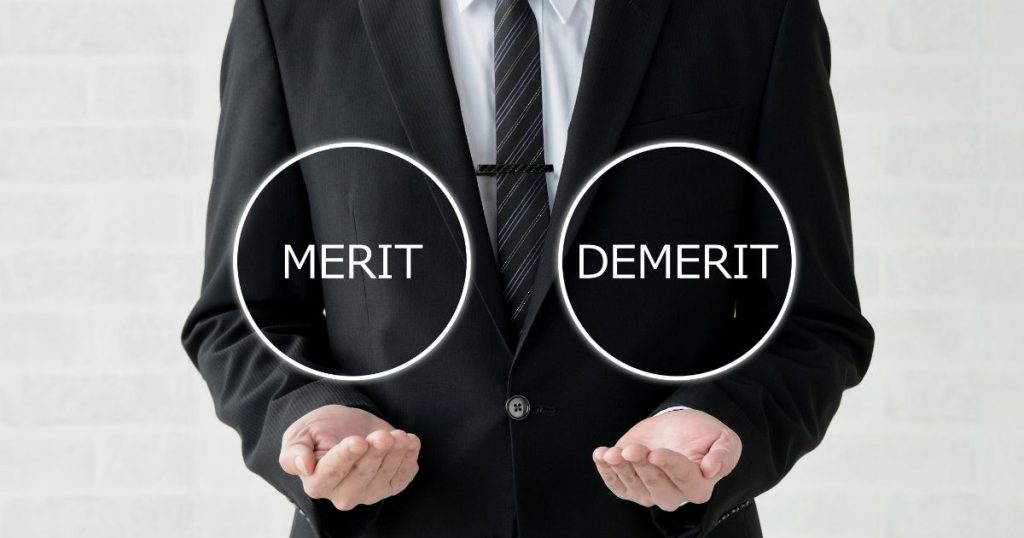
多くの生成AIツールには、無料プランと有料プランが用意されています。
ここでは、両者の主な違いと、それぞれのメリット・デメリットについて整理しておきましょう。
自分の目的に合ったプランを選ぶことで、AIのパフォーマンスを最大限に引き出せます。
無料で使える範囲と注意点
無料プランの最大の魅力は、コストをかけずに高性能な文章生成AIを試せることです。
以下のような基本機能は、ほとんどのツールで無料で利用可能です:
- 簡単な短文作成
- 基本的なプロンプト入力と文章出力
- 登録不要で使えるお試しモード
ただし、次のような制限に注意が必要です:
- 文字数制限:長文が出力できない場合がある
- 回数制限:1日◯回までといった使用制限がある
- 機能制限:画像生成・フォーマット指定などが利用できない
無料プランは「まず使ってみたい」「少しだけ試したい」という方に最適です。
有料版で得られる3つのメリット
文章生成AIを本格的に活用したい場合、有料プランの導入を検討する価値があります。
特に次の3点が大きなメリットとして挙げられます:
- 長文や複雑な文章の出力が可能
例えばChatGPTのGPT-4モデルは、有料ユーザーのみが利用可能です。
より自然で文脈に沿った文章が生成できます。 - 高頻度・大量利用が可能
ビジネスで日常的に活用する場合、無料プランでは回数が足りないケースがあります。
有料版なら制限なく使える場合がほとんどです。 - 追加機能の解放
ファイルアップロード・チーム共有・API接続など、プロ仕様の機能を活用できます。
費用対効果を考慮し、どのタイミングで有料に切り替えるべきかを見極めることが重要です。
無料から始めるときのチェックリスト
まずは無料で使える生成AIを活用したいという方のために、チェックしておくべきポイントを以下にまとめました。
以下の観点を押さえておくと、トラブルなく安心して利用を始められます:
- 利用規約を確認する(商用利用の可否をチェック)
- 入力データの取り扱い(保存されるかどうかを確認)
- 機能制限の有無(生成文字数や回数など)
- 言語対応(日本語対応かどうか)
- サポート体制(問い合わせやヘルプが整備されているか)
生成AIで文章作成したい時におすすめの無料ツールを選ぶには、これらのチェック項目をひとつひとつ確認しながら比較するのが効果的です。
無料ツールの注意点|生成AIを安全かつ賢く使うポイント
無料で使える生成AIツールは便利で魅力的ですが、利用にあたっては一定のリスクや注意点もあります。
この章では、著作権・情報の扱い・コピペリスクなど、使用時に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。
安全にAIを活用するためにも、事前に理解しておきましょう。
著作権・コンテンツの所有権問題
生成AIによって作成された文章は、一見すると完全にオリジナルに見えます。
しかし、ツールによっては著作権やコンテンツの所有権が曖昧になるケースも存在します。
特に無料ツールでは、「生成された文章の利用範囲」が明確に定められていないこともあるため注意が必要です。
商用利用前に必ず確認すべき規約とは?
商用目的で文章を使用する場合、必ず利用規約を確認しましょう。
中には「非営利利用に限る」「商用は別途ライセンス契約が必要」などの制限が設けられているツールもあります。
例えば、無料版では商用不可でも、有料プランなら使用可能になるケースがあります。
規約違反によるトラブルを防ぐためにも、使用前に「商用可否」「著作権の帰属先」「再配布の条件」などを事前に確認することが重要です。
コピペチェックとAI生成文の重複リスク
生成AIによる文章はオリジナルのように見えても、他のユーザーにも類似の文章が出力されている可能性があります。
そのため、特にWebコンテンツに使用する場合は、コピーコンテンツ判定を受けないよう注意が必要です。
コピーコンテンツとして判定されるケース
AIが同一プロンプトに対して類似した文章を出力することは珍しくありません。
その結果、複数のサイトでほぼ同じ文章が掲載されると、Googleのアルゴリズムによりコピーコンテンツと判断される恐れがあります。
このような事態を防ぐには、以下の対策が有効です:
- 出力内容をコピペチェックツールで確認
- 一部の表現を自分なりにアレンジ
- 見出し構成や文体をオリジナルに編集
AIの力を借りつつ、人間の視点で最終調整することが、SEO的にも安全です。
プライバシー・個人情報の入力は避けるべき?
生成AIは入力された情報をもとに文章を作成します。
そのため、プライバシーや機密性の高い情報を不用意に入力するのは避けるべきです。
ここでは、その理由と対策を解説します。
入力データが学習に使われる可能性も
多くの生成AIツールでは、ユーザーが入力したデータを内部的に保存・解析し、AIモデルの学習に活用する場合があります。
これはサービス向上のために行われる処理ですが、意図せず機密情報が残るリスクもあります。
特に「名前」「住所」「企業名」などの個人情報や機密情報は絶対に入力しないのが鉄則です。
また、サービスによっては「入力データは学習に利用されません」と明記されているものもあるため、安心して使いたい場合はそのような明記のあるAIツールを選びましょう。
文章生成AIを効果的に活用するコツ

生成AIを使って文章を作成するだけでなく、より質の高いアウトプットを得るには、工夫とテクニックが必要です。
この章では、プロンプト設計や文体調整、チェックの方法など、実践的な活用術を紹介します。
良質なプロンプトの作り方
生成AIの性能を最大限に引き出すためには、プロンプト(指示文)の質が非常に重要です。
何を、どのように、誰に向けて書くのかを明確に伝えることで、より目的に合った文章が出力されます。
「誰に、何を、どのように伝えるか」の明確化
プロンプトを作成する際は、以下の3点を明確に意識することで精度が大きく向上します:
- 誰に:対象読者(例:中学生向け/ビジネスパーソン向け)
- 何を:伝えたい主旨(例:AIの仕組み/使い方のコツ)
- どうやって:文章のトーンや構成(例:丁寧に/箇条書きで/会話形式で)
たとえば「SEOに強いブログの書き出しを300文字で作成して」といった具体的な指示にすると、精度の高い出力が得られます。
トーンや文体を調整するコマンドの使い方
生成AIには、出力される文章の雰囲気(トーン)や形式(文体)を調整できる機能があります。
これを使いこなすことで、読み手に合った文章表現が可能になります。
以下のようなコマンドをプロンプトに加えることで、出力内容をコントロールできます:
- 「ですます調で丁寧に説明してください」
- 「ビジネス向けにフォーマルな文体で」
- 「親しみやすく、口語体でカジュアルに」
このように、文体や口調のトーンを明示的に指定することで、文章の印象が大きく変わります。
用途に応じて使い分けるのがポイントです。
校正・ファクトチェックを怠らない
どれほど優れた生成AIでも、事実誤認や文法のミスがゼロとは言い切れません。
AIは「それらしく見える文章」を作るのは得意ですが、情報の正確性までは保証してくれないケースも多いのです。
そのため、以下のようなチェックは必ず行いましょう:
- データの出典を確認:統計や引用が正しいか
- 文法や表現の整合性:主語と述語の一致など
- 日本語の自然さ:不自然な表現がないか
AIに任せっぱなしにせず、人間の視点で最終確認を行うことが信頼性の高いコンテンツづくりにつながります。
任せきりにしない「編集力」の重要性
生成された文章はあくまで「たたき台」であり、最終的なクオリティを左右するのは編集力です。
AIが作った文章に、読者への配慮や感情の込もった言葉を加えることで、伝わる力が大きく変わってきます。
最後は人間の視点で“伝わる文章”に仕上げよう
編集の際には、次の3つの視点を意識してみましょう:
- 読者の理解度に合わせた表現:難しすぎず、簡単すぎず
- 論理的な構成:起承転結やPREP法を活用
- 心に響く言葉選び:AIには出せない“人間らしさ”を加える
AIと人間、それぞれの得意分野を活かすことで、最高の文章が完成します。
活用で失敗しないための5つの心得
生成AIを活用する際には、基本的なマナーやリスク対策も重要です。
以下の5つを心得として押さえておくと、安心かつ効果的に利用できます:
- 生成結果は必ず目を通す:誤情報やミスがないか確認する
- 人間の感性で整える:冷たい印象の文章には温かみを加える
- 用途に応じてツールを選ぶ:小説・ビジネスなど適材適所
- AIに頼りすぎない:思考停止せず、自分の意図を持つ
- ルールや規約を守る:著作権・商用利用の範囲を守る
これらのポイントを意識することで、生成AIの利用価値は飛躍的に高まります。
よくある質問(Q&A)

ここでは、生成AIで文章作成を始めたいと考えている方からよく寄せられる疑問や不安に対して、わかりやすく回答していきます。
初めてAIツールを使う方も、これを読めば安心してスタートできるはずです。
無料でも商用利用できますか?
多くの生成AIツールでは、無料プランでも商用利用が可能ですが、利用規約の確認が必須です。
たとえば、ChatGPTやNotion AIなどは、無料でも一定の商用利用が許可されていますが、ツールによっては「個人利用のみ」や「クレジット表記必須」といった制限がある場合もあります。
公式サイトの利用規約やFAQをチェックし、「商用利用OK」と明記されているものを選ぶのが安心です。
学生のレポートや論文に使ってもいい?
学校の課題やレポートに生成AIを使用する際は、学校側のガイドラインや提出ルールに従う必要があります。
近年、多くの教育機関では「AIの使用は補助的な参考に留める」「必ず出典を明記する」といったルールが設けられています。
また、AIで作成した文章をそのまま提出するのは盗用とみなされる可能性があるため、あくまで「参考資料」として活用し、自分の言葉でリライトするのが適切です。
スマホだけで使えるアプリはありますか?
はい、スマートフォンで使える文章生成AIアプリは多数存在します。
代表的な例としては、ChatGPTアプリ(iOS/Android)、Notion AIアプリ、CanvaのMagic Writeなどがあります。
これらはアカウント登録後すぐに使えるうえ、スマホでの操作に最適化されており、外出先や移動中でも手軽に文章生成が可能です。
日記・メモ・SNS投稿の下書きにも便利です。
自然な日本語を書けるAIはどれ?
日本語に最適化されたツールとしては、Catchy、ELYZA Pencil、Transcopeなどの国産AIがおすすめです。
これらは日本語特有の敬語・丁寧語の文体にも対応しており、自然で読みやすい文章を生成できます。
また、ChatGPTも日本語の精度が非常に高く、文脈を踏まえた表現や適切な語彙選択が可能です。
日本語の自然さを重視する場合は、こうしたツールを選ぶと良いでしょう。
小説やエッセイの続きを書いてもらえる?
はい、MuseやAIのべりすと、ChatGPTなどは「続きを書く」指示に対応可能です。
特に、プロンプトで前段の文章や登場人物、状況設定を与えると、それに応じた展開をスムーズに生成してくれます。
創作中に行き詰まった時や、結末のアイデアが浮かばない時などに活用すれば、創作の幅を大きく広げられます。
ただし、オリジナリティを持たせるためには、自分なりの編集や構成の見直しも重要です。
まとめ|まずは無料で生成AIを試してみよう

ここまで、文章生成AIの仕組みや活用方法、目的別の選び方、注意点、具体的なおすすめツールについて解説してきました。
最後に、これから使い始める方に向けて、最初の一歩をスムーズに踏み出すためのヒントをまとめます。
最初に試すべきおすすめAIツール3選
生成AIに初めて触れる方におすすめしたいのが、以下の3つのツールです:
- ChatGPT(GPT-3.5):高精度な汎用性と自然な対話が魅力。登録は必要ですが、無料で利用可能。
- LeapMe:登録不要ですぐに使える手軽さ。SNSや短文作成に最適。
- Catchy:日本語対応に優れた国産ツール。ブログ・広告文など実用的な文章生成に強い。
まずはこの3つの中から、あなたの目的に合ったツールを選んで試してみるとよいでしょう。
使ってみることで、自分にとってのベストなAIツールが見えてくるはずです。
書くストレスを減らして創作をもっと楽しく
文章を書くのが苦手だったり、時間がかかったりする人にとって、生成AIはまさに頼れるアシスタントです。
文章作成の「ゼロから考える」負担を軽減し、構成や文体のアイデアをスピーディーに提供してくれます。
大切なのは、AIに「書かせる」だけでなく、「活用する」意識です。
自分の表現を磨くための道具として、生成AIを賢く使いこなしていきましょう。
これからの時代、AIと人間が協力して書くというスタイルが、ライティングの新たな常識となるでしょう。
AI×DX支援サービスのご案内

「AIを使って業務のデジタル化や自動化を進めたいけれど、どのツールを使えばいいのかわからない」「運用できる人材が社内にいない」というお悩みはありませんか?
freedoor株式会社では、単なるAIツール導入のご提案にとどまらず、企業全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための総合支援を行っています。システム開発、Webマーケティング、コンサルティングなど、幅広い分野で培ったノウハウを活かし、最先端のAI技術とビジネス課題のベストマッチを実現。自社内のみで完結しづらい部分を外部パートナーとしてサポートし、企業の持続的な成長を強力にバックアップします。
特に、昨今需要が高まっているAIによる動画生成や画像生成、チャットボットをはじめとしたさまざまなAIソリューションにも対応。これまでに培った総合力をもって、貴社が抱える経営課題・現場課題に合わせたオーダーメイドのDX化支援プランをご提案いたします。
AI導入支援
「どのAIツールを選定するべきか」「自社のシステムに合うカスタムモデルを開発できるか」「導入後の運用フローをどう構築するか」など、AI導入時に生じる悩みをトータルでサポートします。試行段階のPoC(概念実証)から本格導入、既存業務とのシステム統合に至るまで、幅広く対応。DX推進の鍵となるAI活用を、スピード感を持って実現します。
WEB/システム開発
自社サイトや既存の業務システムへAI機能を組み込む場合、ユーザー体験設計やセキュリティ面、運用管理など、多岐にわたる専門的知見が必要です。freedoorはシステム開発やアプリケーション構築の実績が豊富なため、「AIを活かせる開発環境」をスムーズに整備。分析基盤の構築やAPI連携、クラウドインフラの最適化など、DX推進に欠かせない技術面を幅広くサポートします。
WEBマーケティング・SNS運用代行
AIで生成したコンテンツを効果的に運用するには、ユーザー属性や市場動向を捉えたマーケティング戦略が欠かせません。freedoorでは、SEO対策やSNS運用代行、広告運用まで一気通貫でサポート。AIで生み出した魅力的なコンテンツを最大限活用し、顧客との接点拡大やブランド価値向上、海外展開サポートなど、ビジネス成長に直結する戦略を提案いたします。
オンラインアシスタントサービス
AI活用をはじめ、日々の運用タスクや業務サポートを任せたいというお客様には、オンラインアシスタントサービスを提供しています。業務の効率化やチーム全体の生産性向上を目指し、ルーチン業務の代行やスケジュール管理、リサーチなど、幅広い業務を支援いたします。
これらのサービスを柔軟に組み合わせることで、AI導入の試行段階から企業のDX化へと、一貫性のある戦略的なステップを踏むことが可能です。freedoor株式会社は、お客様にとって最適なAI・システム・マーケティング体制を構築し、ビジネスの持続的成長と競争力強化を実現します。
