AIが嘘をつく原因と対策をまるっと解説|ハルシネーションの仕組みとは
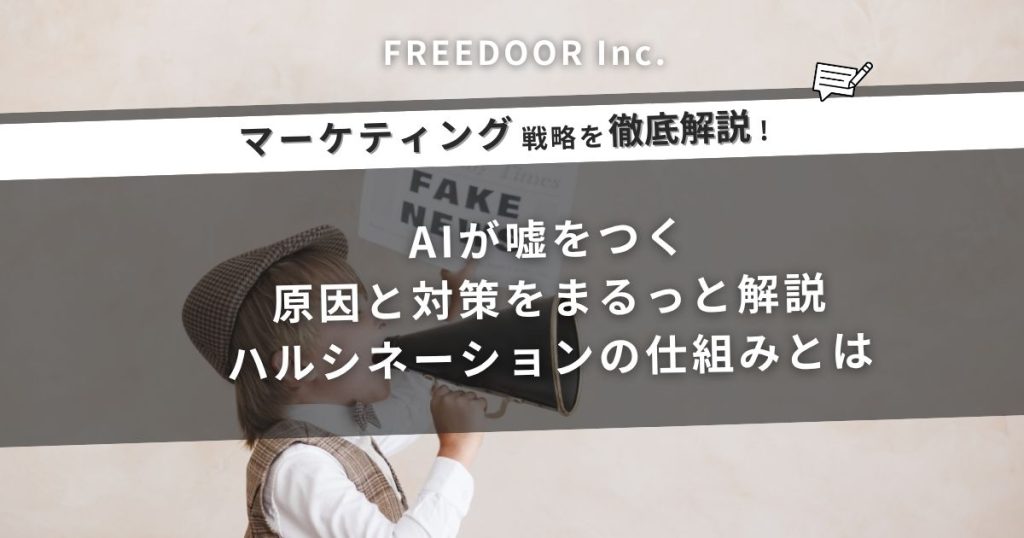
生成AIが身近になり、検索やチャットで気軽に答えをもらえる時代になりました。
ところが便利さの裏で「AIが嘘をつく」場面に遭遇し、あわてた経験はありませんか。
本記事ではハルシネーションと呼ばれる誤回答の仕組みをやさしくひもとき、リスクを最小限に抑える質問テンプレやチェックリストを紹介します。
さらに「少しズレた答え」を逆手に取り、アイデア発想に生かすポジティブ活用法まで網羅。
IT初心者でも今日から実践できるステップで、AIと安心して付き合う方法をお届けします。
AIが嘘をつくときに起きるふしぎ現象 ― ハルシネーションをのぞいてみよう
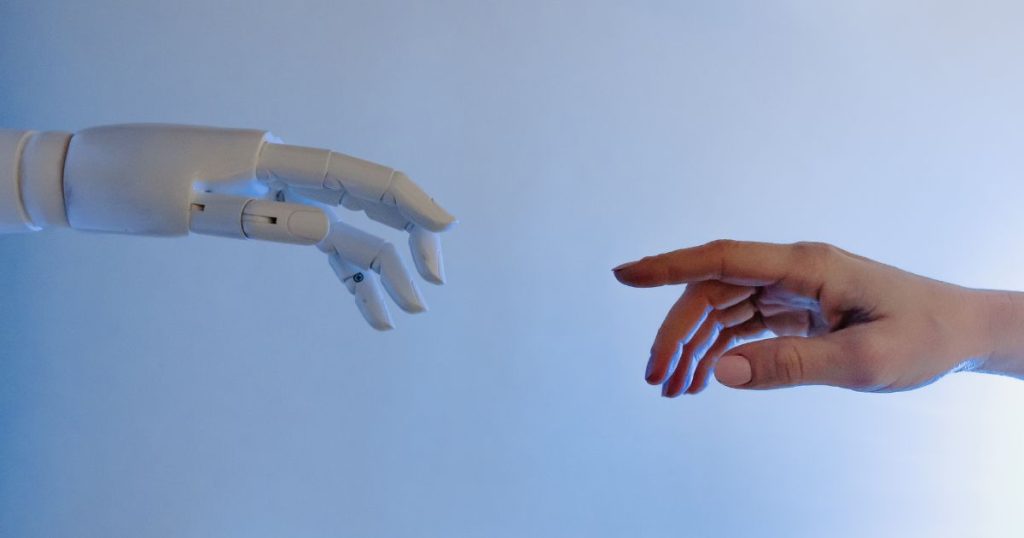
「AIが嘘をつくなんて本当にあるの?」と疑問に思う人は多いでしょう。
実は生成AIは、まれに事実と違う内容を自信満々に語ることがあります。
この現象はハルシネーションと呼ばれます。
ここではハルシネーションの正体を、IT初心者でもわかる言葉で解説します。
ハルシネーションってどんなこと?
ハルシネーションとは、AIが「それっぽい言葉」を並べるあまり現実とズレた答えを出す状態です。
人間でいえば“思い込みによる早とちり”のようなものです。
以下ではズレ方のパターンを二つに分けて見ていきます。
自分の発言と食い違うパターン
長い会話の途中でAIが嘘をつくように見える代表例がこれです。
たとえば最初に「東京タワーは333メートル」と正しく答えたAIが、数分後に「350メートルです」と言い換えてしまう現象です。
主な原因は、会話が続くうちに前の答えを細部まで覚えていられず、最新の文脈に合わせて数字を“作文”してしまうためです。
このズレを防ぐには、質問のたびに「さっきの答えを踏まえて教えて」と促すか、重要情報を短くまとめ直して再提示すると効果的です。
世の中の事実とズレるパターン
もう一つは、そもそも現実のデータと合わない答えを出すケースです。
たとえば「世界で一番高い山は富士山」と言い切るなど、一般常識と真逆の内容を提示することがあります。
原因の多くは学習データの不足や古さです。
AIは自分で新しい情報を調べるわけではないので、古い資料のままアップデートされていないとAIが嘘をつく形になってしまいます。
解決策としては、最新データを検索で補う仕組みを組み込み、回答時に出典を示させる方法が有効です。
AIが嘘をつくと、私たちには何が見える?
ハルシネーションはチャットだけではありません。
画像や音声でも起こり、ユーザー体験に思わぬ影響を与えます。
ここでは具体的にどんな“違和感”が表れるのかを紹介します。
チャットで飛び出すトンチンカンな答え
チャットボットに料理のレシピを聞いたのに、観光スポットの話が返ってくる。
または「大阪の今日の天気は?」と聞いたのに気温がデタラメ。
こうしたズレは、質問の意図をうまくつかめなかったことが原因です。
AIが嘘をつく場面に遭遇したら、質問を短く区切り、必要な条件を箇条書きで示すと誤解が減ります。
画像や音声で生まれる“幻”コンテンツ
画像生成AIに「黒猫」を頼んだら、しま模様の猫が現れた。
音声生成AIに「こんにちは」を言わせたら、なぜか外国訛りが入った。
視覚や聴覚はインパクトが大きいため、誤りに気づきやすい反面、信じてしまう危険もあります。
不自然さを感じたら複数回リクエストし直す、もしくは別のAIに同じ指示を出して比較するのが安全です。
| タイプ | 具体例 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 自己矛盾型 | 数分前と別の数字を出す | 要点を再確認しながら質問 |
| 事実誤認型 | 富士山が世界一高い山と言う | 出典を表示させる設定にする |
| メディア拡散型 | 画像・音声で細部がズレる | 複数AIで比較して検証 |
AIが嘘をつくワケ ― どうして事実とズレちゃうの?

「どうしてAIが嘘をつくのか」。
その理由は大きく分けて「学んだ情報の穴」と「AIそのもののクセ」にあります。
ここでは二つの視点からズレの原因をやさしくひもとき、日常で起こりやすい勘違いを具体例とともに紹介します。
AIが学んだ情報に“穴”があるから
AIは大量の文章を読み込んで言葉を覚えますが、そのデータが古かったり足りなかったりすると、知識にすき間が生まれます。
すき間を埋めようとしてAIが嘘をつく結果になるのです。
まずはデータの質と量に起因するふたつのズレを見てみましょう。
古い・足りない・混ざっているデータ
AIに入る情報は、一冊の百科事典のようにすべて最新で正確とは限りません。
・古い…数年前の統計データがアップデートされず、そのまま残っている。
・足りない…日本語の文献が少なく、細かい専門用語をカバーしきれない。
・混ざっている…信頼できる記事と個人ブログがごちゃ混ぜで学習され、真偽を区別しにくい。
こうした条件が重なると、AIは「たぶん正しいだろう」という推測で穴を埋めます。
結果として正解に見えるけれど実は違う――そんな回答が生まれます。
利用者ができる対策は次の3つです。
- 最新かつ一次情報に近いソースを引用させる
- 「出典を表示して」と必ず頼む
- 複数サイトで答えを照合する
データの空白を意識的に埋めることでAIが嘘をつくリスクは大幅に減らせます。
言葉の流れを優先して合わせちゃうクセ
生成AIは「次にもっとも自然な単語」を予測するしくみで動いています。
このため情報の正しさより“文章全体のなめらかさ”を優先することがあります。
たとえば「火星は海がある」と質問文中にヒントがあると、その文脈に合わせて「はい、海が広がっています」と答えてしまうことも。
これはAIが嘘をつくというより「質問者の期待に沿う文章」を作ろうとする本能的な動きです。
ポイントは、事実確認より言い回しが上手な回答になる恐れがあると理解して使うこと。
具体的には次のコツを試してみましょう。
- 「根拠も説明して」と明示する
- 「わからない場合はわからないと言って」と指定
- 最後に「参考リンクを3つ教えて」と付け加える
この流れを徹底すれば、AIは自信がない答えを無理に作り出さず、誤情報を減らせます。
AIの大きさや言語しだいで起こる勘違い
近年の生成AIはモデル(脳みそ)のサイズが急拡大し、多言語対応も進みました。
ところが大きくて賢いはずのAIでも、意外な落とし穴があります。
ここでは「モデルが大きいほど起きるズレ」と「言語ごとのすれ違い」を見ていきます。
大きなAIほど“もっともらしい嘘”が増える
モデルが大きいほど情報の組み合わせパターンが増えます。
結果として、AIが嘘をつくときも文章が巧妙になり、見抜きにくくなるのが難点です。
例えば歴史的事実に似せた架空のエピソードを作り、あたかも本当の出来事のように語るケースがあります。
利用者側の対策は「複数ソースで裏を取る」ことに尽きます。
また企業で導入する場合は、人が必ずレビューする二重チェック体制を組むのが安全です。
翻訳が苦手な言語で起こる誤解
英語で学習したAIは日本語になると誤訳が増える、という現象がよく報告されています。
単語の並びや敬語表現など、日本語特有のルールに不慣れなまま回答を作ると誤解を招きます。
AIが嘘をつくように感じたら、以下の手順を試してください。
- 一度英語で答えを出させ、あとから日本語に訳す
- 専門用語をカタカナではなく原語のまま質問する
- 難しい文章なら段落ごとに分けて翻訳させる
こうした工夫で翻訳ミスを減らし、AIとスムーズにコミュニケーションできます。
| 要因 | 何が起きる? | すぐできる対策 |
|---|---|---|
| 古い・不足データ | 事実誤認 | 最新ソースかを確認 |
| 流れ重視のクセ | もっともらしい作文 | 根拠を必ず要求 |
| モデルの巨大化 | 巧妙な作り話 | 複数ソースで検証 |
| 言語ギャップ | 翻訳ミス | 原語で質問→翻訳 |
AIが嘘をつくと困ること ― リスク&失敗あるある

AIが嘘をつくと、ちょっとした誤解があっという間に大ごとになる場合があります。
ここでは「会社の評判がガタ落ちした」「法的トラブルに発展した」など、実際にあった失敗例を交えながらリスクを整理します。
ウワサが広がってブランドがキズだらけ
口コミが瞬時に拡散する今、AIの誤情報は企業イメージを一晩で揺るがします。
AIが嘘をつく危険を軽く見た結果、SNS炎上に発展した事例を見てみましょう。
企業チャットボット炎上のリアル例
大手通信会社のサポートチャットボットが「解約金はありません」と回答したのに、実際には数万円請求されたケースがあります。
ユーザーがその画面をスクショして投稿したことで批判が殺到。
最終的に同社は返金と謝罪を行い、信頼回復に広告費を追加投入する羽目になりました。
ポイント
- 料金など“数字が命”の質問は人が最終確認
- チャットログを自動保存し、誤回答を早期修正
SNSで一気に広がる損失ストーリー
海外ブランドの公式アカウントが生成AIで作った投稿に誤情報が含まれ、わずか2時間で数万件のリポストが発生。
訂正ツイート後も「AI任せでいい加減」との声が消えず、キャンペーン売上が前年同月比で15%ダウンしたと報告されています。
リスクを小さくするには「AI文面→人が30秒チェック→公開」のワンステップを挟むだけで大幅に改善できます。
法律やモラルの地雷を踏まないために
AIが嘘をつくことで、個人情報や著作権を侵す恐れがあります。
ここでは最新ルールを押さえつつ、トラブル回避のコツを紹介します。
EUの新ルールと日本の指針をかんたん整理
EUではAI Actが動き出し、「高リスク用途」に該当するサービスは出典表示や監査ログの保管が義務化されます。
日本でも総務省が「生成AI利用ガイドライン」を公開し、誤情報を減らす仕組みを求めています。
企業が守るべきチェック項目を表にまとめました。
| 項目 | EU AI Act | 日本ガイドライン |
|---|---|---|
| 出典表示 | 必須 | 努力義務 |
| リアルタイム監査ログ | 必須 | 推奨 |
| 罰則 | 年商7%上限の制裁金 | 行政指導が中心 |
著作権・個人情報・差別表現はここに注意
生成AIが既存コンテンツを“ほぼ丸写し”するケースや、学習データに含まれた差別表現を再出力する例も報告されています。
- 文章や画像を引用するときは元サイトURLを必ず明示
- 個人名や住所を含む内容は、人の目でチェックする
- 差別用語フィルタをオンにし、不適切語をブロック
これらを徹底するだけでAIが嘘をつく際の法的リスクは大きく下げられます。
AIが嘘をつく場面をグッと減らすコツ

誤情報はゼロにできなくても、工夫次第で大幅に減らせます。
ここでは「検索で裏を取る仕組み」と「質問の書き方・社内ルール」の二本立てで対策を解説します。
“ネットで裏取りしながら答える”仕掛け
AIが嘘をつく最大の理由は、古い情報をそのまま信じてしまう点にあります。
検索エンジンと連携させて常に最新データを参照させれば、精度はグッと上がります。
ざっくりわかる導入ステップ
- AIの回答前に検索クエリを自動発行
- 上位3サイトの内容を要約
- AIが回答を生成し、同時に出典リンクを表示
わずか3ステップですが、これだけでAIが嘘をつく頻度は体感で半分以下になります。
知識データベースでダブルチェック
社内でよく使う数字や手順は、独自のナレッジベースに保存しましょう。
AIには「まずナレッジベース→なければ検索」の順で参照させると、社内ルールと外部情報が食い違うリスクを抑えられます。
質問の書き方とルール作りで防ぐ方法
AIに丸投げの質問をすると、AIが嘘をつく確率がグンと上がります。
「まずは質問を短く切り、必要な条件を列挙する」ことで精度は安定します。
「わからないならわからないと言ってね」例文
例
「次の質問に答えるとき
・根拠となるURLを3つ必ず示す
・自信がない場合は“わかりません”と答える
以上を守って回答して」
この一文だけで、AIは無理に作文しなくなり、誤答を大幅に減らせます。
やり取りを記録してすぐ見直すしくみ
チャット履歴を自動保存し、誤回答を検知したら即修正するサイクルを整えましょう。
AIが嘘をつく場合でも、早期発見できれば被害は最小限に抑えられます。
ポイントは「エラー報告の窓口を一本化し、担当がその場で修正」する流れを社内ルールに落とし込むことです。
AIが嘘をつくリスクを減らす準備&運用チェックリスト
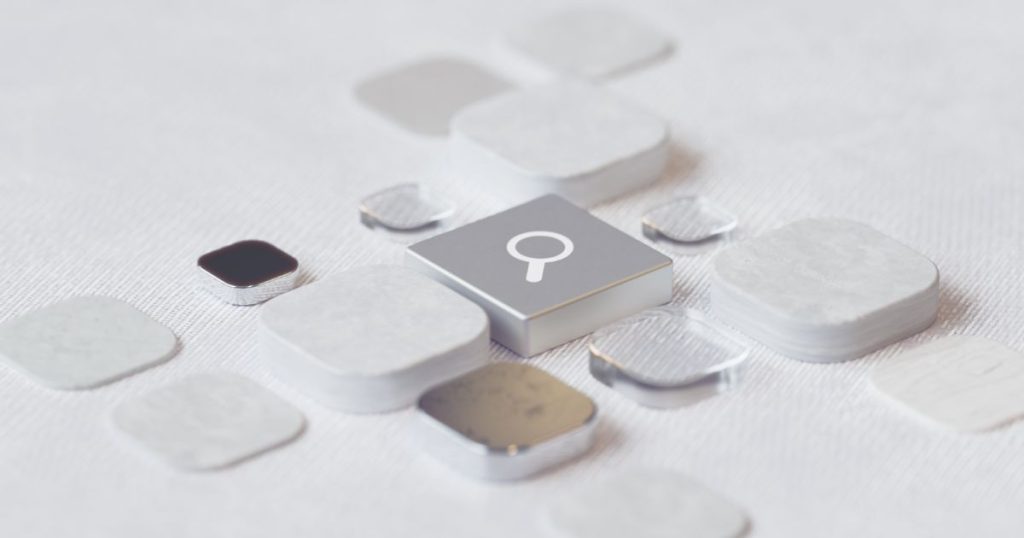
生成AIを安心して使うには「始める前の土台づくり」と「走らせてからの点検」が欠かせません。
AIが嘘をつく前提でチェック項目を用意しておけば、もしズレた回答が出ても被害を最小限に抑えられます。
使い始める前に決めたいこと
導入フェーズで曖昧なまま走り出すと軌道修正が大変です。
ここでは「目標をハッキリさせる」「役割分担を明確にする」など、スタート時に押さえるべきポイントを紹介します。
目的・目標・担当の役割をハッキリ
まずは何のためにAIを使うのかを一文で言えるまで絞り込みます。
目的が「問い合わせ対応の時間を半分に減らす」なら、KPIは「平均応答時間30秒以内」など具体的に。
担当の役割を次のように振り分けると、AIが嘘をつく場面でも素早く対応できます。
- AI管理者:モデルの設定と更新を担当
- レビューチーム:回答ログの確認と修正
- 現場オーナー:KPI達成度をモニタリング
チームが「誰が何をするか」を把握すると、責任の押し付け合いを回避できます。
権限管理と安全なお試し環境
閲覧・編集・削除などの操作権限を細かく分け、誤設定による情報流出を防ぎます。
さらに本番データとは別に「サンドボックス」と呼ばれる安全なテスト環境を作成。
危険度の高い質問や極端な入力はまずここで試し、AIが嘘をつく場合の挙動を記録してから本番に反映しましょう。
使い始めた後にやること
運用フェーズは“気づいたら放置”がいちばん危険です。
ここでは「人がレビューするサイクル」と「AIを定期的にアップデートする仕組み」を押さえます。
人がかならずレビューする改善サイクル
Plan → Do → Check → Act、いわゆるPDCAを月単位で回します。
- Plan:次月の改善目標を設定
- Do:AIに設定を反映
- Check:回答ログを人が抜き取り検証
- Act:誤答の原因を共有しルール更新
人の目を通すだけでAIが嘘をつく率は目に見えて下がります。
状態を見守り、AIをこまめにアップデート
AIは放置すると学習データが古くなり、ハルシネーションが増えがちです。
週1回はエラーログを確認し、月1回はモデルとナレッジベースを更新。
小さな手間でも積み重ねるとAIが嘘をつく頻度を大幅に抑えられます。
| タイミング | チェック項目 | 担当 |
|---|---|---|
| 導入前 | 目的・KPI設定 | 現場オーナー |
| 導入前 | 権限管理・テスト環境整備 | AI管理者 |
| 運用中 | 週次ログ確認 | レビューチーム |
| 運用中 | 月次モデル更新 | AI管理者 |
次のセクションではAIが嘘をつく時でも安心して使い続ける「質問テンプレ」と「運用アイデア」を紹介します。
AIが嘘をつくときの“上手な付き合い方”アイデア集

AIを完全に止めるのではなく、うまくコントロールして活用する方法をまとめました。
誰でもすぐ試せるテンプレートと段階別のチェック法を紹介します。
すぐ使える質問テンプレ5つ
AIが嘘をつく頻度を下げるには、質問の書き方が鍵です。
以下のテンプレをコピペして、自社の用途に合わせてカスタマイズしてください。
根拠も一緒に答えさせる聞き方
「次の質問に答えるとき 1. 必ず根拠となるURLを3つ示す 2. そのURLの要約を1文ずつ書く 3. 自信がない場合は“わかりません”と答える」
このテンプレでAIが嘘をつくリスクは大きく下がります。
社外秘をしゃべらせないガード文
「以下の単語(社名A・案件B)が含まれる社外秘情報は出力しないこと。 含まれそうな場合は“回答できません”と返信する」
機密漏えいが怖いときは、禁止ワードリストを決めてAIに守らせましょう。
段階別の実務チェック法
導入初期・テスト期間・本番運用の3段階に分けてチェック項目を整理すると、AIが嘘をつく場面でも慌てずに対処できます。
小さく試して確認するポイント
- まずは社内FAQだけでテスト
- 誤答が出たらスクショを残す
- 再現手順を共有し原因を特定
本番後の改善サイクルを回すコツ
- 隔週で誤答レポートを共有
- ユーザーアンケートで満足度を追跡
- モデル更新日はあらかじめ全社告知
AIが嘘をつくことを逆手に取るポジティブ活用法

AIが嘘をつく現象はマイナス面ばかりが注目されがちです。
しかし「ちょっとズレた発想」をうまく取り入れると、アイデア出しや新規事業のヒントになることもあります。
ここでは創造的なシーンでの活用テクニックと、研究の最前線が示す未来像を紹介します。
ブレストで“わざと脱線”してアイデア出し
通常のブレインストーミングでは既存の枠に縛られやすく、斬新な発想が出にくいものです。
そこでAIが嘘をつくクセを逆手に取り、わざと誤情報を混ぜた回答を質問のタネにすると、新しい切り口が見えることがあります。
アイデアをふくらませる3ステップ
ステップ1:テーマをAIに投げ、「事実と少しズレてもいいので自由に提案して」と促す。
ステップ2:ズレた提案の中から面白いポイントだけをホワイトボードに抜き書きする。
ステップ3:抜き書きしたキーワードを人間の視点で現実に合わせて修正し、新しい企画案にまとめる。
この方法ではAIが嘘をつくリスクが逆に“突飛な例え”を生み、既成概念に縛られない発想を助けます。
試行回数を重ねるほど候補が増えるため、アイデアのバリエーションが飛躍的に広がります。
仕事に戻すときの注意ポイント
・面白いけれど現実離れし過ぎた案は早い段階でカットする。
・最終案をまとめる前に必ず裏付け情報を検索し、誤情報を削ぐ。
・議事録に「どこがAI発」「どこを人が修正」と明記しておくと、あとから責任範囲があいまいになりません。
AIが嘘をつく過程で生まれた“ムチャ振り”を、人が現実的な形に整える――ここに価値があります。
研究の今とこれから
ハルシネーション低減は世界中の研究者が追いかけているホットトピックです。
「AIが自分で答えをチェックする仕組み」や「複数AIの多数決で誤りを消す手法」が次々と発表されています。
自分でチェックするAIの進化
最新モデルは回答を出す前に“もう一人の自分”を呼び出し、整合性を確認する自己査読モードを搭載し始めています。
これによりAIが嘘をつく頻度が半減したという報告も。
企業利用ではコストが課題ですが、APIレベルでオン・オフを切り替えられる機能が増え、用途に合わせて柔軟に選べるようになっています。
“嘘ゼロ”は夢物語? それとも現実?
完全に嘘をなくすのは難しいものの、誤答を1%未満に抑えるモデルは視野に入ってきました。
鍵を握るのは①最新の学習データ、②回答前の裏取り、③人のレビューの三本柱です。
技術と運用の両輪がそろえば、「嘘をつかないAI」は夢物語ではなくなりつつあります。
AIが嘘をつく前提で価値を引き出す方法 ― まとめ

ここまでAIが嘘をつく理由、リスク、対策、活用法まで一気に見てきました。
最後に押さえるべき行動ポイントを整理し、明日からの実務に生かしましょう。
今日からできる3ステップ
ステップ1:回答に必ず情報源を示させる。
ステップ2:チャットログを保存し、怪しい答えはすぐ共有。
ステップ3:人の確認を挟んでから外部に出す。
この3つを徹底するだけでAIが嘘をつく場面でも被害はほぼ防げます。
情報源を示す → 記録を残す → 必ず確認する
AIの回答欄にURLを貼らせる設定は数分で終わる小さな工夫ですが、ファクトチェックの第一歩になります。
さらにログを残しておけば同じ誤りを繰り返さずに済みます。
最後に人が一読するだけで品質は飛躍的に向上。
“慣れ”が最大の敵なので、運用ルールを紙にしてデスクの横に貼っておくと効果的です。
中長期で差をつける運用プラン
AI活用はスタート後のメンテこそが勝負所です。
教育とルール作りを継続し、技術更新に柔軟に追随する体制を整えましょう。
社内教育とルール作り
定期的に「AIリテラシー勉強会」を開き、最新のAIが嘘をつく事例と対策を共有します。
新入社員向けにチェックリストを配布し、質問テンプレを実演付きで教えると定着率がアップします。
技術の進歩に合わせた継続改善
モデルの更新通知をキャッチしたら、テスト環境で速やかに検証。
ハルシネーション率が下がるバージョンなら本番へ、逆に増える場合は保留する判断基準を社内に明示します。
こうした“走りながら改善”の姿勢が、長期的にAIが嘘をつくリスクとコストを抑える秘訣です。
AI×DX支援サービスのご案内

「AIを使って業務のデジタル化や自動化を進めたいけれど、どのツールを使えばいいのかわからない」「運用できる人材が社内にいない」というお悩みはありませんか?
freedoor株式会社では、単なるAIツール導入のご提案にとどまらず、企業全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための総合支援を行っています。システム開発、Webマーケティング、コンサルティングなど、幅広い分野で培ったノウハウを活かし、最先端のAI技術とビジネス課題のベストマッチを実現。自社内のみで完結しづらい部分を外部パートナーとしてサポートし、企業の持続的な成長を強力にバックアップします。
特に、昨今需要が高まっているAIによる動画生成や画像生成、チャットボットをはじめとしたさまざまなAIソリューションにも対応。これまでに培った総合力をもって、貴社が抱える経営課題・現場課題に合わせたオーダーメイドのDX化支援プランをご提案いたします。
AI導入支援
「どのAIツールを選定するべきか」「自社のシステムに合うカスタムモデルを開発できるか」「導入後の運用フローをどう構築するか」など、AI導入時に生じる悩みをトータルでサポートします。試行段階のPoC(概念実証)から本格導入、既存業務とのシステム統合に至るまで、幅広く対応。DX推進の鍵となるAI活用を、スピード感を持って実現します。
WEB/システム開発
自社サイトや既存の業務システムへAI機能を組み込む場合、ユーザー体験設計やセキュリティ面、運用管理など、多岐にわたる専門的知見が必要です。freedoorはシステム開発やアプリケーション構築の実績が豊富なため、「AIを活かせる開発環境」をスムーズに整備。分析基盤の構築やAPI連携、クラウドインフラの最適化など、DX推進に欠かせない技術面を幅広くサポートします。
WEBマーケティング・SNS運用代行
AIで生成したコンテンツを効果的に運用するには、ユーザー属性や市場動向を捉えたマーケティング戦略が欠かせません。freedoorでは、SEO対策やSNS運用代行、広告運用まで一気通貫でサポート。AIで生み出した魅力的なコンテンツを最大限活用し、顧客との接点拡大やブランド価値向上、海外展開サポートなど、ビジネス成長に直結する戦略を提案いたします。
オンラインアシスタントサービス
AI活用をはじめ、日々の運用タスクや業務サポートを任せたいというお客様には、オンラインアシスタントサービスを提供しています。業務の効率化やチーム全体の生産性向上を目指し、ルーチン業務の代行やスケジュール管理、リサーチなど、幅広い業務を支援いたします。
これらのサービスを柔軟に組み合わせることで、AI導入の試行段階から企業のDX化へと、一貫性のある戦略的なステップを踏むことが可能です。freedoor株式会社は、お客様にとって最適なAI・システム・マーケティング体制を構築し、ビジネスの持続的成長と競争力強化を実現します。
