電話対応が営業成果を左右する!インサイドセールスとコールセンター連携で売上を最大化する方法とは?
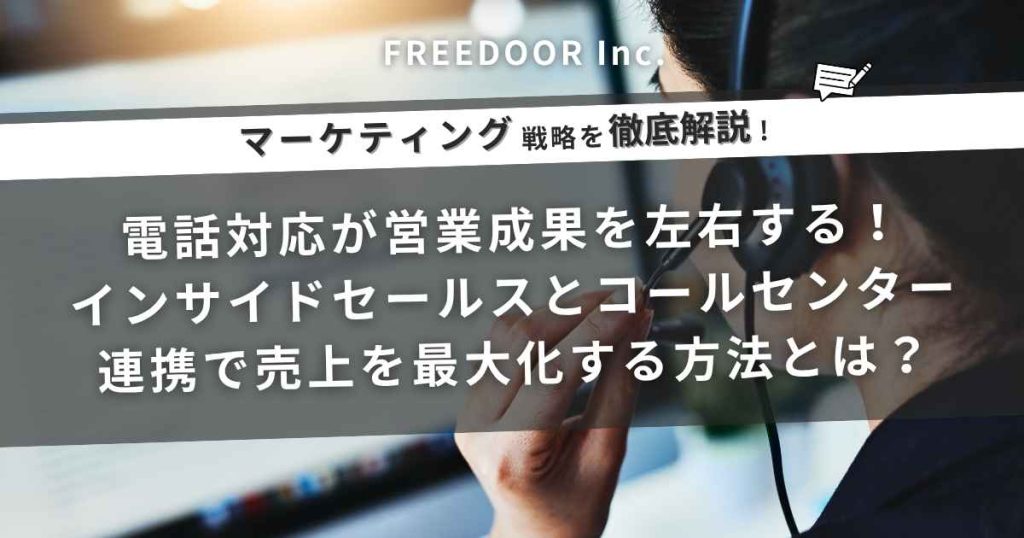
「電話対応が忙しすぎて、本業に集中できない」「せっかくの問い合わせが活かされていない」──そんな悩みを抱えるマーケティングや営業部門は少なくありません。
実は、電話応対は単なる窓口業務ではなく、営業成果を左右する“マーケティングの起点”となる重要なタッチポイントです。
本記事では、コールセンター業務を効率化しながら、インサイドセールスと連携して売上につなげる仕組みの作り方を解説。
さらに、導入事例を交えながら、成果を出す電話対応の最前線を紹介します。
コールセンターでインサイドセールスを始めるべき理由

「問い合わせ対応だけで終わってしまっている」「せっかくの電話を営業に活かせていない」といった声は少なくありません。
ここでは、なぜ今コールセンターにインサイドセールスの考え方が必要なのか、その理由をわかりやすく解説します。
テレアポとのちがい、ちゃんと知っていますか?
まずは混同しやすい「テレアポ」と「インサイドセールス」の違いから整理しておきましょう。
似ているようで、役割も目的も全然違います。
インバウンドとアウトバウンドの違いって?
簡単にいうと、テレアポは企業からお客様へ連絡する“攻め”の営業、インサイドセールスはお客様からの問い合わせを起点にした“受け”の営業です。
| 項目 | テレアポ | インサイドセールス(受電型) |
|---|---|---|
| スタート地点 | 企業側から一方的に電話 | お客様からの問い合わせが起点 |
| 対象 | 見込み客(まだ関係性なし) | 興味を持って問い合わせた顧客 |
| アプローチ方法 | 主に電話でアポ取り | 情報提供や相談対応しながら関係構築 |
このように、インサイドセールスは「売り込み」より「伴走」に近いスタイル。だからこそ、コールセンターとの相性が良いのです。
成果の測り方もこんなに違う
テレアポでは「架電数」「アポ件数」といった“数”で評価されがちですが、インサイドセールスでは以下のような“質”の指標が重視されます。
- 商談化率:実際に商談につながった割合
- フォローアップ数:定期的な接触によって温度感を維持している件数
- リードの成熟度:購入意欲が高まっているかどうか
つまり、ただ数をこなすのではなく、「どれだけ相手の気持ちに寄り添えたか」「次の営業ステップに繋げられたか」が問われるのがインサイドセールスです。
電話窓口がそのまま営業チャンスになる理由
次に、なぜ電話対応そのものが営業に直結するのかを見ていきましょう。ちょっとした会話の中に、実は大きなビジネスチャンスが眠っているんです。
顧客の本音が詰まった“問い合わせ”という資産
「この機能ってどうなってますか?」「価格感だけ知りたいのですが」といった何気ない質問。その裏には、購買意欲の“芽”が隠れています。
そうした問いに丁寧に対応し、相手の背景やニーズを少しでも深掘りできれば、それはもう立派なリード育成の第一歩です。問い合わせは「相談」であり、「意思表示」でもあるのです。
受電から営業につなぐ、シンプルな流れ
受けた電話をそのままにせず、以下のようなステップを踏むことで営業に変換できます。
- 受電で簡単なヒアリング
- 内容をチャットやCRMで即共有
- インサイドセールスが温度感を見極めてフォロー
- 商談につながれば営業チームへバトンタッチ
このように、受電→共有→フォロー→商談という流れが社内で回っていれば、コールセンターがそのまま“営業チームの入口”になります。
インサイドセールスでコールセンターを導入すべき企業とは?

どの企業でもインサイドセールスとコールセンターの連携が効果を発揮するわけではありません。ここでは、特に導入効果が高い企業の特徴について、わかりやすく解説していきます。
こういう商材・こういうビジネスなら相性バツグン
インサイドセールスとコールセンターの連携は、商材の性質や営業スタイルによって向き不向きがあります。まずは、相性が良いパターンから見ていきましょう。
検討期間が長いサービスや高額商材
たとえば、以下のようなビジネスでは、導入検討に時間がかかる傾向があります。
- 法人向けのソフトウェア(SaaS)
- 高額な設備機器
- 医療・人材・不動産などの専門サービス
これらは、お客様がすぐに「買います」とはならないケースが多く、継続的な関係構築と情報提供が欠かせません。電話での相談や問い合わせに素早く、丁寧に対応することで、信頼を獲得しやすくなり、最終的な契約につながる確率も高まります。
パッケージ型・説明が必要ない商品
一方で、決まったプランや料金体系がある商品・サービスもインサイドセールスと相性が良いです。理由はシンプルで、問い合わせ内容に一貫性があり、対応をマニュアル化しやすいからです。
たとえば以下のような商材です:
- クラウド会計ソフトの有料プラン
- 動画配信プラットフォームの法人契約
- 営業代行サービスの月額パッケージ
こうした商品は、問い合わせ時点で顧客のニーズが明確なことが多く、コールセンター側の一次対応だけで、かなり詳細な情報提供や仮説立てが可能です。
リード(見込み顧客)を眠らせていませんか?
せっかく問い合わせが来ているのに、「そのまま放置してしまっている」「後から振り返ることもない」――そんな状況に心当たりはありませんか?
電話を取って満足していませんか?
お客様の問い合わせにその場で答えて、対応完了にしていませんか?
実はそれ、すごくもったいないことなんです。
なぜなら、問い合わせが来たということは「興味・関心がある」という証拠。言い換えれば、営業的に“温度の高いリード”である可能性が高いのです。
だからこそ、問い合わせ対応で終わらせず、次につなげる仕組みが必要です。
一人ひとりの対応任せだと、チャンスを逃します
担当者ごとに対応の仕方が違っていて、情報も属人的になっている――こんな状況ではせっかくのチャンスも逃してしまいます。
特にチームで動いている組織では、対応履歴やお客様の声をチーム全体で共有し、追跡できる体制が欠かせません。そのためにも、インサイドセールスとコールセンターの連携は、情報の一元化と対応品質の安定に大きく役立ちます。
インサイドセールスと連携するコールセンターの作り方

では実際に、営業につながるコールセンターをどうやってつくればよいのでしょうか?ここでは、基本的な仕組み作りから、リード(見込み顧客)の質を高めるための具体的なポイントまで解説します。
最初に整えておきたい基本の仕組み
まず大切なのは、電話を受けた後にどんな対応をするかを決めておくこと。体制づくりの土台となる「ヒアリング項目」や「情報共有の仕方」をしっかり設計することで、属人的な対応から脱却できます。
話す内容とヒアリング項目を決める
オペレーターが受け答えをする際、誰にでも同じクオリティで対応できるようにするには、あらかじめ「聞くべき内容」を明確にしておくことが必要です。たとえば以下のような項目です:
- 問い合わせ内容の分類(料金・機能・導入方法など)
- 担当者の部署・役職
- 導入検討の時期や予算感
- 競合との比較検討状況
こうした項目をスクリプトやチェックリスト化しておくことで、誰が対応してもムラのないヒアリングが可能になります。
情報はその場で営業チームと共有
ヒアリングで得た情報は、リアルタイムで営業チームと共有することが重要です。メールでも可能ですが、今はSlackやChatworkなどのチャットツールと連携できるサービスも多くあります。
たとえば以下のような流れが理想です:
- 電話対応中に顧客情報を入力
- 入力内容がそのままチャットで営業に通知
- 必要に応じてインサイドセールスが即時フォロー
スピード感が求められる現代営業において、「即共有→即アクション」は非常に大きな武器になります。
リードの「温度感」を見極めるコツ
すべての問い合わせがすぐに商談になるわけではありません。だからこそ、今アプローチすべきか、少し時間を置くべきかを見極める「温度感」の判定が重要です。
ホットリードの見つけ方
ホットリード(すぐに商談化する見込みが高い顧客)を見分けるポイントは以下のとおりです:
- 明確な導入時期を聞いてきた
- 具体的な比較対象(他社名)を挙げている
- 「今すぐ話を聞きたい」と急いでいる
こうした反応がある場合は、すぐに営業チームへエスカレーションすべきです。
その後の動きにつなげる担当アサインの流れ
温度感に応じた「担当者の振り分け」も仕組み化しましょう。たとえば以下のようなマトリクスが有効です:
| 温度感 | 対応部門 | 対応内容 |
|---|---|---|
| 高(今すぐ導入希望) | 営業部門 | 商談化・提案資料の送付・オンライン面談 |
| 中(情報収集中) | インサイドセールス | 定期的なメール配信・ホワイトペーパー案内 |
| 低(なんとなく興味あり) | マーケティング部門 | メールマガジン登録・セミナー案内 |
こうした流れをチーム全体で共有しておくことで、「せっかくの問い合わせが埋もれる」という機会損失を防ぐことができます。
インサイドセールスを活かすコールセンターの実践テクニック

インサイドセールスとコールセンターが連携しても、仕組みだけでは成果につながりません。ここでは、実際の電話対応の中で活かせる工夫やテクニックを紹介します。「受けるだけ」から「攻めに転じる」対応へと進化させましょう。
“受け”だけじゃない、かける電話の活用法
多くのコールセンターでは、受信対応(インバウンド)が主な役割になっています。しかし、必要に応じて「こちらから連絡する」アウトバウンドの動きも取り入れることで、より強い営業体制が構築できます。
見込み客へのタイミングを意識した電話アプローチ
問い合わせを受けた後、「そろそろ決断したいタイミングかも」と思ったら、こちらからフォローの電話をするのも有効です。重要なのは“タイミング”です。
次のような状況が狙い目です:
- 過去に資料請求してから1〜2週間経った
- セミナーやイベント後のフォロー期間
- Webページ内での行動データから関心が高まっていると判断できるとき
こうした場面では、「気になることは解決できましたか?」という自然なトーンで連絡することで、相手も構えず会話に入ってくれます。
断られてもムダじゃない、通話内容の蓄積が資産になる
電話営業に対して「断られるからやりたくない」と思う方も多いですが、実は断られること=失敗ではありません。
大切なのは、断られた理由を残しておくこと。たとえば以下のように記録すると、次回のアプローチやマーケ施策にも活かせます。
| 断られた理由 | 今後の活用方法 |
|---|---|
| 予算がない | コストパフォーマンス訴求のコンテンツ制作 |
| 他社と比較中 | 競合比較表や事例資料を送付 |
| まだ導入時期じゃない | 2ヶ月後に再アプローチのスケジュール登録 |
このように、すべての通話が“顧客理解の材料”になります。断られても落ち込まず、情報資産を増やしていく気持ちで対応しましょう。
現場で役立つ電話営業のコツ
ここでは、実際にインサイドセールスが電話をかけるときに意識してほしいコツを紹介します。営業経験がなくてもできる「ちょっとした工夫」が成果を左右します。
初回対応からアポ設定までをひとつの流れにする
「どこで会話を切り上げるか」「どうやって商談に誘導するか」に悩む方も多いでしょう。おすすめは、初めから“アポ取得”をゴールにせず、お客様にとって自然な流れの中でアポイントに誘導することです。
たとえばこんな会話の流れが自然です:
- 課題やお困りごとをヒアリング
- 「実は似たような会社さんで、こういう解決例があります」
- 「よければ、詳しくお話しできる時間を10分ほど取りませんか?」
このように、お客様に「押し売りされている感」を与えないようにするのがポイントです。
架電後にしっかり振り返ることが成果につながる
最後に、意外と軽視されがちなのが「振り返り」です。1件ごとの通話が終わった後に、どんな情報が得られたか、何を次に活かせるかを簡単にメモしておくだけでも、次回の成果が変わります。
以下のようなテンプレートを用意しておくのもおすすめです:
- 話した内容(簡潔に)
- お客様の反応・温度感
- 次回の対応予定・時期
この習慣をチーム全体で共有すれば、情報の蓄積も進み、営業活動全体の精度がどんどん高まります。
コールセンター業務をfreedoorに任せるメリット

ここまで読んで「仕組みはわかったけど、実際に運用するのは大変そう…」と感じた方もいるかもしれません。
そんな時こそ頼れるのが、コールセンター業務の運用代行サービスです。
特にfreedoorなら、インサイドセールスと連携した体制を“最初から整えてくれる”のが大きな魅力です。
fondeskとの連携で、すぐに始められる
freedoorは、電話受付サービス「fondesk」の正規代理店。
fondeskがもつ柔軟で便利な機能を、そのまま利用できます。これにより、システム導入や社内の手間なく、すぐに本格運用がスタートできます。
チャット通知や営業時間設定で柔軟に対応
fondeskを使えば、受電内容はリアルタイムでチャット通知されるため、すぐに社内共有→営業アクションが可能です。
また、営業時間も自由にカスタマイズできるので、
- 平日9時〜18時だけ対応
- 祝日は対応除外
- 曜日ごとに受付時間を調整
といった細かい設定もOK。会社の運用スタイルに合わせて柔軟に対応できます。
自社名で名乗るなど、細やかなカスタマイズも可能
電話を受けるときの名乗り名も、「◯◯株式会社の◯◯でございます」など、御社のスタッフのように対応可能です。
これにより、「電話の外注感」を感じさせず、お客様に自然な印象を与えることができます。
freedoor独自の強みとは?
fondeskの基本機能に加えて、freedoor独自の「人の力」と「運用設計力」で、より営業につながる体制づくりを支援してくれます。
ヒアリングからスクリプト作成まで手厚くサポート
導入時には、freedoorの専任担当者がヒアリングを実施し、
- どういう問い合わせが多いか
- どんなトークが理想か
- 誰にどこまでエスカレーションするか
といった内容を一緒に整理しながら、御社に最適な受電スクリプトや運用マニュアルを作成します。
電話で得た情報をもとに営業代行にもつなげられる
freedoorは、コールセンター業務だけでなく営業代行のサービスも提供しています。
つまり、
- 受けた問い合わせを営業チームに引き継ぐ
- 引き継がれたリードに対して、freedoor側が営業活動を実施
といった連携も可能です。受電で終わらず、売上につながる仕組みが構築できます。
日報・月報による可視化と改善提案
日々の対応内容は、日報や月報のレポート形式で定期提出。これにより、
- どんな問い合わせが多いか
- どのくらい営業に活用できているか
といった内容を“見える化”し、改善の提案まで行ってくれます。
まさに、“頼れるパートナー”という立ち位置で並走してくれる存在です。
コールセンターでインサイドセールスを実現した企業事例

理論や仕組みだけでは「うちでも本当にできるのか?」と不安に思う方もいるかもしれません。
ここでは、実際にコールセンター運用代行を導入し、インサイドセールスと連携して成果を上げた企業の事例をご紹介します。
年間1,000時間の工数削減を実現|人材系企業
ある人材サービス企業では、日々の電話対応が社員の負担となっていました。
1日あたり100件以上の着信があり、本来の業務が後回しになっていたのです。
そこで受電代行を導入し、電話対応を8割以上外部に委託。
対応内容はリアルタイムでチャット共有されるため、必要な情報は逃さずキャッチできる体制を構築できました。
結果として年間1,000時間以上の業務工数を削減。社員が本来の業務に集中できるようになり、生産性が大きく向上しました。
応対の品質が安定し、問い合わせ対応がラクに|IT企業
このITベンチャー企業では、問い合わせ内容が属人的になり、対応品質にばらつきが出ていました。
そのため、よくある質問に対するトークスクリプトやマニュアルを整備し、誰が対応してもブレのない受け答えができる仕組みを導入。
さらに、インサイドセールスチームが対応履歴を見て即時アプローチをかける体制を整えたことで、顧客対応のスピードも向上しました。
少人数体制でも運用できた|医療スタートアップ
少人数で運営する医療系スタートアップでは、電話対応のたびに業務が止まるという課題がありました。
受電代行を導入し、fondeskと連携することで、必要な場合だけ対応するスタイルに切り替え。
これにより、社内のオペレーションがスムーズになり、問い合わせ対応もストレスなくこなせるようになりました。
商談数が2倍に増えた|SaaS企業
このSaaS企業では、せっかくの問い合わせを営業に活かしきれず、商談化率が低いことが課題でした。
受電代行を導入後は、インサイドセールス型の体制に変更し、受電→即共有→フォロー→商談という流れをスムーズに構築。
その結果、問い合わせ対応後にすぐ営業フォローが入るようになり、月間商談数は2倍に増加。成約率の向上にもつながりました。
インサイドセールス型コールセンターを始めるには?まずは無料相談へ

「ここまで読んだけど、うちに合ってるのか分からない」「始めたいけど、何から手をつけたらいい?」という声も多いかと思います。
そんなときは、まずfreedoorの無料相談を活用してみてください。
丁寧なヒアリングで、御社の課題にぴったりの受電体制をご提案します。
こんなお悩み、freedoorなら解決できます
以下のような悩みを持っている企業には、freedoorの導入が非常に効果的です。
「どこから手をつければいいか分からない」
受電対応の課題を感じていても、具体的に何を改善すべきかわからない場合もあります。
freedoorでは、最初の無料相談で業務フローや課題点を一緒に整理し、最適な体制を一緒に考えてくれます。
「チャット連携でチームと情報を共有したい」
SlackやChatworkなど、社内で活用しているチャットツールとスムーズに連携可能。
受電内容をそのままチームに共有することで、業務連携のスピードも格段にアップします。
無料相談の流れと申込み方法
freedoorの無料相談は、面倒な登録もなく、以下の流れで進みます。
- フォームから問い合わせ
→下記ボタンから問い合わせ。 - オンラインで無料相談(30分〜1時間程度)
→ 御社の業務フローや現状の悩みをヒアリング。 - 最適な運用設計をご提案
→ 必要に応じてスクリプトや体制案まで提示してくれます。
契約前提の商談ではないので安心です。
ちょっとした相談や「こんなことってできるの?」というレベルの質問でも、親身に対応してくれます。
まずはお気軽に、freedoorに相談してみてはいかがでしょうか?
