【初心者向け】「検出 – インデックス未登録」とは?原因から解決方法までわかりやすく解説
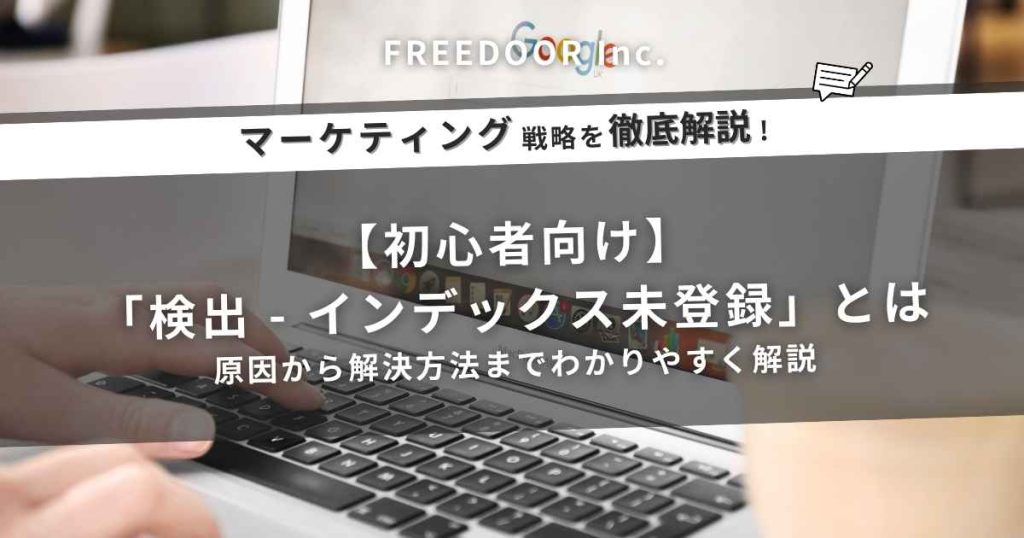
Googleサーチコンソールで「検出 – インデックス未登録」と表示されて戸惑っていませんか?URLは検出されているのに、なぜか検索結果に表示されない──。この状況は多くのWeb担当者やブロガーが直面する問題ですが、適切な原因分析と対処をすれば、インデックスされる可能性は十分にあります。
この記事では、「検出 – インデックス未登録」の意味、よくある原因、改善策、そして大規模サイトでの戦略的な対応方法まで、徹底的に解説します。難しい専門用語は使わず、初心者でも理解できるよう丁寧にまとめました。ぜひ最後まで読み進めて、検索上位を目指すためのヒントをつかんでください。
「検出 – インデックス未登録」とは何か?

Googleサーチコンソールに表示されるステータスの意味
Googleサーチコンソールを見ていて「検出 – インデックス未登録」と出てくると、ちょっとドキッとしますよね。これは、Googleのクローラーがそのページの存在を確認したけれど、まだインデックス(検索結果に載せる処理)していない状態を意味します。
例えば、あなたが新しくブログ記事を公開したとしましょう。そのURLをGoogleが見つけるところまでは完了。でも、Googleはまだ「このページはインデックスするほどじゃないかな…」と判断している段階です。つまり、見つけたけど、登録は保留中というわけです。
この状態がずっと続くと、検索結果にそのページが表示されないままになってしまいます。せっかく書いた記事が誰にも見られないなんて、もったいないですよね。
大事なのは、これはエラーというより“保留中の通知”だということ。焦らず、原因を見つけて丁寧に対応すれば、多くの場合はインデックスされるようになります。
検出されたのに登録されないってどういうこと?
「ページは検出されたのに、なぜ登録(インデックス)されないの?」と感じる方は多いと思います。これは、Googleのロボット(クローラー)がページの存在を認識したものの、検索結果に載せる価値があるかどうかをまだ判断できていない状態と考えるのがわかりやすいです。
たとえるなら、書類審査に通ったけれど、面接にはまだ呼ばれていないようなもの。あなたのページが存在していることはGoogleに伝わっているけれど、「今はまだ様子見しよう」と判断されているわけですね。
ここで重要なのは、“検出=クロール”された、でも“インデックス=登録”されていないという違いをきちんと理解しておくことです。以下に、簡単な比較表でまとめてみました。
| ステータス | 意味 | 検索結果に出る? |
|---|---|---|
| 検出 – インデックス未登録 | Googleがページの存在を認識しているが、登録はしていない | × 出ない |
| クロール済み – インデックス未登録 | Googleがページの中身まで読んだが、登録していない | × 出ない |
| インデックス登録済み | Googleが内容を認めて検索結果に反映している | ○ 出る |
つまり、「検出 – インデックス未登録」は、まだスタート地点に立ったばかりという段階なんですね。このあと、どうアプローチすれば良いかを順を追って解説していきます。
表示されるタイミングとその裏にある検索エンジンの挙動
「検出 – インデックス未登録」というステータスは、ページを公開してから数日〜数週間以内に表示されることが多いです。特にサイトを立ち上げたばかりだったり、新しいページを大量に追加した直後に見かける方が多いのではないでしょうか。
この現象の背景には、Googleの検索エンジンの“クロールとインデックスの仕組み”が関係しています。Googleは、以下のような流れでウェブページを処理します。
- 検出(Discovery):ページのURLが何らかの方法でGoogleに知られる
- クロール(Crawling):ロボットが実際にそのURLにアクセスして内容を確認する
- インデックス(Indexing):中身を分析し、検索結果に載せるべきかを判断
「検出 – インデックス未登録」というのは、ステップ1の“検出”までは済んでいるけれど、まだステップ2や3に進んでいない、もしくは進んでも“保留”とされている状態です。
なぜ保留になるかというと、Googleはクロールやインデックスの「優先順位」をつけて処理しているためです。価値があると判断されたページから先に処理され、それ以外は後回しになることがあります。
特に以下のようなページは、保留されやすい傾向があります:
- コンテンツが薄い・同じような内容が多い
- 更新頻度が低いサイトの新規ページ
- 内部リンクがなく、孤立しているページ
このような仕組みを知っておくと、焦らずに対処できますよね。次章からは、「検出 – インデックス未登録」と似たようなステータスとの違いや、原因、改善方法を具体的に見ていきましょう。
「クロール済み – インデックス未登録」との違い

両者の仕組みの違い
「検出 – インデックス未登録」と「クロール済み – インデックス未登録」、どちらも検索結果にページが出てこない状態ですが、実は内部の処理レベルが異なります。
簡単に言うと、検出だけ=URLを見つけた段階、クロール済み=中身をちゃんと読んだ段階。それぞれのステータスの違いを以下にまとめました。
| ステータス | Googleの処理段階 | 中身を読んでる? | インデックス状況 |
|---|---|---|---|
| 検出 – インデックス未登録 | URLの存在だけ確認 | × 読んでいない | 未登録 |
| クロール済み – インデックス未登録 | ページの内容をクロール済み | ○ 読んでいる | 未登録 |
つまり、「クロール済み」の方が一歩進んだ段階です。ページ内容を見た上で「これは検索結果に載せなくてもいいかな」と判断された可能性が高いんです。
状況別のGoogleの評価プロセス
Googleはすべてのページを即座にインデックスしてくれるわけではありません。実際には以下のように、ページの“重要度”や“品質”などを見て、優先度をつけてインデックスを行います。
- 重要な情報(ニュース記事・話題性のある内容)は優先的にインデックス
- 情報量が少ない、重複しているページは後回しまたは見送り
- アクセスできない、表示が遅いページはスキップされることも
つまり、「クロール済み – インデックス未登録」と出ている場合は、Googleは中身を確認した結果、“現時点では価値が低い”と判断したとも言えるのです。
どちらのステータスがより深刻か?
では「検出 – インデックス未登録」と「クロール済み – インデックス未登録」、どちらがより深刻なのでしょうか?結論から言えば、クロール済みなのにインデックスされない方が、少し厄介です。
なぜなら、Googleは実際にページを見ているのに、あえてインデックスしないという選択をしているからです。つまり、中身に対して“価値がない”と判断された可能性があるということ。
一方、検出だけの状態はまだチャンスがあります。クロールすらされていない状態なので、ページ内容を改善したり、内部リンクを増やすことでインデックスされる見込みがあるからです。
どちらの状態も放置はおすすめできませんが、クロール済み – インデックス未登録は、より迅速な改善が必要です。
「検出 – インデックス未登録」になる主な原因とは?
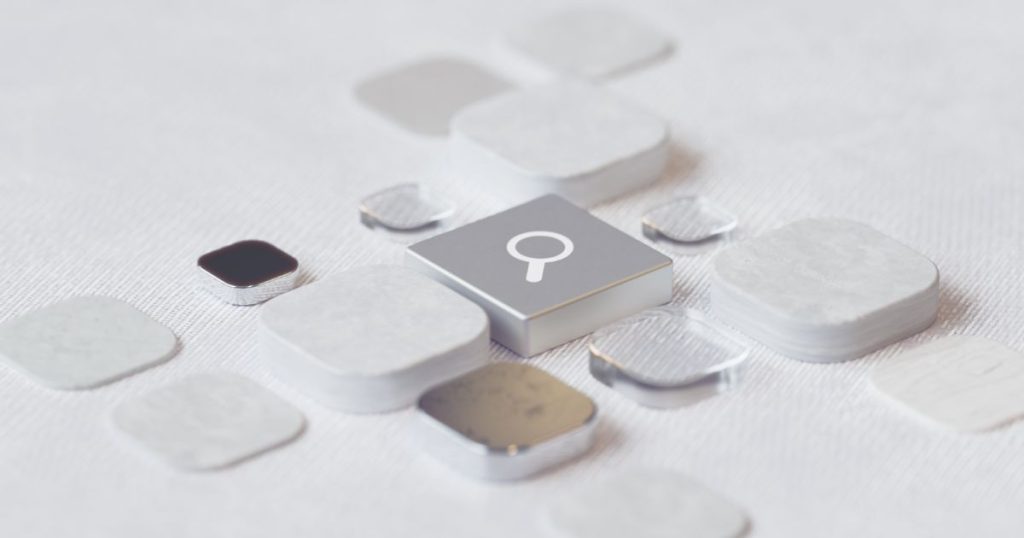
「検出 – インデックス未登録」が表示されると、「一体なにが悪かったの?」と不安になりますよね。でも安心してください。原因はある程度パターン化されており、しっかり見直せば改善できます。
ここでは、よくある原因を4つに分けてご紹介します。それぞれの特徴を知って、自分のサイトの状態と照らし合わせてみましょう。
原因①:コンテンツの品質が低い・類似している
コピーコンテンツ・AI生成コンテンツの扱い
Googleは今、オリジナリティとユーザーの役に立つ情報をとても重視しています。そのため、以下のようなページはインデックスを見送られる傾向があります。
- 他サイトとほぼ同じ内容(コピペ)
- AIツールで自動生成しただけの文章
- テンプレートの流用が多く、どれも似たような構成
AIツールを使うこと自体は問題ではありませんが、人間の視点で再編集したり、独自の体験や具体例を加える工夫が必要です。Googleは「誰が書いたか」「その人の経験や専門性はあるか」を重視しています。
EEAT(専門性・権威性・信頼性・経験)の欠如
EEATとは、Googleが高品質コンテンツと判断するための基準です。以下のポイントに注意して、サイト全体の質を高めていきましょう。
- 専門性:テーマについて詳しい内容が書かれているか
- 権威性:その情報源として信用される立場か(例:実名・実績)
- 信頼性:正しい情報をもとにしているか
- 経験:実体験に基づいた発信か
たとえば、「SEOのやり方」を紹介する記事なら、実際に順位改善した経験談があるとEEATの評価が高まります。Googleは“誰がそれを言っているか”をしっかり見ています。
原因②:サーバーやサイト構造に問題がある
サーバーエラー・過負荷・応答遅延
Googleのクローラーがページにアクセスした際にエラーや遅延が発生すると、「このページは今はスキップしておこう」と判断されやすくなります。
具体的な例:
- 500エラー(サーバー内部エラー)
- 503エラー(サービス利用不可)
- 表示に数秒以上かかる
特に共用サーバーを利用しているサイトや、アクセス集中があるときには注意が必要です。表示速度はユーザー体験だけでなく、インデックスにも影響することを覚えておきましょう。
クローラビリティを妨げる構造
Googleのクローラーは、サイト内のリンクをたどってページを見つけていきます。つまり、内部リンクがないページや、リンクがJavaScriptなどで隠れていると、クロールがうまく進まないことがあります。
よくあるNG例:
- ナビゲーションからたどれない孤立ページ
- クローラーが読み取れないJSベースのリンク構造
- サイトマップにURLが載っていない
クローラーが迷子にならないように、シンプルでわかりやすいサイト構造を意識しましょう。
原因③:Googleにとって重要なページと判断されていない
クローラーに「優先度が低い」と見なされる理由
Googleは“クロールバジェット”というリソースを使ってページを巡回しています。これは「一つのサイトにつき、クロールできる量や頻度には限りがある」ということです。
そのため、以下のようなページは後回し、またはスルーされやすくなります。
- 内容が薄く、他ページと差別化できていない
- 似たようなURLパターンが大量にある
- 外部リンクや内部リンクがほとんど貼られていない
Googleに「このページは大事」と思わせる工夫が必要です。リンクの強化や、検索ニーズに応える質の高いコンテンツを用意することが大切です。
原因④:クロール待ち状態(大規模サイトによくある問題)
ページ数が数百〜数千あるようなサイトでは、「とりあえず検出したけど、あとでじっくり見に行くね」というクロール待ちの状態になることが珍しくありません。
特に以下のようなケースは注意が必要です。
- 商品ページやブログ記事を一気に大量追加した
- 新サイトを公開したばかり
- 同じようなテンプレページが続いている
このような場合は、内部リンクの調整やサイトマップの送信、Search Consoleからのインデックスリクエストなどで、クロールの優先度を上げる対策が有効です。
原因を特定するためのチェックポイント

「検出 – インデックス未登録」と表示されたら、まずは落ち着いて状況を分析しましょう。Googleがなぜそのページをインデックスしなかったのか、ヒントは必ずどこかにあります。
ここでは、具体的に確認すべき3つのポイントをご紹介します。これをチェックするだけでも、原因がかなり絞り込めるはずです。
Googleサーチコンソールで確認すべき箇所
最初に確認すべきは、やはりGoogleサーチコンソールです。以下の情報をしっかり見てみましょう。
- URL検査ツール:対象のURLがGoogleにどう認識されているか確認できます。
- インデックスカバレッジ:サイト全体のステータスをチェック。検出・未登録の傾向がわかります。
- サイトマップ:ちゃんとGoogleに送信されているかどうか。
特にURL検査ツールでは、次のような情報を重点的に見てください。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| クロール済みかどうか | クロールされていない場合は、robots.txtやURL構造に問題がある可能性 |
| ページがインデックスに登録されているか | 未登録なら、その理由を記載したメッセージがあることも |
| ページの取得状態 | エラーやリダイレクトが起きていないか |
robots.txtやnoindexの設定ミスを見直す
よくあるミスの一つが、「自分では気づかないうちにインデックスを拒否する設定になっている」パターンです。以下の2つを必ずチェックしましょう。
- robots.txt:
Disallow: /や特定のディレクトリがブロックされていないか - <meta name=\”robots\” content=\”noindex\”>が設定されていないか
サイト制作時やリニューアル中に一時的に設定したまま、うっかり本番公開してしまっているケースも多いです。公開前・公開後に必ずチェックするクセをつけましょう。
クロール統計とログの活用方法
Googleがあなたのサイトをどれだけ巡回しているかは、クロールの統計データを見ることでわかります。以下のような視点で確認しましょう。
- 過去90日間のクロールリクエスト数
- クロール応答速度
- クロール済みのページ数とステータス
これらは、サーチコンソールの「設定 → クロール統計」から確認できます。クロール数が極端に少ない場合は、そもそもGoogleに注目されていない可能性が高いため、内部リンクやサイト構造を見直す必要があります。
より詳細な分析がしたい場合は、サーバーログを確認し、Googlebotがいつ・どのページにアクセスしているかを把握するのも効果的です。
「検出 – インデックス未登録」を改善する具体的な方法

「検出 – インデックス未登録」と表示されているページも、適切に対処すればGoogleにしっかり登録(インデックス)されるようになります。ここでは、具体的で今すぐ実践できる改善方法を4つご紹介します。
URL検査ツールで再インデックスリクエスト
まず最初に試すべきは、Googleサーチコンソールの「URL検査ツール」です。インデックスされていないURLを入力して、「インデックス登録をリクエスト」ボタンを押すことで、Googleに再クロールをお願いできます。
この操作を行うと、通常よりも早くクロールしてもらえる可能性が高まります。ただし、何度も繰り返すと逆効果になることがあるので、1ページにつき1〜2回にとどめましょう。
また、複数ページを一括で対応したい場合は、XMLサイトマップを更新して再送信するのも有効です。
ページ品質の向上(コンテンツ追加・構造化データ)
Googleがインデックスするかどうかを判断する最大の基準は、そのページが「役に立つかどうか」です。次のような対策で、コンテンツの質を高めましょう。
- 読者の疑問に答える内容を追加(Q&A形式やFAQ)
- 画像や図表を使って視覚的にわかりやすくする
- 構造化データ(Schema.org)を使って、ページの意味を明示する
- 関連ページへの内部リンクを増やす
また、ユーザーの滞在時間や直帰率も間接的にインデックスの判断材料になります。読者が「読んでよかった」と思えるページ作りを心がけましょう。
サーバーリソースの最適化・改善
Googleのクローラーは、サーバーの反応が遅かったり、エラーが多かったりするとクロールを後回しにすることがあります。次のような点を見直してみましょう。
- サーバーの応答速度(表示スピード)
- 500番台エラー(内部エラー・サービス不可など)の有無
- CDNの導入による負荷分散
- 不要なプラグインやスクリプトの整理
特に共用サーバーを使っている場合は、アクセスの多い時間帯に負荷がかかってGooglebotが弾かれることもあります。安定した環境=インデックスされやすい環境といえるでしょう。
robots.txtやメタタグの設定を確認
基本中の基本ですが、インデックスをブロックする設定が無意識に入っていないかもチェックしておきましょう。
よくあるチェックポイント:
robots.txtで対象のURLがDisallowされていないか- HTMLに
<meta name=\"robots\" content=\"noindex\">が入っていないか - canonicalタグの設定が正しく、他ページに転送されていないか
特に開発段階で設定していた「noindex」や「Disallow」を消し忘れるミスは多く見られます。本番公開のときはインデックスを許可する設定になっているか、必ずチェックしてください。
大規模サイトでの「検出 – インデックス未登録」への戦略的対応

ページ数が多い大規模サイトでは、Googleにすべてのページをインデックスしてもらうのは簡単ではありません。Googleにはクロールバジェット(巡回できる上限)があるため、すべてのページが均等に扱われるわけではないのです。
ここでは、効率的に“登録されるべきページ”をインデックスさせるための戦略的な対応策を紹介します。
インデックス不要なページの除外設計
noindexとcanonicalの使い分け
大規模サイトでは、すべてのページをインデックスさせる必要はありません。むしろ、重複コンテンツや薄いページは、最初から除外するほうが健全です。
そのために活用したいのが、「noindex」と「canonical」の設定です。
- noindex:検索結果に出さなくていいページ(例:絞り込みURL、プライバシーポリシー)
- canonical:似たようなページがある場合、正規URLをGoogleに伝える設定
どちらを使うべきか迷った場合は、重複ページを整理する意図があればcanonical、それ以外はnoindexという使い分けが基本です。
XMLサイトマップに優先URLのみ記載する
XMLサイトマップは、Googleに「このページを優先的に見てほしい」と伝えるリストのようなものです。全ページを載せるのではなく、特にインデックスしてほしいページだけを記載するのがベストです。
こうすることで、クロールバジェットを効率よく使え、重要ページのインデックス確率が上がります。
内部リンク構造を最適化し、クローラビリティを強化する
Googleは、ページ同士のつながりを「内部リンク」で判断します。孤立したページにはたどり着きにくいため、重要なページにはできるだけ内部リンクを集めるように設計しましょう。
具体的な対策例:
- カテゴリーページから新着・人気記事へのリンクを設置
- パンくずリストで階層構造を明確に
- 関連記事の自動表示ウィジェットを使う
トップページや上位カテゴリからリンクされているページほど、Googleにとって「重要」と判断されやすいので、重要ページへの導線は明確にしましょう。
定期的なクロールバジェットの分析と最適化
最後に、大規模サイトを運営している場合は、自分のサイトがどのくらいクロールされているかを定期的に確認することも重要です。
分析すべき項目:
- クロールされたページ数と失敗数
- Googlebotがよくアクセスしているディレクトリ
- クロールの頻度・タイミング
Googleサーチコンソールの「クロール統計」や、サーバーログ分析ツールを使うことで、どこにバジェットが集中しているか、無駄があるかが見えてきます。
その結果をもとに、不要ページを除外したり、重要ページを再設計するといった施策につなげましょう。
よくある質問と誤解を正すQ&A
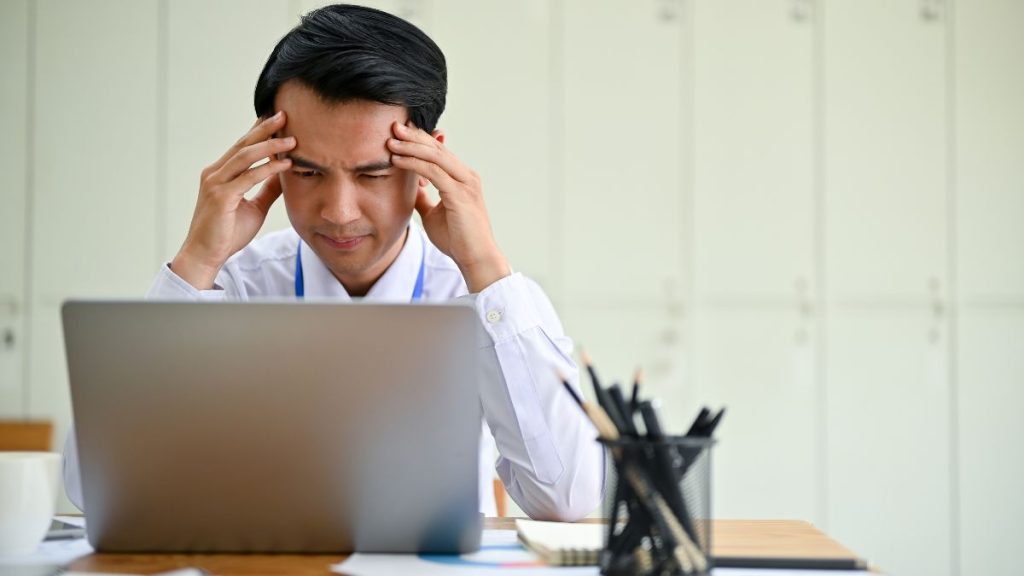
「検出 – インデックス未登録」について調べていると、ネット上にはさまざまな情報があります。ただ、古い情報や誤解を招きやすい説明も多いため、ここで正しい知識をQ&A形式で整理しておきましょう。
Q. XMLサイトマップを送れば解決しますか?
A. 必ずしも解決するとは限りません。
確かにXMLサイトマップをGoogleに送ることで、ページの存在を伝えることはできます。しかし、あくまで「存在を知らせる手段」であって、インデックス登録を保証するものではありません。
大事なのは、そのページのコンテンツが価値あるものかどうか。質の高いコンテンツであれば、サイトマップをきっかけにクロール・インデックスされやすくなります。
Q. robots.txt でブロックされてると表示されますか?
A. 表示される可能性はあります。
Googleがrobots.txtでブロックされているページのURLを何らかの経路(リンク・サイトマップなど)で検出した場合、「検出 – インデックス未登録」と表示されることがあります。
ただし、その場合はサーチコンソールの詳細に「robots.txt によりブロック」などの注釈が記載されていることが多いです。まずはURL検査ツールでクロール可能か確認してみましょう。
Q. 数百件あっても問題ないの?
A. サイトの規模や構造によって変わります。
大規模なECサイトやメディアなどでは、数百〜数千件の「検出 – インデックス未登録」が発生することは珍しくありません。問題なのは、それらの中にインデックスされるべき重要なページが含まれているかどうかです。
たとえば、商品の詳細ページや問い合わせフォームなど、検索流入が欲しいページが未登録であれば改善すべきです。一方で、一覧絞り込みページなど、インデックスの必要がないページであれば、noindexの活用を検討しましょう。
Q. AIコンテンツはインデックスされにくい?
A. 質によります。自動生成だけではインデックスされにくい傾向があります。
AIを使ったコンテンツがすべて悪いわけではありません。ただ、情報が曖昧だったり、誰が書いたのか不明な記事はGoogleに評価されにくく、インデックスが保留されることもあります。
AIを使う場合は、人間が最終チェックし、オリジナリティと正確性を高めることが大切です。経験や具体例、信頼できる出典を加えると、インデックスされやすくなります。
Q. noindexからindexに戻すとどうなる?
A. 戻しても、すぐにインデックスされるとは限りません。
過去にnoindexを設定していたページを、あとから解除しても、Googleが再度クロールしてインデックス判断を行うまでには時間がかかります。
URL検査ツールからインデックス登録のリクエストを送ったり、内部リンクやサイトマップに再度追加して、Googleに「このページが重要ですよ」とアピールすることが必要です。
まとめ:適切な対策で「検出 – インデックス未登録」は防げる

「検出 – インデックス未登録」は、一見すると不安になる通知ですが、正しい知識と対策をとれば決して怖いものではありません。
この状態は、Googleが「ページの存在は知っているけれど、今はまだ登録しないよ」と判断している状況です。その背景には、コンテンツの品質やサイトの構造、サーバーの応答など、さまざまな要因があります。
この記事のポイントをまとめると、以下のようになります。
- 「検出 – インデックス未登録」は、クロールも未実施の「保留状態」
- 「クロール済み – インデックス未登録」は、より深刻な“内容評価後の不登録”
- 主な原因は、コンテンツの質・内部リンクの弱さ・技術的ミス
- Googleサーチコンソールとrobots.txt設定の確認は必須
- インデックスされるには「価値のあるページ」とGoogleに伝える工夫が必要
特に大規模サイトやAI生成コンテンツが増えている現在では、ページの取捨選択やクロールバジェットの意識がますます重要になっています。
あなたのページが「Googleから見て登録すべき」と判断されるように、読者目線での価値提供を忘れずに意識していきましょう。
これで「検出 – インデックス未登録」への不安が少しでも解消されたなら幸いです。地道な改善を重ねて、検索結果にしっかり表示されるコンテンツを作っていきましょう。
LLMO・AIO時代に対応したSEO戦略ならfreedoorへ

AI検索の普及により、従来のSEO対策だけでは成果につながらないケースが増えています。
freedoor株式会社では、SEOの枠を超えたLLMO・AIOにも対応した次世代型コンサルティングを展開しています。
freedoorが提供する「LLMO・AIOに強いSEOコンサルティング」とは?
以下のようなAI時代に適した施策を、SEO戦略に組み込むことで検索とAIの両方からの流入最大化を図ります。
- エンティティ設計によって、AIに正確な意味を伝えるコンテンツ構成
- 構造化データやHTMLマークアップでAIフレンドリーな設計
- 引用されやすい文体やソース明記によるAIからの信頼獲得
- GA4と連携したAI流入の可視化・分析
- LLMs.txtの導入と活用支援
これらの施策により、AIに選ばれ、引用され、信頼されるサイトづくりが可能になります。
SEOとAI最適化を両立させるfreedoorの強み
freedoorでは、以下のような強みを活かして、LLMO・AIOに対応したSEO戦略を提案しています。
| 支援内容 | 具体施策 |
|---|---|
| キーワード設計 | AIが拾いやすい構造・文体への最適化を含めて提案 |
| コンテンツ改善 | ファクト重視、引用構成、E-E-A-T強化の文章設計 |
| 効果測定 | GA4によるAI流入・引用トラッキングサポート |
| 技術支援 | 構造化データ・LLMs.txt・パフォーマンス最適化支援 |
SEOとAI最適化を融合したい方は、freedoorのサービスをご活用ください。
