【徹底解説】Webアクセシビリティとバリアフリーの違いとは?
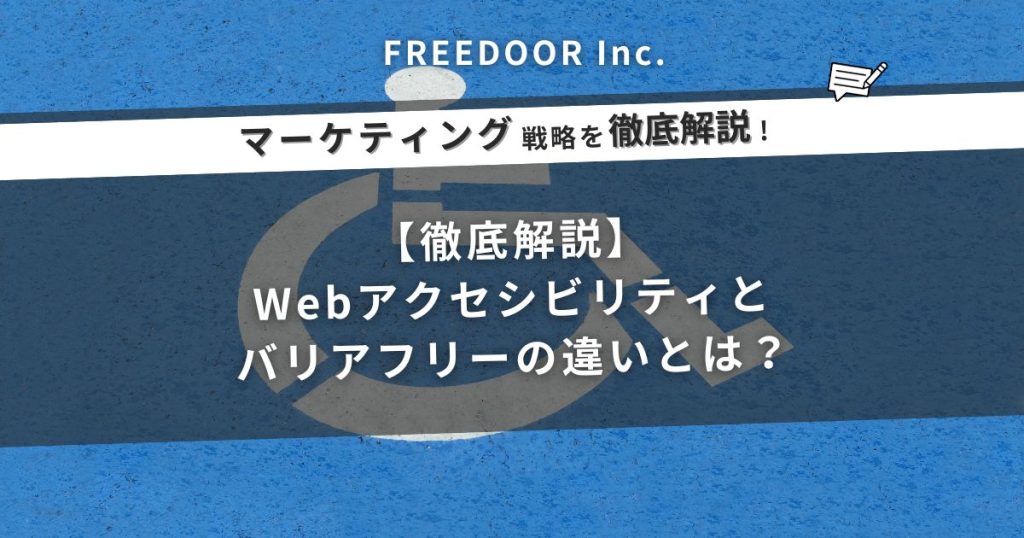
近年、多様なユーザーの利便性を考慮する取り組みとして、「バリアフリー」や「Webアクセシビリティ」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
バリアフリーと言えば、段差のない建物や手すりの設置など、物理的な障壁を取り除くイメージが強いでしょう。一方のwebアクセシビリティは、デジタル空間において誰もが情報をスムーズに得られる状態を指します。
しかし、両者が具体的にどのように違うのか、または共通する理念とは何かを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。
本記事では、「Webアクセシビリティとバリアフリーの違い」というテーマを軸に、バリアフリーの定義や取り組み事例、webアクセシビリティが目指す世界観、そして両者を組み合わせることで得られるメリットを徹底解説します。
最後まで読むことで「バリアフリーとアクセシビリティの違いは?」「物理的な障壁だけじゃないの?」といった疑問が解消され、多角的な視点を得られるはずです。
1. 「バリアフリー」と「Webアクセシビリティ」は何が違うのか?

「バリアフリー」と「webアクセシビリティ」は、いずれも人々が快適に利用できる環境づくりを目指す概念でありながら、着目する領域が異なるために混同されがちです。
まずは、両者が扱う課題領域と背景となる考え方の違いを整理してみましょう。
1-1. バリアフリーは「物理的障壁の除去」から発展した概念
バリアフリーと聞くと、真っ先に思い浮かぶのは車椅子の方や高齢者でも利用しやすい施設でしょう。たとえば建物内の段差を無くす、エレベーターやスロープを設置するといった施策が代表的です。もともとは物理的な障壁(バリア)を無くす取り組みが中心となり、福祉や建築設計の分野で発展してきました。
近年は身体障害だけでなく、視覚障害者や聴覚障害者への配慮、さらには言語的なバリアや制度面でのバリアを排除することなど、心理的・制度的なバリアフリーにも広がりを見せています。ただし、社会一般でのイメージは依然として物理空間での障壁を取り除く施策として認識されやすいのが現状です。
1-2. Webアクセシビリティは「デジタル空間での利用しやすさ」を追求
一方、Webアクセシビリティはオンラインやアプリケーションといったデジタル空間で、障がいの有無やユーザーの環境を問わずに情報にアクセスできる状態を目指す取り組みです。
たとえば、スクリーンリーダー(音声読み上げソフト)に対応したテキスト構造やコントラスト比の確保、キーボード操作だけでもフォーム送信が可能な設計などが該当します。視覚障がいのある方だけでなく、高齢者や色覚特性のある方、さらには通信環境が不安定な地域に住む人々も快適に利用できるデザインを追求するのがwebアクセシビリティの本質といえるでしょう。
1-3. 共通点は「誰もが使いやすい環境を作る」という理念
バリアフリーとwebアクセシビリティは、物理空間とデジタル空間という違いこそあれど、根本にあるのは「障壁をなくし、多様な人に優しい環境を整える」という考え方です。
オフラインの施設におけるバリアフリーと、オンラインの世界におけるwebアクセシビリティを組み合わせれば、リアルとデジタルの両面でインクルーシブな社会を実現できる可能性が高まります。
ただし、実際の取り組み方法や必要とされる技術、ガイドラインは大きく異なるため、それぞれの特性を正しく理解することが重要となります。
2. バリアフリーの定義と具体的事例:物理的障壁を取り除く取り組み

それではまず、「バリアフリー」という言葉がどのように生まれ、具体的にはどんな取り組みを指すのかを見ていきましょう。これを知ることで、「webアクセシビリティ」との相違点や接点がより明確になります。
2-1. バリアフリーの原点は物理空間での障害除去
バリアフリー(Barrier-free)という言葉は、英語の「Barrier(障壁)」と「Free(自由)」を組み合わせたもので、障壁を取り除いて自由に行動できる状態を意味します。
元々は高齢者や身体障がい者の方が外出や移動をしやすいように、公共交通機関や建物の段差を無くすなど、主に建築・設備の分野で発展しました。
具体的には、以下のような事例が挙げられます。
- 駅のホームと車両間の段差解消、エレベーターの設置
- 店舗や施設の入口にスロープを設置し、車椅子利用者でも入りやすく
- 手すりや点字ブロックの整備で安全性を確保
- ユニバーサルデザインのトイレ(広めのスペース、手すり、オストメイト対応など)
これらの施策を総称して「バリアフリー化」と呼び、公共空間だけでなく、個人の住宅にも広まり始めています。
さらに最近では、高齢者や障がい者の方だけでなく、ベビーカーを押す保護者やけが人、子どもなど、一時的に移動が困難な人にとっても便利な環境づくりとして、幅広い支持を得ています。
2-2. 制度的・心理的バリアフリーへの拡張
バリアフリーの概念は当初「物理的障壁の解消」が中心でしたが、近年は「制度的」「心理的」なバリアを取り除こうとする動きも注目を集めています。
たとえば公共サービスの手続きで障害者が差別や不都合を被らないように配慮する、職場での合理的配慮を徹底して障害者の雇用を促進するといった取り組みです。
こうした拡張により、バリアフリーはより包括的な概念へと変化していますが、一般的なイメージとしては物理空間のバリアを取り除くニュアンスが色濃く残っています。
3. Webアクセシビリティとは?デジタル空間におけるインクルーシブ設計

次に、「webアクセシビリティ」の概念を深掘りしていきます。バリアフリーが物理空間を対象とするのに対し、webアクセシビリティはデジタルコンテンツやオンラインサービスにおける「障壁除去」を目指すのが特徴です。
3-1. Webアクセシビリティの定義
webアクセシビリティ(Web Accessibility)とは、障がいの有無や利用環境を問わず、誰でもWebサイトやアプリを利用できる状態を指します。
たとえば視覚障がい者はスクリーンリーダーを使ってサイト内容を読み上げる、色覚特性のある方が配色で混乱しないようコントラストを高める、高齢者が文字サイズを拡大しやすいUIを用意するといった具体的施策が該当します。
「バリアフリー」と共通するのは「誰にとっても使いやすくする」という思想ですが、対象となる空間がオンラインであり、そのために必要な技術的・デザイン的配慮が独自の領域として確立されている点が大きな違いです。
3-2. 代表的なガイドライン(WCAG/JIS X 8341-3)
webアクセシビリティの世界には、国際的に広く参照されるガイドラインとしてWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)があります。国内では、WCAGをもとに作られたJIS X 8341-3がウェブアクセシビリティの基準として定着しています。
主に、
- テキスト代替の提供(画像や動画にalt属性、字幕など)
- コントラスト比の確保
- キーボード操作のみでサイト機能が利用可能
- フォーム入力エラーのわかりやすい表示
- 動きの速いコンテンツ、点滅のある要素への配慮
など、多岐にわたるチェックポイントが存在します。
これらを正しくクリアすることで、高齢者、障がい者、さらにはスマホ回線が不安定なユーザーなど、あらゆる利用者が平等にWebコンテンツを楽しめる状態が実現するのです。
3-3. 「ユニバーサルデザイン」との違い
webアクセシビリティと混同されやすいのが「ユニバーサルデザイン」です。
ユニバーサルデザイン(UD)は、最初から可能な限り多様なユーザーに合わせて設計する思想を指します。たとえば商品のパッケージや公共施設、家電製品などで使われるアプローチで、「誰もが直感的に使える、分かりやすいデザイン」を目指します。
一方、アクセシビリティは障害や環境による利用制限をなくすことを主眼としており、ユニバーサルデザインの一部として位置付けられることも多いです。ただし、webアクセシビリティはより具体的・技術的なガイドラインに基づいている点が特徴的と言えます。
4. バリアフリーとWebアクセシビリティを具体事例で比較・共通点を探る

ここまでの説明を踏まえ、実際の事例でバリアフリーとwebアクセシビリティを対比させてみましょう。対象とする空間が「物理」か「デジタル」かの違いはあれど、両者が果たす役割には意外な共通点や相乗効果が見えてきます。
4-1. 駅や店舗の段差解消 × オンラインサービスのアクセシビリティ
たとえば、駅のホームと車両の段差をなくす、建物にスロープを設置するといった施策は典型的なバリアフリーです。車椅子やベビーカーを利用している人でも移動しやすくなり、転倒リスクを減らせます。
一方、鉄道会社や商業施設の公式ウェブサイトも、視覚障がい者でもスクリーンリーダーを使って経路検索や時刻表を確認できるよう、アクセシビリティを確保している例があります。
現実世界とデジタル空間の両方で「段差(障壁)」を取り除くことで、オンラインとオフラインのシームレスな利便性を提供できるのです。
4-2. 施設予約のしやすさ:店舗の段差解消 vs Web予約フォームのアクセシビリティ
レストランやホテルなどでは、車椅子利用者でも利用しやすいように入り口の段差をなくし、テーブルや客室の動線を広めにとるなどのバリアフリー対応が行われています。
これに加えて、Webでの予約フォームがキーボード操作だけで使いやすかったり、文字サイズを自由に拡大できたりすれば、高齢者や視力が弱い方でもネット予約をスムーズに行えます。
こうしてリアルとデジタル両面のバリアを取り除くことで、「施設を利用する前から、利用後のアンケートに至るまでストレスなく体験できる」という総合的なユーザー満足度を高めることが可能です。
4-3. 共通する理念:誰にも優しい環境づくり
バリアフリーとwebアクセシビリティは、課題解決の対象空間が異なるとはいえ、根底にある思想はほぼ共通しています。それは、「多様な人が安心して利用できる環境を作ろう」というインクルーシブな考え方です。
バリアフリー施策が物理的な障壁をなくすことで車椅子利用者や高齢者を支えるように、webアクセシビリティもデジタル空間での障壁(コントラスト不足、スクリーンリーダー未対応など)をなくすことで、多くのユーザーに情報アクセスの機会を提供します。
したがって、どちらか一方の取り組みだけを行うのではなく、リアルとデジタル両方でバリアをなくすことが、より充実したインクルーシブ社会の実現につながるといえるでしょう。
5. Webアクセシビリティがもたらすメリット:CSR・SEO・ユーザー拡大

バリアフリーは公共施設や建築の分野で不可欠な施策として認識されていますが、webアクセシビリティに関しては「デジタル対応はコストがかかるのでは?」と思われることも少なくありません。
実際には、webアクセシビリティへの取り組みは多大なメリットをもたらします。ここでは、その代表的なポイントを解説します。
5-1. コストではなく投資:ユーザー満足度とCVRアップ
webアクセシビリティの改善は、障がいの有無に関わらずすべてのユーザーにとって使いやすいサイトを作ることにつながります。
文字サイズや色のコントラストが見やすくなる、フォーム入力が簡単になるなど、ユーザビリティが高まれば離脱率が下がり、問い合わせや購入に至る確率が向上する可能性があります。
例えば「高齢者向けECサイトでフォームを改善し、問い合わせ数が大幅にアップした」という事例も多々報告されており、webアクセシビリティはビジネス効果にも直結すると考えてよいでしょう。
5-2. CSR・SDGsの視点で企業ブランドを高める
障がい者や高齢者への配慮は、CSR(企業の社会的責任)やSDGsといった取り組みにも深く関連します。誰もが等しく情報にアクセスできるようにすることは、「持続可能な社会を作る」という理念にも沿った行動です。
こうした姿勢をオウンドメディアや広報活動で明示することで、企業イメージやブランド価値が向上し、投資家や消費者からの評価が高まる効果も期待できます。
5-3. SEO面でのプラス効果
Googleをはじめとする検索エンジンは、ユーザーにとって使いやすいサイトを高く評価すると言われています。
アクセシビリティの観点で、正しい文書構造(見出しタグやテキスト代替の適切な設定)やページ表示速度の向上、モバイル対応などを行えば、SEO(検索エンジン最適化)面でもプラスに働く可能性があるのです。
もちろん、アクセスアップによる売上増も見込めるため、結果として中長期的な投資効果が期待できます。
6. freedoor株式会社のWebアクセシビリティ対応支援

freedoor株式会社は、企業や自治体をはじめとする多様なサイト運営者向けに、Webアクセシビリティを強化するためのコンサルティングや運用サポートを提供しています。
ユーザー調査やアクセス解析を通じた課題抽出から、具体的な改善施策の提案・実装まで、ワンストップで対応可能です。さらに、社内教育プログラムやチーム体制構築の支援も行い、長期的なアクセシビリティ品質の維持をサポートします。
アクセシレンズ:クラウド型アクセシビリティツール
なお、弊社が提供する「アクセシレンズ」は、専用のスクリプトを追加するだけで多彩なアクセシビリティ機能を実装できる
クラウド型SaaSツールです。
文字拡大やコントラスト調整、音声読み上げなどの支援機能が充実しており、WCAG 2.1やJIS X 8341-3:2016(レベルAA)といった基準に沿ったサイト改善を効率的に実現します。
詳しくは、アクセシレンズのサービス紹介ページ をご覧ください。
アクセシビリティ診断・コンサルティング
「アクセシビリティと言っても、どこから始めていいか分からない」――そんなお声に対して、まずはサイト診断を通して現状の課題を洗い出すところから着手します。
JIS X 8341-3やWCAGなどの基準を踏まえ、使いやすさ・読みやすさを妨げている要因を明確にし、優先度をつけて改善策を提案。
サイト全体の構造やデザイン指針の見直しから、管理体制の構築まで総合的にコンサルティングを実施します。
WEBアクセシレンズを活用した効率的な診断
freedoorが提供する「WEBアクセシレンズ」は、サイト内のアクセシビリティ状況を自動的に解析し、改善すべきポイントをレポート化するツールです。
- サイト内のテキストコントラストやalt属性の有無、フォームの可用性などを自動でチェック
- 問題点が見つかった箇所は具体的な修正提案を表示
- 定期的なスキャンやレポート機能によって改善状況を可視化
担当者が一つひとつ手動で確認する手間を大幅に削減しながら、高度なアクセシビリティ基準をクリアするサイトづくりをスピーディーに進めることが可能です。
Web開発・運用面でのサポート
アクセシビリティ対応では、テクニカルな知見が求められる場面が少なくありません。
例えば、既存のCMS(コンテンツ管理システム)をアクセシビリティ対応仕様にカスタマイズする、JavaScriptやAPI連携部分で特定の支援技術(スクリーンリーダーなど)に対応する、などです。
freedoorはシステム開発やアプリケーション構築の経験も豊富なため、エンジニアリング領域のサポートが必要な際にもワンストップで対応可能。
サイト運用が長期にわたる場合も、継続的な監査や改善提案を行い、アクセシビリティ品質を安定して保つお手伝いをいたします。
Webマーケティング・ユーザー拡大支援
アクセシビリティを高めることは、より多くのユーザーに届くサイトを構築することにも直結します。
freedoorでは、SEOやコンテンツマーケティング、SNS運用代行などのノウハウを組み合わせ、アクセシビリティの向上をビジネス成果に結び付ける戦略を提案いたします。
「ユーザーが見やすい・使いやすいサイト」は検索エンジンからも評価されやすく、CVRの向上や問合せ件数アップが期待できます。
オンラインアシスタントによる継続サポート
アクセシビリティ対応の取り組みは一度で終わりではなく、サイトの更新や新規ページ追加のたびに点検・修正が必要になります。
freedoorでは、日常の運用タスクや更新業務を支援するオンラインアシスタントサービスを展開。アクセシビリティ対策が疎かにならないよう、継続的にフォローアップいたします。
必要な部分だけを柔軟に任せられるため、社内リソースを有効活用しながら高品質なサイト運用が可能です。
企業サイトのアクセシビリティ向上でビジネスを強化
freedoor株式会社のWebアクセシビリティ対応支援は、単なる課題発見やツール導入に留まりません。
「企業サイトがユーザーにとって本当に使いやすいか」「その結果、問い合わせ数や売上、ブランド価値をどこまで伸ばせるか」という経営視点を持ちながら、戦略的にサービスを展開しています。
Webアクセシビリティ=すべての人にとっての使いやすさを追求する取り組みであり、高齢化社会や多様なデバイス環境への対応が強く求められる今日、企業価値を高める重要なポイントとなります。
freedoorでは、アクセシビリティによるユーザー拡大・ビジネス成長を総合的にサポートしながら、企業の持続的発展をバックアップいたします。
Webアクセシビリティ導入に関するご質問やご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▶ Webアクセシビリティ対応支援の詳細はこちら
7. まとめ:両者の違いを理解し、より多くの人に配慮した環境を実現しよう

本記事では、「Webアクセシビリティとバリアフリーの違い」という切り口から、両者がどのような概念であり、どのように共通点や相乗効果を生み出すかについて解説してきました。
改めてポイントを振り返ってみましょう。
- バリアフリー:物理的障壁(段差、移動困難など)を除去し、高齢者や障がい者でも利用しやすい空間を作る取り組み
- Webアクセシビリティ:デジタル空間(Webサイトやアプリ)で誰もが情報にアクセスできるようにする仕組みや設計
- 両者の違い:オフライン(物理)とオンライン(デジタル)で対象領域が異なる
- 共通の理念:「人々が抱える障壁を取り除き、誰も排除しない社会」を目指す
- webアクセシビリティのメリット:CSR/SDGsとの親和性、ユーザー拡大、CVRやSEOへの好影響
物理空間でのバリアフリーを推進するだけでは、オンライン上で不便を感じる人々の問題は解決しませんし、その逆も同様です。
リアルとデジタルの両方のバリアを取り除くことで、高齢者や障がい者はもちろん、一時的にけがをしている人や乳幼児を連れた保護者など、より多くの人が安全・快適に社会活動に参加できるようになるのです。
企業や自治体が先進的にこの両軸を意識して取り組めば、インクルーシブなブランディングや社会的評価を高めるチャンスともなるでしょう。
「バリアフリー」は施設や交通機関などを中心に、法律や政策面でも強く推進されてきました。一方で「webアクセシビリティ」は近年急速に注目度が上がり、国内外で法整備やガイドライン(WCAG、JIS X 8341-3など)が進んでいます。
もし自社サイトやサービスで「アクセシビリティをどう導入すればいいかわからない」と感じたら、専門ツールやコンサルティングサービスを検討するのも一つの手段です。
これからの時代、物理とデジタルの両側面でのバリア除去が、誰もが活躍できる社会を実現する大きな鍵となるでしょう。ぜひ、バリアフリーとwebアクセシビリティの違いを正しく理解し、総合的なアプローチでより多くの人に配慮した環境を実現してみてください。
