Webアクセシビリティと法律|知っておくべきリスクと回避策
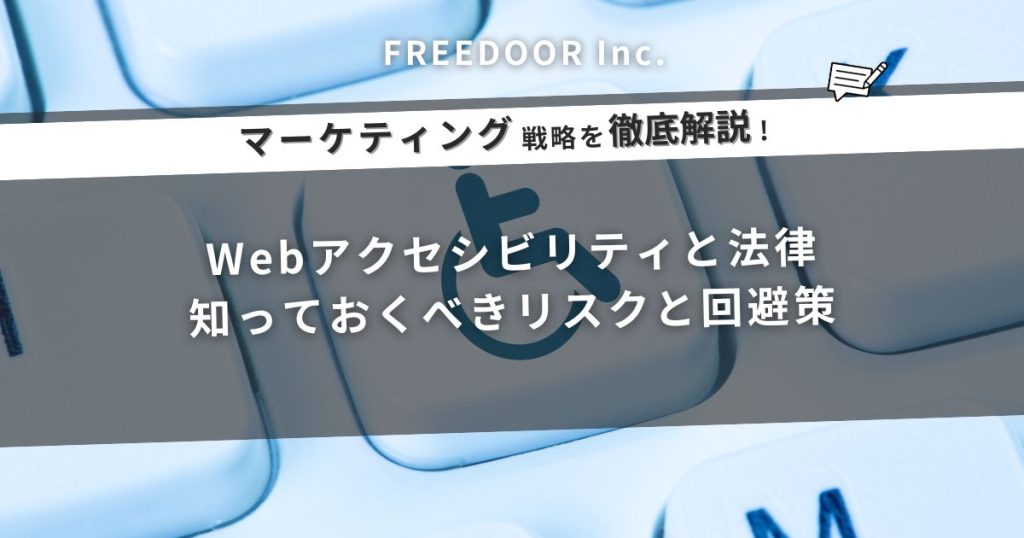
昨今、多様なユーザーがインターネットを利用するようになり、Webアクセシビリティの重要性がかつてないほど注目されています。
ところが、「障害や高齢などの特性を持つ方がWebサイトを利用できない状態を放置していると、法律に違反するリスクはあるのか?」「企業サイトがアクセシビリティを無視していたら訴訟されることもあるのか?」など、法律やリスクに関心を持つ企業担当者やサイト運営者が増えているようです。
本記事では、『Webアクセシビリティの法律リスク』という視点から、国内外の法規制や実際のトラブル事例、回避策・導入メリットを網羅的に解説します。
Webアクセシビリティがいかに法的リスクや企業イメージに影響を与えるのかを理解し、トラブルを避けながら多様なユーザーに選ばれるサイトづくりを進めましょう。
1. なぜ今「Webアクセシビリティ」と「法律・リスク」が結びつくのか

Webアクセシビリティとは、あらゆるユーザーが不自由なくWebサイトを利用できる状態を目指す概念です。従来は「障害のある方にも配慮しましょう」というボランティア的な視点で語られることが多かったものの、近年は法的義務やコンプライアンスの観点で注目されています。
そこでまず、なぜ「Webアクセシビリティ」と「法律・リスク」がここまで密接になってきたのか、3つの背景要因を整理してみましょう。
1-1. 世界的なインクルーシブ社会の潮流
国連の「障害者権利条約」や「持続可能な開発目標(SDGs)」、欧米各国の福祉関連法令など、世界規模で障害者への差別解消や多様性尊重の動きが活発化しています。
特にWeb利用においては、スクリーンリーダーで情報を取得する視覚障がい者や、キャプションや文字情報を必要とする聴覚障がい者の存在がクローズアップされました。これらの動きを受けて、多くの国でアクセシビリティを義務化する流れが強まっているのです。
もしサイト運営者が無視し続ければ、法的な罰則や社会的批判を受ける可能性が高まります。
1-2. 国内外での法整備とガイドラインの普及
日本では「障害者差別解消法」や「JIS X 8341-3」が、アメリカでは「ADA(Americans with Disabilities Act)」、EUでは「Webアクセシビリティ指令」など、それぞれの法令や規格においてアクセシビリティ確保が明確に打ち出されるようになりました。
これにより、公共機関だけでなく民間企業にも法的義務や努力義務が発生し、ウェブサイトを含むデジタルコンテンツにおいて「アクセシビリティを確保しているかどうか」が厳しく問われるようになったのです。
さらに、ガイドラインとしては「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)」が世界標準となり、日本でもJIS規格として参照されています。
1-3. 訴訟リスク・クレームリスクの顕在化
近年、特にアメリカでウェブサイトがアクセシビリティに対応していないことを理由に訴えられるケースが増えています。ECサイトや大学の公式サイトなど、さまざまな事業者が「サービスを利用できない」と障害者団体や個人から訴訟を起こされ、高額な和解金や改修費用を支払う事態に。
日本ではまだ裁判例が限定的ですが、SNSを通じた企業批判や炎上リスクが高まっており、クレームが法的手段に発展する可能性も決して無視できません。
このように、「Webアクセシビリティ」と「法律・リスク」の関係は今や企業のコンプライアンスやブランド戦略、コーポレートリスク管理において非常に重要なテーマとなっています。
2. 日本国内の主要法律・ガイドライン:企業が知っておくべきポイント

「Webアクセシビリティの法律リスク」の中でも障害者差別解消法やJIS X 8341-3(WCAG準拠)は重要な軸です。ここでは、国内で具体的に企業が押さえておきたい法律・ガイドラインを整理します。
2-1. 障害者差別解消法(2016年施行)
2016年に施行された「障害者差別解消法」は、障害のある人に対して差別的な取り扱いを禁止し、合理的配慮を提供することを求める法律です。
公共機関には法的義務が、民間企業には努力義務が課されているとはいえ、実際には社会的要請が高まるにつれ「未対応のまま放置している企業=コンプライアンス上問題あり」と見なされる傾向が強まっています。
Webアクセシビリティは情報バリアフリーの一環として解釈されるため、特にサイト運営やEC、オンラインサービスを提供する事業者は対策を求められる場面が増えつつあります。
2-2. JIS X 8341-3とWCAG
国内のWebアクセシビリティ基準としては、JIS X 8341-3が代表的です。これは国際標準のWCAG 2.x(最新はWCAG 2.2が策定中)をベースに、日本向けの表記・注釈を加えたもの。
達成基準としてA、AA、AAAの3段階があり、多くの場合はAAを目標とすることが推奨されています。
具体的には、以下のような要件が含まれます:
- 画像や動画にテキスト代替(alt属性、字幕など)があるか
- コントラスト比(文字色・背景色の差)は十分か
- キーボード操作だけで主要な機能を使えるか
- フォームエラー表示やナビゲーションがわかりやすいか
- 動きや点滅のあるコンテンツがある場合の配慮
これらの基準をしっかり満たせば、法的リスクを大幅に低減できるだけでなく、ユーザー満足度の向上にも貢献します。
2-3. 総務省・経産省など省庁のガイドライン
公共機関や行政サービスにおけるWebサイトは、総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」などをもとにJIS X 8341-3(WCAG)準拠を基本としています。
また、経済産業省やデジタル庁などもデジタル政策の一環として、アクセシビリティの確保を推奨。行政機関だけでなく、公共事業の受託企業や大手企業が率先して取り組むことで、社会全体への波及が期待されています。
今後、法改正やガイドラインの強化が進めば、事実上「Webアクセシビリティは必須」という流れが加速すると見られています。
3. 海外で起きている訴訟事例から学ぶリスクのリアル

「日本国内ではまだ訴訟リスクがそこまで顕在化していない」と思う方もいるかもしれません。しかし、海外、とりわけアメリカでの事例を見れば、Webアクセシビリティ未対応が法的トラブルに直結する例は多数報告されています。
ここでは、その代表的な訴訟事例と教訓についてご紹介します。
3-1. ADA法違反によるECサイトの訴訟
アメリカのADA(Americans with Disabilities Act)では、障害のある方に対するサービスの提供を妨げる行為が禁止されています。物理的な店舗だけでなく、オンラインショップやWebサービスも対象になるという解釈が広まり、多くの企業がスクリーンリーダーに対応していない、キーボード操作だけで購入手続きが完了できないなどの理由で訴訟を起こされました。
たとえば有名なECプラットフォームや大手アパレルブランドが高額な和解金やサイト改修費用を負担し、大きく報じられたケースもあります。
こうした動きは、日本企業が海外展開する際にも無関係とは言えず、グローバルサイトを運営している場合はADA訴訟の対象となる可能性があります。
3-2. 大学や公共機関も例外ではない
アメリカの大学や公共機関のウェブサイトが、「視覚障がい者が講義資料を利用できない」「オンライン登録手続きで操作が困難」といった理由で訴えられた事例も報告されています。
日本でも、大学の入試情報ページや講義動画の字幕対応など、高等教育機関でのアクセシビリティが重要視される傾向が出てきました。公共性が高いほど、クレームや法的要求も強くなる傾向があるため、大学・公共機関は早めの対策が望まれます。
3-3. ブランドイメージ・株価への影響
訴訟リスクが現実化すれば、単に裁判費用や和解金の問題にとどまらず、企業のブランドイメージや株価にも影響を及ぼしかねません。
特にSNSが普及している現代では、「この企業は障害者に配慮しない」「社会的責任を果たしていない」という印象が瞬時に拡散され、炎上や不買運動に発展する可能性があります。
こうした海外での事例を他山の石とし、日本企業も「早めのアクセシビリティ対応がリスクヘッジにつながる」ことを認識する必要があるでしょう。
4. Webアクセシビリティを怠るリスク:法律違反だけじゃない

「Webアクセシビリティ違反は、法律トラブルに直結する」との認識が広がっていますが、実際にはそれ以外にも複合的なリスクが存在します。具体的には以下のような問題が発生する可能性があります。
4-1. 障害者差別解消法違反の指摘と行政指導
民間企業は努力義務とされていますが、障害者差別解消法への対応を全く行わず、クレームが起きた場合には行政指導や勧告を受けるリスクがあります。
また、不祥事としてマスコミに取り上げられれば、レピュテーション低下につながり、顧客離れや売上減少といった二次的被害も出かねません。
4-2. ユーザー離脱や機会損失
例えばECサイトであれば、高齢者が文字の小ささやコントラスト不良で商品を確認できなかったり、フォーム入力に苦労したりすれば購買意欲を失います。
視覚障がい者向けのスクリーンリーダーに未対応であれば、そもそもサイト利用が難しく顧客になり得ない層が発生します。
これは法律リスクというより、ビジネスの機会損失と直結する重大な問題です。
4-3. BtoB取引における信頼低下
最近では、公共機関や大手企業との取引条件としてJIS X 8341-3のAA適合などが暗黙の要件となる場合があります。
下請け企業がアクセシビリティ対応のノウハウを持っていないと、入札で不利になったり、取引停止を食らうリスクもあり得るでしょう。
このように、法的リスク以外の経営上のリスクも多面的に存在するのがアクセシビリティ問題の怖いところです。
5. リスク回避だけじゃない!Webアクセシビリティ導入のメリット

ここまで「法律違反のリスク」や「クレーム・訴訟」というネガティブ側面を強調してきましたが、実はWebアクセシビリティ対応はポジティブなメリットを数多くもたらします。
「コストだけが増えるのでは?」と思われがちですが、むしろ長期的には大きなリターンが期待できるのです。
5-1. すべてのユーザーにとって使いやすいサイトへ
アクセシビリティを向上させる施策は、一般ユーザーの利便性やユーザビリティ改善にもそのまま活用できます。
たとえばコントラストを高める、文字サイズを調整しやすいデザインにする、フォームのエラー表示をわかりやすくするなどは、障害がないユーザーにとっても大きな利点となります。
結果的に滞在時間が延びたり、離脱率が低下したり、CVR(コンバージョン率)が上昇するといった効果も期待できるのです。
5-2. 新規顧客の取り込みと市場拡大
日本は超高齢社会であり、高齢者がスマホやタブレットを積極的に利用するケースも増えています。また、障害のある方々も日常的にインターネットを活用している時代です。
これらの層に対してアクセス可能な設計を整えておけば、新たな顧客として取り込める市場拡大の可能性が生まれます。
「アクセシビリティ対応=商機拡大」という意識を持つことで、マイナスイメージだけでなくプラスの効果を具体的に想定できるでしょう。
5-3. 企業ブランディングやCSR評価の向上
多様性を尊重する姿勢や、障害者・高齢者への配慮は、CSR(企業の社会的責任)やSDGs文脈にも合致します。
アクセシビリティ対応を公表することで、投資家やステークホルダーに好印象を与えるだけでなく、社内のインクルーシブな文化や従業員エンゲージメントを高める要素にもなり得ます。
こうした取り組みは長期的な企業価値向上やリスクヘッジにもつながるため、「善行」というよりは「戦略的投資」と捉えるべきでしょう。
6. 具体的対策:Webアクセシビリティ対応のステップとチェックリスト

それでは、実際に企業やサイト運営者が「Webアクセシビリティ 法律 リスク」を回避しながら、メリットを享受するにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、具体的な対策ステップを提案します。
6-1. 現状分析:ツール診断とユーザーテスト
まずは自社サイトやアプリの現状を可視化するところからスタートしましょう。
- 自動診断ツール:WAVE, axe, Siteimproveなどの無料/有料ツールを活用して、コントラスト比やalt属性の有無などをスキャン
- 手動チェック:キーボード操作のみでサイトを使ってみる、スクリーンリーダー(NVDA、JAWSなど)での読み上げを試す
- 実ユーザーテスト:視覚障がい者や高齢者に協力いただき、実際の使い勝手をヒアリング
この段階でサイトの問題点や優先順位が明確になるため、改修計画を立てやすくなります。
6-2. JIS X 8341-3(WCAG)適合レベルの目標設定
続いて、A、AA、AAAのどのレベルを目指すかを社内で方針として決めましょう。公共機関レベルではAAを基本としていますが、すべてのサイトでAAAレベルを実現するのは難易度が高い場合もあります。
サイトの規模や運営予算、ユーザー層を踏まえながら、実現可能な目標設定を行うことが重要です。
6-3. 実装とテスト:段階的な改修と専門家の活用
具体的な改修では、優先度と工数を見極める必要があります。トップページや主要コンテンツなどアクセス数の多い部分から手を付ける、またはフォーム入力やショッピングカートなどCVに直結する機能から対策する、といった方法が考えられます。
大規模サイトであれば、アクセシビリティ専門コンサルやエンジニアの支援を受けると効率的です。改修後はツールで再診断したり、ユーザーテストを繰り返し、品質向上を図りましょう。
6-4. 継続的なモニタリングと法改正への対応
Webアクセシビリティは一度整えたら終わりではありません。コンテンツの追加やデザイン変更で、いつの間にか支援技術への対応が崩れていることがあります。
また、法律やガイドライン(WCAG)は改定される可能性があるため、定期的に監査を行い、新たな要件が加わった場合は迅速に対応できる体制を整えましょう。
社内教育やガイドラインの周知徹底も欠かせません。担当者だけでなく、デザイナーや開発チームがアクセシビリティの基本を理解していると、日常的に品質が保たれやすくなります。
7. freedoor株式会社のWebアクセシビリティ対応支援

freedoor株式会社は、企業や自治体をはじめとする多様なサイト運営者向けに、Webアクセシビリティを強化するためのコンサルティングや運用サポートを提供しています。
ユーザー調査やアクセス解析を通じた課題抽出から、具体的な改善施策の提案・実装まで、ワンストップで対応可能です。さらに、社内教育プログラムやチーム体制構築の支援も行い、長期的なアクセシビリティ品質の維持をサポートします。
アクセシレンズ:クラウド型アクセシビリティツール
なお、弊社が提供する「アクセシレンズ」は、専用のスクリプトを追加するだけで多彩なアクセシビリティ機能を実装できる
クラウド型SaaSツールです。
文字拡大やコントラスト調整、音声読み上げなどの支援機能が充実しており、WCAG 2.1やJIS X 8341-3:2016(レベルAA)といった基準に沿ったサイト改善を効率的に実現します。
詳しくは、アクセシレンズのサービス紹介ページ をご覧ください。
アクセシビリティ診断・コンサルティング
「アクセシビリティと言っても、どこから始めていいか分からない」――そんなお声に対して、まずはサイト診断を通して現状の課題を洗い出すところから着手します。
JIS X 8341-3やWCAGなどの基準を踏まえ、使いやすさ・読みやすさを妨げている要因を明確にし、優先度をつけて改善策を提案。
サイト全体の構造やデザイン指針の見直しから、管理体制の構築まで総合的にコンサルティングを実施します。
WEBアクセシレンズを活用した効率的な診断
freedoorが提供する「WEBアクセシレンズ」は、サイト内のアクセシビリティ状況を自動的に解析し、改善すべきポイントをレポート化するツールです。
- サイト内のテキストコントラストやalt属性の有無、フォームの可用性などを自動でチェック
- 問題点が見つかった箇所は具体的な修正提案を表示
- 定期的なスキャンやレポート機能によって改善状況を可視化
担当者が一つひとつ手動で確認する手間を大幅に削減しながら、高度なアクセシビリティ基準をクリアするサイトづくりをスピーディーに進めることが可能です。
Web開発・運用面でのサポート
アクセシビリティ対応では、テクニカルな知見が求められる場面が少なくありません。
例えば、既存のCMS(コンテンツ管理システム)をアクセシビリティ対応仕様にカスタマイズする、JavaScriptやAPI連携部分で特定の支援技術(スクリーンリーダーなど)に対応する、などです。
freedoorはシステム開発やアプリケーション構築の経験も豊富なため、エンジニアリング領域のサポートが必要な際にもワンストップで対応可能。
サイト運用が長期にわたる場合も、継続的な監査や改善提案を行い、アクセシビリティ品質を安定して保つお手伝いをいたします。
Webマーケティング・ユーザー拡大支援
アクセシビリティを高めることは、より多くのユーザーに届くサイトを構築することにも直結します。
freedoorでは、SEOやコンテンツマーケティング、SNS運用代行などのノウハウを組み合わせ、アクセシビリティの向上をビジネス成果に結び付ける戦略を提案いたします。
「ユーザーが見やすい・使いやすいサイト」は検索エンジンからも評価されやすく、CVRの向上や問合せ件数アップが期待できます。
オンラインアシスタントによる継続サポート
アクセシビリティ対応の取り組みは一度で終わりではなく、サイトの更新や新規ページ追加のたびに点検・修正が必要になります。
freedoorでは、日常の運用タスクや更新業務を支援するオンラインアシスタントサービスを展開。アクセシビリティ対策が疎かにならないよう、継続的にフォローアップいたします。
必要な部分だけを柔軟に任せられるため、社内リソースを有効活用しながら高品質なサイト運用が可能です。
企業サイトのアクセシビリティ向上でビジネスを強化
freedoor株式会社のWebアクセシビリティ対応支援は、単なる課題発見やツール導入に留まりません。
「企業サイトがユーザーにとって本当に使いやすいか」「その結果、問い合わせ数や売上、ブランド価値をどこまで伸ばせるか」という経営視点を持ちながら、戦略的にサービスを展開しています。
Webアクセシビリティ=すべての人にとっての使いやすさを追求する取り組みであり、高齢化社会や多様なデバイス環境への対応が強く求められる今日、企業価値を高める重要なポイントとなります。
freedoorでは、アクセシビリティによるユーザー拡大・ビジネス成長を総合的にサポートしながら、企業の持続的発展をバックアップいたします。
Webアクセシビリティ導入に関するご質問やご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▶ Webアクセシビリティ対応支援の詳細はこちら
まとめ:Webアクセシビリティを競争力に変え、法律リスクを回避しよう

本記事では、「Webアクセシビリティの法律リスク」という切り口で、日本国内外における法的背景や訴訟事例、企業が被り得るトラブルとその回避策を詳しく解説してきました。
改めて、ポイントを振り返ってみましょう。
- 近年の世界的な法整備の流れにより、Webアクセシビリティは「社会的要請」や「法的義務」として企業に求められる
- 障害者差別解消法やJIS X 8341-3(WCAG)の遵守は、公共機関だけでなく民間企業の信頼確保にも直結
- 海外ではADA法違反の訴訟が多発し、高額な和解金やブランドダメージを受けた企業も多数
- 国内でもSNS炎上や行政指導などのリスクが顕在化しつつある。アクセシビリティ未対応は機会損失にもつながる
- Webアクセシビリティ対応は法的リスク回避だけでなく、ユーザー拡大や売上・ブランド価値向上などのポジティブ効果が大きい
- 具体的な対策としては、現状診断→ガイドライン準拠目標設定→段階的実装→継続監査という流れが基本
まだ国内では大規模な訴訟事例こそ少ないものの、リスクが「ない」わけでは決してありません。むしろ、これから法律や社会的評価が厳しくなるほど、アクセシビリティ未対応であることのデメリットは大きくなる一方です。
一方で、アクセシビリティ対応をしっかり行うことで、すべてのユーザーにとって快適なサイトを提供でき、ビジネス機会を拡大し、企業イメージを上げることが可能になります。
「Webアクセシビリティの法律リスク」に不安を感じた企業ほど、今回の内容を踏まえ、早期から戦略的にアクセシビリティ対応を進めていただければ幸いです。
社内での合意形成が必要な際は、海外訴訟の動向や国内法の改正見込みなどを資料として示すのも効果的でしょう。自社のウェブやアプリが多様なユーザーに開かれたプラットフォームとなれば、リスクを回避するだけでなく、企業としての持続的成長を強力に後押ししてくれるはずです。
