YouTubeショートを非表示にする5つの手順|おすすめ欄から消す方法と注意点まとめ

「気づいたらショートばかり見てしまう」「おすすめ欄がショートだらけで見づらい」。
そんな悩みを抱えていませんか?
YouTubeショートは手軽で楽しい反面、時間を奪われやすく、落ち着いて動画を楽しみたい人には少し厄介な存在です。
本記事では、YouTubeショートをスマホ・PC別に非表示へ近づける方法をわかりやすく解説します。
「関心がない」設定や拡張機能、履歴リセットを組み合わせることで、ショートをほとんど見かけない快適な環境をつくることが可能です。
初心者でも簡単に実践できる手順を紹介しますので、ぜひ今日から試してみてください。
はじめに:YouTubeショートを非表示にしたい人が急増している理由

最近、「YouTubeショートを非表示にしたい」という声が本当に増えています。
通勤の合間やちょっとした休憩中に、ついショート動画を開いてしまい、「気づいたら30分経っていた…」なんて経験、ありませんか?
数十秒の短い動画が次々に流れてくるので、止めどころがなくなってしまうんですよね。
もちろんショート動画は気軽に見られて楽しいコンテンツです。
でも、一方で「時間を奪われてしまう」「本来見たい動画が出てこない」といったストレスを感じる人も少なくありません。
特に最近は、ホーム画面やおすすめ欄がショートばかりになっていて、通常の動画を探すのに苦労するという声も目立ちます。
ショート動画が“便利すぎる”ことが悩みの種に
ショートがここまで広がった理由のひとつは、YouTubeアプリが自動再生を前提に設計されているからです。
スワイプするだけで次の動画が流れるため、無意識のうちに長時間視聴してしまいます。
便利な反面、集中力が削がれたり、気づけば深夜まで見続けてしまったり…。
「ながら見」や「時間の浪費」に悩む人が急増しているのです。
- 短時間で終わるはずが、止まらなくなる
- エンタメ中心で学び系動画が埋もれてしまう
- おすすめ欄がショートだらけになる
こうした現象は、YouTubeのおすすめアルゴリズムが「視聴時間」を最も重視していることにも関係しています。
一度でもショートを何本か見ると、YouTubeのAIが「この人はショートが好きなんだ」と判断し、関連動画をどんどん表示してしまうのです。
保護者が心配する「子どもとショート動画」の関係
もうひとつ大きな理由が、子どもへの影響です。
ショート動画はテンポが速く、刺激的な映像が多いので、子どもがハマりやすい傾向があります。
「一度見始めるとやめられない」「勉強よりスマホを優先してしまう」といった悩みを抱える保護者も増えています。
実際、教育関係者の中には「集中力の低下」や「思考の浅さ」を指摘する声もあるほどです。
そのため、家庭内では「YouTubeショートを見られないようにしたい」というニーズが非常に高まっています。
Googleのファミリーリンク機能を使って制限をかけたり、ブラウザ設定を工夫したりと、家庭ごとに対策を考える人も増えているのです。
「見たくない人」が増えた背景にある“アルゴリズム疲れ”
実は、ショートを非表示にしたい人が増えている背景には、「アルゴリズム疲れ」という新しい現象もあります。
YouTubeやSNSのおすすめ機能があまりに強力なため、自分で探すよりも“見せられている”感覚になるんです。
その結果、「自分で選びたい」「もっと落ち着いたコンテンツを見たい」という声が広がっています。
YouTubeショートは楽しい反面、見る人のペースを崩しやすい側面があります。
だからこそ、「自分の生活リズムを取り戻したい」「学びたい動画だけ見たい」と感じる人が、ショートの非表示設定を求めるようになっているのです。
この記事でわかること
この記事では、そんな悩みを持つ方に向けて、YouTubeショートをできる限り表示させない方法をわかりやすく紹介します。
スマホ版・パソコン版の具体的な操作から、AIの学習リセット、拡張機能の使い方まで、ステップごとに詳しく解説します。
「完全に消す」のは難しくても、「ほとんど出てこない環境」は誰でも作れます。
次のセクションから、実際の仕組みと非表示のコツを見ていきましょう。
YouTubeショートは完全に非表示にできる?【仕組みと限界】

結論から言うと、現時点ではYouTubeショートを「完全に」非表示にすることはできません。
アプリやブラウザの設定だけでショート動画を完全に消すことは、YouTubeの仕組み上むずかしいのです。
その理由は、YouTubeのおすすめ機能が「AIによる自動学習」で成り立っているからです。
そもそもYouTubeショートとは?
YouTubeショートとは、縦型・60秒以内の短い動画コンテンツのこと。
スマホでスクロールするだけで次々と再生されるため、手軽で楽しい反面、つい見過ぎてしまう人が多いのが特徴です。
YouTubeとしてもこの形式を強く推しており、ショートはアルゴリズム的にも優遇されています。
つまり、「YouTubeの中でショートは“標準装備”になっている」と考えるとわかりやすいでしょう。
完全に消せない理由
YouTubeのAI(アルゴリズム)は、あなたの視聴履歴や再生時間、評価した動画の傾向をもとに、次に表示する動画を自動的に判断しています。
そのため、「ショートを見たくない」と思っても、設定でショート機能自体をオフにする項目は用意されていません。
YouTubeアプリやブラウザの中では、ショートが「YouTubeというサービスの一部」として組み込まれているからです。
ただし、「完全に消す」ことはできなくても、ショートを「ほとんど見かけない状態にする」ことは十分可能です。
たとえば次のような方法を組み合わせることで、ショートの表示を最小限に抑えられます。
- ① 「関心がない」を繰り返し選んでAIに学習させる
- ② 特定のチャンネルをブロック・非表示にする
- ③ 「視聴履歴」を削除しておすすめ傾向をリセットする
- ④ Chromeなどの拡張機能でショート欄そのものを非表示にする
こうした設定をコツコツ続けることで、YouTubeのAIは「ショートは好まれていない」と学習し、だんだんと表示頻度を下げてくれます。
人によっては、ホーム画面からショートがほとんど消えることもあります。
「おすすめ」からショートを減らすコツ
ショートを非表示に近づけるポイントは、「AIに正しい信号を送る」ことです。
つまり、「見たい動画」と「見たくない動画」をはっきり区別するのがコツです。
ショートを再生せずにスルーし、代わりに長めの通常動画を視聴すると、AIが「この人はショートより長尺動画を好む」と判断してくれるようになります。
| 設定内容 | 効果 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 「関心がない」を選択 | ショートの表示が徐々に減る | ★★★★★ |
| 視聴履歴を削除 | おすすめ内容をリセットできる | ★★★★☆ |
| チャンネル非表示 | 同じ投稿者のショートをブロック | ★★★☆☆ |
| 拡張機能の活用 | PCでは完全非表示に近づける | ★★★★★ |
「非表示設定」と「自己管理」のバランス
一方で、どんなに設定を工夫しても、アルゴリズムが自動的に新しい動画を提案してくるため、完全にゼロにすることはできません。
そこで大切なのは、設定と同時に「自分の視聴習慣を整える」ことです。
ショートを開かない習慣をつけるだけでも、AIの学習が変わり、数日後にはおすすめ欄の傾向が変わってきます。
つまり、YouTubeショートを“完全に非表示”にすることはできなくても、
「AIに自分の好みを理解させて、ショートを避けるように仕向ける」ことは可能です。
次のセクションでは、スマホで実際に設定を変える方法を、手順ごとに紹介していきます。
YouTubeショートを非表示にする5つの方法【スマホ版】

スマホでYouTubeを見ている方の多くが、「ショートが止まらない」「おすすめ欄がショートだらけ」と感じているのではないでしょうか。
ここでは、YouTubeショートをできるだけ表示させないための、実用的な5つの方法を紹介します。
すべてアプリ内で簡単にできるので、今日からすぐに試してみてください。
①「関心がない」を繰り返して学習させる
最も手軽で効果的なのが、「関心がない」設定です。
YouTubeアプリでショート動画を長押しすると、メニューの中に「関心がない」が表示されます。
これを繰り返すことで、YouTubeのAI(アルゴリズム)が「このジャンルは見たくないんだな」と学習してくれます。
ポイントは、「数回だけ」では効果が薄いこと。
おすすめ欄にショートが出てくるたびに、根気よく「関心がない」を選び続けることで、次第にショートの露出が減っていきます。
また、再生しないことも重要です。
一度でも再生すると、AIが「興味がある」と判断してしまうため、開かずに「関心がない」を押すのがコツです。
- ショートを開かずに「長押し」→「関心がない」を選択
- 数日間繰り返すと、おすすめの傾向が変わってくる
- 見たい動画だけを視聴して、AIの学習を誘導する
② チャンネル単位で非表示にする
次に効果的なのが、特定のチャンネルを非表示またはブロックする方法です。
ショート動画の中には、同じ投稿者が連続して出てくることがあります。
その場合、チャンネルごと非表示にすると、関連動画もまとめて表示されにくくなります。
やり方は簡単です。
ショート動画の右上の「︙(縦の3点メニュー)」をタップし、「このチャンネルをおすすめに表示しない」を選択します。
これを数チャンネル分繰り返すと、似た系統のショートも減っていきます。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. ショート動画右上の「︙」をタップ | メニューを開く |
| 2. 「このチャンネルをおすすめに表示しない」を選択 | AIがその投稿者を除外学習 |
| 3. 数チャンネル繰り返す | 関連動画全体の露出が減少 |
③ 「視聴履歴」からショート動画を削除してAI学習をリセット
もしショートを何度も見てしまった場合、YouTubeのAIが「あなたはショートが好き」と判断してしまいます。
その状態をリセットするには、視聴履歴を削除するのが効果的です。
手順は以下の通りです。
- YouTubeアプリの右上アイコン → 「設定」 → 「履歴とプライバシー」
- 「視聴履歴を削除」を選択
- 「視聴履歴を一時停止」にチェックを入れる
これでAIが過去のショート視聴データを使わなくなります。
ただし、通常の動画も履歴リセットされるため、再び自分の好みに合わせたい場合は、見たいジャンルの動画をいくつか再生して再学習させましょう。
④ ファミリーリンク・ペアレンタル設定で制御する(子ども向け)
お子さんがショート動画を見すぎてしまう場合は、Googleのファミリーリンク機能を使うと安心です。
保護者が子どものアカウントを管理できるようになり、ショート動画や特定アプリの使用時間を制限できます。
設定方法は、保護者のスマホに「Family Link」アプリをインストールし、子どものGoogleアカウントを登録します。
そこから「YouTube」や「YouTube Kids」の利用時間・視聴制限を設定できます。
たとえば、
- 「YouTube Kids」モードを使ってショート非対応にする
- アプリの利用時間を1日あたり〇分に制限する
- 寝る時間以降は自動で利用停止にする
こうした設定を組み合わせることで、子どもの「つい見すぎてしまう」習慣を防げます。
また、スマホだけでなく、タブレットやパソコンにも同じ設定を反映できるのが便利です。
⑤ Evercastなどの専用ツールでフィード除外【中上級者向け】
最後は少し応用的な方法です。
Evercastなどの外部ツールを使うと、YouTubeのフィード(おすすめ欄)からショートを自動的に除外できます。
これは内部的に「特定URL(/shorts/)」を非表示にする仕組みを使っており、かなり効果的です。
ただし、こうしたツールは公式アプリ内ではなく、ブラウザやカスタムビューアで利用する形になるため、完全初心者には少しハードルが高いかもしれません。
とはいえ、ショートをほぼ見かけなくなるレベルで効果があるため、「どうしても完全に消したい」という人にはおすすめです。
以上の5つを組み合わせれば、スマホでもかなり快適なYouTube環境をつくることができます。
次のセクションでは、パソコンでショートを非表示にする方法を詳しく見ていきましょう。
YouTubeショートを非表示にする4つの方法【パソコン版】

パソコンでYouTubeを利用している場合も、ショート動画がおすすめ欄やホーム画面に頻繁に表示されることがあります。
スマホと違ってPCではブラウザ機能を活かせるため、より柔軟な方法で非表示にすることが可能です。
ここでは、手軽に試せる4つの対策を紹介します。
① 「×」ボタンでおすすめ動画を手動削除
もっともシンプルな方法が、おすすめ欄に出てくるショート動画を手動で消すことです。
YouTubeのホーム画面やサイドバーにあるショート動画のサムネイルにマウスを合わせると、「×」マーク(またはメニューアイコン)が表示されます。
ここで「この動画をおすすめに表示しない」を選ぶと、その動画や関連するショートが減っていきます。
この操作を繰り返すことで、YouTubeのアルゴリズムが「あなたがショートに関心を持っていない」と学習します。
結果的に、数日後にはホーム画面のおすすめがかなり通常動画寄りに変化することもあります。
- おすすめ欄でショートにカーソルを合わせる
- 右上の「×」またはメニューから「おすすめに表示しない」を選択
- 定期的に繰り返すことで、AIのおすすめ傾向が変わる
② 「関心がない」設定を反復してアルゴリズム調整
スマホ同様、パソコンでも「関心がない」設定が有効です。
ショート動画やおすすめ欄の動画を右クリックまたはメニューから「関心がない」を選択するだけでOK。
同じジャンルのショートが表示されづらくなります。
特にポイントとなるのは、「似たテーマの動画が出てきたらすぐ反応する」ことです。
1回の設定ではなく、日々の視聴中に見かけるたびに反復することで、アルゴリズムが確実に変わっていきます。
焦らず少しずつAIに学習させていくイメージを持ちましょう。
③ Chrome拡張機能でショートを除外する
PCで最も効果的なのが、このブラウザ拡張機能</strongを使う方法です。
Google Chromeをはじめとする主要ブラウザには、「YouTubeショート」を自動的に隠してくれる便利な拡張機能があります。
代表的なものは次の3つです。
| 拡張機能名 | 特徴 | 使いやすさ |
|---|---|---|
| Unhook YouTube | YouTube上の「Shorts」セクションやコメント欄も非表示にできる | ★★★★★ |
| DF Tube(Distraction Free for YouTube) | おすすめ・コメント・トレンドなど、不要な要素を個別に非表示にできる | ★★★★☆ |
| Hide Shorts for YouTube | ショート動画だけをピンポイントで消せる軽量ツール | ★★★★☆ |
これらはChromeウェブストアからインストールできます。
設定画面で「Hide Shorts(ショートを非表示)」のチェックをオンにするだけで、YouTubeのホーム画面やサイドバーからショートが完全に消えます。
スマホでは実現できないほど効果が高いため、PC利用者には最もおすすめの方法です。
④ ホーム画面を「登録チャンネル」中心に切り替える
もうひとつの工夫として、YouTubeのトップページを「登録チャンネル」中心に切り替える方法があります。
ショートの多くは「おすすめ」タブで表示されるため、自分が登録しているチャンネルの動画だけを見るようにすると、ショートの出現率を自然に下げられます。
- 左メニューの「登録チャンネル」をクリック
- お気に入りのチャンネル動画だけを一覧表示
- ショートよりも長尺・学び系コンテンツが中心に
また、ブラウザのブックマークに「https://www.youtube.com/feed/subscriptions」を登録しておくと、
ホーム画面を開かずに直接登録チャンネル一覧へアクセスできます。
毎回「おすすめ欄」を通らないことで、ショートを見る機会そのものを減らせるのです。
ブラウザ別のおすすめ設定まとめ
| ブラウザ | おすすめ方法 | 補足 |
|---|---|---|
| Chrome | 拡張機能「Unhook」「DF Tube」で完全除外可能 | 最も設定自由度が高い |
| Safari | アドブロック系アドオンを活用してショートを隠す | スマホよりもPC版Safariの方が柔軟 |
| Microsoft Edge | Chrome拡張を流用可能、同様に非表示化できる | 会社PC利用者にもおすすめ |
このように、パソコンではショート非表示の自由度が高く、
特に拡張機能を使えば「実質的な完全非表示」も実現可能です。
次のセクションでは、この状態を維持するために押さえておきたい「設定ポイント」を紹介します。
【補足】非表示を維持するための設定ポイント
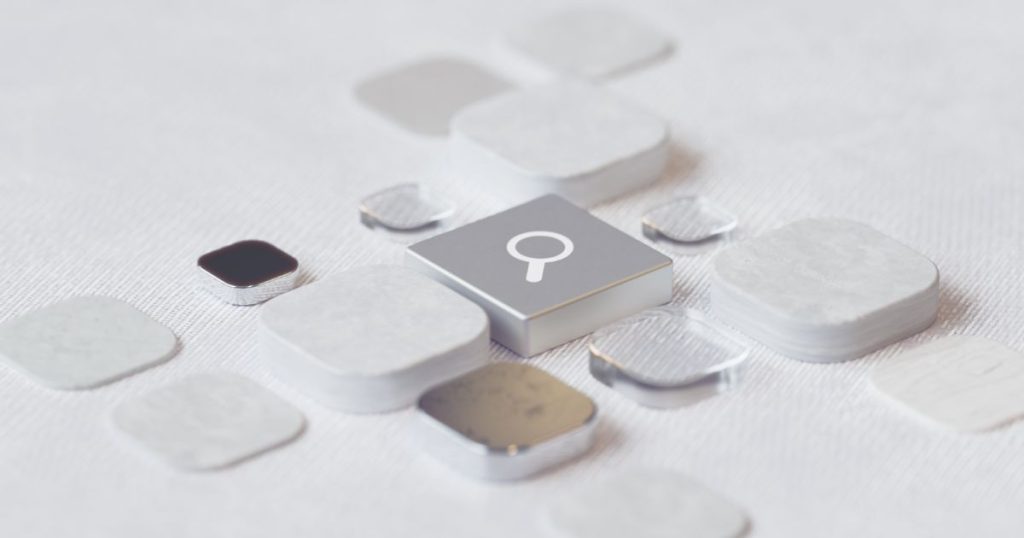
「ショートを非表示にしたはずなのに、また出てきた…」という経験はありませんか?
これはYouTubeのアルゴリズムが常に学習を続けているため、一時的に設定しても時間が経つと元に戻ってしまうことがあるからです。
ここでは、非表示の状態を長く維持するためのコツを紹介します。
「履歴」や「おすすめ」の仕組みを理解する
まず押さえておきたいのは、YouTubeのおすすめ表示は「視聴履歴」と「滞在時間」によって決まるということです。
つまり、どんな動画をどれくらい見たかが、次のおすすめ内容を左右しています。
ショートを一度でも開くと、YouTubeは「この人はショートに興味がある」と判断し、同じような動画を次々と表示してしまうのです。
そのため、非表示設定を長持ちさせるには、ショートを開かずにスルーするのが重要です。
ショートを避け、通常の動画や学び系コンテンツを積極的に視聴することで、AIが「長尺動画が好き」と学習し、自然とショートの表示を減らしてくれます。
一度視聴したジャンルは再び出やすくなる
YouTubeは、あなたが「興味を持ったジャンル」を記憶する仕組みになっています。
そのため、一度でも再生したテーマ(たとえばエンタメ系・恋愛・お笑いなど)は、時間が経っても再び表示されやすい傾向があります。
これを防ぐには、以下のような対応が効果的です。
- 見ないジャンルの動画を開かない(サムネを押さない)
- 「関心がない」を何度も選択してAIに伝える
- 新しいジャンルの動画(教育・ニュースなど)を積極的に再生する
これらを続けると、AIが「この人は別のジャンルに興味を持ち始めた」と判断し、表示内容が切り替わります。
ショートを避けるだけでなく、「何を見るか」も重要なポイントです。
アルゴリズムをリセットしたい場合の手順(履歴削除+再学習)
「ショートばかり表示されて手がつけられない…」という場合は、思い切って履歴を削除してリセットするのもひとつの手です。
AIの学習データを消してしまえば、過去の嗜好に基づいたおすすめがリセットされ、新しい傾向に切り替わります。
手順は簡単です。
- YouTube右上のアイコン → 「設定」 → 「履歴とプライバシー」
- 「視聴履歴を削除」を選択
- 「視聴履歴を一時停止」をオンにする(しばらくおすすめが固定されます)
この状態で、自分が見たいジャンルの動画を5〜10本ほど視聴しましょう。
すると、YouTubeのAIが再び学習を始め、次第にショート以外の動画が中心に表示されるようになります。
「履歴削除 → 再学習 → AI誘導」の流れを定期的に繰り返すのがおすすめです。
ショートをうっかり再生しないための小技
日常的にショートを開かないようにするには、ちょっとした工夫も効果的です。
- ホーム画面を開かずに「登録チャンネル」タブから視聴する
- ブックマークに「https://www.youtube.com/feed/subscriptions」を設定
- サムネイルで「縦型」「短尺」の動画はスルーする癖をつける
特にPCでは「Unhook YouTube」などの拡張機能を使えば、サムネイル上にショートマーク(再生時間60秒以内)を非表示にできるため、誘惑を減らせます。
このように、意識と設定の両方を整えることで、非表示の効果を長くキープすることができます。
次のセクションでは、設定をしても「なぜかショートが戻ってくる」という場合の、よくある原因と対処法を紹介します。
【トラブル対応】非表示設定が戻ってしまう場合の対処法

「ショートを非表示にしたのに、気づいたらまた出てきた!」
このような声はとても多いです。
実は、YouTubeの仕組み上、設定を変えても自動的に復元されてしまうことがあります。
ここでは、非表示設定が戻ってしまう主な原因と、それぞれの対処法をわかりやすく紹介します。
バージョンアップ後に再表示される理由
もっとも多い原因が、YouTubeアプリやブラウザのアップデートです。
アプリが最新版に更新されると、内部の設定が初期化されることがあります。
特にスマホの場合、「関心がない」設定やおすすめの傾向が一部リセットされることがあるため、再びショートが表示されてしまうのです。
この場合の対処法はシンプルです。
- アップデート後に再度「関心がない」設定を繰り返す
- チャンネルごとの非表示設定も確認し直す
- アプリの自動更新をオフにして、手動で管理する
また、ブラウザ拡張機能を使っている場合も、バージョン更新のタイミングで一時的に設定が無効になることがあります。
拡張機能の再インストールまたは再起動を行えば、多くの場合は元通りになります。
拡張機能が効かない時のチェックポイント
パソコンで拡張機能を使っている人の中には、「急にショートが消えなくなった」というケースもあります。
その場合は、以下の点をチェックしましょう。
| チェック項目 | 確認方法 | 対処法 |
|---|---|---|
| 拡張機能がオフになっていないか | ブラウザ右上のパズルマーク → 拡張機能管理 | 「有効」にチェックを入れる |
| ブラウザが最新か | 設定 → Chromeのバージョンを確認 | 最新版に更新後、ブラウザを再起動 |
| キャッシュやCookieが残っていないか | 設定 → プライバシーとセキュリティ | 一度削除し、YouTubeに再ログイン |
これでも改善しない場合は、拡張機能を一度削除し、再インストールしてみましょう。
とくに「Unhook YouTube」や「DF Tube」は、YouTubeの仕様変更に合わせて頻繁に更新されているため、古いバージョンだと動作しないことがあります。
アカウント同期の影響(スマホとPCでズレる場合)
もうひとつ見落としがちなのが、アカウントの同期設定です。
スマホでショートを非表示にしても、同じGoogleアカウントでログインしているパソコンでは、その設定が反映されないことがあります。
逆に、PC側の拡張機能でショートを隠しても、スマホアプリには影響しません。
この場合は、次のように使い分けるのが効果的です。
- スマホ:アプリ内で「関心がない」「チャンネル非表示」を活用
- PC:拡張機能でショートをブロック
- タブレット:ブラウザ経由でPCと同じ拡張機能を利用
端末ごとに設定を最適化しておくことで、再表示リスクを最小限に抑えられます。
また、視聴履歴の共有も注意が必要です。
スマホでショートを見てしまうと、その履歴がPC側にも同期され、再びおすすめにショートが出てしまうことがあります。
定期的な「見直し」が一番の予防策
ショートの非表示設定は、一度やって終わりではなく、定期的に見直すのがポイントです。
1〜2か月に一度、「設定」「履歴」「拡張機能」を確認し、リセットやアップデートを行うと安定して非表示を維持できます。
YouTubeは日々アップデートされるサービスです。
その変化に合わせて、小まめに設定を整えることで、ストレスのない視聴環境を保てます。
次のセクションでは、ユーザーからよく寄せられる質問をまとめて解説します。
YouTubeショートの活用と非表示のバランス【運用者視点】

ここまで「ショートを非表示にしたいユーザー向け」の設定方法を紹介してきましたが、
一方で、動画を配信する側(運用者)にとっては「ショートをどう扱うか」も非常に大切なテーマです。
YouTubeショートは確かに多くのユーザーを惹きつける一方で、「見たくない」と感じる層も存在します。
ここでは、ショートに対する視聴者の傾向と、運用者として意識すべきポイントを整理します。
ショートを嫌う視聴者層と好む層の違い
まず、YouTubeショートに対する反応はユーザー層によって大きく異なります。
若年層(10〜20代)はテンポの早い情報やエンタメを好む傾向があり、ショートに強く惹かれます。
一方で、30代以上では「落ち着いて情報を得たい」「集中して学びたい」と考える人が多く、ショートを煩わしく感じることがあります。
簡単にまとめると、以下のような特徴があります。
| 視聴者層 | ショートへの印象 | 視聴傾向 |
|---|---|---|
| 10代〜20代 | テンポがよく、短時間で楽しめるので好印象 | エンタメ・恋愛・美容などを中心に連続視聴 |
| 30代〜40代 | 情報が浅く感じる・集中を乱されると感じる | 長尺の解説・レビュー・教育系を好む |
| 50代以上 | 画面の切り替えが多く疲れる、内容が速すぎると感じる | テレビ的な構成や音声説明付きの動画を好む |
このように、ショートはすべての人に歓迎されるわけではありません。
だからこそ運用者は、自分のチャンネルの視聴者層をしっかり把握し、「誰のためにショートを作るのか」「どんな視聴体験を提供したいのか」を明確にすることが大切です。
YouTubeアルゴリズムがショートを推す背景
では、なぜYouTubeはここまでショートを前面に押し出しているのでしょうか。
理由は大きく3つあります。
- ① 視聴時間の最大化
ショートは短い動画を連続再生させる仕組みで、結果的に長時間アプリを利用させる効果があります。 - ② TikTok・Instagram Reelsとの競争
他SNSのショート動画人気を受け、YouTubeも「縦型動画文化」に対応するためショートを強化しています。 - ③ クリエイター発掘の効率化
新しい投稿者が短時間でバズるチャンスを得られるため、YouTube全体のコンテンツ多様化につながっています。
つまり、YouTubeにとってショートは“ユーザーを離さない仕組み”であり、同時に“新しいクリエイターを発掘する場”でもあるのです。
そのため、今後もアルゴリズム的にはショートを優遇する流れが続くと考えられます。
運用者は「非表示設定ユーザー」を想定して動画設計を行うべき理由
一方で、ショートを敬遠する層が一定数いることも事実です。
運用者としては、ショートだけに依存せず、「ショートを見ない人にも届く設計」を考えることが重要です。
たとえば、次のようなアプローチが効果的です。
- ショートと通常動画の連動設計:
ショートで興味を引き、詳細は本編動画へ誘導する。 - チャンネル構成の整理:
「ショート」タブを別カテゴリー化し、メイン動画の印象を損なわないようにする。 - 非ショートユーザー向けの再生リスト設計:
長尺・学習系・レビュー系などをまとめて配置し、落ち着いて見たい人に寄り添う。
特に大切なのは、「ショートを見ない」層を想定したトーンやテンポづくりです。
情報を詰め込みすぎず、静かな間をつくることで、年齢層の高い視聴者にも安心して見てもらえます。
つまり、YouTube運用では「ショートを活かす力」と「ショートを避ける人への配慮」、この2つのバランスを取ることが理想です。
アルゴリズムを理解しつつ、視聴者の多様なスタイルに合わせた運用設計が、これからの時代に求められるスキルといえるでしょう。
まとめ:自分に合った視聴環境を作ろう

ここまで、YouTubeショートを非表示に近づける方法を紹介してきました。
結論として、YouTubeショートを完全に消すことはできません。
しかし、設定の工夫と視聴習慣の見直しによって、ショートを最小化することは十分可能です。
まず試してほしいのは、「関心がない」を繰り返し選ぶこと。
この地味な行動が、実はAIにとって最も強い信号になります。
さらに、拡張機能を活用すれば、パソコン上ではショートをほとんど見かけなくなるでしょう。
そして、「視聴履歴を削除」してAIの学習をリセットするのも非常に効果的です。
- 関心がない: 繰り返すことでAIが学習し、ショート表示が減る
- 拡張機能: PCではほぼ完全にショートを非表示にできる
- 履歴リセット: おすすめ傾向を一度リセットして再学習させる
また、子どもや家族でYouTubeを利用している場合は、Googleのファミリーリンクを活用して安全な視聴環境を整えましょう。
時間制限や利用制御を設定しておくことで、子どもが無意識にショートを見続けてしまうリスクを防げます。
大人でも、「集中したい時間はショートを見ないようにしたい」ときは、拡張機能やブックマークを活用してホーム画面を通らず視聴するのがおすすめです。
最後に大切なのは、定期的に設定を見直すことです。
YouTubeは頻繁に仕様が変わるため、一度設定して終わりではなく、1〜2か月に一度は確認するのが理想です。
履歴やおすすめ傾向をチェックして、自分にとって快適な視聴環境を保つようにしましょう。
YouTubeショートは使い方次第で、時間を奪う存在にも、情報収集の味方にもなります。
自分の目的に合わせてコントロールすることで、もっと健やかに、もっと心地よくYouTubeを楽しむことができます。
今日から少しずつ設定を見直して、あなたにぴったりの視聴スタイルを整えてみてください。
プロがサポートするショート動画制作代行サービス

もし「ショート動画を作りたいけれど、どこから手をつければいいかわからない」というお悩みがあれば、freedoorのショート動画制作代行サービスを活用してみませんか。
freedoorでは、業界最安水準の価格でありながら高品質なショート動画制作と、動画を活用したSNS運用サポートを一括して提供しています。短い尺で最大限の魅力を伝えるノウハウを活かし、集客やブランド認知拡大に貢献いたします。
freedoorのショート動画制作代行サービスとは?
単に動画を制作するだけでなく、アカウント運用に必要なすべての工程を一貫してサポートできる点が大きな特徴です。以下のような領域をカバーし、お客様の課題に合わせた最適なプランをご提案します。
- アカウント分析と最適化
過去投稿やフォロワー属性を徹底的に分析し、効果的な投稿スケジュールやコンテンツ戦略を立案します。 - コンテンツ企画・制作
ターゲット層の興味を引くクリエイティブやショート動画を制作。写真・リールなどのビジュアルを洗練し、魅力あるコンテンツを提供します。 - エンゲージメント戦略の設計
保存やシェアを促す投稿づくりから、フォロワーとのコミュニケーション強化まで、成果を生む施策を実施します。 - データ分析と改善提案
投稿後のパフォーマンスを分析し、次回のコンテンツ制作に活かせる改善点を提案します。
実績紹介
freedoorを導入した多くの企業様が、フォロワー数やエンゲージメント率を劇的に伸ばしています。
- 飲食店様
課題:不定期な投稿が原因で、地域での認知度が低かった。
成果:半年でフォロワー数が25倍に増加し、SNS経由での来店予約が急増。 - 美容サロン様
課題:フォロワー数が伸び悩み、新規顧客獲得の壁に直面していた。
成果:半年でフォロワー数が2.6倍に増加し、リールの平均再生回数が5万回を突破。 - ハウスメーカー様
課題:ブランディングの一環としてSNSを活用したかったが、運用手段が定まっていなかった。
成果:半年でフォロワー数が6倍に増加し、問い合わせ数も倍増。
このように、freedoorではショート動画を中心に据えたSNS運用の全体最適を図り、成果につなげるサポートを提供しています。
今なら無料相談受付中
「動画制作やSNS運用についてもっと詳しく知りたい」「自社の課題に合った具体的な対策を知りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。フォロワー数の増加やエンゲージメント向上に必要なポイントを丁寧にお伝えし、最適な施策をご提案いたします。
動画制作からSNS運用に関するお悩みまで、一括して解決できる無料相談を実施中です。
お気軽にお問い合わせいただき、ショート動画を最大限に活かしたマーケティング戦略を一緒に築き上げましょう。
