【導入事例付き】webアクセシビリティによるCVR向上と費用対効果とは?
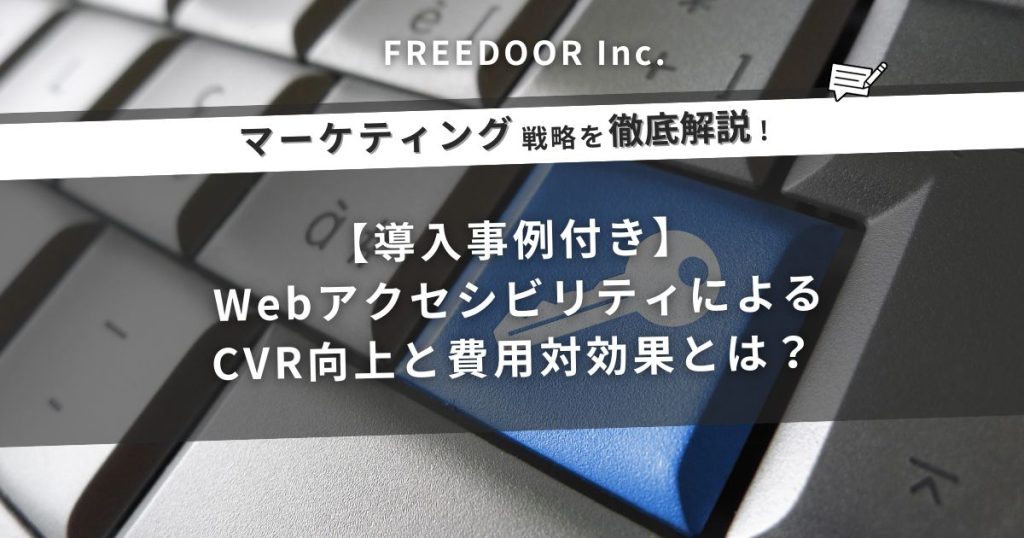
近年、Webアクセシビリティへの注目度が急速に高まっています。
「アクセシビリティ」とは、視覚・聴覚・身体などの障害や高齢化といった多様なユーザー特性を前提に、誰もがオンラインサービスやWebサイトを平等に利用できるように配慮することを指します。
単なる福祉的な側面だけでなく、企業がビジネスを成長させるうえでも大きなメリットがあるという点で、各業種・業界から関心を集めているのです。
特に、本記事のタイトルにもあるように、「Webアクセシビリティの導入がなぜCVR向上につながるのか?」「費用対効果は本当に見合うのか?」という疑問を抱えるWeb担当者や経営層は多いでしょう。
そこで本記事では、企業のWebアクセシビリティ導入メリットについて、以下のポイントを網羅的に解説していきます。
- webアクセシビリティが企業にとって重要な理由
- 導入メリットとしてのCVRアップ・ユーザー拡大効果
- 企業ブランディングやコンプライアンス(法令順守)への影響
- 導入時の費用対効果(ROI)はどう考えるか
- 具体的な導入事例から見る成功の秘訣
「コストに見合う効果があるのか」「具体的な事例を知りたい」「実際にどれくらいCVRが変わるのか」といった疑問を持つ方は、ぜひ最後までご覧ください。
本記事を読み終える頃には、アクセシビリティ対応を行うことで得られるビジネス上のメリットや企業価値の向上が、いかに大きなリターンをもたらすのかが理解できるはずです。
1. Webアクセシビリティとは?企業が注目すべき理由

まずは、「Webアクセシビリティとは何か」を明確にしておきましょう。
Webの世界においてアクセシビリティ(Accessibility)とは、障がいの有無や年齢、使用デバイス、ネット接続環境などにかかわらず、すべてのユーザーが情報にアクセスしやすい状態を意味します。
例えば、画面読み上げソフト(スクリーンリーダー)に対応したテキスト構造やalt属性の設定、高齢者が読みやすいコントラスト比の確保、聴覚障がい者向けの字幕付与などが含まれます。
1-1. WCAGやJIS X 8341-3といったガイドライン
webアクセシビリティの基本指針として国際的に広く参照されるのが、WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)です。
日本国内では、このWCAGをベースにしたJIS X 8341-3が整備されており、公共機関や企業サイトの多くがこれらのガイドラインに沿っているかどうかが評価されるケースも増えています。
具体的には、テキスト代替(alt属性)の適切な付与、フォームのラベル設定、コントラスト比の基準など、細かいチェックポイントが存在します。
1-2. 企業が注目すべき背景
かつては「アクセシビリティ=障がい者向けの配慮」という位置づけでした。しかし、高齢化の進展やスマートフォン利用者の増加に伴い、サイトの見やすさ・使いやすさを改善することが、結果的にすべてのユーザーにとってプラスになると認識されるようになりました。
また、障害者差別解消法や総務省のガイドラインなど法律や行政指針の影響で、公共機関だけでなく民間企業にもアクセシビリティ対応が求められる流れが強まっています。これにより、企業としてのコンプライアンスやリスク回避の観点でも、アクセシビリティは無視できない要素となりつつあるのです。
さらに、海外展開を見据える企業にとっては、アメリカのADA法(Americans with Disabilities Act)などを背景に、サイトのアクセシビリティ対応が訴訟リスクを軽減する意味合いも持ちます。
こうした国内外の潮流が合わさり、アクセシビリティの導入メリットを「CSR(企業の社会的責任)」や「ブランディング」だけでなく、純粋な「ビジネス成長戦略」の一環として捉える企業が増えているのです。
2. 導入メリット1:CVRアップとユーザー拡大に直結する理由

企業がwebアクセシビリティを導入する大きなモチベーションの一つが、CVR(コンバージョン率)の向上です。
「アクセシビリティを高める」=「障害者のためだけの施策」というイメージがあるかもしれませんが、実際には幅広いユーザビリティ改善にもつながるのがポイント。ここでは、CVRアップとユーザー拡大という観点から、その具体的な理由を掘り下げます。
2-1. ユーザビリティの向上が離脱率を下げる
アクセシビリティ対応を進めると、自然とサイトの使いやすさ(ユーザビリティ)も向上していきます。例えば:
- フォームの入力項目がわかりやすくなり、エラー時の説明が明確になる
- 文字サイズや色のコントラストが最適化され、読みやすいデザインになる
- キーボードだけで操作可能になり、タブレット端末でもストレスなく操作できる
こうした改善は、障がいのある方だけでなく、あらゆる年齢層・環境のユーザーの利便性を高め、結果的にサイト滞在時間の延長や離脱率の低下を促します。
離脱率が下がればフォーム送信や商品購入などのコンバージョンにつながる可能性が高まり、CVRアップという形で数字に表れやすいのです。
2-2. 新たなユーザーセグメントを取り込める
webアクセシビリティ対応を行うと、これまでサイトを利用しにくかった層(例:視覚障がい者、高齢者、色覚特性を持つユーザーなど)を新たな顧客として取り込める可能性があります。
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、高齢者がスマホやPCを使いこなすケースが急増中。見づらいサイトよりも見やすい・わかりやすいサイトの方が支持されやすいのは言うまでもありません。
さらに、海外ユーザーに向けて英語対応や多言語対応をする際にも、アクセシビリティ対応が進んでいれば翻訳やデザインの最適化がスムーズです。こうして市場の拡大とCVRアップを同時に狙えるのが、webアクセシビリティの強みとなります。
2-3. 事例:フォーム改修でCVRが1.5倍に
あるECサイトでは、フォームのアクセシビリティ改善を中心としたリニューアルを実施しました。具体的には、ラベルの追加、エラー表示のわかりやすさ、キーボード操作のしやすさ、カラーユニバーサルデザインの導入などです。
その結果、高齢者が途中で入力を諦めるケースが激減し、最終的な購入手続きまで進む割合が大幅に増加。リニューアル前後の比較でCVRが1.5倍になったという報告もあります。
こうした導入メリットは、決して一部の企業だけが得られるものではありません。多くのサイトが抱える「見にくい」「使いにくい」といった課題を、アクセシビリティを切り口に解決することで広い層のユーザーにアプローチできるのです。
3. 導入メリット2:企業ブランディング・コンプライアンスへの効果

CVRや売上などの直接的な成果だけでなく、企業イメージやコンプライアンスの面でも大きなメリットがあります。特に近年は、CSRやSDGsに絡めてアクセシビリティを推進する企業が目立ってきました。ここでは、その背景と効果を解説します。
3-1. CSRやSDGsでの評価向上
多様な人々が利用しやすいサイトを構築することは、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念にも合致します。
企業がアクセシビリティへの取り組みを積極的に公表することで、投資家やステークホルダーからの評価が高まりやすく、ESG投資の対象として注目されるケースも増えています。
また、社内外へのメッセージとして「私たちはすべての人がアクセスできるサービスを提供する企業です」と明示できる点で、ブランディング戦略にもプラスに働きます。
3-2. 法的リスク・コンプライアンス対応
アクセシビリティを軽視していると、障害者差別解消法などの国内法や、海外進出時にはADA法(アメリカ)などに触れる可能性が出てきます。
たとえばアメリカでは、ECサイトや大学のサイトが「視覚障がい者に配慮していない」という理由で訴訟を起こされ、多額の和解金を支払う事態が増加中です。
日本国内でも、SNS炎上やクレームのエスカレートを経て、社会問題として取り上げられるリスクは決して小さくありません。
つまり、アクセシビリティ対応を行うことでコンプライアンス上のリスク回避ができ、企業としての危機管理面でも大きなメリットがあるといえます。
3-3. 企業事例:大手金融機関の社会的評価向上
とある大手金融機関では、webアクセシビリティ専門チームを社内に置き、ガイドライン(JIS X 8341-3)のAAレベルを目標にサイト全体を改修。
その結果、高齢者を中心にコールセンターの問い合わせ数が減少(サイト上で十分情報を得られるようになったため)し、経費削減にもつながりました。
さらに、アクセシビリティ報告書を公表したことで、「利用者に優しい金融機関」というイメージが広まり、社会的評価やブランド価値が向上したといわれています。
このように、企業イメージや信頼獲得にも大きく貢献するのが、アクセシビリティのもう一つの導入メリットです。
4. 費用対効果はどう計算する?導入コストとROIの考え方

いざアクセシビリティ対応を進めようとすると、「コストがどれだけかかるのか」「ROI(投資回収率)は本当に高いのか」といった疑問が出てきます。ここでは、導入コストの考え方と費用対効果を最大化するポイントを整理しましょう。
4-1. 主な導入コストの内訳
webアクセシビリティのコストには、以下のような項目が含まれます。
- サイト監査費用:専門家やツールで現状分析するためのコスト
- デザイン・コーディング修正:コントラストやHTMLタグ修正、スクリーンリーダー対応
- システム改修:フォームやアプリケーションの入力補助機能追加など
- 継続的なモニタリング:アップデートごとのチェック、アクセシビリティツールのライセンス費用など
- 社内研修・啓蒙活動:担当者やデザイナー・エンジニアへの学習コスト
サイト規模や現在の構造によって大きく変動しますが、全面リニューアル級になる場合はそれなりの費用がかかることを念頭に置きましょう。
4-2. ROIを高めるためのステップ
費用対効果を最大化するためには、闇雲にすべてを対応するのではなく、優先順位をしっかり設定することが重要です。以下のステップが参考になります。
- 現状分析:アクセス解析やツール診断で最もユーザー離脱が多い箇所、重要コンテンツを特定
- 優先度付け:トップページや主要フォームなど、CVや問い合わせに直結する箇所から対応
- 段階的な実装:まずは容易に修正できる部分(alt属性や色調整など)を行い、大規模改修は徐々に
- 効果測定:改修前後でCVRや離脱率、問い合わせ数を比較し、成果を可視化
- 継続的な運用:サイト更新や新規ページ追加時にもアクセシビリティ基準を守る体制づくり
これらのステップを踏むことで、投資に見合うリターンを得やすくなり、アクセシビリティ改善が企業成長に直結しやすくなります。
4-3. 無理なく始める小規模改善例
「全面改修はハードルが高い」という企業は、小規模改善から始めてみましょう。例えば:
- トップページや主要ランディングページのコントラスト・色使いを見直す
- 主要バナーや画像にalt属性を設定し、スクリーンリーダーで意味がわかるようにする
- フォームの必須項目やエラー表示をわかりやすくし、入力補助を追加
これだけでも離脱率低減やCVR向上の効果が現れることがあります。改善効果を体感してから大規模改修に進むというアプローチをとる企業も増えています。
5. 【導入事例付き】アクセシビリティ導入でCVRが上がった企業の成功ポイント

ここでは、実際にwebアクセシビリティを導入し、CVRを大きく向上させた企業の事例をもとに、成功のカギとなるポイントを明らかにします。数字を上げている企業は、いったいどのようなステップを踏んだのでしょうか。
5-1. 事例:BtoC通販サイトでの大幅CVRアップ
あるBtoCのアパレル通販サイトでは、長年「高齢者への配慮が足りない」「フォーム入力がわかりにくい」といった声があがっていたものの、コストを理由に後回しになっていました。
そこで、ECサイト全体をアクセシビリティ優先で再設計し、以下のような改善を施しました。
- 背景色と文字色のコントラストを基準以上に保ち、文字を読みやすく
- フォントサイズを一段大きくし、調整機能も追加
- 商品画像にaltテキストを設定し、スクリーンリーダー対応を強化
- フォームのステップと入力支援を強化し、エラー表示をわかりやすく改善
その結果、お問い合わせ数が2倍以上に増えただけでなく、購入完了率(CVR)が約1.8倍に伸びたとの報告です。高齢者・障がい者だけでなく、若い世代からも「使いやすい」「情報が見やすい」と評判が良くなり、結果的に全ユーザー層のコンバージョン向上へとつながったのです。
5-2. 成功ポイント1:ユーザーテストの活用
成功企業の多くは、改修前にユーザーテストをしっかり行っています。特に障がいのある方や高齢者をモニターとして招き、実際の操作感や不便に感じる点を洗い出す工程を重視しているのです。
このアプローチにより、ツールでは発見しにくい細かな使い勝手の問題を見逃さずにすむため、最終的な完成度が高まります。
5-3. 成功ポイント2:チェックリストとガイドラインの明確化
「何をどこまで対応すればアクセシビリティが確保できるか」を明確にするため、多くの企業はWCAGやJIS X 8341-3の基準を社内向けにアレンジしたチェックリストを作成しています。
例えば、「画像には必ずaltを入れる」「見出しタグは論理構造に沿って配置」「フォームのエラー提示は視覚・聴覚の両面でわかりやすく」など、ルールを可視化することで、全員が同じ基準で作業できるようになり、ブレが減ります。
5-4. 成功ポイント3:継続的なモニタリングと改善
アクセシビリティ対応は一度やれば終わりではありません。サイト運営を続けるなかで新機能を追加したり、デザインを変更するたびに問題が再発する可能性があります。
成功企業は、定期的な監査やツールによるモニタリングを設定し、新たな課題を速やかに発見・修正しているのです。こうして常に高い水準を維持することで、CVRやユーザー満足度の上昇カーブを継続的に描けます。
6. freedoor株式会社のWebアクセシビリティ対応支援

freedoor株式会社は、企業や自治体をはじめとする多様なサイト運営者向けに、Webアクセシビリティを強化するためのコンサルティングや運用サポートを提供しています。
ユーザー調査やアクセス解析を通じた課題抽出から、具体的な改善施策の提案・実装まで、ワンストップで対応可能です。さらに、社内教育プログラムやチーム体制構築の支援も行い、長期的なアクセシビリティ品質の維持をサポートします。
アクセシレンズ:クラウド型アクセシビリティツール
なお、弊社が提供する「アクセシレンズ」は、専用のスクリプトを追加するだけで多彩なアクセシビリティ機能を実装できる
クラウド型SaaSツールです。
文字拡大やコントラスト調整、音声読み上げなどの支援機能が充実しており、WCAG 2.1やJIS X 8341-3:2016(レベルAA)といった基準に沿ったサイト改善を効率的に実現します。
詳しくは、アクセシレンズのサービス紹介ページ をご覧ください。
アクセシビリティ診断・コンサルティング
「アクセシビリティと言っても、どこから始めていいか分からない」――そんなお声に対して、まずはサイト診断を通して現状の課題を洗い出すところから着手します。
JIS X 8341-3やWCAGなどの基準を踏まえ、使いやすさ・読みやすさを妨げている要因を明確にし、優先度をつけて改善策を提案。
サイト全体の構造やデザイン指針の見直しから、管理体制の構築まで総合的にコンサルティングを実施します。
WEBアクセシレンズを活用した効率的な診断
freedoorが提供する「WEBアクセシレンズ」は、サイト内のアクセシビリティ状況を自動的に解析し、改善すべきポイントをレポート化するツールです。
- サイト内のテキストコントラストやalt属性の有無、フォームの可用性などを自動でチェック
- 問題点が見つかった箇所は具体的な修正提案を表示
- 定期的なスキャンやレポート機能によって改善状況を可視化
担当者が一つひとつ手動で確認する手間を大幅に削減しながら、高度なアクセシビリティ基準をクリアするサイトづくりをスピーディーに進めることが可能です。
Web開発・運用面でのサポート
アクセシビリティ対応では、テクニカルな知見が求められる場面が少なくありません。
例えば、既存のCMS(コンテンツ管理システム)をアクセシビリティ対応仕様にカスタマイズする、JavaScriptやAPI連携部分で特定の支援技術(スクリーンリーダーなど)に対応する、などです。
freedoorはシステム開発やアプリケーション構築の経験も豊富なため、エンジニアリング領域のサポートが必要な際にもワンストップで対応可能。
サイト運用が長期にわたる場合も、継続的な監査や改善提案を行い、アクセシビリティ品質を安定して保つお手伝いをいたします。
Webマーケティング・ユーザー拡大支援
アクセシビリティを高めることは、より多くのユーザーに届くサイトを構築することにも直結します。
freedoorでは、SEOやコンテンツマーケティング、SNS運用代行などのノウハウを組み合わせ、アクセシビリティの向上をビジネス成果に結び付ける戦略を提案いたします。
「ユーザーが見やすい・使いやすいサイト」は検索エンジンからも評価されやすく、CVRの向上や問合せ件数アップが期待できます。
オンラインアシスタントによる継続サポート
アクセシビリティ対応の取り組みは一度で終わりではなく、サイトの更新や新規ページ追加のたびに点検・修正が必要になります。
freedoorでは、日常の運用タスクや更新業務を支援するオンラインアシスタントサービスを展開。アクセシビリティ対策が疎かにならないよう、継続的にフォローアップいたします。
必要な部分だけを柔軟に任せられるため、社内リソースを有効活用しながら高品質なサイト運用が可能です。
企業サイトのアクセシビリティ向上でビジネスを強化
freedoor株式会社のWebアクセシビリティ対応支援は、単なる課題発見やツール導入に留まりません。
「企業サイトがユーザーにとって本当に使いやすいか」「その結果、問い合わせ数や売上、ブランド価値をどこまで伸ばせるか」という経営視点を持ちながら、戦略的にサービスを展開しています。
Webアクセシビリティ=すべての人にとっての使いやすさを追求する取り組みであり、高齢化社会や多様なデバイス環境への対応が強く求められる今日、企業価値を高める重要なポイントとなります。
freedoorでは、アクセシビリティによるユーザー拡大・ビジネス成長を総合的にサポートしながら、企業の持続的発展をバックアップいたします。
Webアクセシビリティ導入に関するご質問やご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▶ Webアクセシビリティ対応支援の詳細はこちら
7. まとめ:Webアクセシビリティ導入で企業成長を加速させよう

最後に、本記事で解説してきたポイントをまとめます。
「webアクセシビリティによるCVR向上と費用対効果」は、多くの企業が抱える「ユーザビリティ改善」「ブランド価値向上」「法的リスク回避」という課題を一挙に解決する大きなポテンシャルを秘めています。
- webアクセシビリティ:誰もがオンラインサービスを利用しやすい状態を作る取り組み。WCAGやJIS X 8341-3が指針となる。
- 導入メリット1 – CVRアップ:離脱率低下・フォーム改善・新規ユーザー層の取り込みなど、直接的な売上増に結びつく。
- 導入メリット2 – 企業ブランディング&リスク回避:CSRやSDGsでの評価向上、障害者差別解消法やADA法対応による法的リスク回避。
- 費用対効果:段階的なアプローチと継続的な運用体制でROIを最大化できる。小規模改善からでも効果を実感しやすい。
- 導入事例:フォーム改善などでCVR1.5倍、2倍といった成果を上げる企業が実際に存在。成功の鍵はユーザーテストとチェックリスト整備、継続的な監査。
企業成長を目指すのであれば、アクセシビリティは単なる「社会的配慮」ではなく、ビジネス競争力を高める戦略的な投資と捉えるべきフェーズに来ています。
むしろ、ユーザー数や売上に直結する以上、早期に取り組んだ企業ほど先行者メリットを得やすいとも言えるでしょう。
企業によるwebアクセシビリティ導入メリットについて、ぜひ本記事で得た知識を活用し、自社サイトのアクセシビリティを強化してみてください。
最後に、以下の点をチェックしながらアクセシビリティ導入の一歩を踏み出すのがおすすめです:
- 小規模な改善(コントラストやフォーム修正)から着手し、効果測定を行う
- 専門家や支援ツールを活用し、ガイドラインに沿った改修を進める
- 定期的なユーザーテスト・モニタリングを習慣化し、品質を保つ
これらを実行することで、CVRの向上だけでなく、企業イメージの向上、リスク回避、ユーザー満足度アップなど、多方面で大きなリターンを期待できるでしょう。
今こそ、webアクセシビリティを導入して企業成長を加速させるチャンスです。
