【事例付き】Webアクセシビリティ導入メリット徹底解説|具体的ステップと成功事例
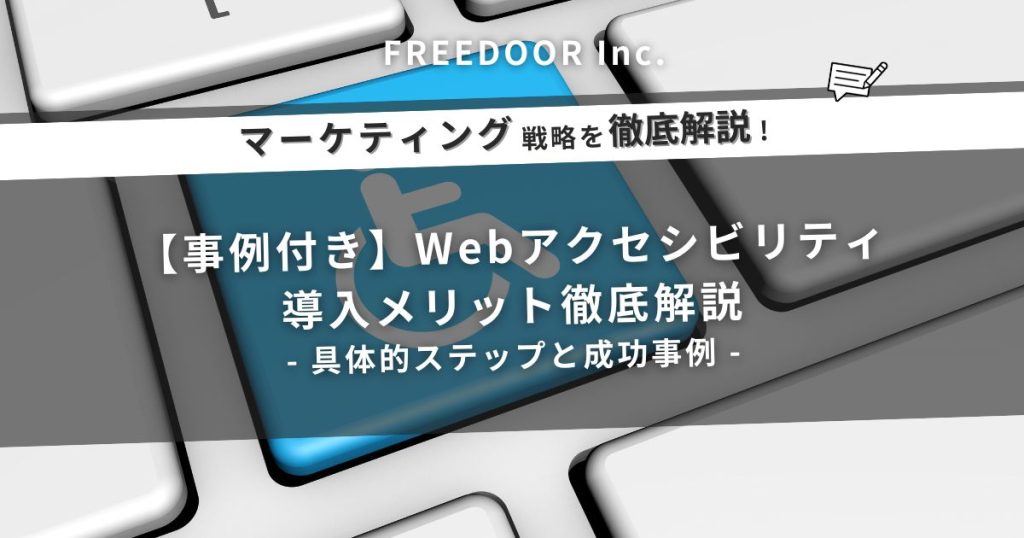
近年、急速に注目度が高まっている「webアクセシビリティ」。ウェブサイトを運営する企業の担当者はもちろん、マーケティングやIT部門に携わる方にとっても「アクセシビリティ対応は必須ではないか」「導入でどんなメリットがあるのか」と気になるポイントではないでしょうか。
本記事では、webアクセシビリティの導入メリットを軸に、実際の事例や導入ステップ、必要となるツールの活用方法までを徹底解説します。
読了後には、アクセシビリティがもたらすビジネス上の恩恵や具体的な導入方法、そして企業価値を高めるうえでの重要性をしっかり理解できるはずです。
1. なぜ今「webアクセシビリティ導入」が注目されているのか

webアクセシビリティが注目されている背景には、大きく分けて以下のような理由があります。
- 法令・ガイドラインの動向
- 多様なユーザー環境の拡大
- 企業の社会的責任(CSR/SDGs)意識の高まり
まず、法令・ガイドラインの動向としては、日本国内では「障害者差別解消法」をはじめとする法律や「JIS X 8341-3」というウェブアクセシビリティに関する規格が整備され、行政サイトや一部の企業サイトに対応が求められてきました。また、総務省が発行するガイドラインに沿う形で、公共機関のウェブサイトはアクセシビリティに配慮した設計を行う必要があります。近年は改定や最新情報のアップデートが頻繁に行われていることから、「法令を遵守しなければトラブルになるかもしれない」「社会の要請として取り組むべき」という認識が広まってきたのです。
次に、多様なユーザー環境の拡大です。スマートフォンやタブレットの普及、さらには高齢化社会の進展によって、ウェブを利用するユーザー層はかつてないほど多様になっています。視覚・聴覚などの障害がある方だけでなく、高齢で文字が見えにくい方、電波状況が不安定な地域で利用する方など、さまざまな状況に対応できるサイト設計が求められています。
さらに、企業の社会的責任(CSR/SDGs)意識の高まりという側面も無視できません。SDGs(持続可能な開発目標)の中には、誰もが平等に情報へアクセスできる世界を目指す理念が含まれています。ウェブアクセシビリティは、その理念を体現する施策の一つとして位置付けられやすいのです。こうした背景から、アクセシビリティ対応が「コスト負担」というよりも「企業価値を高める投資」として捉えられるようになってきました。
このように、多様な理由が重なり合い、企業・公共機関を問わず「webアクセシビリティ」を本格的に導入する機運が高まっています。
2. webアクセシビリティ導入で得られる5つのメリット

webアクセシビリティ導入には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、大きく5つに分けて解説します。
メリット1:ユーザー層の拡大
アクセシビリティ対応を行うことで、これまでサイト利用に困難を感じていたユーザー層を取りこめるようになります。たとえば、文字のコントラストを高くしたり、スクリーンリーダーで読み上げやすい構造にしたりすることで、視覚障がいを持つ方や高齢者にも使いやすいサイトへと変わるのです。
日本は超高齢社会に突入しています。視力の低下や聴力の衰えに悩む方が今後ますます増えていく中で、アクセシビリティに配慮したサイト設計をしている企業は、その大きな潜在市場を取り込みやすくなります。これにより、問い合わせ数や購入数など、サイトの重要指標も上昇が期待できるでしょう。
メリット2:コンバージョン率(CVR)の向上
ウェブアクセシビリティ対応は「ユーザーにやさしいサイト」を作る一助となります。つまり、使いやすさ(ユーザビリティ)の向上に直結するのです。ユーザビリティが高いサイトは離脱率を下げ、フォーム送信や商品購入などのコンバージョン率を高めます。
実際、ボタンやフォームの配置を見直し、キーボード操作だけでもスムーズに遷移できるようにしたり、補助テキストを充実させたりした結果、問合せ数や売上が大幅に伸びた事例もあります。アクセシビリティ導入は単なる「障害者配慮」で終わらず、広範囲のユーザーに「ストレスフリーな体験」を提供することに直結するのです。
メリット3:企業イメージ・ブランド力の強化
「すべての人に使いやすいウェブサイトを目指します」というメッセージは、企業の社会貢献や思いやりの姿勢をアピールする大きなポイントになります。
特に最近では、企業がSDGsやCSR活動を積極的に公表することが一般的になってきました。投資家や取引先からの評価にも関わるため、ウェブアクセシビリティ対応は企業イメージの向上に貢献し、ブランド力を底上げするきっかけにもなります。
メリット4:法的リスクの回避
海外では、アクセシビリティ対応が不十分なサイトに対して訴訟が起こった事例も少なくありません。アメリカなどでは企業や大学が視覚障がい者から訴えられ、社会的批判を受けたケースが報告されています。
日本国内でも、公共機関を中心にガイドラインや標準規格が整備されてきました。今後は民間企業にも強く求められる可能性が高いです。特に、障害者差別解消法が広義に適用されるようになれば、アクセシビリティ未対応が「差別」とみなされるリスクも否定できません。
早めに対応を進めることで、法的リスクの回避やクレーム発生率の低下といった効果が期待できます。
メリット5:検索エンジン最適化(SEO)の向上
アクセシビリティ対応は、実はSEOにもプラスに働くといわれています。例えば、以下のような取り組みが挙げられます:
- テキスト代替(alt属性)を適切に設定し、画像の意味を検索エンジンに伝わりやすくする
- 見出しや文書構造を正しくマークアップして、クローラビリティを改善する
- ページ読み込み速度を意識して、ページを軽量化する
これらはいずれも、SEOの基本的な推奨事項でもあります。ユーザビリティと検索エンジン双方に良い影響をもたらす点で、アクセシビリティの取り組みは非常に有益です。
3. 他社はどうやって成功している?導入事例とビフォーアフター

ここでは、実際にアクセシビリティ導入によって成果を上げた企業の事例や、具体的なビフォーアフター例を紹介します。
事例1:BtoB企業の問い合わせが2倍に
あるBtoBメーカーのウェブサイトでは、「資料請求フォームが視覚障がい者向けに配慮されていない」「コントラスト比が低くテキストが読みにくい」といった問題を抱えていました。そこでサイト全体の配色や見出し構造を見直し、アクセシビリティのガイドライン(WCAGやJIS X 8341-3)に準拠する形でフォームを改修。結果として、従来から懸念されていたフォーム途中離脱が大幅に減少し、資料請求数が1.8倍、問い合わせ全体数が2倍に増加したそうです。
事例2:ECサイトの売上が1.5倍に
アパレル系のECサイトでは、文字サイズが小さい、キーボード操作に対応していないなどの問題が散見されました。特に高齢者が商品を選びにくい、欲しいサイズが見つけにくいといった課題が顕在化していたのです。アクセシビリティを含むユーザビリティ改善を総合的に実施し、画面上の文字サイズや説明文を大きく、わかりやすく変更。すると、50代以上の購入率が大幅に伸び、結果的にサイト全体の売上が1.5倍にまで成長しました。
事例3:公共機関サイトのクレーム激減
公共機関のウェブサイトで多かったクレームは「音声読み上げに対応していない」「色の区別が付きにくい」などでした。特に視覚障がい者や色覚特性のあるユーザーからの不満が重なっていたため、スクリーンリーダー対応のテストを実施したり、配色を変えてコントラスト比を上げたりという徹底した見直しを実施。結果的にクレーム件数が激減し、さらに一般利用者からも「見やすくなった」と高評価のフィードバックが寄せられたそうです。
これらの事例からわかるように、アクセシビリティ導入は新たなユーザーや顧客を開拓し、既存の利用者にとっても「より快適な体験」を提供する手段です。コンバージョン数や売上アップなど、ビジネス成果に直結する形で大きな変化が期待できます。
4. 導入プロセスとチェックリスト:最初に押さえるポイント

「メリットはわかったけれど、具体的に何から着手すればいいの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、導入プロセスを5つのステップに分けて解説します。また、その際に便利なチェックリストのポイントにも触れていきます。
- 現状調査
- 対応方針の策定
- チェックリスト作成と優先度付け
- 実装とテスト
- 運用と継続改善
ステップ1:現状調査
まずは、自社サイトがどれだけアクセシビリティに対応できているかを客観的に把握する必要があります。
専門ツールを使った機械的なチェックに加え、実際に障害を持つユーザーの声やアンケート調査なども参考にすると、より深い課題が見えてくるでしょう。
ポイント:「画像にaltタグが適切についているか」「コントラスト比はガイドラインを満たしているか」「キーボードだけで操作可能か」を確認するといった基本的な項目からスタートしましょう。
ステップ2:対応方針の策定
現状を把握したら、どのガイドラインや規格に準拠するのか、どのレベル(A、AA、AAAなど)を目標とするのかを定めます。
日本の場合、JIS X 8341-3が代表的で、これに準拠することでWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)との互換性もある程度担保されることが多いです。どこまで対応するかは、運営者の目的や予算、サイト規模によって異なります。
ステップ3:チェックリスト作成と優先度付け
具体的な改善項目を整理したら、優先度をつけて取り組む順番を決めます。たとえば、文字のコントラストやフォントサイズの改善は比較的対応コストが低く効果も大きいです。一方、大規模なサイト構造の見直しやフォームの大改修などは工数がかかるかもしれません。
加えて、テンプレート化したチェックリストを作成すると、サイトを更新するときや新規ページを追加するときにも同じ基準でチェックできるようになります。
ステップ4:実装とテスト
実際に対応策を実装したら、ユーザーテストや専門ツールを用いた検証を行いましょう。
たとえば、スクリーンリーダーを使用して適切に読み上げられるか、キーボード操作のみで重要なコンテンツにアクセスできるかなどを確かめます。また、高齢者をモニターとして招いて実際に操作してもらうのも有効です。
こうしたテストをきちんと実施することで、思わぬところで問題が発生していないかを見逃さずに済みます。
ステップ5:運用と継続改善
webアクセシビリティは一度対応すれば完了というものではありません。サイトは常に更新され、新しい機能が追加されることで、アクセシビリティの観点から見れば新たな課題が生まれる可能性があります。
定期的な監査・モニタリングと社内教育・啓蒙を行い、継続的な改善のサイクルを回すことが大切です。
5. 活用したいツールと外部支援:効率的に導入メリットを得るコツ

「自社だけでやるには不安」「サイト規模が大きすぎて全部を手作業でチェックするのは難しい」――そう感じる担当者の方に向けて、ツールや外部支援の活用方法をお伝えします。
1. チェックツールの活用
webアクセシビリティ診断を自動で行ってくれるツールは多数存在します。
例えば、axeやWAVE、Siteimproveなどはページをスキャンし、潜在的なアクセシビリティ上のエラーや警告を一覧表示してくれます。
さらに効率的な導入メリットを追求したい場合は、「WEBアクセシレンズ」などのサービスを活用すると、一度の診断だけでなく継続的なモニタリングやレポート機能が提供されるため、運用段階での手間を大幅に削減できます。
2. 外部コンサル・専門家の支援
大規模サイトや、より高度なレベルでの対応を目指す場合は、アクセシビリティ専門家やコンサル会社の支援も選択肢となります。第三者の視点で監査やアドバイスを受けることで、社内で気づきにくい問題点が明るみに出ることがあります。
また、教育プログラムを導入して社内にアクセシビリティ担当者を育成する取り組みも効果的です。継続運用するためには、社内リソースを充実させる必要があるからです。
3. 継続的なモニタリングの重要性
ツールや外部支援を活用しても、「導入した時点で終わり」ではありません。
サイトを更新するたびに、自動診断ツールや専門家の監査を適宜利用し、最新状態での課題を発見・修正するプロセスを組み込むのが理想です。これにより、アクセシビリティの水準を常に維持しながら、ビジネスメリットを最大限に活かすことができるでしょう。
6. freedoor株式会社のWebアクセシビリティ対応支援

freedoor株式会社は、企業や自治体をはじめとする多様なサイト運営者向けに、Webアクセシビリティを強化するためのコンサルティングや運用サポートを提供しています。
ユーザー調査やアクセス解析を通じた課題抽出から、具体的な改善施策の提案・実装まで、ワンストップで対応可能です。さらに、社内教育プログラムやチーム体制構築の支援も行い、長期的なアクセシビリティ品質の維持をサポートします。
アクセシレンズ:クラウド型アクセシビリティツール
なお、弊社が提供する「アクセシレンズ」は、専用のスクリプトを追加するだけで多彩なアクセシビリティ機能を実装できる
クラウド型SaaSツールです。
文字拡大やコントラスト調整、音声読み上げなどの支援機能が充実しており、WCAG 2.1やJIS X 8341-3:2016(レベルAA)といった基準に沿ったサイト改善を効率的に実現します。
詳しくは、アクセシレンズのサービス紹介ページ をご覧ください。
アクセシビリティ診断・コンサルティング
「アクセシビリティと言っても、どこから始めていいか分からない」――そんなお声に対して、まずはサイト診断を通して現状の課題を洗い出すところから着手します。
JIS X 8341-3やWCAGなどの基準を踏まえ、使いやすさ・読みやすさを妨げている要因を明確にし、優先度をつけて改善策を提案。
サイト全体の構造やデザイン指針の見直しから、管理体制の構築まで総合的にコンサルティングを実施します。
WEBアクセシレンズを活用した効率的な診断
freedoorが提供する「WEBアクセシレンズ」は、サイト内のアクセシビリティ状況を自動的に解析し、改善すべきポイントをレポート化するツールです。
- サイト内のテキストコントラストやalt属性の有無、フォームの可用性などを自動でチェック
- 問題点が見つかった箇所は具体的な修正提案を表示
- 定期的なスキャンやレポート機能によって改善状況を可視化
担当者が一つひとつ手動で確認する手間を大幅に削減しながら、高度なアクセシビリティ基準をクリアするサイトづくりをスピーディーに進めることが可能です。
Web開発・運用面でのサポート
アクセシビリティ対応では、テクニカルな知見が求められる場面が少なくありません。
例えば、既存のCMS(コンテンツ管理システム)をアクセシビリティ対応仕様にカスタマイズする、JavaScriptやAPI連携部分で特定の支援技術(スクリーンリーダーなど)に対応する、などです。
freedoorはシステム開発やアプリケーション構築の経験も豊富なため、エンジニアリング領域のサポートが必要な際にもワンストップで対応可能。
サイト運用が長期にわたる場合も、継続的な監査や改善提案を行い、アクセシビリティ品質を安定して保つお手伝いをいたします。
Webマーケティング・ユーザー拡大支援
アクセシビリティを高めることは、より多くのユーザーに届くサイトを構築することにも直結します。
freedoorでは、SEOやコンテンツマーケティング、SNS運用代行などのノウハウを組み合わせ、アクセシビリティの向上をビジネス成果に結び付ける戦略を提案いたします。
「ユーザーが見やすい・使いやすいサイト」は検索エンジンからも評価されやすく、CVRの向上や問合せ件数アップが期待できます。
オンラインアシスタントによる継続サポート
アクセシビリティ対応の取り組みは一度で終わりではなく、サイトの更新や新規ページ追加のたびに点検・修正が必要になります。
freedoorでは、日常の運用タスクや更新業務を支援するオンラインアシスタントサービスを展開。アクセシビリティ対策が疎かにならないよう、継続的にフォローアップいたします。
必要な部分だけを柔軟に任せられるため、社内リソースを有効活用しながら高品質なサイト運用が可能です。
企業サイトのアクセシビリティ向上でビジネスを強化
freedoor株式会社のWebアクセシビリティ対応支援は、単なる課題発見やツール導入に留まりません。
「企業サイトがユーザーにとって本当に使いやすいか」「その結果、問い合わせ数や売上、ブランド価値をどこまで伸ばせるか」という経営視点を持ちながら、戦略的にサービスを展開しています。
Webアクセシビリティ=すべての人にとっての使いやすさを追求する取り組みであり、高齢化社会や多様なデバイス環境への対応が強く求められる今日、企業価値を高める重要なポイントとなります。
freedoorでは、アクセシビリティによるユーザー拡大・ビジネス成長を総合的にサポートしながら、企業の持続的発展をバックアップいたします。
Webアクセシビリティ導入に関するご質問やご要望がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▶ Webアクセシビリティ対応支援の詳細はこちら
7. まとめ:アクセシビリティは企業価値を高める重要な投資

本記事では、「webアクセシビリティの導入メリット」を軸に、主なメリット・導入事例・具体的なステップ・ツール活用法などを幅広く解説してきました。
- アクセシビリティ対応は、単なる法令順守や障害者配慮ではなく、企業価値を高める投資になり得る
- マーケティング・ブランディング効果や、CVR向上・売上増加といったビジネス上の成果にもつながりやすい
- 継続的なモニタリングと改善が不可欠であり、ツールや外部支援を上手に活用すると導入負荷を下げられる
今後、国内外を問わず、アクセシビリティへの取り組みはますます加速していくことが予想されます。
コストとしてではなく、「より多くのユーザーに快適な体験を提供し、企業のブランディングや売上アップにつなげる戦略投資」として捉えることで、企業としての競争優位性を高めるチャンスともいえるでしょう。
もし具体的な診断ツールを探している、あるいはコンサルティング支援をご検討されている場合は、「WEBアクセシレンズ」をはじめとする専門サービスをぜひチェックしてみてください。実際の運用や社内教育にも活かせる充実したレポート機能やアドバイスが得られるため、スムーズな導入・改善が可能になります。
これを機に、アクセシビリティ対応を「誰もが安心して利用できるウェブ」と「企業の持続的な成長」を両立させるための優れた選択肢として捉えてみてはいかがでしょうか。
