動画広告とは何か?メリット・デメリット・配信媒体をわかりやすく紹介

「動画広告とは何だろう?」そう思ったことはありませんか。 近年はYouTubeやTikTokをはじめ、SNSやWebメディアで動画広告を目にする機会が急増しています。
文字や画像だけでは伝えきれない情報を、映像と音声を組み合わせて直感的に届けられるのが最大の魅力です。
本記事では動画広告の基本的な定義や市場の最新動向、種類ごとの特徴、メリット・デメリット、そして成功事例までをわかりやすく解説します。
これから動画広告を活用してみたい方や、自社に合った運用方法を探している方に役立つ内容になっています。
動画広告とは?

「動画広告」とは、その名の通り映像や音声を使って商品やサービスを伝える広告のことです。
写真や文字だけの広告と比べて、より多くの情報を短時間で伝えられるのが最大の特徴です。例えば、飲食店の広告なら文字だけでは味や雰囲気を伝えるのが難しいですが、動画なら「湯気の立つ料理」「笑顔で食べるお客さん」の様子を映すことで、よりリアルに魅力を届けられます。
近年、動画広告が注目を集めている背景には大きく3つの流れがあります。
- SNSの利用増加:InstagramやTikTok、YouTubeなど、動画を前提にしたプラットフォームの利用者が急増しています。
- 通信環境の進化:5G回線の普及により、高画質な動画もスムーズに視聴できるようになりました。
- ユーザー行動の変化:文章よりも動画で情報を得たい人が増え、自然と動画広告を見る機会が多くなっています。
つまり、動画広告はただ「映像の広告」ではなく、時代の流れに合った「新しいコミュニケーション手段」といえます。
企業にとってはブランドの世界観をストーリーで伝えられるチャンスであり、ユーザーにとっては「短時間でわかりやすい情報源」になります。
たとえば、同じ新商品の紹介でも「テキスト広告」では機能説明が中心になりますが、「動画広告」なら以下のように広がりが生まれます。
| テキスト広告 | 動画広告 |
|---|---|
| ・商品の特徴を文字で説明 ・写真は1〜2枚程度 |
・実際に使っているシーンを映像で紹介 ・音や動きで臨場感を演出 ・利用者の声や雰囲気も同時に伝わる |
このように、動画広告は情報量が多く、印象に残りやすいという特性を持っています。
これからの時代において「動画広告とは何か」を理解することは、集客やブランディングを考えるうえで欠かせない第一歩になるでしょう。
動画広告の市場動向と最新トレンド

最近、動画広告の市場がとても熱くなっています。
「動画広告をやってみたいけど、市場はどれくらい大きいの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは日本国内のデータをもとに、成長の勢いと注目トレンドを見ていきましょう。
広告費全体における動画広告のシェアと成長率
サイバーエージェントが公表した調査によれば、2024年の国内動画広告市場は 7,249億円 に達し、前年比で約 115.9% の拡大を見せています。
このうちスマートフォン向け動画広告が約 5,750億円 を占め、全体の約 79% を占めたというデータもあります。
つまり、動画広告の主戦場はスマホということです。
さらに、将来的な予測では、2028年には市場規模が 1兆1,471億円 にまで拡大するとの見通しが立てられています。
このような大きな成長を背景に、企業が動画広告を検討するケースはますます増えてきています。
国内外の成長率データと予測
過去を振り返ると、2023年には動画広告市場は 6,253億円 に達し、前年比 112% の成長を達成していました。
このデータをもとにした予測では、2027年には 1兆228億円 を超える可能性が指摘されています。
このように、年を追うごとに市場が拡大していく流れがはっきり見えます。
また、国際的にも同様の傾向があり、モバイル動画広告の需要が世界的に増えていることが報告されています。
ショート動画や縦型動画・ライブ配信などの新潮流
成長を牽引しているのは、ただ「動画」であるというだけではなく、フォーマットの変化です。
特に注目されるのは以下の要素です:
- 縦型動画広告(タテ型フォーマット):2024年には前年比 171.1%の伸びを見せ、900億円規模に達しました。
2023年時点では、縦型動画広告は市場全体の 8.4% 程度でしたが、2024年には 12.4% にまでシェアを拡大しています。
予測では2028年には縦型動画広告の割合は 18.2% に達すると見られています。 - コネクテッドテレビ(Connected TV, CTV)向け広告:スマホだけでなくテレビでネット接続された環境での動画視聴も増えており、この分野の広告投資も急拡大しています。2024年には前年比 137.8%の伸びを示し、1,020億円規模になったとのデータがあります。
- ライブ配信広告やインタラクティブ動画:リアルタイム性を活かした広告手法は、視聴者との双方向性を高めやすいため注目が集まっています。特にSNSプラットフォーム上でライブ中に広告を挟んだり、視聴者が参加できる仕掛けを入れた動画が増えています。
- 短尺/ショート動画:TikTokやYouTube Shortsのように数秒〜数十秒で完結する動画が主流になりつつあります。テンポよくメッセージを伝える形式が、ユーザーの離脱を防ぐ観点からも重視されています。
このように、フォーマットや配信先デバイスが多様化しており、動画広告も“ただ作ればいい”時代から“どの形式でどこに出すか”を考える時代に変わってきています。
次のセクションでは、こうした形式の違いを整理しつつ、自社に合った広告手法を選ぶ方法を見ていきます。
動画広告の種類

ひとくちに「動画広告」といっても、実は配信の仕組みや表示される場所によっていくつもの種類に分かれます。
それぞれの特徴を理解することで、自社の商品やサービスに合った広告手法を選びやすくなります。
ここでは代表的な6つのタイプを紹介します。
インストリーム広告
インストリーム広告は、YouTubeのように動画の前後や途中に挿入される広告です。
多くのユーザーが日常的に目にする形式で、ブランドの認知度を一気に高めたいときに有効です。
ただしスキップされる可能性も高いため、最初の数秒で惹きつける工夫が欠かせません。
インバナー広告
インバナー広告は、Webサイトのバナー枠に埋め込まれた動画が自動再生される仕組みです。
記事を読んでいる最中に自然と目に入るため、認知や興味づけに向いています。
ただし音声がオフの状態で流れることも多いため、テロップでメッセージを伝える工夫が大切です。
インリード広告
インリード広告は、記事をスクロールすると途中で表示される形式です。
ユーザーの行動に合わせて表示されるため、受け入れられやすい傾向があります。
特にニュースメディアや情報サイトでよく利用されており、記事を読む流れの中で自然にアピールできます。
SNSフィード広告
SNSフィード広告は、InstagramやTikTokなどのタイムライン上に表示される広告です。
通常の投稿に溶け込むように出てくるので、広告っぽさが薄く、ユーザーに違和感を与えにくいのが特徴です。
特に若年層へのアプローチやトレンド性の高い商品には相性が良い広告形式です。
ストーリーズ広告
ストーリーズ広告は、InstagramやFacebookの「24時間で消えるストーリーズ」に表示されます。
画面いっぱいに縦型で表示されるため、没入感がありメッセージを伝えやすいのが魅力です。
時間が短い分、シンプルで直感的に理解できる内容にすることが成功のカギになります。
リワード広告
リワード広告は、アプリ利用者が「動画を視聴する代わりにポイントやアイテムを獲得できる」という仕組みの広告です。
ゲームアプリでよく見かける形式で、ユーザーのモチベーションが高いため最後まで見てもらえる可能性が高いのが特徴です。
「広告を見たい」と思わせる仕組みなので、エンゲージメントを高めたい場合に効果的です。
まとめ:種類ごとの特徴比較
それぞれの広告形式を整理すると以下のようになります。
| 種類 | 表示場所 | 特徴 |
|---|---|---|
| インストリーム広告 | 動画の前後や途中 | 認知拡大に強いがスキップされやすい |
| インバナー広告 | Webサイトのバナー枠 | 自然に目に入るが音声なし視聴が多い |
| インリード広告 | 記事スクロール時 | ユーザー行動に合わせて表示、受け入れられやすい |
| SNSフィード広告 | Instagram・TikTokのタイムライン | 通常投稿に溶け込む形で違和感が少ない |
| ストーリーズ広告 | SNSのストーリーズ | 縦型で没入感が強い、短時間勝負 |
| リワード広告 | アプリ内 | ユーザーのモチベーションが高く最後まで見られやすい |
このように動画広告にはさまざまな種類があります。
大事なのは「誰に」「どのタイミングで」見てもらいたいのかを考え、最適な形式を選ぶことです。
次のセクションでは、こうした広告を利用するメリットについて詳しく見ていきましょう。
動画広告のメリット
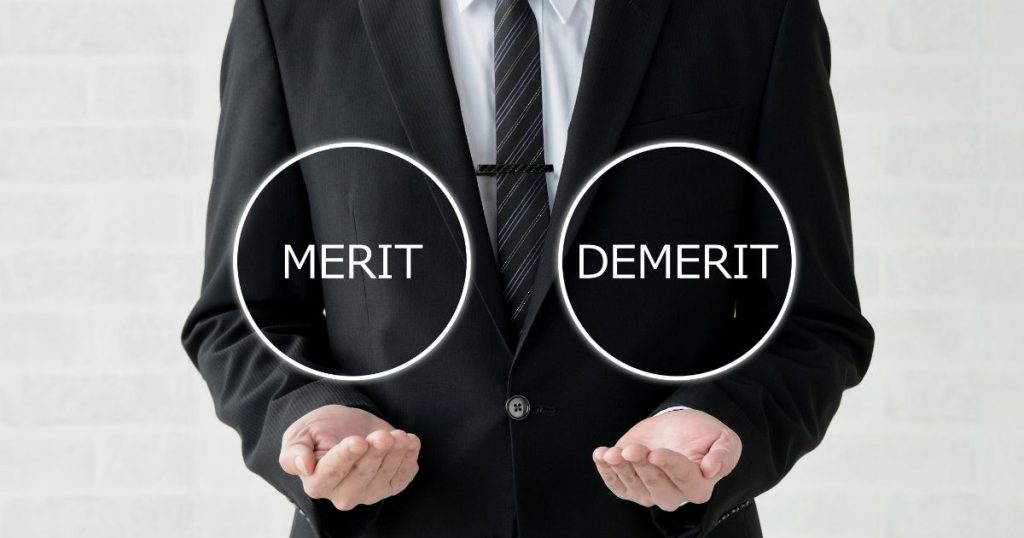
動画広告には、他の広告では得られない多くの魅力があります。
ここでは代表的なメリットをわかりやすく整理してみましょう。
テキストや画像よりも情報量が多く伝わる
動画は視覚と聴覚の両方に働きかけられるため、同じ時間で伝えられる情報量が圧倒的に多いのが特徴です。
例えば新商品の紹介では、文字だけだと「特徴を読む」ことしかできませんが、動画なら「使っている様子」「音」「雰囲気」まで伝えられます。
情報が直感的に伝わるため、理解が早く、記憶にも残りやすいのです。
感情に訴えやすく、購買行動を促進
動画はストーリー性を持たせやすいため、感情を動かすことができます。
たとえば飲料のCMで「暑い夏に冷えたドリンクを一口飲む」シーンを見れば、言葉で説明しなくても「飲みたい」と思わせることができます。
人の心を動かすことで、購買意欲やブランドへの好感度を自然に高める効果が期待できます。
効果測定を行いやすく改善が可能
デジタルの動画広告は効果測定がしやすいのも大きなポイントです。
再生回数、視聴完了率、クリック率など、数値で効果を確認できるため、「どの部分で視聴者が離脱したのか」「どんな内容なら最後まで見てもらえるのか」を検証できます。
これにより改善を繰り返し、広告効果を高めていけるのです。
ブランド認知から購入まで幅広い目的に対応
動画広告は目的に合わせて使い分けられるのも強みです。
・ブランドを知ってもらうための認知拡大
・商品の使い方を理解してもらう教育的な活用
・購入や資料請求へつなげる直接的な訴求
このように、広告のゴールに合わせて柔軟に設計できます。
モバイルファースト時代に最適化しやすい
現代では多くの人がスマートフォンで情報を得ています。
動画広告は縦型や短尺動画との相性が良く、スマホ利用者に自然に届きます。
「隙間時間に手軽に見られる」点も大きなメリットで、忙しい生活の中でもユーザーにリーチできるのです。
メリットのまとめ
整理すると、動画広告のメリットは以下の通りです。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 情報量の多さ | 映像+音声で短時間に多くの情報を伝えられる |
| 感情訴求 | ストーリーや演出で購買意欲を刺激できる |
| 効果測定のしやすさ | 数値データを活用し改善が可能 |
| 幅広い目的に対応 | 認知から購入促進まで幅広く使える |
| モバイル適性 | スマホユーザーに最適化しやすい |
このように、動画広告は「伝わりやすさ」と「改善のしやすさ」を兼ね備えた、とても強力な手法です。
次のセクションでは、こうしたメリットと対比する形でデメリットや注意点についても見ていきましょう。
動画広告のデメリット・注意点

動画広告には多くのメリットがありますが、もちろん注意しておくべき点も存在します。
あらかじめデメリットを理解しておくことで、無駄なコストや失敗を防ぎ、より効果的に活用できるようになります。
ここでは代表的なデメリットと注意点を整理してみましょう。
制作コストが比較的高い
動画広告は制作にお金と時間がかかるという弱点があります。
カメラ撮影、編集、ナレーションやBGMなど、写真広告よりも工程が多いため費用が膨らみやすいのです。
最近はスマホで簡単に撮れる動画広告ツールも増えていますが、クオリティを追求する場合は外注が必要になるケースもあります。
予算に応じた計画を立てることが重要です。
制作期間が長くなりやすい
シナリオ作成から撮影、編集までの流れを踏むと、どうしても完成までに時間がかかることがあります。
「新商品の発売に合わせたいのに間に合わない」といった事態にならないよう、スケジュール管理を意識する必要があります。
急ぎのキャンペーンには短尺の簡易動画や既存素材の活用を検討すると良いでしょう。
無音再生への弱さ
多くのユーザーは音声をオフにした状態で動画を見ているといわれています。
そのため、音声だけに頼った広告は内容が伝わらず、効果が半減してしまいます。
字幕やテロップを入れる、映像だけで意味が分かるようにするなど、無音でも成立する工夫が欠かせません。
広告疲れ・スキップへの対策が必要
動画広告が増えるにつれて、ユーザーは「また広告か」と感じてスキップすることも増えています。
同じ広告を何度も流すと「広告疲れ」を招き、逆にブランドイメージを損なうリスクもあります。
配信頻度を調整したり、クリエイティブを複数用意してローテーションする工夫が求められます。
デメリットのまとめ
整理すると、動画広告の主なデメリット・注意点は以下のようになります。
| デメリット | 内容 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| 制作コスト | 撮影・編集などで費用がかかる | 予算に応じて内製と外注を使い分ける |
| 制作期間 | 完成までに時間がかかりやすい | スケジュールを逆算して計画する |
| 無音再生 | 音声依存だと伝わりにくい | 字幕や映像で補足する |
| 広告疲れ | ユーザーが飽きやすくスキップされる | 複数パターンを作って配信を分散 |
このように、動画広告は強力な手法である一方で、気をつけなければ逆効果になるリスクもあります。
しかし、デメリットを理解して対策を講じれば、むしろ効果を高めるチャンスにもつながります。
次のセクションでは、実際に制作する際に押さえておくべきポイントを詳しく見ていきましょう。
動画広告を制作する際のポイント

動画広告を成功させるには、ただ「かっこいい映像」を作ればいいというわけではありません。
目的やターゲットを明確にし、見る人にとって分かりやすく、最後まで視聴してもらえる工夫が必要です。
ここでは制作時に押さえておきたい大切なポイントを紹介します。
目的・ターゲットを明確にする
最初に決めるべきは「何のために動画広告を出すのか」という目的です。
ブランドの認知を広げたいのか、商品の購入につなげたいのか、資料請求や問い合わせを増やしたいのかによって、動画の構成やメッセージは大きく変わります。
また誰に見てもらうのか(ターゲット)を意識することで、訴求内容や表現のトーンもブレなくなります。
冒頭数秒で惹きつける工夫
動画広告は冒頭3〜5秒が勝負といわれています。
なぜなら、多くのユーザーは興味を持たなければすぐにスキップしてしまうからです。
インパクトのある映像や、疑問を投げかけるフレーズを使うことで「続きが見たい」と思わせる工夫が必要です。
字幕・テロップを活用する
最近は無音で動画を視聴する人が増えているため、音声だけに頼るのは危険です。
セリフやナレーションを字幕で表示したり、強調したい部分にテロップを入れることで、音がなくても内容が伝わります。
また、色やフォントを工夫することで視覚的に印象を残しやすくなります。
スマホ視聴を意識したフォーマット
動画広告の多くはスマートフォンで視聴されています。
そのため縦型(9:16)や短尺(15秒前後)の動画が特に有効です。
テレビCMのような横型動画をそのまま流すより、スマホに最適化した縦型動画のほうが没入感が高く、視聴完了率も向上します。
CTA(行動喚起)を明確にする
広告の最後に「次にどうしてほしいか」をしっかり示すことも重要です。
例えば「今すぐ購入」「資料請求はこちら」「公式サイトでチェック」など、行動につながるメッセージを動画の終わりに入れることで、成果に直結します。
ポイントのまとめ
制作時に押さえておくべきポイントを整理すると次の通りです。
- 目的とターゲットを最初に明確にする
- 冒頭3〜5秒で視聴者を惹きつける
- 無音でも伝わるように字幕・テロップを入れる
- スマホに最適化した縦型・短尺動画を意識する
- 最後にCTAで行動を促す
これらを意識して動画広告を制作すれば、限られた予算や時間でも高い効果を得られやすくなります。
次のセクションでは、実際にどの媒体で動画広告を配信するのが効果的かを見ていきましょう。
動画広告でおすすめの媒体

動画広告は「どの媒体で配信するか」によって効果が大きく変わります。
媒体ごとにユーザー層や利用シーンが違うため、目的やターゲットに合わせて選ぶことが大切です。
ここでは代表的な5つの媒体を紹介します。
YouTube
YouTubeは世界最大の動画プラットフォームで、国内外で幅広い世代に利用されています。
インストリーム広告やバンパー広告などフォーマットも豊富で、リーチを広げたい企業にとって最適です。
検索機能を持っているため「能動的に情報を探すユーザー」にもリーチできる点が強みです。
TikTok
TikTokはZ世代を中心に人気のプラットフォームです。
短尺でテンポの良い動画が好まれるため、拡散力が非常に高いのが特徴です。
「バズ」を狙いたい商品や、話題性を重視するプロモーションに向いています。
Instagramは写真・動画を中心に利用されるSNSで、特にストーリーズ広告やリール広告との相性が抜群です。
おしゃれでビジュアルに強い訴求ができるため、ファッション・美容・ライフスタイル関連の商品やサービスにぴったりです。
Facebookは利用者の年齢層が広く、特に30代〜50代のビジネス層にも強いプラットフォームです。
友人・知人とのつながりをベースにしているため、信頼性を重視した広告展開に向いています。
Instagramと併用して広告配信ができる点も魅力です。
X(旧Twitter)
X(旧Twitter)は情報の速報性に強い媒体です。
ニュースやトレンドと絡めて動画広告を出すことで拡散力を高められます。
拡散性が高い一方で、ユーザーの滞在時間は短いため「インパクトのある短尺動画」に適しています。
媒体の特徴比較
それぞれの媒体の特徴を一覧にまとめると次の通りです。
| 媒体 | 主なユーザー層 | 特徴 | 向いている目的 |
|---|---|---|---|
| YouTube | 全年代 | 圧倒的なリーチ力、広告形式が豊富 | 認知拡大・理解促進 |
| TikTok | 10代〜20代中心 | 拡散力が高い、短尺動画に特化 | 話題化・ブランド浸透 |
| 20代〜30代中心 | ビジュアル訴求に強い、ストーリーズが人気 | ファッション・美容・ライフスタイル訴求 | |
| 30代〜50代中心 | 信頼性が高い、ビジネス利用者が多い | BtoB・幅広い世代への訴求 | |
| X(旧Twitter) | 10代〜40代中心 | 速報性が高くトレンドに強い | キャンペーン拡散・短期集客 |
媒体選びは「どの層に」「どんな目的で」届けたいのかによって変わります。
例えば、認知を広げたいならYouTube、話題性を狙いたいならTikTok、信頼性を重視するならFacebook、といった形で戦略的に使い分けましょう。
次のセクションでは、こうした媒体を活用した成功事例について見ていきます。
動画広告の成功事例

ここまでで動画広告の特徴や媒体について紹介してきました。
「実際にどんな成果が出ているのか?」が気になる方も多いのではないでしょうか。
そこでBtoCとBtoB、それぞれの分野での成功事例を見ながら、動画広告の可能性を具体的にイメージしていきましょう。
BtoC(EC・アプリ・飲食業界など)の事例
消費者向けビジネスでは、動画広告の効果がとても分かりやすく表れます。
例えばECサイトでは、短尺のスタイリング動画を使って「着こなしイメージ」を見せた結果、購入率が大きく向上した事例があります。
飲食店では「調理の様子」や「食べる瞬間の笑顔」を映すことで来店数が増加したケースもあります。
またアプリのプロモーションでは、利用シーンを動画で見せることで「便利さ」が伝わり、ダウンロード数が伸びたという結果も報告されています。
BtoB(SaaS・サービス業など)の事例
企業向けサービスでも、動画広告は有効に働いています。
特にSaaSのようなソフトウェアは機能が複雑で、文字や画像だけでは伝わりにくいことが多いです。
そこで「サービスを使う流れ」をアニメーションや解説動画にまとめた結果、理解度が高まり問い合わせ数が増加した例があります。
またBtoBのセミナー告知動画をSNSに配信することで、参加者数が大幅に伸びたケースもあります。
短尺動画と長尺動画の使い分け
成功事例を見てわかるのは、短尺動画と長尺動画をうまく使い分けている点です。
短尺動画は「興味を引くきっかけ」に最適で、SNSやモバイル視聴との相性が抜群です。
一方で長尺動画は、商品説明やサービス理解など「深く知ってもらう段階」に効果を発揮します。
つまり「短尺で興味を持たせ、長尺で理解を深める」という流れを作ることが成功の鍵になります。
事例のまとめ
以下の表に、事例のポイントを整理しました。
| 分野 | 活用方法 | 成果 |
|---|---|---|
| BtoC(EC) | 着こなしイメージの短尺動画 | 購入率の向上 |
| BtoC(飲食) | 調理シーンや食事シーンを映す | 来店数の増加 |
| BtoC(アプリ) | 利用シーンを見せる | ダウンロード数の増加 |
| BtoB(SaaS) | サービス説明をアニメーション化 | 問い合わせ数の増加 |
| BtoB(セミナー告知) | SNSで告知動画を配信 | 参加者数の増加 |
このように、動画広告は業界や商材を問わず成果を出しやすいのが特徴です。
次のセクションでは、よくある疑問に答える形でFAQをまとめていきます。
よくある質問(FAQ)

動画広告を検討している方からよく寄せられる疑問をまとめました。
「これから始めたいけど不安…」という方はぜひ参考にしてください。
Q1: 動画広告の制作費はどれくらいかかる?
費用は内容や制作方法によって大きく変わります。
自社でスマホ撮影と簡単な編集を行えば数万円で始められますが、本格的に撮影チームを入れて制作する場合は数十万〜数百万円かかるケースもあります。
最近ではオンラインサービスやテンプレートを活用した低コストの制作方法も増えているため、まずは予算に合わせて選ぶのがおすすめです。
Q2: 効果測定はどの指標を使うべき?
動画広告の効果を測るには複数の指標を組み合わせることが大切です。
代表的なのは「再生回数」「視聴完了率」「クリック率(CTR)」「コンバージョン率(CVR)」などです。
再生回数だけを見るのではなく「最後まで見てもらえたか」「広告から購入や問い合わせにつながったか」をチェックすることで、本当の効果が見えてきます。
Q3: 広告は短尺と長尺どちらが効果的?
どちらが効果的かは目的によって違うと考えるのが正解です。
・認知拡大 → 短尺(6〜15秒程度)
・理解促進 → 長尺(30秒〜数分)
短尺は「興味を持ってもらうため」、長尺は「しっかり理解してもらうため」と役割分担を意識すると効果的です。
Q4: 自社で制作するのと外注するのはどちらが良い?
自社で制作するメリットは低コストとスピードです。
一方、外注のメリットは高いクオリティと企画力にあります。
「予算は限られているけどスピード重視」なら内製、「ブランドイメージをしっかり作り込みたい」なら外注、といった選び方がおすすめです。
両方を組み合わせ、企画や撮影は外注、日常的な運用は内製といった方法も有効です。
Q5: 動画広告を始めるのに最低限必要な準備は?
最低限必要なのは次の3つです。
- 目的の明確化(何を達成したいか)
- ターゲットの設定(誰に届けたいか)
- 媒体の選定(どこで配信するか)
この3つが決まれば、あとは予算に応じて制作方法を選び、実際に動画を作成していく流れになります。
以上がよくある質問とその回答です。
次のセクションでは、記事全体を振り返りながらまとめをしていきます。
まとめ|動画広告の活用で成果を最大化しよう

ここまで、動画広告の基本から市場の動向、種類やメリット・デメリット、制作のポイントや成功事例までを紹介してきました。
改めて振り返ると、動画広告は「情報を直感的に伝えられる力」と「感情を動かす力」を持っており、他の広告手法にはない魅力があります。
動画広告は、目的やターゲットを明確にすれば認知拡大から購入促進まで幅広く活用できる万能な手段です。
一方で、制作コストや無音再生への対応といった注意点もありますが、工夫次第で乗り越えられるポイントでもあります。
「冒頭数秒で惹きつける」「テロップで補足する」「スマホ視聴を意識する」といったシンプルな工夫だけでも効果は大きく変わります。
市場の動向を見ても、動画広告は今後さらに成長し続けると予想されています。
YouTubeやTikTok、Instagramなど、それぞれの媒体には特色があり、自社の商品やサービスに合った選び方をすることで成果につながります。
また、短尺動画と長尺動画を組み合わせる戦略も、多くの成功事例から有効性が示されています。
つまり、動画広告は「やるかやらないか」ではなく「どう取り入れるか」が大切な時代になっています。
まだ取り組んでいない企業にとっては、早めに導入しノウハウを蓄積することで、競合との差をつけられるチャンスです。
これから動画広告を始める方は、まずは小さくテストをしながら改善を重ねていきましょう。
そして徐々に自社に合ったスタイルを見つけていくことで、売上やブランド力の向上につながるはずです。
動画広告を上手に活用すれば、企業の成長を支える大きな武器になるでしょう。
動画広告を成果につなげたいなら、freedoorにご相談ください

動画広告は「作って出す」だけでは効果を最大化できません。
大切なのは媒体ごとの特性を理解した運用ノウハウと、ユーザーの心を動かす動画クリエイティブの掛け合わせです。
freedoorは、YouTube・TikTok・Instagram・Facebookといった主要プラットフォームすべてで実績を持ち、
企画・制作から配信・運用改善までワンストップで対応しています。
「どの媒体から始めたらいいのか分からない」という段階からでも、課題や目標に応じて最適なプランをご提案できます。
- Facebook広告で効率よくリードを獲得
- Instagramのリール・ストーリーズで認知拡大
- TikTokで短尺動画の拡散と若年層アプローチ
- YouTubeで理解促進&ブランディング強化
媒体ごとにページは分かれていますが、まずは「問い合わせ窓口ひとつ」でご相談いただけます。
「どの媒体がいいのか」「制作もお願いしたい」など、最初の段階から気軽にご相談いただければ、最適な運用方法をご提案いたします。
